ROUND7 国民の命を守るため東京オリンピックの中止を!編 26
教授・井上寿一氏コラム◇菅政権の東京五輪迷走は戦時中と酷似・広がる懐疑

■井上寿一氏へのインタビュー記事|戦時中、政府が大局的な判断できずに情勢を悪化させた
 国内外で東京オリンピック・パラリンピック開催への懐疑論が広がっている。新型コロナウイルスの感染収束が見えない中、なぜ五輪を開くのか、多くの人が納得できていない。現状を、政府が大局的な判断をできずに情勢を悪化させ続けた戦時中になぞらえる声も。五輪本来の姿を含めて問い直し、今どうすべきかを考える。新型コロナウイルス対策と東京オリンピック・パラリンピックを巡る政府の迷走は、80年前の太平洋戦争時と酷似している。政策の優先順位が不明瞭で、大義名分は次々と変わる。あの戦争の結末は言うまでもない。今回は、どんな「終戦」があるだろうか。
国内外で東京オリンピック・パラリンピック開催への懐疑論が広がっている。新型コロナウイルスの感染収束が見えない中、なぜ五輪を開くのか、多くの人が納得できていない。現状を、政府が大局的な判断をできずに情勢を悪化させ続けた戦時中になぞらえる声も。五輪本来の姿を含めて問い直し、今どうすべきかを考える。新型コロナウイルス対策と東京オリンピック・パラリンピックを巡る政府の迷走は、80年前の太平洋戦争時と酷似している。政策の優先順位が不明瞭で、大義名分は次々と変わる。あの戦争の結末は言うまでもない。今回は、どんな「終戦」があるだろうか。 去年の今ごろは、厳しいロックダウン抜きでも感染拡大を抑え込めそうだった。あの段階でもっと徹底して封じ込めて以後の対策を万全にすべきだったが、かえって楽観論が広まったように思う。その後は政府が感染拡大防止と、経済活動や五輪開催のどれを優先したいのか、国民にはわかりにくくなった。緊急事態宣言も繰り返されて、天王山がいくつも現れた。戦時中も同様だった。真珠湾攻撃にハワイを占領する徹底性はなかった。楽観と慢心のあげく開戦6カ月後に「不要不急」のミッドウェー海戦で大敗する。続くガダルカナル島の戦いは、島を放棄する決断ができず、兵力を逐次投入して泥沼化した。その後も陸海軍は戦略を統合できず、別々の天王山を設けて戦力を分散させた。
去年の今ごろは、厳しいロックダウン抜きでも感染拡大を抑え込めそうだった。あの段階でもっと徹底して封じ込めて以後の対策を万全にすべきだったが、かえって楽観論が広まったように思う。その後は政府が感染拡大防止と、経済活動や五輪開催のどれを優先したいのか、国民にはわかりにくくなった。緊急事態宣言も繰り返されて、天王山がいくつも現れた。戦時中も同様だった。真珠湾攻撃にハワイを占領する徹底性はなかった。楽観と慢心のあげく開戦6カ月後に「不要不急」のミッドウェー海戦で大敗する。続くガダルカナル島の戦いは、島を放棄する決断ができず、兵力を逐次投入して泥沼化した。その後も陸海軍は戦略を統合できず、別々の天王山を設けて戦力を分散させた。 五輪の大義名分は東日本大震災の復興記念だったが、「人類が新型コロナに打ち勝った証し」に切り替わった。ところが、1年前よりも日本の感染者は多く、説得力がない。丸川珠代五輪担当相は「コロナ禍で分断された人々の間に絆を取り戻す大きな意義がある」と言う。素直に同意できる人は、ほぼいないだろう。80年前も大義名分は場当たり的に変わった。暴支膺懲(ぼうしようちょう)(横暴な中国を懲らしめろ)から東亜新秩序へ、自存自衛から大東亜共栄圏へ。本当の目的が資源確保だったのは明らかだった。五輪も建前と別の意図が透けている。メンツと与党の衆院選対策だ。
五輪の大義名分は東日本大震災の復興記念だったが、「人類が新型コロナに打ち勝った証し」に切り替わった。ところが、1年前よりも日本の感染者は多く、説得力がない。丸川珠代五輪担当相は「コロナ禍で分断された人々の間に絆を取り戻す大きな意義がある」と言う。素直に同意できる人は、ほぼいないだろう。80年前も大義名分は場当たり的に変わった。暴支膺懲(ぼうしようちょう)(横暴な中国を懲らしめろ)から東亜新秩序へ、自存自衛から大東亜共栄圏へ。本当の目的が資源確保だったのは明らかだった。五輪も建前と別の意図が透けている。メンツと与党の衆院選対策だ。■戦争は昭和天皇のご聖断で終わったが五輪は政府と国民・国民の間でも分裂している
 あの戦争の途中から、国民は「たぶん勝てないが、負けてどうなるかもわからない」と感じだした。終わらない戦争に本音は目の前の生活優先となり、動員学徒の工場への出勤率などは段々と下がった。今の場合は「五輪は開催しても成功にほど遠く、開催の意義も失われている。だが、やらないとどうなるかもわからない」が平均的な感覚だろう。緊急事態宣言下でも通勤電車は満員で、深夜まで酒を提供する飲食店が出ている。あの戦争は、指導者層の意見が割れて、昭和天皇の「ご聖断」と「玉音放送」で終わった。今は、政府と国民、さらに国民の間でもコロナ禍と五輪をめぐって分裂している。今ならば何がこの状況を終わらせられるだろうか。
あの戦争の途中から、国民は「たぶん勝てないが、負けてどうなるかもわからない」と感じだした。終わらない戦争に本音は目の前の生活優先となり、動員学徒の工場への出勤率などは段々と下がった。今の場合は「五輪は開催しても成功にほど遠く、開催の意義も失われている。だが、やらないとどうなるかもわからない」が平均的な感覚だろう。緊急事態宣言下でも通勤電車は満員で、深夜まで酒を提供する飲食店が出ている。あの戦争は、指導者層の意見が割れて、昭和天皇の「ご聖断」と「玉音放送」で終わった。今は、政府と国民、さらに国民の間でもコロナ禍と五輪をめぐって分裂している。今ならば何がこの状況を終わらせられるだろうか。 戦後復興が早く進んだ背景に戦時中の経験があった。戦時中、短期間ながら社会の平等化が相対的に進み、人々は公の目標に協力すれば私生活も良くなると実感した。その延長で、戦後は国家と国民が高度成長で共に豊かになった。今回も私たちはコロナ禍で多くを学んだ。情報技術の習熟、新しいビジネスモデルなどに活路を見いだした。「この間に身につけた技術や能力から未来を切り開こう」。こうしたコロナ後、五輪後を見据えた思考が必要ではないだろうか。
戦後復興が早く進んだ背景に戦時中の経験があった。戦時中、短期間ながら社会の平等化が相対的に進み、人々は公の目標に協力すれば私生活も良くなると実感した。その延長で、戦後は国家と国民が高度成長で共に豊かになった。今回も私たちはコロナ禍で多くを学んだ。情報技術の習熟、新しいビジネスモデルなどに活路を見いだした。「この間に身につけた技術や能力から未来を切り開こう」。こうしたコロナ後、五輪後を見据えた思考が必要ではないだろうか。<プロフィール> 井上寿一(いのうえとしかず) 1956年生まれ 学習院大教授、前学長
専門は日本政治外交史 著書「はじめての昭和史」など
 投稿者によって、タイトル付けを行いました。
投稿者によって、タイトル付けを行いました。 ■ころころ変わる政府の五輪大義 「復興五輪」→「コロナに打ち勝った証し」→「平和の祭典」
ここからは投稿者の文章/戦争研究家はどなたも、コロナ禍の政府の対応は大失敗した戦争中と変わらないと言う。私は土曜12-13時、BS-TBS「関口宏のもう1度!近現代史」の番組を観ています。ノンフィクション作家・評論家の保阪正康氏が、戦争の過ちなどを丁寧に評論しています。何の根拠もなく精神論だけで敵国に立ち向かい、失敗すれば反省もなく南方の兵士に玉砕を求めることの繰り返し。南方の兵士を「コロナ禍の国民」に置き換えれば理解しやすい。「五輪の大義」を調べたら、次々と変わっていた。2014年・安倍首相(当時)「『復興五輪』とし日本が生まれ変わるきっかけとしなければならない」、20年・同「人類がコロナに打ち勝った証しとして完全な形で実施したい」、21年2月・菅首相「人類がコロナとの闘いに打ち勝った証しとて、安全安心の大会を実施したい」、21年6月・同「平和の祭典、一流のアスリートが集まり、スポーツの力を世界に発信する」。底辺に一環として流れるものは、国威発揚と政府・自民党の維持。だからコロナ禍でも、強引に開催しようとしている。
次号/与良政談★菅首相「五輪に勝負を賭けた」一か八かは菅政治の本質、でも国民の命は
前号/山田孝男・編集委員コラム◇五輪貴族・五輪ファミリーが最大の感染リスク(警戒の大穴)











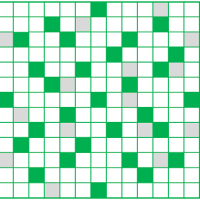











 1月 ベスト10
1月 ベスト10 










 2月のピックアップ!
2月のピックアップ!














