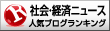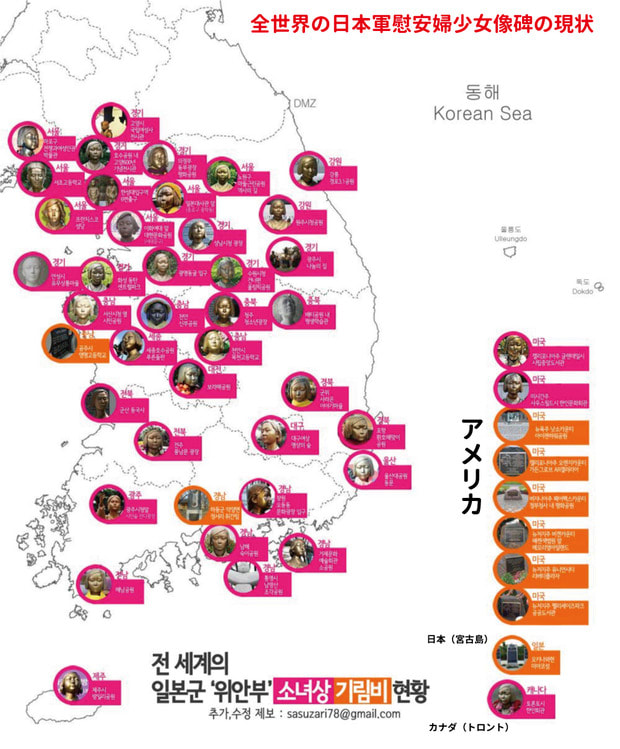瓢箪島の教育は<<社畜化が目的>>なので、服従、個性殺し目的。
英語などわざと使えないのを教えて海外に逃げ出せないようにしている。
日本に居ると、低能の人間に足を引っ張られまくるので、才能ある人間は、早く日本から出たほうが良い。それには英語が必要なので親が理解を示して幼稚園から英語教育をすべきだしできればアメリカンスクールに入れたほうが良い。
日本の教育を受けると<<盆栽人間にされる>>

学校の"班活動"が日本の子供を潰している
7/2(火) 14:00配信
プレジデントオンライン
学校の
ルーシー・クレハン氏
日本の子供の「15歳時点の学力」は世界トップレベルにある。だが「世界大学ランキング」では苦戦しており、大学生の“質の低下”を嘆く声も聞かれる。なぜそうなってしまうのか。国際学力テスト「PISA」で優秀な成績を収める5カ国を実地調査したルーシー・クレハン氏は「日本が集団主義を重んじ、小・中学校で『班活動』を行っていることが背景にある」と指摘する――。
■15歳時点では優秀なのに、大学時点では質が低い?
3年に1度、15歳を対象に実施される国際学力テスト、PISA。日本はこのテストで毎回、高い順位をマークしている。一方で高等教育に目を転じると、「世界大学ランキング」の上位に日本の大学名はなく、大学生の「質の低下」が指摘されて久しい。この逆転はなぜ起きるのか?
英国の教育アドバイザーのルーシー・クレハン氏は、日本をはじめPISAの成績上位国を実地調査し、その結果を『日本の15歳はなぜ学力が高いのか? 』(邦訳は早川書房)にまとめた。このほど来日したクレハン氏に、日本の教育における課題について聞いた(聞き手は早川書房編集部)。
■成功を生むのは「過剰なほどの自信」
まず、「世界大学ランキング」は、学生の能力の高低を表すものではありません。その点に注意する必要があります。指標となっているのは論文の引用数や研究予算ですから、良い環境で教わることができるかどうかの判断基準にはなりえますが、PISAの順位とそのまま比べることはできません。
そのうえで、初等・中等教育と大学教育では、求められる能力に違いがあることもたしかです。大学で必要とされる能力は、ペーパーテストに正解できる力ではありません。議論をしたり、新しいアイデアを作ったりする能力のほうが重要です。そして、欧米の学生は日本の学生に比べて、そうした能力にたけています。これは小・中学校の段階からそうですし、学力に関係なく子どもたち全般に共通して言えることです。
オックスフォード大学に通っていた学生時代、先生にこう言われました。「良い成績を取る学生は、本を読んで内容が理解できない時、自分が悪いとは思わない。著者が悪いと考える」。成功をめざすのなら、過剰なほどの自信をもって突き進むぐらいが良い、ということでしょう。良い論文は、ひとつのアイデアをつきつめて、「これがいいんだ」と主張するものです。「これもあるし、あれもある」と指摘するだけの論文は、二流にすぎませんよね。大学、あるいは社会に出てからは、自分の考えを、間違いをおそれずに自信を持って発信できる能力が求められます。
■出る杭が伸びにくい日本の集団主義
日本の子どもたちにこうした自信が身につきづらいのは、日本特有の「集団主義」のネガティブな面だと言えます。
拙著に記したとおり、私が実地調査した5カ国(フィンランド、日本、シンガポール、中国、カナダ)のなかでも、「集団」を重んじる文化や制度が根づいているのが日本の教育現場の特徴でした。
例えば、日本の小・中学校では活動のほとんどを「班」単位で行いますよね。班の仲間と一緒に座り、勉強し、給食を食べ、学校じゅうを掃除する。学習成果は班の努力として評価され、個々の生徒のあいだの能力の違いはあまり問題にされません。褒められるときも、個人ではなく班が褒められます。こうした文化が、「出る杭を伸びにくく」していることは事実でしょう。
私が授業見学をした限りでは、小学生はみんな元気に挙手をしていましたが、中学生になるとそうした積極性が見られなくなるようでした。「ちゃんと整列しなさい」「もっと行儀よくしなさい」と先生から繰り返し指導されているうちに、自信を失ってしまうのだと思います。
とはいえ、集団主義には良い面もたくさんあります。そのおかげで、日本の子どもたちはみな礼儀正しく、他者と協調できる。それらを生かしたうえで、自分の考えを相手に伝える力を身につけさせることは可能なはずです。
たとえば、高校受験の評価手段として、試験の点数だけではなく、プレゼンテーションの能力も加味してはどうでしょうか。学んだことを先生や友人に向けて発表する時間を中学校の授業のなかで設け、その能力に成績をつける。そうすれば生徒も先生も真剣に取り組むでしょうし、その中で生徒には自信がついていくことでしょう。その際には、お互いを笑ったりするのではなく、尊重しあうことが大切です。
■なぜ「ゆとり教育」を導入したのか
かつて実施された「ゆとり教育」も、子どもたちに自信をつけさせるという意味では有効な教育政策でした。
ご存じのとおり、日本の小・中学校では1990年代の後半から2000年代の前半にかけてカリキュラムの3分の1を減らしました。土曜日を段階的に休日にしていき、子どもたちに自分の興味を追求させるための「総合的な学習の時間」を設けたのです。
だいたいにおいて規範を細かく定める文部科学省にしてはきわめて異例のことですが、総合的な学習の時間にどのような活動を行うのかは、主に各学校に任せられました。これは教師たちが構造化された「問題解決手法」を授業に取り入れるよりも、さらに先進的な取り組みでした。どんな問題を解決するか、どんな疑問に取り組むかを、子どもたち自身が決めるのですから。
■日本の生徒が世界一になる可能性を潰した
ところが、2003年に実施したPISAの結果が2004年に発表され、日本の読解力の得点が下がったとわかるや、その原因としてゆとり教育が槍玉に挙げられました。批判に応えて、日本政府は次第に数学や国語の時間を増やすようになり、2011年、ゆとり教育のほとんどは廃止されました。教科書は分厚くなり、「総合的な学習」に使われた時間の多くはほかの科目に取って代わられ、縮小されました。
PISAの成績の下落というほんのささいなつまずきで、日本の政府はうろたえ、「受験地獄」の軽減と、見たことのない問題の解決において日本の生徒たちが世界一になる可能性の、両方に効果的であったはずの改革を廃止してしまったのです。
根本的な問題は、そもそもこの改革が何を目指したものなのかが忘れられてしまったことです。ゆとり教育は、PISAの点数を上げるためのものではありませんでした。子どもたちにかかるプレッシャーを軽減し、彼らの創造性や問題解決能力を伸ばすためのものだったはずです。
教育プログラムを機能させるには、政治的な見栄えだけで決めるのではなく、長期的な狙いをしっかりと持つことが必要です。シンガポールのように超エリート教育に邁進する国もあれば、フィンランドのように「遊び」を重視する国もあります。それらの国もカリキュラムをマイナーチェンジすることはありますが、方針自体を変えるわけではありません。そして、目標を達成するための手段を決めるにあたっては、政治家だけでなく専門家がしっかりと関わる必要があります。
■試験で良い点数をとらせるだけが教育ではない
2000年と2012年に行った調査によれば、日本の子どもたちの学校に対する満足度は、この期間に世界のどの国より増加しています。そして問題解決のテストでは、日本の生徒は、PISAのトップだった上海をはじめ、ほかのほとんどの国よりまさっていました。私には、ゆとり教育が目指そうとしたことは、ちゃんと成し遂げられたように思えるのです。
子どもを賢くするだけが、教育の目的ではありません。教育はその後の人生に備えるための羅針盤です。過去に何があり、自分たちがどこから来たのかを知るためには、歴史を学ぶ必要があります。数学や科学の知識は、生活の中で活用することができます。語学を学ぶのは、他者と適切にコミュニケーションを取るためです。こうしたスキルは試験に合格するためだけではなく、生きるうえで重要なのです。
さらに言えば、子どもたちが良い人間、幸せな人間になるために、教育が必要です。失敗や挫折にどう向き合い、やる気をどのように保つのか。こうしたことを教えるのは、子どもたちがさまざまな問題を抱える昨今、決して簡単ではありません。それでもなお、教育は私たちの社会においてもっとも重要な営みです――すべてを良い方向に向かわせる力を秘めているのですから。
----------
ルーシー・クレハン(Lucy Crehan)
教育研究者
オックスフォード大学で心理学と哲学を学ぶ。自閉症児の教育に1年間携わったのち、ロンドン・サウスウェストの中等学校で3年間教鞭を執る。ケンブリッジ大学で教育学の修士号を取得。その後、2年間にわたって世界を旅してまわり、各国の教育を実地調査した。帰国後、クラウドファンディングで資金を募り、調査の記録を『日本の15歳はなぜ学力が高いのか? 』(2016)にまとめたほか、世界各国の教師の昇進コースに関する報告書をユネスコに提出した。イギリスのNPO団体「エデュケーション・ディベロップメント・トラスト」に所属。