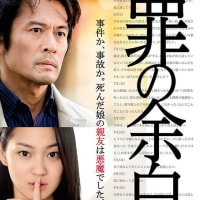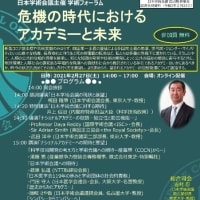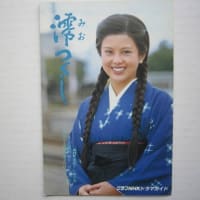ずばり、
評論家的レビューではテーマは出てこない。
それが研究史の羅列。
「変革者としてレビュー」ができるかどうかがポイント。
「これまでの他の多くの研究でこういうことが分かった、ああいうことも分かった。しかし、このことが分かんないと問題になっている。だからそれに取り組んで、答えを得た」
と書いたとしよう。
これってどう?
ん。ま、多分、レビューにはなっているね。
でも、きっとこのような論文はめちゃめちゃ多いよ。しかも同じテーマで。
なぜなら、解かれていない問題は皆知っている。
そのようなテーマはきっと解くための方法や論理に問題があるので、解かれていない。
しかも注目されているテーマであればあるほど、とんでもない競争の中にある。
そのときには、なぜ解けなかったのかということに焦点を当てた独創的レビューが必要で、論文の焦点は答えだけではなく方法にある。
このような場合、答えを得たら、投稿するためには一刻の猶予も許されない。
先に出されたら知的先取権はなくなり、幸運にも発行されても2ばんせんじ。
こういうのを既問未答問題という。
それに対して「変革の視点」によるレビューから出てくる醍醐味の1つに、まだ誰も問いかけていない、しかし自然を理解するために本質的なとてつもない「問い」に気がつく事があることである。
このような問いは、実は革命を起こす。
本質的であればあるほど、常識を覆す可能性がある。
すなわち質の高いレビューとは実はテーマの発掘なのである。
さて、あなたが書こうとしているテーマとレビューの関係はどうなっているかな?
というのでintroをうまく書けるかどうかは論文の雌雄を決するのである。
そして、これをうまくかけたら、あとはすらすら、といくはずである。
どこかで生き詰まっているとしたら、それは十中八九、introがうまくかけていないんだね。
さて、次は方法と記載データに関して。
評論家的レビューではテーマは出てこない。
それが研究史の羅列。
「変革者としてレビュー」ができるかどうかがポイント。
「これまでの他の多くの研究でこういうことが分かった、ああいうことも分かった。しかし、このことが分かんないと問題になっている。だからそれに取り組んで、答えを得た」
と書いたとしよう。
これってどう?
ん。ま、多分、レビューにはなっているね。
でも、きっとこのような論文はめちゃめちゃ多いよ。しかも同じテーマで。
なぜなら、解かれていない問題は皆知っている。
そのようなテーマはきっと解くための方法や論理に問題があるので、解かれていない。
しかも注目されているテーマであればあるほど、とんでもない競争の中にある。
そのときには、なぜ解けなかったのかということに焦点を当てた独創的レビューが必要で、論文の焦点は答えだけではなく方法にある。
このような場合、答えを得たら、投稿するためには一刻の猶予も許されない。
先に出されたら知的先取権はなくなり、幸運にも発行されても2ばんせんじ。
こういうのを既問未答問題という。
それに対して「変革の視点」によるレビューから出てくる醍醐味の1つに、まだ誰も問いかけていない、しかし自然を理解するために本質的なとてつもない「問い」に気がつく事があることである。
このような問いは、実は革命を起こす。
本質的であればあるほど、常識を覆す可能性がある。
すなわち質の高いレビューとは実はテーマの発掘なのである。
さて、あなたが書こうとしているテーマとレビューの関係はどうなっているかな?
というのでintroをうまく書けるかどうかは論文の雌雄を決するのである。
そして、これをうまくかけたら、あとはすらすら、といくはずである。
どこかで生き詰まっているとしたら、それは十中八九、introがうまくかけていないんだね。
さて、次は方法と記載データに関して。