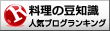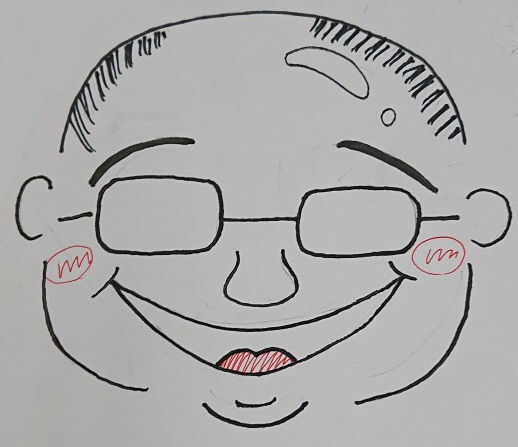【前の答】バター
Q1,さて、牛酪は何と読むのでしょう?
c,バター
Q2,誰がボクをヨーロッパに伝えるきっかけとなった?
a,アレキサンダー大王
→紀元前4世紀のアレキサンダー大王の東方遠征をきっかけに、
ヨーロッパに伝えられたと言います
Q3,ヨーロッパに伝わる途中、ボクの用途が変わりました。何でしょう?
c,消毒用
→傷口に塗ることで、化膿止めとして使われていました
【今日の話】
西京みそは普通のみそに比べると塩分が控えめで(4%~6%)、甘味が際立っています。
みそ漬けにした時に魚の色をそのままに残し、他のみそに比べ塩分が少なめで塩辛さがないので、
魚が持つ本来の味を損なわずに最適だそうです。
このみそを育んだのが京都の水。
かつて、巨椋池(おぐらいけ)があった京都は、地下にミネラル豊富な水瓶があるのです。
ということで、タイトルの空欄には「水」が入ります。
Q1,西京みその「西京」の由来は?
a,東の都東京に対し、西の都西京
b,京都府西京区
c,右京の別名
Q2,西京みそが分類されるのは?
a,白みそ b,合わせみそ c,赤みそ d,酢みそ
Q3,西京漬けは、西京みそを何等で伸ばしてつけ込んだものですか。
a,酒 b,みりん c,砂糖水 d,塩水
Q4,西京漬けはいつ頃からつくられていたでしょうか?
a,平安時代 b,室町時代 c,江戸時代
Q1,さて、牛酪は何と読むのでしょう?
c,バター
Q2,誰がボクをヨーロッパに伝えるきっかけとなった?
a,アレキサンダー大王
→紀元前4世紀のアレキサンダー大王の東方遠征をきっかけに、
ヨーロッパに伝えられたと言います
Q3,ヨーロッパに伝わる途中、ボクの用途が変わりました。何でしょう?
c,消毒用
→傷口に塗ることで、化膿止めとして使われていました
【今日の話】
西京みそは普通のみそに比べると塩分が控えめで(4%~6%)、甘味が際立っています。
みそ漬けにした時に魚の色をそのままに残し、他のみそに比べ塩分が少なめで塩辛さがないので、
魚が持つ本来の味を損なわずに最適だそうです。
このみそを育んだのが京都の水。
かつて、巨椋池(おぐらいけ)があった京都は、地下にミネラル豊富な水瓶があるのです。
ということで、タイトルの空欄には「水」が入ります。
Q1,西京みその「西京」の由来は?
a,東の都東京に対し、西の都西京
b,京都府西京区
c,右京の別名
Q2,西京みそが分類されるのは?
a,白みそ b,合わせみそ c,赤みそ d,酢みそ
Q3,西京漬けは、西京みそを何等で伸ばしてつけ込んだものですか。
a,酒 b,みりん c,砂糖水 d,塩水
Q4,西京漬けはいつ頃からつくられていたでしょうか?
a,平安時代 b,室町時代 c,江戸時代