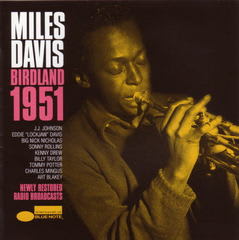以前「物を捨てられない男」と自身を称したことがありましたが、これはどうも母親譲りの性格らしく、母の「いらない物整理」はここ数年幾度となく繰り返されてきました。
そんな中、昨日は自分の部屋の押し入れを整理したのだそうで、そこから出てきたのが必要性を疑う父の遺品の数々。
まっ、それでも母の思い出の品なら「捨てる必要は無いんじゃないの」と言ったのですよ、そしたら
「○○(私です)、こんなのも出てきたから、かあちゃんには分かんないし、あんたいるかいらないか見てくれっか」
と、段ボールいっぱいのレコードを渡されました。
父が亡くなって十数年が過ぎた今、記憶の扉の何処を開いても、父がレコードを聴いている姿は思い浮かびません。何時何処でどうやって聴いていたのか?

まず目立ったのは、ど~んと箱入りの国際情報社発刊『日本民謡集 ふるさとのうた』という全16枚のLP全集でありまして
「おいおい、今どき小学校の音楽室にもこんなもんは無いんじゃないの?」
一枚取って盤面を見てみると、ほとんど聴いた形跡もありません。おそらくは会社のお付き合いか何かで買わされた類か、こういったセット物好き(これは先日遊びに来た姉に遺伝の兆候が見られますが)の血が騒いだか、どちらかでありましょうが、なんだかもったいないような・・・・
あとはEP盤も含んだ諸々。
「どれどれ、春日八郎に村田英雄、ふむふむ、日野てる子、倍賞千恵子、フランク永井に園まり、北島三郎・・・・・・ひぇ~~」
一貫性が全くありませんし、誰かが好きで買い集めたという風もない、さほど興味もなく買ってしまったという感じでしょうか。
そんな中、ちょっと嬉しいというか、興味が湧いたのは、EP盤2枚、西田佐知子と緑川アコであります。

小学校1年生の頃、近くに父方の伯母夫婦が住んでおりました。義理の叔父は土木建築業でそこそこの会社を経営しておりまして、まっあの頃は地方の何処にでもいた「土建成り上がり小金持ち?」だったわけで、子どもがいないにもかかわらず、レーシングカーのセットなんてものを持ってたんですねぇ、私はそれを借りるのが楽しみでたまに遊びに行っていました。そんな時、いつもバックに流れていたのが西田佐知子だったんです。(なんと当時ステレオを叔父は持っていました。)
♪ アカシヤの雨に打たれて このまま 死んでしまいたい ・・・・♪
(違う違う、アカシア)
今でも、歌詞を覚えています。
その西田佐知子の「コーヒールンバ」が出てきたのです。
ほら、陽水がカバーしたあれです。(ザ・ピーナッツも歌っていましたが、陽水がカバーしたのは西田佐知子が歌った歌詞でした。)
昨晩ヘッドホンで聴いてみたら、なんとも良い声ですねぇ、関口宏一人のものにしておくにはもったいない(笑)
緑川アコは「夢は夜ひらく」でありますよ。
♪ 七に二をたしゃ 九になるが
九になりゃまだまだ いい方で
四に四をたしても 苦になって
夢は夜ひらく ♪
お~~といかん、これは三上寛だ(笑)
♪ いのち限りの 恋をした
たまらないほど 好きなのに
たった一言 いえなくて
夢は夜ひらく ♪
こっちが、緑川アコ・バージョンでありました。
この歌もいろんな人がカバーしていましたよねぇ、私は藤圭子の「圭子の夢は夜ひらく」世代ですかね。(印象に残っているのは、三上寛なんですが...笑)
♪ 赤く咲くのは けしの花
白く咲くのは 百合の花
どう咲きゃいいのさ この私
夢は夜ひらく ♪
いちいち歌うこたぁないって?
ともかく、父のレコードが出てきて、これをどうしようかと思案中です。
テープなんていうんだったら処分もやぶさかではないのですが、レコードとなるとねぇ・・・・
おそらくは母親譲りの「物を捨てられない性格」が、このレコードも守り続ける事へとなるのでしょうけどね。
♪ 夢は夜ひらく 唄っても
ひらく夢など あるじゃなし
まして夜など くるじゃなし
夢は夜ひらく ♪
「うるさ~~~い!!!!!!」
「・・・・・・・・・・!?」
昭和歌謡に夢をひらいても、大声で歌っちゃいけませんわね。(笑)
さて、今日の一枚は、バド・パウエルです。
アル・ヘイグを紹介したら、やっぱバドでしょ、てんで考えてみたのですが、おそらくバドの所有アルバムはほとんど紹介済みだったような・・・・・・
いやいやいや、このアルバムを紹介していなかったとは、これも「こんなメジャーを紹介しても・・・」みたいな変な考えがはたらいたのでありましょうか?
このアルバムは、今は亡き我が親友I君が、最も愛した一枚でます。
彼の部屋で何度「クレオパトラの夢」を聴いたことか・・・・・
すでに過去の人となりつつあったバド、フランシス・ウルフが撮影した写真を見て、「今度のアルバムのタイトルはTHE SCENE CHANGESにしよう。」
年以上に衰えを感じさせる自分自身、それをのぞき見る息子アール・ダグラス・ジョン・パウエル、この写真にバドは何を感じとったのでしょうか?
超人気盤ですから、説明は不要でしょう。「クレオパトラの夢」を聴きながら、「親友の夢」でも今晩は見ましょうか、まさに「夢は夜ひらく」ってとこかな。
THE SCENE CHANGES / THE AMAXING BUD POWELL Vol.5
1958年12月29日録音
BUD POWELL(p) PAUL CHAMBERS(b) ART TAYLOR(ds)
1.CLEOPATRA'S DREAM
2.DUID DEED
3.DOWN WITH IT
4.DANCELAND
5.BORDERICK
6.CROSSIN' THE CHANNEL
7.COMIN' UP
8.GETTIN' THERE
9.THE SCENE CHANGES