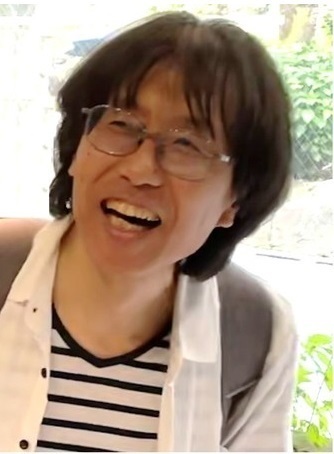『日経サイエンス』の4月号に、サイエンスライターのクラウディア・ウォリスが、
自閉症治療の現場も、ニューロダイバーシティ運動を受けて、変化の波が生じていることをレポートしています[Wallis 2022=2023,p.6]。
これまで自閉症治療は、自閉症の症状をなくし、定型的な行動に合わせて、自閉症らしく見えないようにすることを強いるのを
「至適アウトカム」としてきたわけですが、
今や自閉症の症状はむしろ尊重し、どう扱うかは患者本人と家族とが自らの幸福に寄与するよう自身で決定すべきことへと変わりつつあるということです。
デューク大学の自閉症・脳発達センター所長G・ドーソンは、ある10代の患者が「アイコンタクトを保つ練習なんかもうしたくない」と訴えてきたけれど、
それで構わないのだと明言しています;
また同様に、「体を前後に揺らす方が落ち着くという人がいるなら、それを認めればいいのです。異なるあり方を社会が受け入れるべきだと私は思います」
と述べています[Dawson et als.2022;Wallis 2022=2023,p.6]。
自閉症セルフ・アドボカシー・ネットワークの共同創設者アリ・ネーマンによれば、
あまりにも多くのセラピストが、自閉症者たちに、定型的な見かけを試すテストにパスする方法を“教える”ことに注力しているのが現状だというのですが、
でもその結果当人はどうなっているかといえば、自閉症とみなされまいとして、定型行動から外れていないかチェックするのに
エネルギーと認知力とを使い果たしてしまうというのが実態だといいます[Ne’eman 2021;Wallis 2022=2023,p.6]。
それどころか、自閉症とみなされないよう努めることで、自殺率の高さにも関連することすら見い出されているのです[Cassidy et als.2018;Wallis
2022=2023,p.6]。
「治す」とは何をすることなのか、本当に問われているのではないでしょうか?
実際、その一方では、すでにこのブログでも以前に書いたように(→ニューロダイバーシティの登場!)、
臨床現場にニューロダイバーシティが入ってくるとき、この概念の意味を全く曲解して、
自閉症者たちを「ニューロダイバーシティを持つ人たち」(people with neurodiversity)と呼ぶ医師やセラピストも少なくありません。
・・・これは「ダイバーシティ」の概念の意味をそもそもよく理解しておらず、まるで「ニューロダイバーシティ」ということを
まるで1つの病気や障害の名前のように捉えているのですね。
こうした危険はすでにニューロダイバーシティ運動の火付け役だったジュディ・シンガーが指摘していたことでした[Singer 2019]。
すなわち、「ニューロダイバーシティ」はすべての人のものです。すべての人が「ニューロダイバース」です。
その一員として、自閉症も非自閉症者も、ともにそのままに肯定されるのです。
<文献>
Cassidy, S., Bradley, L., Shaw, R. & Baron-Cohen, S., 2018 Risk markers for suicidality in autistic adults, in Molecular Autism, vol.9, article42, pp.1-14.
Dawson, G., Franz, L., & Brandsen, S., 2022 At a Crossroads—Reconsidering the Goals of Autism Early Behavioral Intervention From a Neurodiversity Perspective, in JAMA
Pediatrics, vol.176, no.9, pp.839-40.
Ne’eman, A., 2021 When Disability is Defined by Behavior,Outcome Measures should not Promote “Passing”, in AMA Journal of Ethics, vol.23, no.7, pp.E569-75.
Singer, J., 2019 Reflections on Neurodiversity. https://neurodiversity2.blogspot.com/
Wallis, C., 2022 Rethinking Autism Therapy, in Scientific American, vol.327, no.6, p.25.=編集部訳、2023「自閉症治療再考――ニューロダイバーシティとしてとらえ直す」『日
経サイエンス』第53巻4号、p.6。