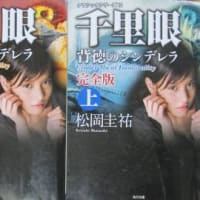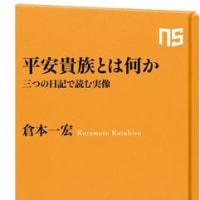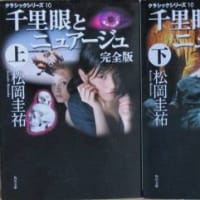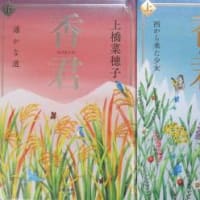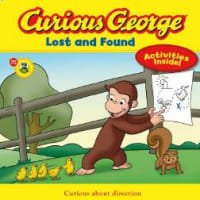昨年8月に、著者の『広重ぶるう』を読んだことがきっかけで、作品を読み継いでいきたい作家の一人となった。本書のタイトルを目にしたことで興味を抱き先に読むことにした。この作品は「小説すばる」に2018年5月号~2021年8月号にほぼ隔月で連載された後、大幅に加筆・修正されて2022年7月に単行本として刊行されている。
「本作品は史実をもとにしたフィクションです」と末尾に明記してある。一言でいえば、伝記風小説。誰についての? 第一章の冒頭部分に出てくる大川カシについて。後に、若松賤子というペンネームで翻訳小説を出版する女性である。巌本善治と結婚した人。
これだけでわかる人がどれだけいるだろうか。私は知らなかった。
手許に国語と日本史について高校生向けの学習参考書がある。それを調べてみたが、明治前期の明治文学の解説、明治文化の解説の中に、若松賤子と巌本善治の名前は出ていない。だが、時代の風潮には屈せず、明治時代前期に女性の地位向上、女子教育の必要性について、出版と教育という分野を通じて活動していた二人だった。私にとっては二人の人物を知る機会になった。
大川カシは成人したのち、島田姓を名乗り母校で教師の道を歩み始める。
カシは、海軍将校と一旦婚約し、周りの人々から祝福される。だが、その婚約を破棄するという選択をする。当時の社会風潮は「良妻賢母」志向であり、夫につくし家庭を守ることを当然視していた。カシは「良妻賢母」の型にはめられることから独立した自らの道を歩み出していく。そして後に、『女学雑誌』の編集長であり、東京府の麹町にある明治女学校の教頭をしている巌本善治と出会い、巌本善治と考え方の上で意気投合できる部分を感じ始める。巌本と結婚し家庭を築きながら、女性の自立した活動と社会への参画をめざすカシは、作家としての道を歩む選択をとる。まず『女学雑誌』に作品を発表しつづけることが作家への契機となる。
カシは若松賤子の名でバアネットの作品を翻訳し『小公子』と題して世に問う。二葉亭四迷が『浮雲』を言文一致の作品として世に問うた。若松賤子は『小公子』で原文一致の翻訳にチャレンジした。『小公子』は現在、岩波文庫の一冊になっている。
つまり、ここで描き出されるのは、大川カシ=島田カシ=巌本カシ=若松賤子の生き様であり、併せて巌本善治の生き様である。
この作品、基本的には、カシの視点からストーリーが綴られていく。
読み始めて、<第二章 会津の記憶>で、カシの元の姓は実は松川であることがわかる。カシは幼少期からある意味で特異な経験をした人だった。
カシは元治元年(1864)3月1日に京の都にある会津藩屋敷で生まれた。京の都でカシの父は島田姓を名乗っていた。1868年に鳥羽伏見の戦いが起こる。カシは身籠もっている母に連れられ会津若松に帰郷する。会津で妹のミヤが生まれる。だが、官軍の東征により、会津で戦争が始まる。その渦中での体験と戦後の父母と一緒の生活がカシの幼少期の原体験となる。だが、数え8つで、カシは大川の養女に出される。大川は横浜の生糸問屋の番頭をしていた人である。カシにとり、会津は家族一緒に過ごせた思い出の時期であるとともに悲惨な記憶が残る時期でもあった。カシの人生の第1ステージは、前半が実父母との生活、後半が養父母との生活である。
このストーリーは、横浜山手178番地に新たに開校された寄宿舎のある学び舎、フェリス・セミナリーから始まる。開校の推進者はキダー先生とその夫・宣教師のローセイ先生である。カシは、この学校の給費生という立場で先生の手伝いをしつつ、寄宿生の一員として、またこの学び舎をわがホームとして成長していく。つまり、カシの人生の第2ステージの始まりとなる。このプロセスで、上記したカシの会津での記憶、大川の養女となっての横浜での生活など-第1ステージ-が回想されて行く。
この第2ステージではフェリス・セミナリーをホームとする境遇のカシとその成長が描き出される。これは、時代背景として、現在のフェリス女学院の建学時期の状況を描くことにもなっていく。その建学の精神と学び舎の状況などが描き込まれていく。明治時代前期に始まったキリスト教伝道者の設立したミッション・スクールの始まりの一事例と言えるだろう。
キダー先生を親のように慕いながら、この学び舎でカシが何を考え、どのように行動するかに読者は興味津々となっていくことと思う。寄宿舎で同室の季子と一緒に、カシは己の意志で受洗し、キリスト者となる。山内季子はカシより6歳上で入学した時に教師も兼ねている女性だった。
1882(明治15)年6月、カシは正式な卒業生、それもフェリス・セミナリーの初めての卒業生となる。
この後、カシの人生の第3ステージがこの学び舎で始まる。寄宿学校に残り、和文教師として採用され、教師としての生活が始まる。「フェリス・セミナリーは、女性が世に出て、男性と同等に、互いに尊敬をもって接することができる教養と知識を身につけさせることを旨としている。無学無知が、女性を貶める要因のひとつであるならば、まず女性自身が意識をし、自らを高める必要がある」(p146)カシは己に課せられた責任を強く感じ始める。
この第3ステージにおいて、上記したカシの婚約と破棄に到るプロセスがカシの人生にとって選択の岐路になる。一方で、カシは1885(明治18)年7月に創刊された『女学雑誌』に翌年から若松しづの名で投稿を始める。
その後に、巌本との出会いが生まれる。おもしろい出会いと二人の関係の発展は、読者にとってもおもしろい。その一方で、カシが労咳と診断される事態が発生する。入院生活もする。
カシの人生の第4ステージは、巌本善治との結婚である。巌本はカシに労咳の持病があることを承知の上で、カシに巌本流のプロポーズをした。
巌本自身もキリスト者である。『女学雑誌』の編集長であり、明治女学校の教頭を兼ねていた。明治女学校は日本人でキリスト教の牧師となった木村熊二と妻の鐙子が設立した。日本のキリスト者により、日本人の資金・寄付金で創設された学校である。
この第4ステージは、カシの人生において、彼女が主体的に選び取った己の生き方を推し進めて行く時期となる。巌本との家庭、ホームを築く一方、作家として生きる道に入って行く。
カシがどのような生き方をするか。また巌本善治がどのような生き方をするか。
本書でお楽しみいただきたい。例えば、新婚旅行で行く大宮の宿で、カシは善治に対し、アメリカの女性文学者アリス・ケアリーの書いた「花嫁のベール」という詩を英文のままで贈るのだ。その内容がふるっている。カシらしい選択である。お楽しみに。
カシの人生の結末にだけふれておこう。1896(明治29)年2月10日、カシは4人目の子を身籠もったままで、死を迎える。
本文は日付の続きに、「カシは澄み渡る青空に翼を広げていた。ああ、わたしはいま、空を駆けている」(p390)が出てくる。本書のタイトルはこの一文に由来するようだ。
その後に、善治とカシの交わす言葉が記されていく。ラスト・シーンは涙を禁じ得ない。
一つ補足しておきたい。妹のみやがカシをサポートしたということ。桜井章一郎が『小公子』の後編の刊行に尽力したことである。当時、桜井は明治女学校の教師をしていた。
明治初期に、女性の教育と女性の活躍について、その活動の一端を担い行動する一方で、自らの生き方として実践した人が居たことを本書で知る機会となった。
単行本の表紙につづく裏表紙には、横浜山手178番地に開校されたフェリス・セミナリーの校舎のイラストが描かれている。当時の雰囲気が感じられる図である。
ご一読ありがとうございます。
補遺 本書を読み、ネット検索してみた。調べるといろいろと学ぶことができる。
若松賤子 近代日本人の肖像 :「国立国会図書館」
若松賤子 :ウィキペディア
若松賤子の略歴 偉人伝 :「会津への夢街道」
若松賤子訳 『小公子』本文 『小公子』の部屋 :「ことばへの窓」(岐阜大学)
忘れ形見 若松賤子 :「青空文庫」
忘れかた美 若松賤子訳 桜井鴎村編 :「国立国会図書館デジタルコレクション」
巌本善治 :ウィキペディア
女学雑誌 :ウィキペディア
桜井彦一郎 ⇒ 桜井鴎村 :ウィキペディア
フェリスの原点 建学の精神 :「フェリス女学院大学」
明治女学校 :ウィキペディア
明治女学校跡 :「東京豊島区の歴史」
明治女学校の世界 藤田美実 :「松岡正剛の千夜千冊」
染井霊園 :ウィキペディア
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
拙ブログ「遊心逍遙記」に記した次の著者作品に対する読後印象記もお読みいただけるとうれしいです。
『広重ぶるう』 新潮社
『我、鉄路を拓かん』 PHP
「本作品は史実をもとにしたフィクションです」と末尾に明記してある。一言でいえば、伝記風小説。誰についての? 第一章の冒頭部分に出てくる大川カシについて。後に、若松賤子というペンネームで翻訳小説を出版する女性である。巌本善治と結婚した人。
これだけでわかる人がどれだけいるだろうか。私は知らなかった。
手許に国語と日本史について高校生向けの学習参考書がある。それを調べてみたが、明治前期の明治文学の解説、明治文化の解説の中に、若松賤子と巌本善治の名前は出ていない。だが、時代の風潮には屈せず、明治時代前期に女性の地位向上、女子教育の必要性について、出版と教育という分野を通じて活動していた二人だった。私にとっては二人の人物を知る機会になった。
大川カシは成人したのち、島田姓を名乗り母校で教師の道を歩み始める。
カシは、海軍将校と一旦婚約し、周りの人々から祝福される。だが、その婚約を破棄するという選択をする。当時の社会風潮は「良妻賢母」志向であり、夫につくし家庭を守ることを当然視していた。カシは「良妻賢母」の型にはめられることから独立した自らの道を歩み出していく。そして後に、『女学雑誌』の編集長であり、東京府の麹町にある明治女学校の教頭をしている巌本善治と出会い、巌本善治と考え方の上で意気投合できる部分を感じ始める。巌本と結婚し家庭を築きながら、女性の自立した活動と社会への参画をめざすカシは、作家としての道を歩む選択をとる。まず『女学雑誌』に作品を発表しつづけることが作家への契機となる。
カシは若松賤子の名でバアネットの作品を翻訳し『小公子』と題して世に問う。二葉亭四迷が『浮雲』を言文一致の作品として世に問うた。若松賤子は『小公子』で原文一致の翻訳にチャレンジした。『小公子』は現在、岩波文庫の一冊になっている。
つまり、ここで描き出されるのは、大川カシ=島田カシ=巌本カシ=若松賤子の生き様であり、併せて巌本善治の生き様である。
この作品、基本的には、カシの視点からストーリーが綴られていく。
読み始めて、<第二章 会津の記憶>で、カシの元の姓は実は松川であることがわかる。カシは幼少期からある意味で特異な経験をした人だった。
カシは元治元年(1864)3月1日に京の都にある会津藩屋敷で生まれた。京の都でカシの父は島田姓を名乗っていた。1868年に鳥羽伏見の戦いが起こる。カシは身籠もっている母に連れられ会津若松に帰郷する。会津で妹のミヤが生まれる。だが、官軍の東征により、会津で戦争が始まる。その渦中での体験と戦後の父母と一緒の生活がカシの幼少期の原体験となる。だが、数え8つで、カシは大川の養女に出される。大川は横浜の生糸問屋の番頭をしていた人である。カシにとり、会津は家族一緒に過ごせた思い出の時期であるとともに悲惨な記憶が残る時期でもあった。カシの人生の第1ステージは、前半が実父母との生活、後半が養父母との生活である。
このストーリーは、横浜山手178番地に新たに開校された寄宿舎のある学び舎、フェリス・セミナリーから始まる。開校の推進者はキダー先生とその夫・宣教師のローセイ先生である。カシは、この学校の給費生という立場で先生の手伝いをしつつ、寄宿生の一員として、またこの学び舎をわがホームとして成長していく。つまり、カシの人生の第2ステージの始まりとなる。このプロセスで、上記したカシの会津での記憶、大川の養女となっての横浜での生活など-第1ステージ-が回想されて行く。
この第2ステージではフェリス・セミナリーをホームとする境遇のカシとその成長が描き出される。これは、時代背景として、現在のフェリス女学院の建学時期の状況を描くことにもなっていく。その建学の精神と学び舎の状況などが描き込まれていく。明治時代前期に始まったキリスト教伝道者の設立したミッション・スクールの始まりの一事例と言えるだろう。
キダー先生を親のように慕いながら、この学び舎でカシが何を考え、どのように行動するかに読者は興味津々となっていくことと思う。寄宿舎で同室の季子と一緒に、カシは己の意志で受洗し、キリスト者となる。山内季子はカシより6歳上で入学した時に教師も兼ねている女性だった。
1882(明治15)年6月、カシは正式な卒業生、それもフェリス・セミナリーの初めての卒業生となる。
この後、カシの人生の第3ステージがこの学び舎で始まる。寄宿学校に残り、和文教師として採用され、教師としての生活が始まる。「フェリス・セミナリーは、女性が世に出て、男性と同等に、互いに尊敬をもって接することができる教養と知識を身につけさせることを旨としている。無学無知が、女性を貶める要因のひとつであるならば、まず女性自身が意識をし、自らを高める必要がある」(p146)カシは己に課せられた責任を強く感じ始める。
この第3ステージにおいて、上記したカシの婚約と破棄に到るプロセスがカシの人生にとって選択の岐路になる。一方で、カシは1885(明治18)年7月に創刊された『女学雑誌』に翌年から若松しづの名で投稿を始める。
その後に、巌本との出会いが生まれる。おもしろい出会いと二人の関係の発展は、読者にとってもおもしろい。その一方で、カシが労咳と診断される事態が発生する。入院生活もする。
カシの人生の第4ステージは、巌本善治との結婚である。巌本はカシに労咳の持病があることを承知の上で、カシに巌本流のプロポーズをした。
巌本自身もキリスト者である。『女学雑誌』の編集長であり、明治女学校の教頭を兼ねていた。明治女学校は日本人でキリスト教の牧師となった木村熊二と妻の鐙子が設立した。日本のキリスト者により、日本人の資金・寄付金で創設された学校である。
この第4ステージは、カシの人生において、彼女が主体的に選び取った己の生き方を推し進めて行く時期となる。巌本との家庭、ホームを築く一方、作家として生きる道に入って行く。
カシがどのような生き方をするか。また巌本善治がどのような生き方をするか。
本書でお楽しみいただきたい。例えば、新婚旅行で行く大宮の宿で、カシは善治に対し、アメリカの女性文学者アリス・ケアリーの書いた「花嫁のベール」という詩を英文のままで贈るのだ。その内容がふるっている。カシらしい選択である。お楽しみに。
カシの人生の結末にだけふれておこう。1896(明治29)年2月10日、カシは4人目の子を身籠もったままで、死を迎える。
本文は日付の続きに、「カシは澄み渡る青空に翼を広げていた。ああ、わたしはいま、空を駆けている」(p390)が出てくる。本書のタイトルはこの一文に由来するようだ。
その後に、善治とカシの交わす言葉が記されていく。ラスト・シーンは涙を禁じ得ない。
一つ補足しておきたい。妹のみやがカシをサポートしたということ。桜井章一郎が『小公子』の後編の刊行に尽力したことである。当時、桜井は明治女学校の教師をしていた。
明治初期に、女性の教育と女性の活躍について、その活動の一端を担い行動する一方で、自らの生き方として実践した人が居たことを本書で知る機会となった。
単行本の表紙につづく裏表紙には、横浜山手178番地に開校されたフェリス・セミナリーの校舎のイラストが描かれている。当時の雰囲気が感じられる図である。
ご一読ありがとうございます。
補遺 本書を読み、ネット検索してみた。調べるといろいろと学ぶことができる。
若松賤子 近代日本人の肖像 :「国立国会図書館」
若松賤子 :ウィキペディア
若松賤子の略歴 偉人伝 :「会津への夢街道」
若松賤子訳 『小公子』本文 『小公子』の部屋 :「ことばへの窓」(岐阜大学)
忘れ形見 若松賤子 :「青空文庫」
忘れかた美 若松賤子訳 桜井鴎村編 :「国立国会図書館デジタルコレクション」
巌本善治 :ウィキペディア
女学雑誌 :ウィキペディア
桜井彦一郎 ⇒ 桜井鴎村 :ウィキペディア
フェリスの原点 建学の精神 :「フェリス女学院大学」
明治女学校 :ウィキペディア
明治女学校跡 :「東京豊島区の歴史」
明治女学校の世界 藤田美実 :「松岡正剛の千夜千冊」
染井霊園 :ウィキペディア
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
拙ブログ「遊心逍遙記」に記した次の著者作品に対する読後印象記もお読みいただけるとうれしいです。
『広重ぶるう』 新潮社
『我、鉄路を拓かん』 PHP