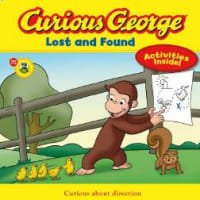此の世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたる事も 無しと思へば
藤原道長が全盛の時期に詠んだ歌。望月は満月のこと。私は道長がまさに満月の夜に己の境地を満月に喩えて高らかに詠んだ歌だと思っていた。
ここしばらく、地元の源氏物語ミュージアムが企画する源氏物語の連続講座を、地の利を生かして毎年受講してきている。その講座のなかで、著者が講師として登壇される機会がある。その際のある講義の途中で、道長が「我が世の望月」を歌ったのは、満月の夜ではなく十六日であり、自然現象としての空の月は欠けていたのです。ではなぜ、歌に望月と詠んだのか。その点について今考えをまとめているところですと触れられたことがあった。それが気になっていた。新聞広告で本書の出版、副題に「我が世の望月」とは何だったのかとあるのを読み、気になっていた事項が語られているかも・・・と思い、早速読んだ。私の関心事項は、第12章「我が世の望月」と題して、論じられている。関心事項についの読み解き方を、なるほどと理解できて、過年度より持ち越していた疑問が解けた。
本書の位置づけは著者が「あとがき」で明記されている。最初にその点をご紹介しておこう。本書のタイトルを「道長ものがたり」とされている。読み始めると、史実だけに基づいた藤原道長伝記とも評論とも少し違うな・・・ということを感じ始めた。歴史物語とされる『大鏡』や『栄花物語』に描かれた道長等についての一節が随時引用され、著者の読み解きが加えられて行く。著者は、幸運ともてはやされた道長の内心は、幸せに満ちていたのかどうか、どうだったのか。この疑問を抱いていたと言う。それゆえ「本書で道長の心を辿ろうと思った」(o290)と語る。そして、「本書のタイトルを『道長ものがたり』としたのも、ゴールに置いたのが史実よりも彼の心であることによる。読者の方々にも、物語を読むように、彼の心に寄り添ってほしいと考えたのだ。」(p291)と。 さらに、その続きに以下の文が続く。
「結果として、従来彼がまといがちであった『傲慢な権力者』の顔一辺倒ではなく、怨霊におびえ、病気に苦しみ、身内の不幸に泣くという弱い部分も分かってもらえたと思う」(p291)と。つまり、政治家道長が何をなし、どのように権謀術数を働かせたのかは、道長を知るための重要な側面である。一方、コインの両面として、源倫子を正妻とし、源明子も妻にして、数多くの娘・息子を持つ生活者としての道長の側面がある。この側面をパラレルに描き出すことで、道長という人物をトータルにとらえた上で、彼の心理心情に迫ろうとしている。様々なエピソードが史実・物語の両面から捕らえ直す形で織り込まれていくので、読みやすい。要所要所で系図が掲載されているので、その時点時点での人間関係がわかりやすい。系図による図解のメリットが発揮されている。
政治家道長、生活者道長の両面は、本書の構成をご紹介すれば、少しイメージしやすくなると思う。
[第一章 超常的「幸ひ」の人・道長]
道長30歳で公卿の時に、長兄・道隆と次兄・道家が病死し、上席公卿たちも同時期に流行の疫病で死亡が相次ぐ。道隆の息子で道長のライバルであった伊週(コレチカ)は自滅の道を歩む。結果的に権力の座が道長に転がり込んでくる。道長は強運の持ち主だった。この点がまず押さえられる。だが、その一方で、道長が源雅信の女倫子を妻にし、倫子という同志を得ていた側面を著者は重視する。まずは雅信のバックアップという点を押せている。
平安時代の言葉では強運を「幸い」と呼んだという。
「あとがき」を読むと、著者はこの「幸い」について、次のように述べている。
「<幸い>は、幸せとは一致しないのである。<幸ひ>は結婚、出産、あるいは仕事など、世俗的で目に見える事柄に関わり、あくまでも世間が認めるような外見の幸運を言うに過ぎない」(p290)と。この第一章では、他人から眺めた道長の外見的な強運をまずとらえている。
[第二章 道長は「棚から牡丹餅」か?]
長兄・道隆が娘の定子を一条天皇の中宮とした時期に、道長は中宮大夫という定子の事務方長官の職にあったという。本書で初めて当時の道長の位置を知った。この章では道長が虎視眈々と雌伏する時期の様子が簡潔に語られていく。政治家道長の一面がイメージできる。
[第三章 <疫>という僥倖]
長兄・道隆一家、つまり中関白家と定子の栄華の状況を語り、一方、一条天皇の母后であり実姉である女院・詮子に頼る道長の状況を描写する。道長は中関白家と距離を取り続ける。道隆の持病・飲水病と疫の流行が、道長に強運をもたらす。
裏付ける史料がない部分は、『大鏡』の引用と推測とにより、道長の内心を著者は語っていく。そこに「道長ものがたり」と題する所以があるといえよう。
[第四章 中関白家の自滅]
中関白家の自滅が、結果的に道長が政治家として汚れ役や重責・秘密を背負う立場になっていかざるをえない場に置かれたと著者は語る。「道長はずっとクリーンでスマートな貴公子で、道兼のように修羅場をかいくぐった経験があるようには思えない」(p72)とそれまでの道長について要約する。道長にとり道兼は次兄であり、父・道家のために修羅場をかいくぐてきた人。その道兼もまた長徳元年に病死したのだ。
道長は政治家へと変容していく。著者は「道長は中関白家の失脚を見越して、確信犯的に手を下した。自らの権力保持のために政治の泥に手を染めたのである」(p87)という。それが「長徳の政変」だったと。
この頃から道長にとって「生涯悩ませることになる多種多様な病悩の始まり」(p87)を迎えるというのは皮肉なことでもある。生活者としての道長を知る上で、実に興味深い。
[第五章 栄華と恐怖]
この章で、著者は重要な点を指摘している。一つは紫式部の歌を冒頭に掲げて、その説明の中で紫式部の考えとして指摘していることである。
「怨霊はむしろ自身の内にある。人が疑心暗鬼を抱く限り、怨霊はそこかに生まれる。自らの恐怖心が自分を蝕むというこのシステムからは、誰も逃れられないのである」(p89)
また、道長は病気がたび重なり、長徳4年(998)には出家願望から辞表を一条天皇に提出したという。道長のこういう側面を初めて知った。著者はその道長を支えたのは家族であると記す。その上で、
「道長は自分と家族のためだと信じれば、ひどく冷酷になることができた。そのやり方は、時にいささか感情的に過ぎると思えるほどである。最初にその標的になったのは姪の中宮定子。道長にとって彼女は、入内を前にした彰子の前に立ち塞がる、目障りな敵だった」(p100)と。定子を排除するために、いじめる立場を貫いていくのだ。
さらに、「つまるところ、人生に何を求めるか。その根源的な願いの点で、道長と一条天皇とはすれ違っていた」(p106)点を、明らかにしている。
[第六章 怨霊あらわる]
「幼き人」彰子の入内と中宮定子の出産。第一皇子の誕生である。道長が「二后冊立」に動いた状況とその背景が語られる。
そして、彰子が中宮になった2ヶ月後に、道長が邪気に憑かれたという。こういう類いの史実は初めて知った。この時も、道長は辞表を提出したとか。
[第七章 『源氏物語』登場]
出家後一条天皇に呼び戻された中宮定子は、第三子を出産するが難産により非業の死を遂げた。中宮定子の死後、出家し青年貴族たちがいた。清少納言筆の『枕草子』は定子を美化した。『枕草子』は当時の貴族たちにとり癒やしになる側面があったようだ。それに対抗する形で、『源氏物語』が道長により公に登場する場が生み出される。こういう読み解きの視点を本書で知った。紫式部の登場となる。
もう一つ、『源氏物語』には定子をモデルにした側面も含まれている。この側面への危惧に対して、「学問好きな一条天皇は儒教精神を理想とし、諷喩という文学の方法についていも知っていた。それどころか、臣下には自分を諷喩する詩文を作るように求めるほどだった」(p147)との読み解きがされていて興味深い。
[第八章 産声]
道長邸である「土御門殿」での彰子の出産。その状況と道長がその折、どのような行動をとったのかが、詳細に描写されていく。「物の怪調伏班」がどのように編成され、どのようなことをおこなったのか。具体的な描写がおもしろい。
道長がどれだけ怨霊を恐れていたかがよくわかる。そのために道長が相当な資金を使っていることも推測できる。
[第九章 紫式部「御堂関白道長の妾?」]
この『道長ものがたり』の章立ての中でも、一番読者の興味を惹きつける箇所ではないかと思う。生前の瀬戸内寂聴尼から直接うかがった説も紹介しつつ、著者の見解が展開されている。
紫式部が『紫式部日記』に記すことと、『紫式部集』に記すこととの間には、ニュアンスが異なると著者は指摘する。その上で、著者の見方が述べられている。お楽しみに。
[第十章 主張する女たち]
平安時代の女性は男の言いなりになっていただけではない。自己を主張した女性たちがいたことを著者は重要な点として押さえている。道長との関係でいえば、正妻となった源倫子がまさに主張する女性だったという。それ故に、第一章で「源倫子という同志」という小見出しも出てくるのだろう。
それと、入内以降耐え続けていた彰子が父とは一線を画する<主張する中宮>への変貌を採りあげている。この点も中宮彰子を理解するのに役立つ。
一条天皇の辞世の和歌の解釈、及び、葬儀について、「土葬か、火葬か」という方法についての背景と経緯の説明は、彰子、道長を知る上で読ませどころになっていると思う。研究者たちの定説を踏まえているのか、著者独自の見解なのかは知らない。こういう箇所にも、人の心の動きを知る上で一考の余地があることに気づかされた。
[第十一章 最後の闘い]
新帝・三条天皇の即位は既定の方向であった。それを受け入れた上で、政治家道長が彰子の生んだ第一の皇子を天皇にするために、三条天皇との間でどのように最後の闘いを進めて行ったのか。その背景事情がよく分かる。
三条天皇は一条天皇の在位期間が長かったので、春宮(居貞親王)としての期間が長かった。春宮の時に、道長の父・兼家の娘、綏子が入内している。道長にとっては腹違いの妹にあたる。綏子にまつわるエピソードも紹介されている。道長の扱い方がよく分かる。
[第十二章 「我が世の望月」]
この章で採りあげられる「望月」についての読み解き方が、冒頭で触れたように私の一番の関心事だった。
道長の和歌を聞いた藤原実資の態度と行動は、以前にどこかで読んで知っていた。しかし、この和歌の背景にある意味合いまでは深く考えていなかった。本章を読んで一歩深く歌意を理解できた気がする。この章もまた、お楽しみいただきたい。
[第十三章 雲隠れ]
著者は、小一条院(敦明親王)の女御・延子と彼女の父・藤原顕光の死、さらには道長の明子腹の長女で、敦明親王の女御になった寬子の死、加えて、道長の四女で敦良親王との間の子を出産した後に死ぬ嬉子について、次々と語っていく。その先で、道長自身が死を迎える状況を記す。「実際には、その死は凄絶だった」(p284)という。史料に基づき具体的な事実が記されている。
著者は、「『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルの一人は、藤原道長だろうと言われる」(p263)という見方を道長の死と重ねている。そして、最後に、『栄花物語』における道長の死についての記述を紹介しているところがおもしろい。
本書は、己の死期を悟った道長が長女の上東門院・彰子に送った一首で締めくくられている。最後にこの歌をご紹介しよう。
言の葉も 絶えぬべきかな 世の中に 頼む方なき もみぢ葉の身は
道長という人物にさらに興味が湧いてきた。
NHK大河ドラマ「光る君へ」の中で、道長がどのような人物として登場するのか、楽しみでもある。
ご一読ありがとうございます。
藤原道長が全盛の時期に詠んだ歌。望月は満月のこと。私は道長がまさに満月の夜に己の境地を満月に喩えて高らかに詠んだ歌だと思っていた。
ここしばらく、地元の源氏物語ミュージアムが企画する源氏物語の連続講座を、地の利を生かして毎年受講してきている。その講座のなかで、著者が講師として登壇される機会がある。その際のある講義の途中で、道長が「我が世の望月」を歌ったのは、満月の夜ではなく十六日であり、自然現象としての空の月は欠けていたのです。ではなぜ、歌に望月と詠んだのか。その点について今考えをまとめているところですと触れられたことがあった。それが気になっていた。新聞広告で本書の出版、副題に「我が世の望月」とは何だったのかとあるのを読み、気になっていた事項が語られているかも・・・と思い、早速読んだ。私の関心事項は、第12章「我が世の望月」と題して、論じられている。関心事項についの読み解き方を、なるほどと理解できて、過年度より持ち越していた疑問が解けた。
本書の位置づけは著者が「あとがき」で明記されている。最初にその点をご紹介しておこう。本書のタイトルを「道長ものがたり」とされている。読み始めると、史実だけに基づいた藤原道長伝記とも評論とも少し違うな・・・ということを感じ始めた。歴史物語とされる『大鏡』や『栄花物語』に描かれた道長等についての一節が随時引用され、著者の読み解きが加えられて行く。著者は、幸運ともてはやされた道長の内心は、幸せに満ちていたのかどうか、どうだったのか。この疑問を抱いていたと言う。それゆえ「本書で道長の心を辿ろうと思った」(o290)と語る。そして、「本書のタイトルを『道長ものがたり』としたのも、ゴールに置いたのが史実よりも彼の心であることによる。読者の方々にも、物語を読むように、彼の心に寄り添ってほしいと考えたのだ。」(p291)と。 さらに、その続きに以下の文が続く。
「結果として、従来彼がまといがちであった『傲慢な権力者』の顔一辺倒ではなく、怨霊におびえ、病気に苦しみ、身内の不幸に泣くという弱い部分も分かってもらえたと思う」(p291)と。つまり、政治家道長が何をなし、どのように権謀術数を働かせたのかは、道長を知るための重要な側面である。一方、コインの両面として、源倫子を正妻とし、源明子も妻にして、数多くの娘・息子を持つ生活者としての道長の側面がある。この側面をパラレルに描き出すことで、道長という人物をトータルにとらえた上で、彼の心理心情に迫ろうとしている。様々なエピソードが史実・物語の両面から捕らえ直す形で織り込まれていくので、読みやすい。要所要所で系図が掲載されているので、その時点時点での人間関係がわかりやすい。系図による図解のメリットが発揮されている。
政治家道長、生活者道長の両面は、本書の構成をご紹介すれば、少しイメージしやすくなると思う。
[第一章 超常的「幸ひ」の人・道長]
道長30歳で公卿の時に、長兄・道隆と次兄・道家が病死し、上席公卿たちも同時期に流行の疫病で死亡が相次ぐ。道隆の息子で道長のライバルであった伊週(コレチカ)は自滅の道を歩む。結果的に権力の座が道長に転がり込んでくる。道長は強運の持ち主だった。この点がまず押さえられる。だが、その一方で、道長が源雅信の女倫子を妻にし、倫子という同志を得ていた側面を著者は重視する。まずは雅信のバックアップという点を押せている。
平安時代の言葉では強運を「幸い」と呼んだという。
「あとがき」を読むと、著者はこの「幸い」について、次のように述べている。
「<幸い>は、幸せとは一致しないのである。<幸ひ>は結婚、出産、あるいは仕事など、世俗的で目に見える事柄に関わり、あくまでも世間が認めるような外見の幸運を言うに過ぎない」(p290)と。この第一章では、他人から眺めた道長の外見的な強運をまずとらえている。
[第二章 道長は「棚から牡丹餅」か?]
長兄・道隆が娘の定子を一条天皇の中宮とした時期に、道長は中宮大夫という定子の事務方長官の職にあったという。本書で初めて当時の道長の位置を知った。この章では道長が虎視眈々と雌伏する時期の様子が簡潔に語られていく。政治家道長の一面がイメージできる。
[第三章 <疫>という僥倖]
長兄・道隆一家、つまり中関白家と定子の栄華の状況を語り、一方、一条天皇の母后であり実姉である女院・詮子に頼る道長の状況を描写する。道長は中関白家と距離を取り続ける。道隆の持病・飲水病と疫の流行が、道長に強運をもたらす。
裏付ける史料がない部分は、『大鏡』の引用と推測とにより、道長の内心を著者は語っていく。そこに「道長ものがたり」と題する所以があるといえよう。
[第四章 中関白家の自滅]
中関白家の自滅が、結果的に道長が政治家として汚れ役や重責・秘密を背負う立場になっていかざるをえない場に置かれたと著者は語る。「道長はずっとクリーンでスマートな貴公子で、道兼のように修羅場をかいくぐった経験があるようには思えない」(p72)とそれまでの道長について要約する。道長にとり道兼は次兄であり、父・道家のために修羅場をかいくぐてきた人。その道兼もまた長徳元年に病死したのだ。
道長は政治家へと変容していく。著者は「道長は中関白家の失脚を見越して、確信犯的に手を下した。自らの権力保持のために政治の泥に手を染めたのである」(p87)という。それが「長徳の政変」だったと。
この頃から道長にとって「生涯悩ませることになる多種多様な病悩の始まり」(p87)を迎えるというのは皮肉なことでもある。生活者としての道長を知る上で、実に興味深い。
[第五章 栄華と恐怖]
この章で、著者は重要な点を指摘している。一つは紫式部の歌を冒頭に掲げて、その説明の中で紫式部の考えとして指摘していることである。
「怨霊はむしろ自身の内にある。人が疑心暗鬼を抱く限り、怨霊はそこかに生まれる。自らの恐怖心が自分を蝕むというこのシステムからは、誰も逃れられないのである」(p89)
また、道長は病気がたび重なり、長徳4年(998)には出家願望から辞表を一条天皇に提出したという。道長のこういう側面を初めて知った。著者はその道長を支えたのは家族であると記す。その上で、
「道長は自分と家族のためだと信じれば、ひどく冷酷になることができた。そのやり方は、時にいささか感情的に過ぎると思えるほどである。最初にその標的になったのは姪の中宮定子。道長にとって彼女は、入内を前にした彰子の前に立ち塞がる、目障りな敵だった」(p100)と。定子を排除するために、いじめる立場を貫いていくのだ。
さらに、「つまるところ、人生に何を求めるか。その根源的な願いの点で、道長と一条天皇とはすれ違っていた」(p106)点を、明らかにしている。
[第六章 怨霊あらわる]
「幼き人」彰子の入内と中宮定子の出産。第一皇子の誕生である。道長が「二后冊立」に動いた状況とその背景が語られる。
そして、彰子が中宮になった2ヶ月後に、道長が邪気に憑かれたという。こういう類いの史実は初めて知った。この時も、道長は辞表を提出したとか。
[第七章 『源氏物語』登場]
出家後一条天皇に呼び戻された中宮定子は、第三子を出産するが難産により非業の死を遂げた。中宮定子の死後、出家し青年貴族たちがいた。清少納言筆の『枕草子』は定子を美化した。『枕草子』は当時の貴族たちにとり癒やしになる側面があったようだ。それに対抗する形で、『源氏物語』が道長により公に登場する場が生み出される。こういう読み解きの視点を本書で知った。紫式部の登場となる。
もう一つ、『源氏物語』には定子をモデルにした側面も含まれている。この側面への危惧に対して、「学問好きな一条天皇は儒教精神を理想とし、諷喩という文学の方法についていも知っていた。それどころか、臣下には自分を諷喩する詩文を作るように求めるほどだった」(p147)との読み解きがされていて興味深い。
[第八章 産声]
道長邸である「土御門殿」での彰子の出産。その状況と道長がその折、どのような行動をとったのかが、詳細に描写されていく。「物の怪調伏班」がどのように編成され、どのようなことをおこなったのか。具体的な描写がおもしろい。
道長がどれだけ怨霊を恐れていたかがよくわかる。そのために道長が相当な資金を使っていることも推測できる。
[第九章 紫式部「御堂関白道長の妾?」]
この『道長ものがたり』の章立ての中でも、一番読者の興味を惹きつける箇所ではないかと思う。生前の瀬戸内寂聴尼から直接うかがった説も紹介しつつ、著者の見解が展開されている。
紫式部が『紫式部日記』に記すことと、『紫式部集』に記すこととの間には、ニュアンスが異なると著者は指摘する。その上で、著者の見方が述べられている。お楽しみに。
[第十章 主張する女たち]
平安時代の女性は男の言いなりになっていただけではない。自己を主張した女性たちがいたことを著者は重要な点として押さえている。道長との関係でいえば、正妻となった源倫子がまさに主張する女性だったという。それ故に、第一章で「源倫子という同志」という小見出しも出てくるのだろう。
それと、入内以降耐え続けていた彰子が父とは一線を画する<主張する中宮>への変貌を採りあげている。この点も中宮彰子を理解するのに役立つ。
一条天皇の辞世の和歌の解釈、及び、葬儀について、「土葬か、火葬か」という方法についての背景と経緯の説明は、彰子、道長を知る上で読ませどころになっていると思う。研究者たちの定説を踏まえているのか、著者独自の見解なのかは知らない。こういう箇所にも、人の心の動きを知る上で一考の余地があることに気づかされた。
[第十一章 最後の闘い]
新帝・三条天皇の即位は既定の方向であった。それを受け入れた上で、政治家道長が彰子の生んだ第一の皇子を天皇にするために、三条天皇との間でどのように最後の闘いを進めて行ったのか。その背景事情がよく分かる。
三条天皇は一条天皇の在位期間が長かったので、春宮(居貞親王)としての期間が長かった。春宮の時に、道長の父・兼家の娘、綏子が入内している。道長にとっては腹違いの妹にあたる。綏子にまつわるエピソードも紹介されている。道長の扱い方がよく分かる。
[第十二章 「我が世の望月」]
この章で採りあげられる「望月」についての読み解き方が、冒頭で触れたように私の一番の関心事だった。
道長の和歌を聞いた藤原実資の態度と行動は、以前にどこかで読んで知っていた。しかし、この和歌の背景にある意味合いまでは深く考えていなかった。本章を読んで一歩深く歌意を理解できた気がする。この章もまた、お楽しみいただきたい。
[第十三章 雲隠れ]
著者は、小一条院(敦明親王)の女御・延子と彼女の父・藤原顕光の死、さらには道長の明子腹の長女で、敦明親王の女御になった寬子の死、加えて、道長の四女で敦良親王との間の子を出産した後に死ぬ嬉子について、次々と語っていく。その先で、道長自身が死を迎える状況を記す。「実際には、その死は凄絶だった」(p284)という。史料に基づき具体的な事実が記されている。
著者は、「『源氏物語』の主人公・光源氏のモデルの一人は、藤原道長だろうと言われる」(p263)という見方を道長の死と重ねている。そして、最後に、『栄花物語』における道長の死についての記述を紹介しているところがおもしろい。
本書は、己の死期を悟った道長が長女の上東門院・彰子に送った一首で締めくくられている。最後にこの歌をご紹介しよう。
言の葉も 絶えぬべきかな 世の中に 頼む方なき もみぢ葉の身は
道長という人物にさらに興味が湧いてきた。
NHK大河ドラマ「光る君へ」の中で、道長がどのような人物として登場するのか、楽しみでもある。
ご一読ありがとうございます。