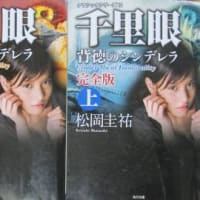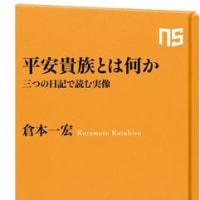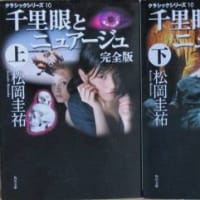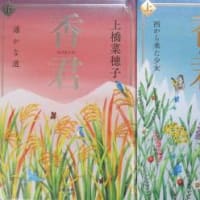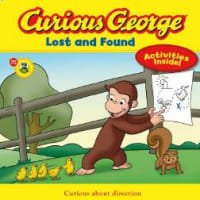表紙カバーの絵に目がとまりまず惹きつけられた。やはりムンクの絵。翻訳が原田マハとなっている。内容も確かめずに読み始めた。本書は2022年2月に刊行されている。
著者はムンク。だが、表紙には「ムンク美術館 原案・テキスト」と併記してある。
本書の冒頭には「言葉の画家、その調べ」と題し、翻訳をした作家・原田マハの一文が載っている。そこに、ムンクは「私は、呼吸し、感じ、苦悩し、生き生きとした人間を描くのだ」と決意表明したと記されている。それが後に「サン=クルー宣言」と呼ばれるようになったそうだ。原田マハは「彼は、目の画家、手の画家というよりも、感性の画家であり、言葉の画家でもあったのだ」と続けている。
本書末尾には、オスロにあるムンク美術館が「ムンクのテクストについて」と題して一文を記す。エドヴァルド・ムンクは生涯にわたって文章を書き続けたという。ムンク美術館にはムンクが書いた1万2千点以上の原稿が所蔵されているという。そのすべてのテクストをホームページで公開することが目指されている。一部がすでに英訳されているとあるので、本書はその英訳の一部なのだろう。
本書は原田マハの翻訳文と、ムンクのテクストの英訳文とがバイリンガルとして併載されている。ここには、ムンクの創作ノート、スケッチブック、手紙文あるいは手紙の下書き、印刷物などの中に記されたムンクの言葉が抽出され、言葉の内容を分類し章立てされて編集されている。
本書の原題は、「LIKE A GHOST I LEAVE YOU」である。直訳すれば、亡霊のように私はあなたから去るという意味だろう。「愛のぬけがら」とは言い得て妙でおもしろい。
本書を読むとおわかりいただけるが、「トゥラ・ラーセンへの手紙の下書き 1899」であるムンクの言葉(p148)の後半にあたる。該当ページを御覧いただきたい。絵も併載されている。
本書は以下の章立てで編集されている。
アートと自然/ 友人と敵/ ノルウェー/ 健康/ ムンク自身/ 愛/
ヴィーゲラン、他の芸術家たち/ 人生観/ お金/ 死
そして、各所にムンクの作品とムンクに関わる様々な写真が併載されている。
久々に書棚から「ムンク展」の図録を引き出して眺めてみた。前年に国立西洋美術館で開催された後、2008年1~3月に兵庫県立美術館で開催された。2008年3月初旬に出かけていた。本書表紙の「マドンナ」は本書のP159にも載っていて、本書末尾に油彩、1894年作と説明されている。見ている気がしたのだが図録を再見すると、ほぼ同じ構図の「マドンナ」だが、図録の絵は、リトグラフ・墨・スクレイバーによる1895年作だった。類似の構図で異なる作品をいくつか制作していることを、本書に併載の絵と手許の図録で知った。
手許の図録にはムンク自身の写真は1枚載るだけなのだが、本書には年代の違う自画像と写真がいくつか載っていて、ムンクの言葉を読み、肖像画・写真を併せてみられるのは興味深い。
ムンクの絵といえば、「叫び」を連想する人が多いと思う。私も真っ先に「叫び」を想起する。ここでは「人生観」の章の後半、p204にその絵が併載され、この絵は19100? と補注にある。図録を見ると、1925年のムンクのアトリエには、左から「不安」「叫び」「絶望」の3点が順に入口の上部に掲げてあった様子を示す写真が載っている。ムンク展では「不安」と「絶望」が出展されていた。余談だが、「叫び」は作品として4バージョンあるようだ。
本書でこれもおもしろいと思うのは、見開きの左ページに「叫び」の絵が載せられ、右ページにはつぎのムンクの言葉がバイリンガルで載せてあること。
「なんて幸運なんだ、君たちは。
君たちには進歩的な両親がいる。
彼らは、君たちに聖書を教えなかった。
聖書が君たちの血の中に
染みつくようにはしなかったのだ。
ああ!
歓びと死後の生にまつわるすばらしい夢たちよ。 」 (創作ノート 1890)
編集された形であるが、本書にはムンクの言葉-愛、欲望、主張、希求、意志、意欲、叫び、懊悩、憤慨、恨み、絶望、批判など-が様々な視点でまとめられている。その言葉が、英語と日本語に翻訳されているだけである。ムンクの断片的な言葉に対する解説は一切ない。読者がその言葉からどのような思いを抱くかは、読者に任されていることになる。
ムンクの言葉自体が、ここにポンと投げ出されているとも言える。その解釈と理解、受容は読者の課題となる。ムンクの真意に沿ってこれらの言葉の意味を追体験しようと思うならば、ムンクの人生という文脈について別途背景情報を知る必要がある。それは書架から久しぶりに取りだしてきた図録を再読しての気づきでもある。
例えば、「アートと自然」の最初に載るムンクの言葉を引用してみる。
「 その時代の信仰。
すなわち、その時代の魂というものを
写さなければならない。
単に装飾芸術であるだけではだめだ。
この装飾という言葉は、
今まで多くのものを台無しにしてきた。 」 (創作ノート 年不詳)
” The religion of time - that is,the soul of time
must be reflected -
There must not only be ornamental art
This word has ruined very much " (Undated note)
ムンクはどのような芸術をめざそうとしたのか。
図録(2007年)の冒頭に「エドヴァルト・ムンク、『装飾』への挑戦」(田中正之、武蔵野美術大学准教授)という論文が載っている。そこには、ムンクが「装飾画家」であったことを論じている。ムンクの一連の作品である<生命のフリーズ>がその一例として語られる。この時のムンク展の第一章は「<生命のフリーズ>:装飾への道」である。そこでの説明にはムンク自身が「全体として生命体のありさまを示すような一連の装飾的な絵画として考えられたもの」と述べていると記されている。
ムンクに沿ってここの言葉を理解するには、例えばこんな背景情報があると読み方を深められる気がする次第。
「アートと芸術」から印象深い言葉をいくつかご紹介しよう。本書は上記のようなスタイルで記されて居る。ここでは通常の文章スタイルで引用するにとどめたい。
*1脚の椅子が、ひとりの人間と同くらいおもしろいものだとしよう。
けれどそのおもしろさは、その椅子が誰かに見られない限り誰にもわからない。
誰かを感動させる椅子を絵にしたら、その絵を見た者を同じ気持ちにさせなきゃならない。つまり、絵に描かれるべきなのは、椅子そのものではなくて、ひとりの人間の体験なんだ。 p23
*写生をするのではない。自然がいっぱいに盛られた大皿に自由に手を伸ばすのだ。
見えるものを描くのではない。見たものを描くのだ。 p28
*私のアートは、人生との不和の理由を探って考えあぐねたことに始まっている。
なぜ私は他人と違うのだ? 頼みもしないのに、どうしてこの世に生を受けたのだ?
この苦しい思いが、私のアートの根っこにある。
これがなければ私のアートは違うものになっていただろう。 p30
*アートは、自然の対極にある。アートは、人間の内なる魂から生まれる。
アートとは、人間の神経、心、頭、脳、目を通して物質化された画のかたちである。
アートとは、結晶化しようとする人間の渇望である。
自然は無限の領域であり、アートはそこから糧を得る。 p35
*私は、心をむきだしにしなくてもいいようなアートを信じない。
文学でも、音楽でも同じだが、あらゆるアートは、心血を注いで創造されるべきだ。
アートとは、心の血のことだ。 p49
こんなムンクの言葉もある。
*もしノルウェーでの生活をつづけていたら、才能を無駄にして立ち直れなかっただろう。
そして恐らく、ソーレンセンやその仲間たちに潰されていただろう。
この40年の間に、自分たちこそが正しいのだと言い張る数々の芸術グループが誕生してきたが、やつらに対抗することができたのも、外国からの支援があったおかげだ。
「ノルウェー」 p90
*人間にとっていちばん恐ろしいふたつの敵を私は受け継いだ。
肺結核と精神障害の遺伝だ。病と狂気と死は、私のゆりかごの横に立つ、黒い天使だった。
「健康」 p112
*結局、僕は君に何もしてやれなかったんじゃないか・・・・・・。
僕という男は、夢見がちで、まず何よりも仕事。
愛は二の次にしてしまう、そんなやつだから。 「愛」 p152
*絵を描いているとき、お金のことを考えたことは一度もない。
私の絵に値がつくようになってはじめて、人々は私の絵に関心をもつようになった。
45歳になるまでは、私の絵を見ただけで「おお、気味が悪い」と叫んでいたくせに。
「お金」 p211
エドヴァルト・ムンクは1863年に生まれ、1944年に他界した。
モダニズムにおける重要な芸術家のひとり。1890年代にシンボリスムの芸術家として頭角を現し、20世紀初頭からはエクスプレッショニスムの先駆者となった。これらがプロフィールとして記されている。右のページにはムンクが椅子に坐る姿を左斜めから撮った写真が載っている。彼のその目は何を眺めているのだろうか・・・・・。
バイリンガルの表記なので、アート小説を数多く書く原田マハさんがどのように訳されているかを楽しみつつ学ぶこともできる。英語学習教材としても役立つのではないかと思う。
ご一読ありがとうございます。
補遺
ムンク美術館 英語版ホームページ Edward Munch's Writings in English
エドヴァルド・ムンク :ウィキペディア
ムンクの「叫び」は何を叫んでいる?描かれた理由と鑑賞ポイントを詳しく説明
:「This is Media」
エドヴァルド・ムンクの生涯と作品の特徴・代表作・有名絵画を解説
:「美術ファン@世界の名画」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
「遊心逍遙記」に掲載した<原田マハ>作品の読後印象記一覧 最終版
2022年12月現在 16冊
著者はムンク。だが、表紙には「ムンク美術館 原案・テキスト」と併記してある。
本書の冒頭には「言葉の画家、その調べ」と題し、翻訳をした作家・原田マハの一文が載っている。そこに、ムンクは「私は、呼吸し、感じ、苦悩し、生き生きとした人間を描くのだ」と決意表明したと記されている。それが後に「サン=クルー宣言」と呼ばれるようになったそうだ。原田マハは「彼は、目の画家、手の画家というよりも、感性の画家であり、言葉の画家でもあったのだ」と続けている。
本書末尾には、オスロにあるムンク美術館が「ムンクのテクストについて」と題して一文を記す。エドヴァルド・ムンクは生涯にわたって文章を書き続けたという。ムンク美術館にはムンクが書いた1万2千点以上の原稿が所蔵されているという。そのすべてのテクストをホームページで公開することが目指されている。一部がすでに英訳されているとあるので、本書はその英訳の一部なのだろう。
本書は原田マハの翻訳文と、ムンクのテクストの英訳文とがバイリンガルとして併載されている。ここには、ムンクの創作ノート、スケッチブック、手紙文あるいは手紙の下書き、印刷物などの中に記されたムンクの言葉が抽出され、言葉の内容を分類し章立てされて編集されている。
本書の原題は、「LIKE A GHOST I LEAVE YOU」である。直訳すれば、亡霊のように私はあなたから去るという意味だろう。「愛のぬけがら」とは言い得て妙でおもしろい。
本書を読むとおわかりいただけるが、「トゥラ・ラーセンへの手紙の下書き 1899」であるムンクの言葉(p148)の後半にあたる。該当ページを御覧いただきたい。絵も併載されている。
本書は以下の章立てで編集されている。
アートと自然/ 友人と敵/ ノルウェー/ 健康/ ムンク自身/ 愛/
ヴィーゲラン、他の芸術家たち/ 人生観/ お金/ 死
そして、各所にムンクの作品とムンクに関わる様々な写真が併載されている。
久々に書棚から「ムンク展」の図録を引き出して眺めてみた。前年に国立西洋美術館で開催された後、2008年1~3月に兵庫県立美術館で開催された。2008年3月初旬に出かけていた。本書表紙の「マドンナ」は本書のP159にも載っていて、本書末尾に油彩、1894年作と説明されている。見ている気がしたのだが図録を再見すると、ほぼ同じ構図の「マドンナ」だが、図録の絵は、リトグラフ・墨・スクレイバーによる1895年作だった。類似の構図で異なる作品をいくつか制作していることを、本書に併載の絵と手許の図録で知った。
手許の図録にはムンク自身の写真は1枚載るだけなのだが、本書には年代の違う自画像と写真がいくつか載っていて、ムンクの言葉を読み、肖像画・写真を併せてみられるのは興味深い。
ムンクの絵といえば、「叫び」を連想する人が多いと思う。私も真っ先に「叫び」を想起する。ここでは「人生観」の章の後半、p204にその絵が併載され、この絵は19100? と補注にある。図録を見ると、1925年のムンクのアトリエには、左から「不安」「叫び」「絶望」の3点が順に入口の上部に掲げてあった様子を示す写真が載っている。ムンク展では「不安」と「絶望」が出展されていた。余談だが、「叫び」は作品として4バージョンあるようだ。
本書でこれもおもしろいと思うのは、見開きの左ページに「叫び」の絵が載せられ、右ページにはつぎのムンクの言葉がバイリンガルで載せてあること。
「なんて幸運なんだ、君たちは。
君たちには進歩的な両親がいる。
彼らは、君たちに聖書を教えなかった。
聖書が君たちの血の中に
染みつくようにはしなかったのだ。
ああ!
歓びと死後の生にまつわるすばらしい夢たちよ。 」 (創作ノート 1890)
編集された形であるが、本書にはムンクの言葉-愛、欲望、主張、希求、意志、意欲、叫び、懊悩、憤慨、恨み、絶望、批判など-が様々な視点でまとめられている。その言葉が、英語と日本語に翻訳されているだけである。ムンクの断片的な言葉に対する解説は一切ない。読者がその言葉からどのような思いを抱くかは、読者に任されていることになる。
ムンクの言葉自体が、ここにポンと投げ出されているとも言える。その解釈と理解、受容は読者の課題となる。ムンクの真意に沿ってこれらの言葉の意味を追体験しようと思うならば、ムンクの人生という文脈について別途背景情報を知る必要がある。それは書架から久しぶりに取りだしてきた図録を再読しての気づきでもある。
例えば、「アートと自然」の最初に載るムンクの言葉を引用してみる。
「 その時代の信仰。
すなわち、その時代の魂というものを
写さなければならない。
単に装飾芸術であるだけではだめだ。
この装飾という言葉は、
今まで多くのものを台無しにしてきた。 」 (創作ノート 年不詳)
” The religion of time - that is,the soul of time
must be reflected -
There must not only be ornamental art
This word has ruined very much " (Undated note)
ムンクはどのような芸術をめざそうとしたのか。
図録(2007年)の冒頭に「エドヴァルト・ムンク、『装飾』への挑戦」(田中正之、武蔵野美術大学准教授)という論文が載っている。そこには、ムンクが「装飾画家」であったことを論じている。ムンクの一連の作品である<生命のフリーズ>がその一例として語られる。この時のムンク展の第一章は「<生命のフリーズ>:装飾への道」である。そこでの説明にはムンク自身が「全体として生命体のありさまを示すような一連の装飾的な絵画として考えられたもの」と述べていると記されている。
ムンクに沿ってここの言葉を理解するには、例えばこんな背景情報があると読み方を深められる気がする次第。
「アートと芸術」から印象深い言葉をいくつかご紹介しよう。本書は上記のようなスタイルで記されて居る。ここでは通常の文章スタイルで引用するにとどめたい。
*1脚の椅子が、ひとりの人間と同くらいおもしろいものだとしよう。
けれどそのおもしろさは、その椅子が誰かに見られない限り誰にもわからない。
誰かを感動させる椅子を絵にしたら、その絵を見た者を同じ気持ちにさせなきゃならない。つまり、絵に描かれるべきなのは、椅子そのものではなくて、ひとりの人間の体験なんだ。 p23
*写生をするのではない。自然がいっぱいに盛られた大皿に自由に手を伸ばすのだ。
見えるものを描くのではない。見たものを描くのだ。 p28
*私のアートは、人生との不和の理由を探って考えあぐねたことに始まっている。
なぜ私は他人と違うのだ? 頼みもしないのに、どうしてこの世に生を受けたのだ?
この苦しい思いが、私のアートの根っこにある。
これがなければ私のアートは違うものになっていただろう。 p30
*アートは、自然の対極にある。アートは、人間の内なる魂から生まれる。
アートとは、人間の神経、心、頭、脳、目を通して物質化された画のかたちである。
アートとは、結晶化しようとする人間の渇望である。
自然は無限の領域であり、アートはそこから糧を得る。 p35
*私は、心をむきだしにしなくてもいいようなアートを信じない。
文学でも、音楽でも同じだが、あらゆるアートは、心血を注いで創造されるべきだ。
アートとは、心の血のことだ。 p49
こんなムンクの言葉もある。
*もしノルウェーでの生活をつづけていたら、才能を無駄にして立ち直れなかっただろう。
そして恐らく、ソーレンセンやその仲間たちに潰されていただろう。
この40年の間に、自分たちこそが正しいのだと言い張る数々の芸術グループが誕生してきたが、やつらに対抗することができたのも、外国からの支援があったおかげだ。
「ノルウェー」 p90
*人間にとっていちばん恐ろしいふたつの敵を私は受け継いだ。
肺結核と精神障害の遺伝だ。病と狂気と死は、私のゆりかごの横に立つ、黒い天使だった。
「健康」 p112
*結局、僕は君に何もしてやれなかったんじゃないか・・・・・・。
僕という男は、夢見がちで、まず何よりも仕事。
愛は二の次にしてしまう、そんなやつだから。 「愛」 p152
*絵を描いているとき、お金のことを考えたことは一度もない。
私の絵に値がつくようになってはじめて、人々は私の絵に関心をもつようになった。
45歳になるまでは、私の絵を見ただけで「おお、気味が悪い」と叫んでいたくせに。
「お金」 p211
エドヴァルト・ムンクは1863年に生まれ、1944年に他界した。
モダニズムにおける重要な芸術家のひとり。1890年代にシンボリスムの芸術家として頭角を現し、20世紀初頭からはエクスプレッショニスムの先駆者となった。これらがプロフィールとして記されている。右のページにはムンクが椅子に坐る姿を左斜めから撮った写真が載っている。彼のその目は何を眺めているのだろうか・・・・・。
バイリンガルの表記なので、アート小説を数多く書く原田マハさんがどのように訳されているかを楽しみつつ学ぶこともできる。英語学習教材としても役立つのではないかと思う。
ご一読ありがとうございます。
補遺
ムンク美術館 英語版ホームページ Edward Munch's Writings in English
エドヴァルド・ムンク :ウィキペディア
ムンクの「叫び」は何を叫んでいる?描かれた理由と鑑賞ポイントを詳しく説明
:「This is Media」
エドヴァルド・ムンクの生涯と作品の特徴・代表作・有名絵画を解説
:「美術ファン@世界の名画」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
「遊心逍遙記」に掲載した<原田マハ>作品の読後印象記一覧 最終版
2022年12月現在 16冊