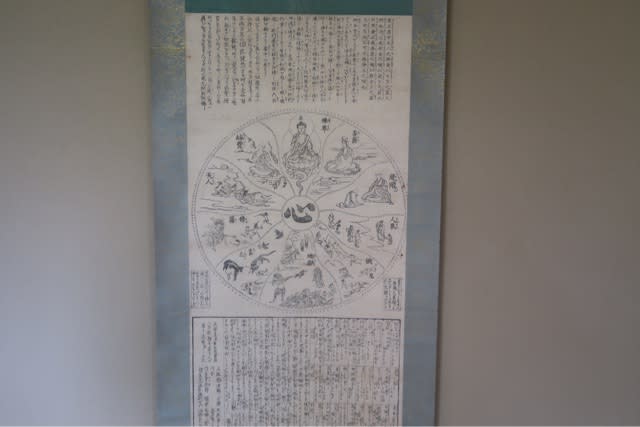金毛院の拝観を終え、法然院の境内を散策しました。山門の屋根が数年前に吹き替えられ、随分と馴染んできたように感じます。やはり、法然院の顔とも言える山門は苔むした茅葺が似合います。


山門前の石柱はお寺で時折、見かけますが、「肉を食べた人、にんにくなどの匂いのきつい食べ物を食した人は山門に入ってはならない。」と言う意味だそうです。仏教では肉や魚を食してはならない戒律や匂いのきつい食べ物は修行の妨げになるからでしょうか。
山門を入ると両側に銀砂壇が迎えてくれます。季節の模様が描かれており、この日は、もみじ🍁と銀杏でした。

浴室は、この日は着物の展示会をされていました。

いつもは本堂内には入れませんが本堂正面前まで行けるのですが、こちらでも台風21号の被害があり、倒木で行けませんでした。


本堂北側にある方丈には、狩野光信(永徳の長男)筆の襖絵(重文)、また、堂本印象が1971年に描いた新襖絵があります。
11月1日から11日まで京都非公開文化財特別公開で伽藍内が公開されこれらの襖絵を見る事ができます。


山門前の石柱はお寺で時折、見かけますが、「肉を食べた人、にんにくなどの匂いのきつい食べ物を食した人は山門に入ってはならない。」と言う意味だそうです。仏教では肉や魚を食してはならない戒律や匂いのきつい食べ物は修行の妨げになるからでしょうか。
山門を入ると両側に銀砂壇が迎えてくれます。季節の模様が描かれており、この日は、もみじ🍁と銀杏でした。


浴室は、この日は着物の展示会をされていました。

いつもは本堂内には入れませんが本堂正面前まで行けるのですが、こちらでも台風21号の被害があり、倒木で行けませんでした。


本堂北側にある方丈には、狩野光信(永徳の長男)筆の襖絵(重文)、また、堂本印象が1971年に描いた新襖絵があります。
11月1日から11日まで京都非公開文化財特別公開で伽藍内が公開されこれらの襖絵を見る事ができます。