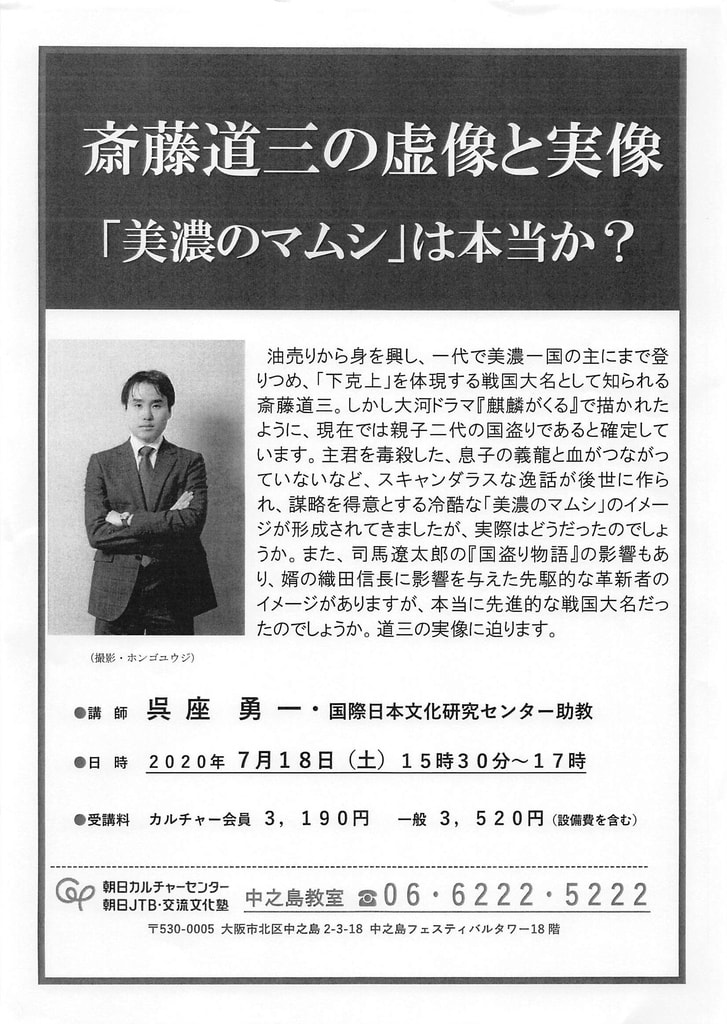7月18日は朝日カルチャーの講座で呉座勇一先生の講座がありました。
日本中世史がご専門で新書では空前のヒット作となった「応仁の乱」の著書です。
今回は、今年のNHK大河「麒麟がくる」で登場した斎藤道三についての講座です。
大河では本木雅弘さんが演じていた道三が凄くかっこよく、道三のイメージがすっかり変わってしまった感があります。
しかし、文献を中心に考察を重ねられ、作家の方々の小説や新説を次々と論破されまさす。
その切れ味の良さが呉座先生の特徴だと思います。
①江戸時代の斎藤道三像
『信長公記』の著書として知られる太田牛一「大かうさまくんきのうち」(1610年頃)によると道三は山城国(今の京都)西岡の出身で美濃国(今の岐阜)で長井藤左衛門に仕え西村と名乗る。やがて主の首を切り、長井新九郎と名乗る。
やがて美濃国の守護大名土岐頼芸(ときよりのり)に仕え斎藤道三と名乗る。土岐殿御息二郎殿を婿に取り毒殺。次に御舎弟八郎殿を婿に取り、切腹させ、大桑(おおが)を乗っ取り候き。とあります。
『堂洞(どうほら)軍記』では、「斎藤山城守と申すは、その昔、都において賤しき笠張りにて有りける人に生まれ、、、」とあります。
『美濃国諸旧記』には「斎藤道三という者あり。その由緒を尋ねるに、元来その祖先、禁裏北面の武士なり、、、その子左近将監基宗、その子道三なり。』
とあり、幼少の頃から優秀で基宗にたいそう可愛がられたようです。
11歳の春に出家させ、京都妙覚寺の日善上人の弟子となり法蓮房と号します。
しかし、還俗し、西岡に帰京し、『奈良屋又兵衛という者の娘を娶り妻となし、彼の家名を改め、山崎屋庄五郎と名乗りで燈油を商いす』とあり、ここで初めて油売りの事が出て来ます。
しかし、この古文書も道三の時代から約100年後に書かれたもので真偽の程は定かではないのではないでしょうか。
②斎藤義龍の実父は土岐頼芸なのか?
太田牛一の『大かうさまくんきのうち』(1610年頃)では「一男新九郎、二男孫四郎、三男喜平次として、兄弟三人これあり。惣別、人惣領たるものは、必ずしも心が緩緩として穏当なるものに候。道三は知恵の鏡も曇り、新九郎は 者(ほれもの)とばかり心得、弟二人を小賢しく利口の者かなと崇敬して、三男喜平次を一色右兵衛大輔になし、居ながら官を進め、これによって弟ども勝に乗ってはばかり、新九郎を蔑ろに持て扱い候。よその聞こえ無念に存じ、十月十三日、作病を構え、奥へ引き入り、平臥候し、、」とあり、病を口実に、弟二人をおびき寄せて謀殺します。
大河ではこの場面も印象的でした。
山鹿素行『武家記紀』(1673)
「正利稲葉山に在城し、入道して道三といい、土岐が妻を妻とす。この妻、土岐が所にて懐妊の子を、山城守の所にて産めり。これ義竜という。その弟孫四郎・喜平次新五郎、三人あり。道三、義竜をうとみ、孫四郎・喜平次を愛し、これを跡に立てんとす。義竜遺恨を存じ、、、」とあります。
また、熊沢正興『武将感状記』(1716)や『美濃国諸旧記』にも同様な記述があり義龍は土岐頼芸の子であった可能性があります。
大河でも義龍が自分の出生に悩み、父道三に詰め寄るシーンが印象的でした。
今では考えられないですが、平安時代以降には自分の妻を部下に譲る風習があったのですね。
③聖徳寺の会見(『信長公記』)
時期については不詳。信長公記には"四月初旬"とのみあります。織田家の事情から考えると、織田信秀が死去した天文21年(1552)3月以降と考えられます。天文23年に信長が今川方の村木砦を攻める際、居城の那古野城を清州織田家に攻められないよう、道三に援軍を出してもらっているので、それ以前に会見を行っているのが自然で天文21年ないし22年4月の出来事で信長19歳か20歳の時のようです。
家臣から信長の"たわけぶり"を聞いていた道三は会見場に来る時の信長が歌舞伎者から、髷を直し正装に着替えて会見場に現れます。あまり会話もなく湯漬けを食し盃を交わしたそうです。
会見後、道三は信長の帰りを見送りますが自分の軍の槍より信長軍の槍の方が長いことに気づき不機嫌になります。
道三側近の猪子平介(高就)に『されば無念なること候。山城のこどさ、たわけが門外に馬を繋ぐべき事、案の内にて候』と述べ、早くも信長の器量を見抜いていたようです。
内容が凄いので以降は続編に書きます。