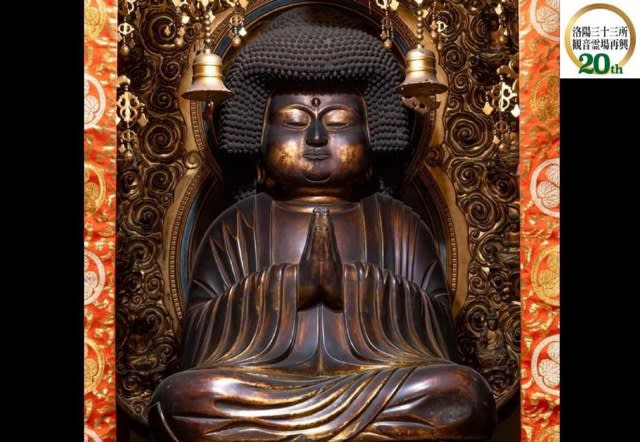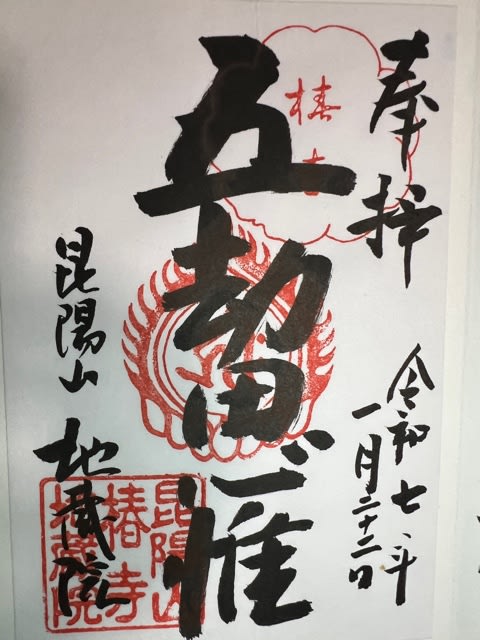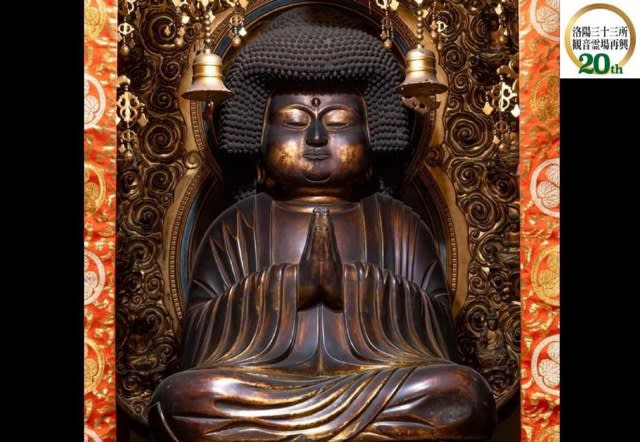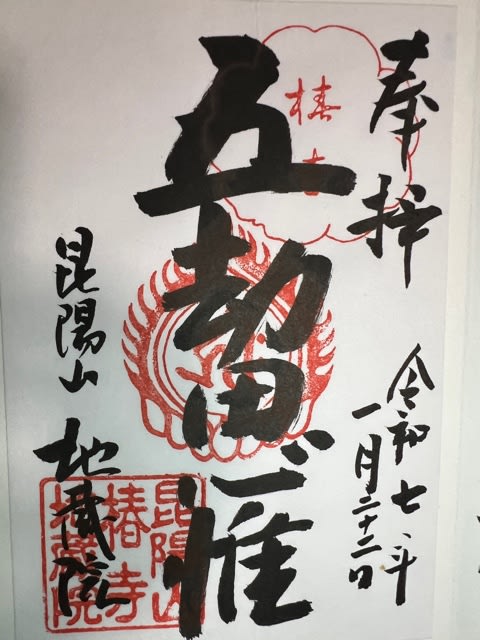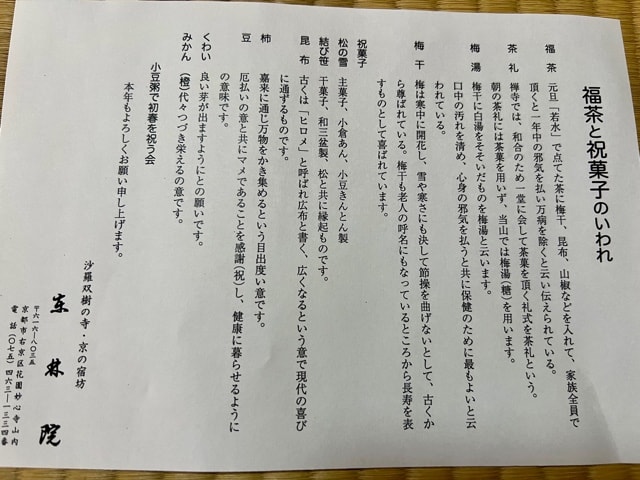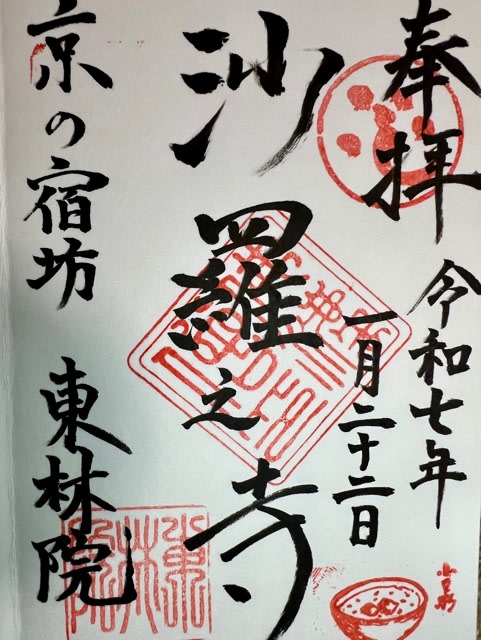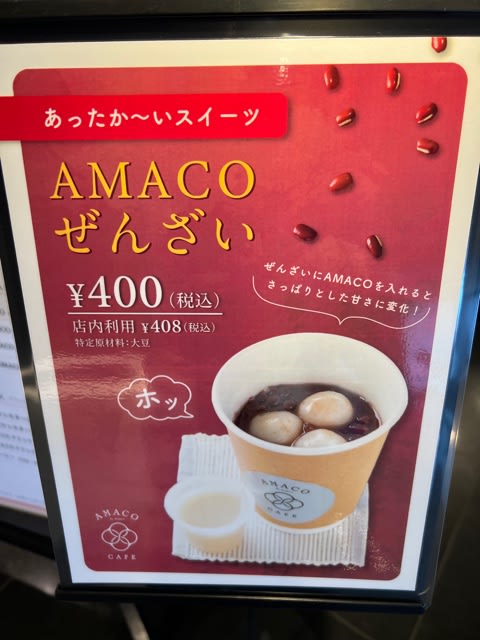1月25日は、仕事を16時に終えて大阪メトロ御堂筋線と阪急電車京都線を乗り継ぎ京都へと来ました。
やって来たのは高台寺の南側にあるパークハイアット京都内にあるイタリアンレストラン「KYOTO BISTRO 」です。
今日(1月25日)と明日(26日)の2日間、予約が取れないお店として知られる"肉割烹かなえ"と"KYOTO BISTRO "とのコラボレーションディナーが開催されます。
初日の25日に予約し参加しました。
パークハイアットの総料理長の井料剛さんです。

肉割烹かなえの店主・北口亮祐さんと榊原圭奈笑(かなえ)さんの挨拶で期待のコースが始まります。
アルコールを頂いてもいいのですが、真剣に?料理を頂きたい時にはノンアルコールかソフトドリンクにしています。
この日は、柚子ソーダを頼みました。
グラスの底にたくさんの柚子の果肉が入っていて、美味しいソーダです。
① 海老芋のスープ
牛テールと塩味のパンナコッタ
京都の伝統野菜の海老芋のスープの下にはパンナコッタが、、、
具材には香ばしく焼かれた牛テールが入っていて、スープだけでも十分に美味しいですが、炙られた牛テールが美味しく、いいアクセントになっています。
② ステーキサンドイッチ
キャラウェイ風味のサバイヨンソース
肉はレアに焼かれ、パンも表面が焼かれているので食感が良くて美味しいです。
それにKYOTO BISTROオリジナルのサバイヨンソースが添えられ、美味しさが倍増します。
キャラウェイは古代ギリシャの時代からパンに入れられていたスパイスです。
ステーキサンドイッチに合わないはずが無いです。
③ サーロインかいわれ巻きとミノの湯引き
オープンキッチンで北口さんが包丁で切られていたサーロインを使った一品です。
中にはかいわれと奈良漬が入っていて、サーロインの脂との相性がバッチリです。
ミノの湯引きにはポン酢のジュレがかかり、ミノの旨み、食感を楽しめました。
④ ピリアうどん
この一品が一番美味しくて感動を覚えました。
和牛やパクチーをはじめ、多くの具材が入っています。
手間暇を惜しまず作られたスープは凄いコクと旨みで溢れています。
お店では中華麺で出されているようですが、うどんもスープが良く絡み非常に非常に美味しかったです。
もちろん、スープも全て飲み干しました。
⑤ ピリアタコス?
メニューに載っていないサプライズの一品です。
かなえさんから"ピリアうどんのスープに漬けて食べて見て下さい"とアドバイスがありましたが、僕は単品で頂きました。
2年前にコラボされた「ケパサ」さんの料理を思い出す一品でした。
⑥ グラニテ
金柑をはじめ柑橘類のフルーツを使ったグラニテで、いいタイミングでの"お口直し"でした。
⑦ フィレ肉の炭火焼き 春菊のピューレ 赤ワインソース
いいお肉を使われているのでしょう。
フィレ肉の柔らかさと芳醇さ、炭火焼きをしているので凄く香ばしさを堪能しました。
赤ワインソースはオーソドックスですが、春菊のピューレはほろ苦くフィレ肉との相性も良かったです。
⑧ デザートブッフェ
最後のデザートはホテルメイドのスイーツバイキングでした。
アフタヌーンティーでも出て来そうなスイーツが食べ放題とは、、、最後の最後まで贅沢感を感じます。
ジェラートも2種あり井料さん自らアイスディッシャーで取り分けて下さいました。
直径20cmくらいのお皿で3枚分のスイーツを、頂きました。
しばらくは、アフタヌーンティーも遠慮したいと思う程に堪能させて頂きました。
井料さんとのお話で「年内にもう一度、コラボレーションディナー」を計画されているそうです。
どんなお店とのコラボか?今から楽しみです。