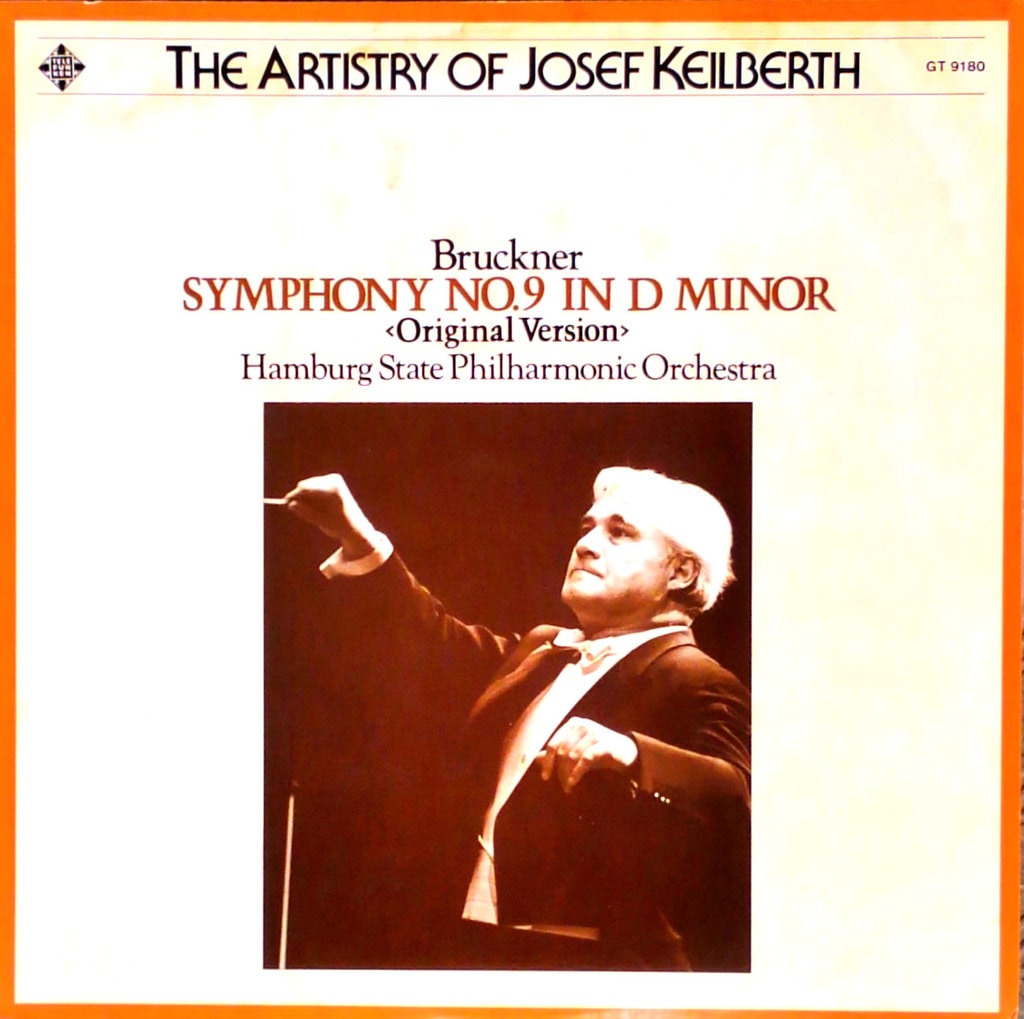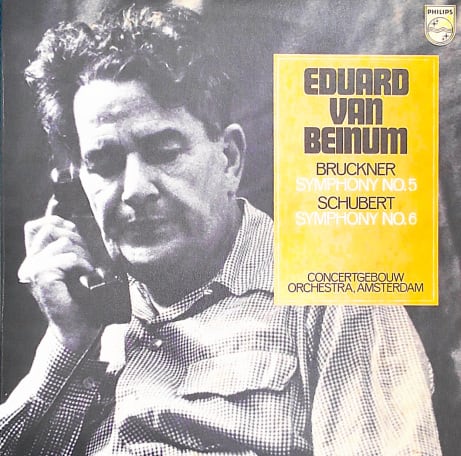ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」
指揮:フェレンツ・フリッチャイ
管弦楽:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
LP:ポリドール MH5009(SE 7211)
ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」ほど録音の数が多い交響曲も滅多にあるまい。それだけ多くのリスナーに愛されている曲であることの証明にもなろう。ドヴォルザークはニューヨークの国民音楽院の院長の就任のため招かれ、アメリカに滞在している時に聴いたアメリカン・インディアンなどの民謡が、この交響曲作曲の切っ掛けであるという。ドヴォルザークの生まれ故郷のハンガリーやボヘミアは、優れた音楽土壌に恵まれた土地柄であり、その土壌をベースとして、当時「新世界」と言われていたアメリカの民謡とが、巧みなオーケストレーションによって、新しい交響曲として誕生したのである。このため、多くのリスナーにとって分りやすい曲想であることが人気の源となっているようだ。このようにドヴォルザークは、常に民謡など国民音楽を重視する姿勢に貫かれているが、ただ単に民謡を真似て作曲するのではなく、「一旦それを昇華させ、作曲家の独自のものとして新たな構想の下に作曲されるべきだ」という持論を持ち、自ら実践した人であり、そしてその最も成功した曲の一つが「新世界交響曲」なのである。このLPレコードでベルリン・フィルを指揮しているのが、49歳の若さで世を去ったハンガリー出身の名指揮者フェレンツ・フリッチャイ(1914年―1963年)である。ハンガリー国立交響楽団音楽監督、ヒューストン交響楽団音楽監督、ベルリン・ドイツ交響楽団首席指揮者 、ベルリン・ドイツ・オペラ音楽監督、バイエルン国立歌劇場音楽総監督などを歴任。フリッチャイは、フルトヴェングラー亡き後のドイツ指揮界をカラヤンと二人で支えた実力者であり、当時の聴衆もフリッチャイの将来に大きな希望を抱いていた。その指揮ぶりは、常に躍動的であり、ダイナミックな表現力に優れ、聴く者に圧倒的なインパクトを与えずには置かないものがあった。晩年になり、その傾向はますます深まり、そのスケールの大きな指揮ぶりは、巨匠と呼ばれるに相応しいところに到達した、と皆が感じた正にその時に、白血病のため多くの人々に惜しまれつつこの世を去ってしまったのだ。このLPレコードには、晩年のフリッチャイの特徴である、スケールが大きく、陰影が濃く、そして深い精神性に支えられた、類稀なる演奏内容が収録されている。「新世界交響曲」の代表的録音として永遠の生命力を有している、と言っても過言でない。録音状態も良い。(LPC)