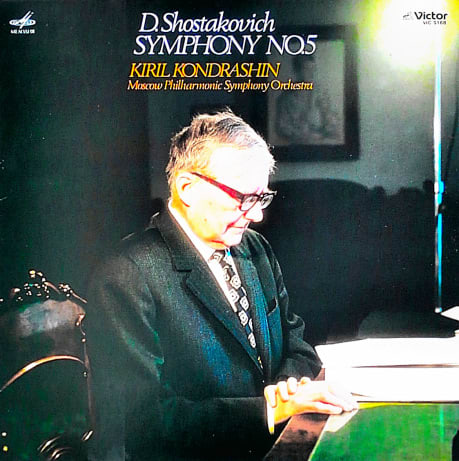シベリウス:交響曲第1番
交響詩「トゥオネラの白鳥」
指揮:ユージン・オーマンディ
管弦楽:フィラデルフィア管弦楽団
イングリッシュホルン(ソロ):ルイス・ローゼンブラット
LP:CBS/SONY SOCT 16
シベリウスは、生涯に7つの交響曲を書いた。このほかにクレルボ交響曲と名付けられた曲がある。ドイツ・オーストリア系を除き、ベートーヴェン以来これほど体系立って交響曲を書いた作曲者はいなかった。それだけにシベリウスは、作曲家として歴史に残る偉大な仕事を成したと高く賞賛されている。7つの交響曲の中では、第2番が最もポピュラーで聴く機会も多い。このLPレコードに収められた交響曲第1番は、第2番に次いで聴きやすい内容となっている。そのためリスナーの中でクラシック音楽を聴き始めて間もないジュニアクラスでも充分楽しめるし、同時にビギナーやシニアクラスのリスナーでも楽しめるような幅広い内容の交響曲となっている。このLPレコードは、ハンガリー出身の名指揮者ユージン・オーマンディ(1899年―1985年)が手兵のフィラデルフィア管弦楽団を指揮した録音であり、一般に“フィラデルフィア・サウンド”と呼ばれているフィラデルフィア管特有の明快で輝かしい音色が誠にもって耳に心地良く響く。特に、LPレコードで聴くと、この“フィラデルフィア・サウンド”の真価がより一層鮮明となる。ユージン・オーマンディは、ハンガリー出身のアメリカ人指揮者。ブダペスト王立音楽院で学び、同音楽院卒業後、ヴァイオリニストとして演奏活動を開始。その後、アメリカに渡り、1924年以降は指揮者に転向。1927年にはアメリカ国籍を取得。1936年、レオポルド・ストコフスキーと共にフィラデルフィア管弦楽団の共同指揮者となる。1938年、ストコフスキーの辞任により後任としてフィラデルフィア管弦楽団音楽監督に就任。以後、1980年に勇退するまで42年の長期にわたって同管弦楽団の音楽監督を務めた。4回ほど来日している。このシベリウスの第1番の交響曲は、ロシア音楽的な色彩が濃い曲と言われることがあるが、実際に聴いてみると後期ロマン派的な雰囲気も漂い、伝統的な交響曲の良さが滲み出ている。オーマンディ指揮フィラデルフィア管のコンビによるこのLPレコードでは、明快極まりない聴きやすい演奏となっており、起伏のある盛り上げ方は他の追随を許さない圧倒的名演を聴かせてくれる。一方、交響詩「トゥオネラの白鳥」は、レンミンカイネン組曲(4つの伝説曲)の中の1曲で、イングリッシュ・ホルン、オーボエ、バス・クラリネットの演奏を中心に、フィンランドの幻想的な美しさを、音そのものによって醸し出しおり、その魅力的な演奏に深く心を揺さぶらされる。(LPC)