去る7月11日
梅雨の合間、台風4号の襲撃前に野草の仲間の皆さんについて平尾台に行った。
前日の大雨で散策は無理(?)と思いつつ山頂に到着したが持参のカッパのお世話にはならずに、済みそうな天気になった。
このメンバーには”雨女”や”雨男”はいらっしゃらない様だ。
この時期は”キヌガサダケ”や”ホウライカズラ”などが見頃だと教えて戴いた。
前回の4月の参加以来久々の参加で美味しいコンビニ弁当が食べられた。

7月になっても高原ではまだアジサイが咲いている。
もっと奇麗に写せると思うが”バッタ”にピントをあわせたつもり。

強い雨が続いていたので一番心配していた「蚊」も少なく半袖でOKだった。

梅雨時に観られる生き物ではやっぱり「カタツムリ」かな?

赤ちゃんのカタツムリ

今日の目玉の”キヌガサダケ”
竹薮で朝の2~3時間位の時間に観れるらしい。

ヒグラシ

ホウリイカズラ(蓬莱)と言って珍しい花らしい

ハチ?虻?

ちょう

キセルマイマイ
陸棲の貝が沢山いるそうなので、夜間にはきっと”ヒメボタル”もいるだろう。

白花の”ホタル袋”だがこの中にホタルが入っているところを写せると凄いのだけど!!
素人には無理だろう!!

昼食後にキキョウを見つけた。
秋の花だと思うのだが????

ネジリ花
ピントがあわない。
風が吹いて花が揺れる?????
腕が未熟!!!!
梅雨の合間、台風4号の襲撃前に野草の仲間の皆さんについて平尾台に行った。
前日の大雨で散策は無理(?)と思いつつ山頂に到着したが持参のカッパのお世話にはならずに、済みそうな天気になった。
このメンバーには”雨女”や”雨男”はいらっしゃらない様だ。
この時期は”キヌガサダケ”や”ホウライカズラ”などが見頃だと教えて戴いた。
前回の4月の参加以来久々の参加で美味しいコンビニ弁当が食べられた。

7月になっても高原ではまだアジサイが咲いている。
もっと奇麗に写せると思うが”バッタ”にピントをあわせたつもり。

強い雨が続いていたので一番心配していた「蚊」も少なく半袖でOKだった。

梅雨時に観られる生き物ではやっぱり「カタツムリ」かな?

赤ちゃんのカタツムリ

今日の目玉の”キヌガサダケ”
竹薮で朝の2~3時間位の時間に観れるらしい。

ヒグラシ

ホウリイカズラ(蓬莱)と言って珍しい花らしい

ハチ?虻?

ちょう

キセルマイマイ
陸棲の貝が沢山いるそうなので、夜間にはきっと”ヒメボタル”もいるだろう。

白花の”ホタル袋”だがこの中にホタルが入っているところを写せると凄いのだけど!!
素人には無理だろう!!

昼食後にキキョウを見つけた。
秋の花だと思うのだが????

ネジリ花
ピントがあわない。
風が吹いて花が揺れる?????
腕が未熟!!!!
今年も又、4月の平尾台の野草散策に誘って頂いた。
昨年の4月はスミレが沢山咲いていたが、
今年は、暖かくてスミレイ以外に”チョウジガマズミ”や”ホタルカズラ”を教えて戴いた。
楽しくて、のんびりした一日で、腹ペコで食べた、コンビに弁当が美味しかった。

オキナグサ

レンゲ草


遠景

ペンペン草

カラス

ホタルカズラ
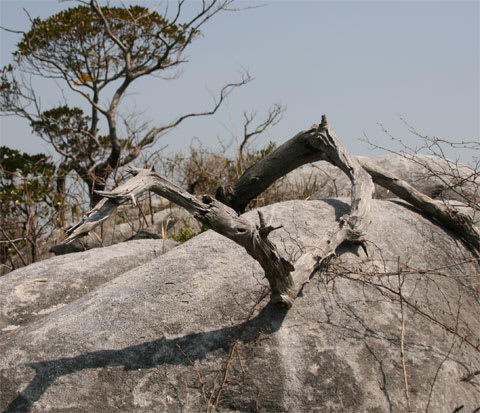
枯れ木

チョウジガマズミ
昨年の4月はスミレが沢山咲いていたが、
今年は、暖かくてスミレイ以外に”チョウジガマズミ”や”ホタルカズラ”を教えて戴いた。
楽しくて、のんびりした一日で、腹ペコで食べた、コンビに弁当が美味しかった。

オキナグサ

レンゲ草


遠景

ペンペン草

カラス

ホタルカズラ
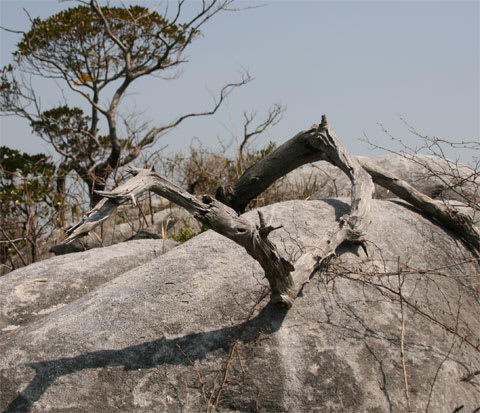
枯れ木

チョウジガマズミ
早春恒例の平尾台の野焼きが好天の中今日行われた。
昨年同様「茶ヶ床園地」げ見学した。
今年も晴天が続いていたのでよく燃えた。
昨年の写真は"こちらにUP"している。


点火前の山

注意事項の説明

山頂より点火

稜線に沿って燃え広がる

カメラの放列


可成燃えた


内側(近場)からの点火

見物場所が風上だったので近くで見れた。


TVカメラも熱心に撮影している


点火作業

午前の部が略燃えた。
昨年同様「茶ヶ床園地」げ見学した。
今年も晴天が続いていたのでよく燃えた。
昨年の写真は"こちらにUP"している。

点火前の山

注意事項の説明

山頂より点火

稜線に沿って燃え広がる

カメラの放列


可成燃えた


内側(近場)からの点火

見物場所が風上だったので近くで見れた。


TVカメラも熱心に撮影している


点火作業

午前の部が略燃えた。
昼食後再度平尾台に登り貫山のヤマラッキョウを見に行った。

昨日の寒さが嘘のような暖かい日中になり、
広場で食べる”おにぎり弁当”が事の他美味しかった。
昼食場所で見つけた、ゲンノショウコとその実である、ミコシ草
尖った種の先に付いている実がミコシに似ているらしい。

アリドウシと云うらしい
茎の節から出ている鋭い棘にアリが刺さるそうだ。

ヤクソウ???????

お馴染みのツタ
例の甲子園の外壁でも今頃咲いているのかな??

午後の2時過ぎに貫山に登った。
青色の秋リンドウが咲いていた。花も6房着いていた。

ハバヤマボク”ヤマボクチ属”
ハバヤマ(葉場山)は草刈山、
ホクチ(火口)は葉の裏の白い綿毛を乾燥させて火を付ける。

山地に生えているラッキョウと云う事で、ヤマラッキョウと名が着けられている。
雨が少ないせいか?花が小さく何だか色も今一だ!

こちらは綺麗だが群生していない。

昨日の寒さが嘘のような暖かい日中になり、
広場で食べる”おにぎり弁当”が事の他美味しかった。
昼食場所で見つけた、ゲンノショウコとその実である、ミコシ草
尖った種の先に付いている実がミコシに似ているらしい。

アリドウシと云うらしい
茎の節から出ている鋭い棘にアリが刺さるそうだ。

ヤクソウ???????

お馴染みのツタ
例の甲子園の外壁でも今頃咲いているのかな??

午後の2時過ぎに貫山に登った。
青色の秋リンドウが咲いていた。花も6房着いていた。

ハバヤマボク”ヤマボクチ属”
ハバヤマ(葉場山)は草刈山、
ホクチ(火口)は葉の裏の白い綿毛を乾燥させて火を付ける。

山地に生えているラッキョウと云う事で、ヤマラッキョウと名が着けられている。
雨が少ないせいか?花が小さく何だか色も今一だ!

こちらは綺麗だが群生していない。
もう流石に平尾台の山頂付近では花も終りに近いので、
今日は最初に麓の苅田町側で最近繁殖し,
水田の畦に咲いている北アメリカ原産の”ヌマツルギク”を観察に行った。

刈入れの済んだ田圃の畦に一面咲いている
菊科のつる草なので繁殖が早い。

こちらはお馴染みのイヌタデ

こちらもお馴染みのミゾソバ
白とピンクが並んで咲いていた

ヌマツルギクの間で見つけたサクラタデ

今日の目玉の一つゴキヅル
黄緑がかった小さな花、種子が合器、碁石入れのような蓋のある器に似ているので
その名が付いたらしい
緑の皮の中に黒い実が見える

こちらもお馴染みのヤブコウジ
通称”十両”の名で呼ばれ秋に赤く熟して翌年の春まで下垂している

こちらも今日の目玉の一つ”キッコウハグマ”
葉が亀の甲羅に似て、3個の花が集まって全体を構成している
通常はもっと高地に行かないと見れないらしく、
こんな低地で通路の横で見れる所は秘密の場所だそうだ。

こちらも”キッコウハグマ”
もう、花が終りに近く一個だけ咲いている。
今日は最初に麓の苅田町側で最近繁殖し,
水田の畦に咲いている北アメリカ原産の”ヌマツルギク”を観察に行った。

刈入れの済んだ田圃の畦に一面咲いている
菊科のつる草なので繁殖が早い。

こちらはお馴染みのイヌタデ

こちらもお馴染みのミゾソバ
白とピンクが並んで咲いていた

ヌマツルギクの間で見つけたサクラタデ

今日の目玉の一つゴキヅル
黄緑がかった小さな花、種子が合器、碁石入れのような蓋のある器に似ているので
その名が付いたらしい
緑の皮の中に黒い実が見える

こちらもお馴染みのヤブコウジ
通称”十両”の名で呼ばれ秋に赤く熟して翌年の春まで下垂している

こちらも今日の目玉の一つ”キッコウハグマ”
葉が亀の甲羅に似て、3個の花が集まって全体を構成している
通常はもっと高地に行かないと見れないらしく、
こんな低地で通路の横で見れる所は秘密の場所だそうだ。

こちらも”キッコウハグマ”
もう、花が終りに近く一個だけ咲いている。
楽しいお弁当タイムを済ませさらに刈入れの済んだ田園沿いを散策した。
今日の2番目の目的である「マメアサガオ」が午後になってもまだ咲いていた。

マメアサガオ
ヒルガオ科・サツマイモ属
アサガオト違って花は夏から秋にかけて咲き、
和名は小さい朝顔の意味
といただいた資料には書いてある。
午後に見に行ったので、もう可也つぼみかけていた。
朝顔はやっぱり、朝見るのが良いようだ。

あぜ道に群生している「ツルボ」

山道で見つけた秋の「ミョウガの花」

まだ、色ずいていない「ウベ」

民家の土手で見つけた「ショウキラン」

低地では珍しい?「ママコナ」

元気で熱心な観察仲間

今回最も見ごろの一つだった
「アゼムシロ」
”別名”ミゾカクシ”
キキョウ科・ミゾカクシ属
溝辺に多く繁っているので溝隠し。
田の畦にむしろを敷き詰めたように生えているので、
アゼムシロの別名が有る。
”
と戴いた資料に記してある。
楽しく、ちょっぴり疲れた、秋の一日だった。
今日の2番目の目的である「マメアサガオ」が午後になってもまだ咲いていた。

マメアサガオ
ヒルガオ科・サツマイモ属
アサガオト違って花は夏から秋にかけて咲き、
和名は小さい朝顔の意味
といただいた資料には書いてある。
午後に見に行ったので、もう可也つぼみかけていた。
朝顔はやっぱり、朝見るのが良いようだ。

あぜ道に群生している「ツルボ」

山道で見つけた秋の「ミョウガの花」

まだ、色ずいていない「ウベ」

民家の土手で見つけた「ショウキラン」

低地では珍しい?「ママコナ」

元気で熱心な観察仲間

今回最も見ごろの一つだった
「アゼムシロ」
”別名”ミゾカクシ”
キキョウ科・ミゾカクシ属
溝辺に多く繁っているので溝隠し。
田の畦にむしろを敷き詰めたように生えているので、
アゼムシロの別名が有る。
”
と戴いた資料に記してある。
楽しく、ちょっぴり疲れた、秋の一日だった。
ずっとご無沙汰していた、平尾台の野草仲間の散策に参加させてもらって
「ヒツジグサ」等の観察会に参加させて貰った。
連日の好天気で秋満開の小倉南区新道寺周辺を散策出来た。
当日の諸先生方お世話になりました。

当日教えてもらった資料によると
「ヒツジグサ」スイレン科・属
貧栄養の水質の池に生息する多年草。
未の刻に開くのでこの名前が付いた。
と記してある。

ヌマダイコン

ヤマジノホトトギス

花の名前は余り判らなかったけど、
久しぶりに食べた野外でのコンビニ弁当、
アルコール無し、
が皆さんとの会話で楽しく、美味しかった。

イノコズチ
これは子供の頃見た記憶が有る。
でも、これは茎が緑で「ヒカゲイノコズチ」らしい。
茎が、赤黒いのがヒナタ・・・・・らしい。

ダイコンソウ
これは葉が野生のダイコンに似ているので判る。
当日の先生方の説によると
”野に所謂「雑草」は無いそうだ!!
すべての草、花々はそれぞれの固有の名前を持っている”と
おっしゃっていた。
「ヒツジグサ」等の観察会に参加させて貰った。
連日の好天気で秋満開の小倉南区新道寺周辺を散策出来た。
当日の諸先生方お世話になりました。

当日教えてもらった資料によると
「ヒツジグサ」スイレン科・属
貧栄養の水質の池に生息する多年草。
未の刻に開くのでこの名前が付いた。
と記してある。

ヌマダイコン

ヤマジノホトトギス

花の名前は余り判らなかったけど、
久しぶりに食べた野外でのコンビニ弁当、
アルコール無し、
が皆さんとの会話で楽しく、美味しかった。

イノコズチ
これは子供の頃見た記憶が有る。
でも、これは茎が緑で「ヒカゲイノコズチ」らしい。
茎が、赤黒いのがヒナタ・・・・・らしい。

ダイコンソウ
これは葉が野生のダイコンに似ているので判る。
当日の先生方の説によると
”野に所謂「雑草」は無いそうだ!!
すべての草、花々はそれぞれの固有の名前を持っている”と
おっしゃっていた。
3月の”野焼き”から略一ヵ月過ぎた平尾台
まだ上手に鳴けない”鶯”の声を聞きながらの
野の花散策暑からず、寒からずの、素晴らしい仲間と天気のハイキングだった。
でも、終ってみれば可なり足に疲労が残っていた。

崖に咲いている”スズシロ”(↑)

????忘れた!!(↑)

よく観る実(↑)

色添えに赤も必要だ(↑)

”スゲの一種”(↑)
イネ科の植物?
長い穂花の上の方が”雄しべ”で下の方が”雌しべ”と教えてもらった

満開の桜(↑)
平尾台は標高が約500m位なので平地に比べてやはり気温が低い。
”千仏鍾乳洞の駐車場の桜”も今が満開だった

何処にでも有る”タンポポ”(↑)

何の”新芽”だろう?(↑)
近づくと”野生の雉”が飛び立ち皆びっくりした。
本当にビックリしたのは雉の方なんだけど!!
まだ上手に鳴けない”鶯”の声を聞きながらの
野の花散策暑からず、寒からずの、素晴らしい仲間と天気のハイキングだった。
でも、終ってみれば可なり足に疲労が残っていた。

崖に咲いている”スズシロ”(↑)

????忘れた!!(↑)

よく観る実(↑)

色添えに赤も必要だ(↑)

”スゲの一種”(↑)
イネ科の植物?
長い穂花の上の方が”雄しべ”で下の方が”雌しべ”と教えてもらった

満開の桜(↑)
平尾台は標高が約500m位なので平地に比べてやはり気温が低い。
”千仏鍾乳洞の駐車場の桜”も今が満開だった

何処にでも有る”タンポポ”(↑)

何の”新芽”だろう?(↑)
近づくと”野生の雉”が飛び立ち皆びっくりした。
本当にビックリしたのは雉の方なんだけど!!
はじめて「平尾台の野焼き」を見物した。
あらかじめ往復葉書で見物を申し込んでいた「茶ヶ床園地」で見物出来た。
朝8時過ぎに自宅を出8時から9時までの参加受付を済ませシャトルバスで見学地に到着したが、火入れまで1時間以上有る。先日老妻君が購入したビデオカメラの「取説」を持って来ていたのでそれを読みながらの実地テストなどをして、時間を過ごした。
常連さんらしい人達が、一番の撮影ポイントらしい地点に、カメラの三脚を並べ、さながら一眼レフカメラの展示会のようだった。
へー望遠レンズってこんなにデッカイのも有るんだー・・・・てな感じで、時間をつぶした。

駐車場に車を止めて、シャトルバスで見学地へ

その前に受付で見学許可章を貰う

常連さん、カメラマニア?ここが撮影ポイントらしい。

消防車も配置へ

稜線にはヘリコプターで人員配置

サイレント、花火の合図で野焼きが始まった

良く燃えている

見学地の360度火が着いているので、煙が廻ってきた

煙に包まれた

すぐ近くの点火

焼け跡

標識

消防車もお昼休み
午前の野焼きが済み自然の郷へ帰りのハイキング

手前の黒い所が焼け跡、奥の枯れ草が午後からの野焼き箇所
あらかじめ往復葉書で見物を申し込んでいた「茶ヶ床園地」で見物出来た。
朝8時過ぎに自宅を出8時から9時までの参加受付を済ませシャトルバスで見学地に到着したが、火入れまで1時間以上有る。先日老妻君が購入したビデオカメラの「取説」を持って来ていたのでそれを読みながらの実地テストなどをして、時間を過ごした。
常連さんらしい人達が、一番の撮影ポイントらしい地点に、カメラの三脚を並べ、さながら一眼レフカメラの展示会のようだった。
へー望遠レンズってこんなにデッカイのも有るんだー・・・・てな感じで、時間をつぶした。

駐車場に車を止めて、シャトルバスで見学地へ

その前に受付で見学許可章を貰う

常連さん、カメラマニア?ここが撮影ポイントらしい。

消防車も配置へ

稜線にはヘリコプターで人員配置

サイレント、花火の合図で野焼きが始まった

良く燃えている

見学地の360度火が着いているので、煙が廻ってきた

煙に包まれた

すぐ近くの点火

焼け跡

標識

消防車もお昼休み
午前の野焼きが済み自然の郷へ帰りのハイキング

手前の黒い所が焼け跡、奥の枯れ草が午後からの野焼き箇所














































