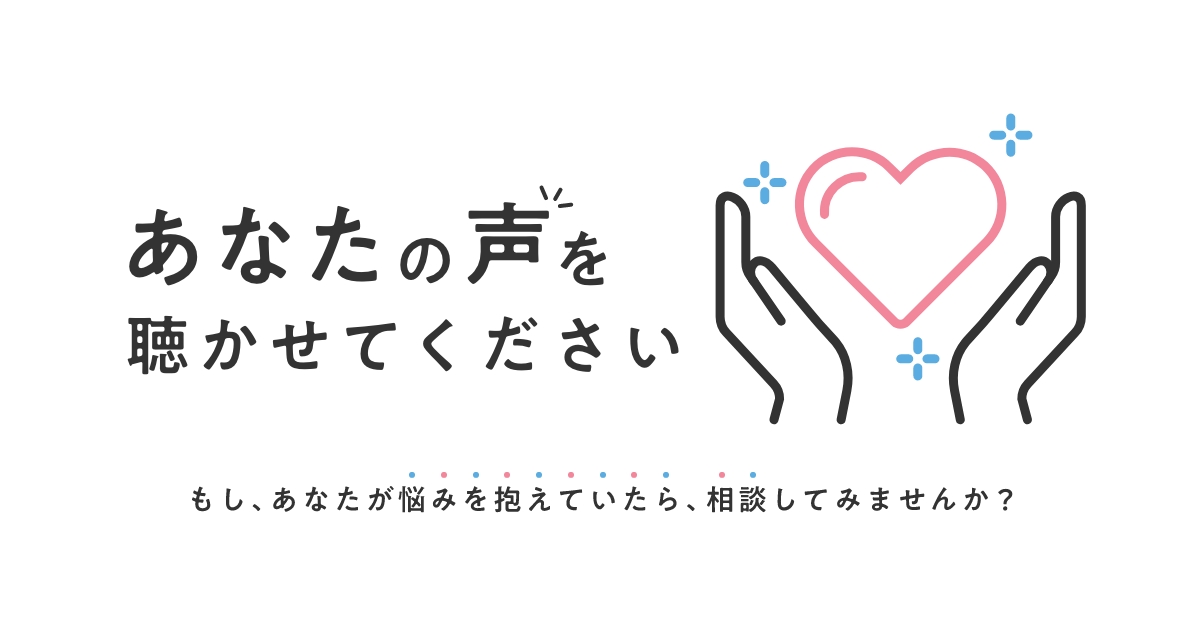最近日本で多くみられるニュースの見出し
オーバードース(ズ)
医薬品を指示以上の量を摂取すること。特に10代、20代での発生率が高い。
で、これに関して市販薬の規制などの話が出ています。それはここでは話しません。今日書きたいのは、そのような行動に出る青少年の動機は?サポートは? です。
酒や煙草や違法薬物に規制があっても使用する人がいるように規制の抑止力は一般の人が思うほど高くありません。 予防政策の方がずっと安価で効果が上がります。
オーバードースをした青少年の動機には
現実逃避 自殺企図 自傷行為
孤立化 ドロップアウト
などがあります。
調べてみると厚労者がこのようなサイトを作っています。
どれぐらいの方がご存じだろうか?学校、職場、近所で家族で広げて欲しい。このようなアクセスは重要です。しかしこれも最悪事態の予防になりますが上記に書いたような気持ちを予防するものではありません。
で、予防策の一つに社会単位での取組。特に学校や大学や職場です。さっき書いたようなサイトのポスターの掲示はもちろんですが、それぞれの団体でどれだけ力を入れているか?医療者や政府は把握しているのだろうか?
さあ、取組とは何か?例えば入学時、入職時のオリエンテーションに独自のサポートシステムの存在を説明する。そして団体それぞれでどれだけメンタルヘルスの教育が職員や関係者に行われているか?保健室の先生以外は生徒をなじるようなことを言ったり、SOSを無視するのでは予防に繋がりません。教員や関係者一人一人が知識を持つことは重要です。職場でもいじめが起こらないような環境づくりは、まず職員の教育から。「ハラスメントはダメ」と言ったらネガティブなものではなく、防止のためにできることの方向性で。
あと、司法への教育も重要です。例えば警察官。予防的な活動をしていますか?パトロール中に不審な子供達を見つけた時、どこへ相談したらこの子供達を救うことができるのか知っていますか?
私が働き住んでいる州ではSafety Check と言うシステムがあります。住人が住人の安全を危惧した時に警察に通報すると安否を確認してくれます。酒屋で酩酊状態の人がさらに酒を購入しに来たと通報することができます。特に車を運転していた、公の場で酩酊状態ならば違法にもなりますから。子供といる場合は本人だけではなく、子供の安否にもつながります。もちろん売らない選択もあります。売らないだけではなく、もう一歩。ここが重要なのです。
医療は医療者と言う事実は変わりませんが予防には医療者だけでは足りないのです。他の団体とコラボレーションすることで予防も大規模に行うことが可能になります。それを誰のリーダーシップでしていくのか?こんなところに看護職、とか看護のスカラーとかAPNとでてくるとかっこ良いのにね〜
冒頭写真: 暖冬で雪がない!!!それでもやっぱりスキー旅行です。北へ