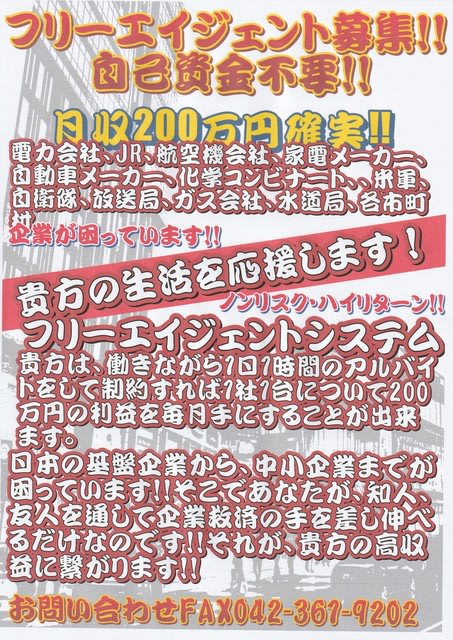日ロ平和条約といてう恫喝に安倍晋三も、たじたじ!!

ロシア側は、平和条約締結の条件として~
・第二次世界大戦の結果、北方領土をロシアに割
譲した。
・歯舞、色丹は渡すが、国後、択捉はロシア領とし
て国境線を引く。
・歯舞、色丹の住民は、国後、択捉にビザなして渡
航を許す。
・歯舞、色丹に米軍基地は置かない。
まあ虫のいい話である。こんな平和条約を締結して、シベリア開発に投資させられてなるもか!!
知られざる戦争「シベリア出兵」の凄惨な真実
 © Japan Business Press Co., Ltd. 提供 シベリア出兵の各国軍によるウラジオストクでの軍事パレード(出所:Wikipedia)
© Japan Business Press Co., Ltd. 提供 シベリア出兵の各国軍によるウラジオストクでの軍事パレード(出所:Wikipedia)
(佐藤 けんいち:著述家・経営コンサルタント、ケン・マネジメント代表)
いまだに解決しない北方領土問題。この問題がボトルネックとなり、いまだに日本とロシアの間では平和条約も締結されず、国境線の最終画定も終わっていない。
膠着状態はすでに75年に及んでおり、日本人にしては息が長いというべきかもしれないが、隣国関係としては異常な状態であることは否定しようがない。国際情勢が流動化し、近隣諸国との関係がギクシャクしがちな現在、北方の潜在的脅威は1日も早く取り除く必要がある。二正面作戦は絶対に避けなくてはならないからだ。
残念なことだが、日本とロシアの関係はこれまで必ずしも良好な関係であったわけではない。4次にわたる日露協商が締結されていた、日露戦争後からロシア革命に至るまでのごく短い「黄金の10年間」は例外として、第2次世界大戦の最末期の1945年8月9日から降伏文書が調印された9月2日までの約3週間にわたったソ連軍による満洲侵攻、南樺太(サハリン)と千島列島への侵攻がもたらした虐殺と略奪は、日本人に拭いがたい不信感を植え付けた。それらの侵攻は、「日ソ中立条約」を踏みにじっての対日戦参戦であり、その後の11年間に及ぶ過酷な「シベリア抑留」につながった。日本全土で空爆を実行し、広島と長崎に原爆を投下した米国よりも、ソ連が嫌いだという人が「冷戦」時代に少なくなかったのは、そのためだ。
この状況は、ソ連崩壊に伴う冷戦崩壊後も、基本的に大きな変化はないようだ。中国共産党政権が急速に膨張して巨大化した2010年代の現在でも、日本人のロシアに対する意識はあまり変化がないように見える。
シベリア出兵はいまだに“知られざる戦争”
だが、日本人は国際情勢の変化をよく認識する必要がある。 中ロを一体として見なすのはやめたほうがいい。
日ロ関係を理解するためには、まずは戦前の約70年間について振り返ってみておくことが重要だろう。
それは「熱戦」の時代であった。
日ロ間で戦われた4つの戦争とは、
・「日露戦争」(1904~1905)、
・「シベリア出兵」(1918~1925)、
・「ノモンハン事件」(1939年)、
・第2次世界大戦末期の日ソ戦(1945年)である。
これに満洲国とソ連との国境紛争であった「張鼓峰事件」(1938年)を加えるべきかもしれない。
日露戦争とノモンハン戦争、第2次世界大戦末期の日ソ戦については、何度となく映画やドラマ化されているので比較的よく知られていることだろう。
今回はその中から、多大な戦費と戦死者数を出したにもかかわらず、現在の日本ではいまだに“知られざる戦争”となっている「シベリア出兵」について重点的に取り上げたい。
前回のコラム記事(「高級チョコを日本に広めたロシア人が受けた仕打ち」http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55430)で、白系ロシア人のモロゾフ一家が難民として日本に移住することになった背景がこの戦争の時代であった。
「岸壁の母」で有名な京都府舞鶴市生まれの私は、シベリア抑留の話を耳にすることが多かった。
また、徳島市生まれの父方の祖父が「シベリア出兵」に出征している。そのため、戦前から戦後にかけて日本人が体験した2つの「シベリア」に長年にわたって強い関心を抱いてきた。
祖父の現地体験については、のちほど触れることにする。
ロシアから見たら侵略戦争だった
シベリア出兵は、第1次世界大戦(1914年7月~1918年11月)末期の1918年8月2日に始まった。ロシア本土からの撤兵は1922年10月25日、北樺太からの最終撤兵は1925年5月15日。足かけ7年に及ぶ戦争であった。
シベリア出兵は、多国籍軍による「シベリア干渉戦争」として始まり、後半は日本のみによる単独出兵となった。
戦費はトータルで約10億円(当時)、戦死者は3500人にも及んだが、ほとんど何も得ることなく終わったこの戦争は、「大正デモクラシー」という時代背景もあり、日本国内ではきわめて批判が多かった。
議会では中野正剛が激しく政府を攻撃し、「日本の近代漫画の祖」とされる北沢楽天による政治風刺漫画が人気を博していた。このような状況のなか、軍部は報道管制を行って都合の悪い情報はすべてシャットアウトし、戦地の正確な状況が国民の目から伏せられた。「知られざる戦争」となった理由がここにある。
だが、それだけではない。戦場となったロシアは革命後の大混乱のさなかであったとはいえ、日本からみればあくまでも他国の領土である。攻め込まれたロシアから見れば、侵略戦争以外の何物でもなかった。農民を主体にしたゲリラ部隊のパルチザンだけでなく、一般住民も多く巻き込まれ、虐殺され、略奪された。ロシアからみれば、日本は何をするか分からない恐ろしい国というイメージを残すことになったのである。この事実は、きちんと認識しておかねばならない。これが、第2次大戦末期のソ連軍侵攻とシベリア抑留につながっているのである。
『はいからさんが通る』とシベリア出兵
ここで、シベリア出兵当時の日本がどういう状況にあったかを見ておこう。
 © Japan Business Press Co., Ltd. 提供 『はいからさんが通る 新装版(1)』(大和和紀著、講談社)
© Japan Business Press Co., Ltd. 提供 『はいからさんが通る 新装版(1)』(大和和紀著、講談社)
『はいからさんが通る』は、1975年から77年にかけて発表された少女マンガだ。半世紀近くにわたって読み継がれてきた名作であるだけでなく、昨年(2018年)にはアニメ映画化されたほか、ドラマ化も何度もされてきた。宝塚歌劇の演目でもある。
『はいからさんが通る』の時代背景は大正ロマンの時代。現代の大学卒業式シーズンの女子大生の袴姿は大正時代のものだ。大正時代といえば「大正デモクラシー」だが、「原始女性は太陽であった」(平塚らいてう)というフレーズで有名なように、大正は「新しい女」の時代の始まりでもあった。働く女性が増えてきた時代でもある。前回のコラムで取り上げたように、「はいから」な洋風生活が浸透してきた時代でもある。
だが一方では、全国規模で爆発した米騒動(1918年)に始まり、シベリア出兵(1918~1925)、関東大震災(1923年)と、国内外で多事多難な時代でもあった。そもそも米騒動は、シベリア出兵宣言の翌日に始まっている。出兵に伴う食糧のコメ買い上げの噂が、さらなる米価急騰を招いたのも原因の1つであった。1973年の石油ショックの際に発生したトイレットペーパー買い占め事件を想起させるものがある。米騒動は陸軍の治安出動によって鎮圧されている。
大正時代は「大衆の時代」の始まりであるが、ロシア革命の影響もあって労働争議が多発し、明治末期の「大逆事件」後に逼塞していた社会主義運動も息を吹き返していた。1925年には「普通選挙法」が成立して成人男子すべてに選挙権が与えられたが、「治安維持法」と抱き合わせの成立であった。
マンガ『はいからさんが通る』は、そんな時代を背景にした作品だ。主人公の婚約者は帝国陸軍の少尉であり、シベリア出兵開始と同時に出征した設定になっている。「シベリア出兵」は、そんな大正時代の出来事であったことを、押さえておきたい。
以上
日本軍のシベリア出兵は多国籍軍による共同出兵として始まった!!
自衛官をシナイ半島の多国籍軍に派遣するのは、シベリア出兵と同じ行為であり、日本国を戦火の坩堝に落とし込んでしまう・・・。
クリックして応援を宜しくお願いします!!