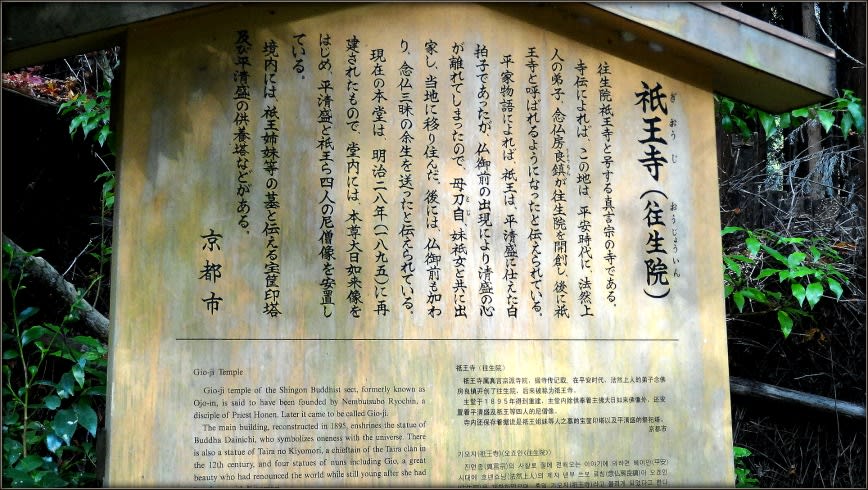あだし野は化野と記します。 「あだし」とは はかない、むなしいとの意で 又「化」の字は「生」が化して
「死」となり この世に再び生まれ化る事や 極楽浄土に往生する願いなどを意図しています。

仏 舎 利 塔 (納骨堂)

境内にまつる八千体を数える石仏・石塔は往古あだし野一帯に葬られた人々のお墓です。
何百年という歳月を経て無縁仏と化し あだし野の山野に散乱埋没していた石仏を
明治中期 地元の人々の協力を得て集め 釈迦宝塔説法を聴く人々になぞらえ配列安祀して
あります。 この無縁仏の霊にローソクをお供えする千灯供養は 地蔵盆の夕刻より行われ
光と闇と石仏が織りなす光景は浄土具現の感があり 多くの参詣があります。
賽(さい)の河原に模して 「西院の河原」 と名づけられました。


地 蔵 堂

竹 の 小径

竹の小径を上がっていくと 「六面体地蔵」がありました。
六道 ・・・ つまり 地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人道・天道 に対応する
六体の地蔵尊に向い 「オン・カカカ・ビサンマエイ・ソワカ」 と
唱えながら時計回りに回るとよいそうです。最初にどのお地蔵様から
拝むかも決まっているようでした。

地蔵真言 「オン・カカカ・ビサンマエイ・ソワカ」
この真言を唱えれば 五穀豊穣・敬愛和合・立身出世などの霊験が得られる。
「オン」は 帰命・供養などの意味があり 神聖な語として インドでは宗教的な言葉の
初めにおかれてきました。 「カ」とは お地蔵様の事で 「カカカ」とは お地蔵さま
お地蔵さま お地蔵さま と一生懸命お地蔵さまを呼ぶのです。
「ビサンマエイ」とは 類まれな尊いお方というような お地蔵さまへの賛歓の気持ちを
表しています。 「ソワカ」は 神聖な言葉の最後につけて その言葉の
完成成就を願う気持ちを表しています。











 実に凄い~ の一語につきました。
実に凄い~ の一語につきました。