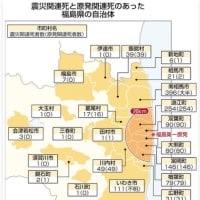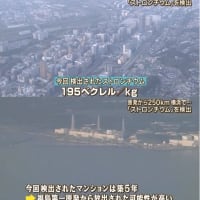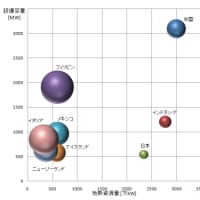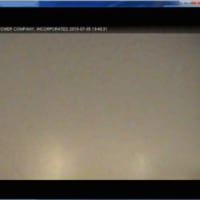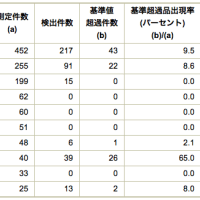夕方偶然、ギャラリーセラーでおこなわれている『鎌谷徹太郎 Proliferation Flower」展を拝見してきました。とてもすばらしい作品群が展示されていて鎌谷徹太郎君の才能をあらためて目の当たりにしました。日本のペインターの中でもトップクラスのアーティストだと僕は思います。朝3時頃に起き、夜の12時まで制作をしているそうです。大体睡眠時間は3時間~4時間、食事とお風呂以外の時間はすべて制作に当てていると伺い、正直驚きました。今回の大作は、1点書き上げるのに約1ヶ月近く時間をかけているそうです。日本のアート界は、かなりさみしい状況が続いていますが、いずれ遠からず明るい未来がやってくると信じています。パルコ出版から出ている『アートディーラー』という本をよかったら読んでみてほしいと、鎌谷徹太郎君にアドバイスしました。今回の展覧会では、『Proliferation Flower -Tribute to Monet –』というタイトルの図録も発行されています。大作5点が、スペースの都合上展示されないのは残念ですが、センス抜群の展覧会だと思います。僕はかなり好きです。以下、展覧会図録からテキストと作品を紹介します。
-----
鎌谷徹太郎 Tetsutaro kamatani(ギャラリーセラー)




Proliferation Flower -Tribute to Monet –
今回の展覧会で発表される鎌谷徹太郎の「Proliferation Flower」シリーズでは、タイトルの通り、増殖した花が画面を覆い尽くしている。一瞥すると、単純にきれいな花の絵だなと感じるだけなのであるが、じっと見ていると、何か不思議な感じが纏わりつく。近づいてみると、一つ一つの花弁は造花で、作家自身により加工、彩色された、本来この世に存在しないものであることが分かる。作家は存在しないものを、繰り返し増殖させて見せることで、本物の花とは違うリアリティーを表現しようとしているのである。「美しい花がある、花の美しさというものはない」という小林秀雄の有名なことばがあるが、鎌谷はどうも「花の美しさはある」といいたいようだ。
欧米のリアリズム(実在論)に対して、日本はもともとノミナリズ(唯名論)的で、美術においても、美しい風景、人物、花を描くことに主眼が置かれてきた。ノミナリズムとは、「普遍概念は名前として存在するのであり、実在するのは普遍概念の形相(フォルマ)ではなく、具体的な個物、つまり個々の具体的な人間や花である」と考える立場である。これに対して、リアリズム(実在論)は「人間や花などの類の概念が形相(普遍概念)として実在する」と考える立場である。リアリズムの立場からすると、人間が花を見て美しいと感じるのは「美という普遍概念(イデア)が実在し、個別の花に美のイデアが分有されているからである」ということになる。小林秀雄が、哲学的にはノミナリズ(唯名論)の立場から発言しているのに対し、鎌谷が逆の立場をとっていることは明白である。鎌谷により創りだされる絵画に、従来の日本の絵画と距離を感じるのもこのことが原因であろう。
鎌谷は、1979年にカラー映像、カラー印刷物が街にあふれる日本に生まれ、インターネットの普及とともに成長してきた。実物は知らないけれども、テレビやカラー印刷物を通してイメージとして認識しているという現象が頻繁に起こり、ネットを通して未知の情報にアクセスすることも容易になった時代である。彼らの世代に、先入観なしに物を見ることはもはや許されない。鎌谷が触発されたというモネは、対象物へのアプローチを「盲目に生まれ、突然一瞬にして目が見えるようになり、目の前のものがそもそも何であるのかを知らないで描き始めるときのことを想像した」と語っている。モネはモチーフに注がれた最初の鮮明な視線こそが、嘘偽りのないものであるとし、想像や先入観で曇っていない視線を重要視したからである。
今回の展覧会をモネに捧げると鎌谷は表現しているが、先入観を持たざるを得ない鎌谷が、リアリズムの立場を取ろうとした時、絵画の成立のさせ方は、モネと異なるアプローチを取らざるを得ない。したがって、哲学的な立場からモネに親近感を覚え、インスピレーションを得たということだと想像できる。波動力学を提唱し、量子力学の確立に貢献した物理学者、シュレーディンガーは「私たちの感覚や知覚は、一連の事象がたびたび同様にくり返されるならば、徐々に意識の領域から消えていき、精神は、自然哲学者の言う客観的な外的世界を、すべて自分自身の素材で造りあげる」といっている。鎌谷がこの言説を知っていたとは思えないが、造花を増殖させることによって、先入観を消し去り、新たな価値観を構築することによってリアリズムの立場をとろうとしていることは明白である。画面からは花の美しさというイデアを感じさせられるが、それは造花によって感じさせられているものであるがゆえに、従来のリアリズムとは隔たりがある。鎌谷がProliferation Flowerで提示しようとしているのは、イメージが現実と等価値に融合してしまった現代に初めて生まれる必然を持った、新世代のリアリズムとでもいうべきものであり、イデアに至るアプローチの違いからくるこの隔たりこそ、鎌谷の創り出す世界のオリジナリティーであり魅力であるといえるだろう。
(ギャラリーセラー テキストより)
-----
鎌谷徹太郎 Tetsutaro kamatani(ギャラリーセラー)




Proliferation Flower -Tribute to Monet –
今回の展覧会で発表される鎌谷徹太郎の「Proliferation Flower」シリーズでは、タイトルの通り、増殖した花が画面を覆い尽くしている。一瞥すると、単純にきれいな花の絵だなと感じるだけなのであるが、じっと見ていると、何か不思議な感じが纏わりつく。近づいてみると、一つ一つの花弁は造花で、作家自身により加工、彩色された、本来この世に存在しないものであることが分かる。作家は存在しないものを、繰り返し増殖させて見せることで、本物の花とは違うリアリティーを表現しようとしているのである。「美しい花がある、花の美しさというものはない」という小林秀雄の有名なことばがあるが、鎌谷はどうも「花の美しさはある」といいたいようだ。
欧米のリアリズム(実在論)に対して、日本はもともとノミナリズ(唯名論)的で、美術においても、美しい風景、人物、花を描くことに主眼が置かれてきた。ノミナリズムとは、「普遍概念は名前として存在するのであり、実在するのは普遍概念の形相(フォルマ)ではなく、具体的な個物、つまり個々の具体的な人間や花である」と考える立場である。これに対して、リアリズム(実在論)は「人間や花などの類の概念が形相(普遍概念)として実在する」と考える立場である。リアリズムの立場からすると、人間が花を見て美しいと感じるのは「美という普遍概念(イデア)が実在し、個別の花に美のイデアが分有されているからである」ということになる。小林秀雄が、哲学的にはノミナリズ(唯名論)の立場から発言しているのに対し、鎌谷が逆の立場をとっていることは明白である。鎌谷により創りだされる絵画に、従来の日本の絵画と距離を感じるのもこのことが原因であろう。
鎌谷は、1979年にカラー映像、カラー印刷物が街にあふれる日本に生まれ、インターネットの普及とともに成長してきた。実物は知らないけれども、テレビやカラー印刷物を通してイメージとして認識しているという現象が頻繁に起こり、ネットを通して未知の情報にアクセスすることも容易になった時代である。彼らの世代に、先入観なしに物を見ることはもはや許されない。鎌谷が触発されたというモネは、対象物へのアプローチを「盲目に生まれ、突然一瞬にして目が見えるようになり、目の前のものがそもそも何であるのかを知らないで描き始めるときのことを想像した」と語っている。モネはモチーフに注がれた最初の鮮明な視線こそが、嘘偽りのないものであるとし、想像や先入観で曇っていない視線を重要視したからである。
今回の展覧会をモネに捧げると鎌谷は表現しているが、先入観を持たざるを得ない鎌谷が、リアリズムの立場を取ろうとした時、絵画の成立のさせ方は、モネと異なるアプローチを取らざるを得ない。したがって、哲学的な立場からモネに親近感を覚え、インスピレーションを得たということだと想像できる。波動力学を提唱し、量子力学の確立に貢献した物理学者、シュレーディンガーは「私たちの感覚や知覚は、一連の事象がたびたび同様にくり返されるならば、徐々に意識の領域から消えていき、精神は、自然哲学者の言う客観的な外的世界を、すべて自分自身の素材で造りあげる」といっている。鎌谷がこの言説を知っていたとは思えないが、造花を増殖させることによって、先入観を消し去り、新たな価値観を構築することによってリアリズムの立場をとろうとしていることは明白である。画面からは花の美しさというイデアを感じさせられるが、それは造花によって感じさせられているものであるがゆえに、従来のリアリズムとは隔たりがある。鎌谷がProliferation Flowerで提示しようとしているのは、イメージが現実と等価値に融合してしまった現代に初めて生まれる必然を持った、新世代のリアリズムとでもいうべきものであり、イデアに至るアプローチの違いからくるこの隔たりこそ、鎌谷の創り出す世界のオリジナリティーであり魅力であるといえるだろう。
(ギャラリーセラー テキストより)