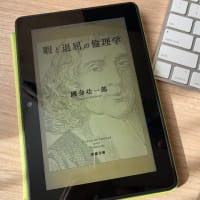グリーフサポート世田谷の松本さんが教えてくれて、
6月28日には坂上香監督のトークセッション付きの
「トークバック 沈黙を破る女たち」
のイベントに一緒に行った。

上映会場がとても面白いところで、
シネマチュプキタバタという
普通のビルを改装した、とってもかわいい映画館。
20人ほどの収容人数でバリアフリーの作りになっている。
「まちけん」という面白いグループが主催で、
全体にとってもほんわか、あたたかい、ゆったりした雰囲気。
終了後の懇親会にも参加して、坂上さんともお話できました。
ハワイでも上映会やりたいです。
映画はグループセラピーやサイコドラマを思い起こさせる。
映画に登場する劇団「メデア・プロジェクト」を率いるローデッサさん。
そこでどんな体験、感情を表現しても大丈夫だという場を
作っていく彼女の力量というか、タフさに圧倒された。
表現が楽しい、表現したらそれをわかるひともいた、表現してもいいんだ、
といった体験があれば、自分の内側に目を向けることに抵抗も少なくなる。
ここで思ったのは「自己表現」について。
日本の教育の中では表現教育がむっちゃ少ない。
チラチラと垣間見るハワイの学校教育の中で「ほぉ〜」と思ったことに
プレゼンテーションがやたらと多い、ということがある。
プレゼンテーション用の折りたたみボードが恒常的にロングスドラッグに売っている。
それだけ買う人たちがいるということなのだろう。
小学校でも中学校でも個人、あるいはグループで発表する機会が多い。
表現を促す場を作るためには、
さまざまな表現を受け入れることができる人が必要になる。
表現自体を「大事なこと」とする価値観がどれくらいあるか。
もう一つ、表現のためには自分の内面が「動いている」ことが必要になる。
気持ちが動く、心が動くとでもいえばいいのかな。
内面が動くけれどストップがかかってしまうのか、
動いていることに気づかないのか
内面に目を向けるということに慣れていないのか…。
「自己表現」というところから見ると、
「感じない子ども こころを扱えない大人」で書いたようなことが
まだ、続いているように感じる。
6月28日には坂上香監督のトークセッション付きの
「トークバック 沈黙を破る女たち」
のイベントに一緒に行った。


上映会場がとても面白いところで、
シネマチュプキタバタという
普通のビルを改装した、とってもかわいい映画館。
20人ほどの収容人数でバリアフリーの作りになっている。

「まちけん」という面白いグループが主催で、
全体にとってもほんわか、あたたかい、ゆったりした雰囲気。
終了後の懇親会にも参加して、坂上さんともお話できました。
ハワイでも上映会やりたいです。

映画はグループセラピーやサイコドラマを思い起こさせる。
映画に登場する劇団「メデア・プロジェクト」を率いるローデッサさん。
そこでどんな体験、感情を表現しても大丈夫だという場を
作っていく彼女の力量というか、タフさに圧倒された。
表現が楽しい、表現したらそれをわかるひともいた、表現してもいいんだ、
といった体験があれば、自分の内側に目を向けることに抵抗も少なくなる。

ここで思ったのは「自己表現」について。
日本の教育の中では表現教育がむっちゃ少ない。

チラチラと垣間見るハワイの学校教育の中で「ほぉ〜」と思ったことに
プレゼンテーションがやたらと多い、ということがある。
プレゼンテーション用の折りたたみボードが恒常的にロングスドラッグに売っている。
それだけ買う人たちがいるということなのだろう。
小学校でも中学校でも個人、あるいはグループで発表する機会が多い。

表現を促す場を作るためには、
さまざまな表現を受け入れることができる人が必要になる。
表現自体を「大事なこと」とする価値観がどれくらいあるか。

もう一つ、表現のためには自分の内面が「動いている」ことが必要になる。
気持ちが動く、心が動くとでもいえばいいのかな。
内面が動くけれどストップがかかってしまうのか、
動いていることに気づかないのか
内面に目を向けるということに慣れていないのか…。

「自己表現」というところから見ると、
「感じない子ども こころを扱えない大人」で書いたようなことが
まだ、続いているように感じる。