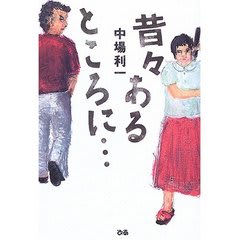≪『ゲゲゲの鬼太郎』が、文法的に正しい『ゲゲゲな鬼太郎』だったら、ここまで印象に残ったか?(助詞の使い方)『課長島耕作』の安定に比べ『取締役島耕作』の落着かなさは、「音」に理由がある!(韻とリズム)ツァラトストラが「こう言った」ではなく、「かく語りき」だったからこその豊かさとは?(古めかしい言い方で)『部屋とYシャツと私』で意図的に隠されている事柄とは?(言葉と言葉の距離)等々、著者が「ぐっときた」55の名タイトルを例に、心に残る理由を考察する。≫
新書としてはかなりくだけた(ふざけた)物言いで作品の顔ともいうべき題名(タイトル)を様々な角度から検証(弄び)した、コラムニスト『ブルボン小林』(作家 長嶋有の変名)の特異な視点と、ごり押しの理論が笑える。
タイトルをつけるのに日々、四苦八苦している人も、この本を読めば命名のエキスパートに……なるかどうかはわからないが、笑いをとる記述だけではなく、納得させられる記述も多々あり、個人的には、ためになった。(たぶん)
なんにせよ、題名(タイトル)を考えるのは、ある意味本編を紡ぎだすよりも難しい作業だ、と常々思っている。
新書としてはかなりくだけた(ふざけた)物言いで作品の顔ともいうべき題名(タイトル)を様々な角度から検証(弄び)した、コラムニスト『ブルボン小林』(作家 長嶋有の変名)の特異な視点と、ごり押しの理論が笑える。
タイトルをつけるのに日々、四苦八苦している人も、この本を読めば命名のエキスパートに……なるかどうかはわからないが、笑いをとる記述だけではなく、納得させられる記述も多々あり、個人的には、ためになった。(たぶん)
なんにせよ、題名(タイトル)を考えるのは、ある意味本編を紡ぎだすよりも難しい作業だ、と常々思っている。