・兵を起こし城を屠( ほふ )る。
漢検協会 完全征服より
ト
ほふ(る)、さ(く)、ころ(す)
屠
【解字】形声。尸+者。尸はしかばねの象形。音符の者トは、多く集まるの意味。死体が多く集まる、牛馬などを殺すの意味を表す。
- ほふる。
- 割く。牛馬などの肉を裂いてばらす。
<新漢語林より>
城市を攻めてその人を皆殺しにすることを 「沛ハイを屠る」 という。
”ほふる” という言葉自体今まで聞いたことがなかった。
辞書を引くと、”ほふる” は、”はふる” が変化したものとある。
でも ”はふる” にしたって同じこと。
語源のヒントと思われるものが、古事記にある。
「その蛇(オロチ)を切り散(ハフ)る」と。
”はふる” に関連した言葉を字訓(白川静)で調べてみた。
祝 (ハフリ) =穢れを祓い散らす
葬る(ハブル)=放り棄てる
溢る(ハフル) =あふれ出る
散る(ハフル) =ばらける
放る(ハフル) =追い払う
屠る(ハフル) =大きな集合体を切り裂く
”はふる” という言葉は全て「基点から離れる、離される」という共通の意味を持つ。
放る(はふる)⇒(ほふる)⇒(ほうる)
葬る(はぶる)⇒(はうむる)⇒(ほうむる)
という具合に変化していった。
--
屠を使った熟語には、「殺す」という意味を持った、
「」「屠腹」
などあるが、「屠蘇」もよく耳にする身近な言葉だ。
屠蘇(屠蘇散、屠蘇延命散)
元日、または三が日に祝儀として飲む薬酒。中国の習俗を伝えたもので、山椒などの生薬を調合した屠蘇散を袋(屠蘇袋)に入れ酒に浸して作る。一年中の邪気を祓い、齢を延ばすと言われ、日本では嵯峨天皇の平安時代から用いられた。中国では、蘇と呼ばれた鬼を屠るということを意味している。
現代日本では、単に正月に飲む酒のことしか指していないようです。
まあ、呑兵衛にとっては酒を飲める理由があれば何でもいいわけでして・・・。
「お屠蘇気分」











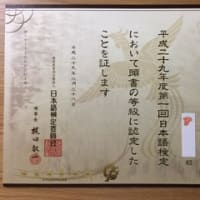
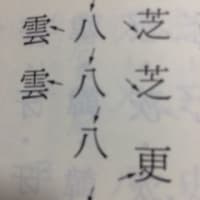
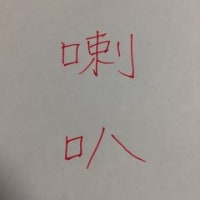





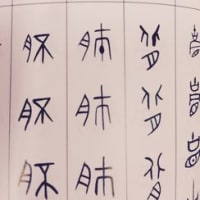








なんで「屠」なんて字が入ってるのかと思ってはみたものの、自分では調べませんでした。
ところで「屠」といえば、漢検の四字熟語辞典(初版第1刷)で、「屠」のついた
屠毒筆墨
屠竜之技
屠所之羊
…が準1級ということになってたんですが、これは1級ですよねぇ?
書物を屠り、竜を屠り、羊を屠る。
やっぱり意味は「ほふる」に違いはないですね。
『常用』に縛られず漢字は自由に
の記事、読ませていただきました。
heyqlowさんのご意見、わたしもその通りだと思います。
常用漢字は、試験するための範囲として設定しているような気がします。
「トンマな放送局」、わたしも子供週刊TVニュースかと思ったこともありました。
仰る通り、文章はバランスだと思います。
仮名と漢字のバランス、漢字の硬さを平仮名が補って調和が取れているはず。
人が読んで厭味にならない程度に漢字を使っていいと思う。
そうでなければ、人間としての素養・教養が失われてしまう。
「もちろん、わざわざむずかしい漢字をつかう必要はない。できるだけ漢字はすくないほうがいい。」
これは、異常ですねえ。常軌を逸してると思います。
まるで何かに洗脳されたような。。。
これは
「態々易しい漢字も無理して平仮名にしている」
ような気がしてなりません。
--
返事、遅くなり申し訳ありませんでした。
少し時期遅れの夏休みを過ごしていました。