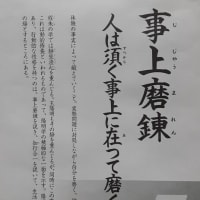先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人 第二十二回 (『祖国と青年』23年2月号掲載)
西郷隆盛 敬天愛人の思想3
永遠の維新者
明治元年十月、戊辰戦役の平定を見た西郷南洲は、後事を薩摩藩の盟友大久保利通と小松帯刀に託して、鹿児島の地へと戻った。
西郷には功を為し遂げた後の、恩賞に預かろうとの気持ちは毛頭無かった。四年前の元治元年、薩摩藩は西郷南洲の力を必要として沖永良部島から戻した。そして、西郷は亡君島津斉彬公の遺志を実現すべく至誠を尽くして奔走し、維新を成し遂げたのである。必要とされた自らの責務を果たし終えたと、西郷は考えた。この名利に対する恬淡さこそ、幾度も辛酸を経て生死超脱の境地に立った西郷の西郷らしい点である。西郷のその姿勢は遺訓の冒頭に次の様に語られている。
●廟堂(天下の大政を司る所・朝廷)に立ちて大政を為すは天道を行ふものなれば、些とも私を挟みては済まぬもの也。いかにも心を公平に操り、正道を踏み、広く賢人を選挙(推挙)し、能く其職に任ふる人を挙げて政柄を執らしむるは、即ち天意也。夫れゆゑ真に賢人と認むる以上は直に我が職を譲る程ならでは叶はぬものぞ。
西郷は、新政府の中枢に立って政治を切り盛りすることなど全く考えていなかった。それは自分の任では無いと思っていた。しかし自らの力が必要とされるなら、いつでも国家の為に尽くそうとの志は常に抱いていた。鹿児島では、藩主忠義から藩の参政に任じられ受けている。
だが、時代は西郷の力を求めた。明治三年十二月、勅使岩倉具視が大久保を同行して鹿児島を訪れ、朝権確立・親兵制(明治新政府は独自の軍隊を保有せず、各藩の軍隊に頼っていた)の必要で一致し、明治四年一月、西郷は鹿児島を出立した。西郷の尽力で薩摩・長州・土佐三藩の兵を徴して親兵が組織され、その上で「廃藩置県」を断行した。更に西郷は、明治天皇の輔導の任を全うすべく、七月には宮中改革を断行した。
『明治天皇紀』には「参議西郷隆盛以為らく」として次の様に記されている。
●国威を発揚せんとせば、宜しく根源に遡りて宮禁(宮中)の宿弊(古くからある弊害)を改めざるべからず。即ち華奢・柔弱の風ある旧公卿を宮中より排斥し、之れに代ふるに剛健・清廉の士を以てして聖徳を輔導(たすけみちびくこと)せしむるを肝要(非常に大切)とす
女官を大幅削減して、皇后の下に置き、天皇の回りには西郷の篤く信任する薩摩の村田新八や高島鞆之助、更には山岡鉄舟等剛直の士を侍従に任じた。明治天皇は、西郷の無私無欲の為人を深く尊敬されていた。西郷も明治天皇に純忠を尽くした。
明治五年の西国行幸時、熊本の小島出港の際に、海軍少輔の川村純義が干満時を間違えた結果、陛下の御乗船時刻が甚だしく遅れ、陪従していた西郷は、川村を叱って怒りに任せて西瓜を庭に投げつけた事があった。明治天皇は後々までこの事を話題にされて居た。又、六年四月末の習志野行軍の際、馬に乗って近衛兵の指揮を執って行軍される明治天皇に西郷は徒歩で付き従い、風雨激しき中天幕で野営される天皇を心配した西郷は、自らテントの前の歩哨に立った。明治天皇が西郷を如何に御信任されていたかは、五月五日皇城焼失の際、天皇は西郷がかつて献上した箪笥だけはまず取り出す様命じられた事からも伺われる。
六月六日、天皇は、西郷の肥満を憂えられて、侍医及び大学医学部の内科教師ドイツ人ドクトル・ホフマンを差遣された。西郷は恐縮して板垣退助宛の書簡に記した。
●少弟(私)此節の病気に付、主上(天皇陛下)より御沙汰を以、医師を被命治養仕候間、医師の命ずる通いたし来候所、最早治養所にては無之候得共、難有御沙汰を以加養いたし候付ては、死する前日迄は治養決て不怠と申居候位に御座候。
遣欧使節団との外交政策での対立
西郷の力を得て、内政が整い始めた明治新政府は、幕末に結んだ不平等条約の改正交渉の為に、使節団を欧米諸国に派遣する事を決定した。使節団は特命全権大使に岩倉具視、副使に木戸孝允、大久保利通、伊藤博文等を配す錚々たる陣容であった。明治四年十一月十二日、岩倉らは横浜を出帆した。当時は船しかなく、約二年に及ぶ外遊となる。
西郷にはその間の本国政府の舵取りが任された。先に記した様に西郷は明治天皇の側にあって純忠を尽くし、君徳の涵養を輔佐し奉った。
西郷は、新政府の高官達の華美な生活に極めて不快感を抱いていた。「遺訓」で西郷は荘内藩士達の前で涙を流しながら次の様に語ったという。
●万民の上に位する者、己を慎み、品行を正しくし、驕奢を戒め、節倹を勉め、職事に勤労して人民の標準となり、下民其の勤労を気の毒に思ふ様ならでは、政令は行はれ難し。然るに草創の始に立ちながら、家屋を飾り、衣服を文り、美妾を抱へ、蓄財を謀りなば、維新の功業は遂げられ間敷也。今と成りては、戊辰の義戦も偏へに私を営みたる姿に成り行き、天下に対し戦死者に対して面目無きぞとて、頻りに涙を催されける。
さらに西郷は、「文明」の本質を次の様に透徹していた。
●文明とは道の普く行はるるを賛称せる言にして、宮室の壮厳、衣服の美麗、外観の浮華を言ふには非ず。世人の唱ふる所、何が文明やら、何が野蛮やら些とも分らぬぞ。予嘗て或人と議論せしこと有り、西洋は野蛮ぢやと云ひしかば、否な文明ぞと争ふ。否な野蛮ぢやと畳みかけしに、何とて夫れ程に申すにやと推ししゆゑ、実に文明ならば、未開の国に対しなば、慈愛を本とし、懇々説諭して開明に導く可きに、左は無くして未開蒙昧の国に対する程むごく残忍の事を致し己れを利するは野蛮ぢやと申ししかば、其人口を莟めて言無かりきとて笑はれける。
日本が目差すべき文明とは、西欧の模倣では無く、東洋の王道に立脚した真の文明でなければならなかった。その為に、西郷は自らを厳しく律して行くと共に、天皇の御聖徳を輔佐し、天皇の政府に相応しい綱紀粛正にも意を注いだ。
明治六年六月、維新以来懸案だった朝鮮との外交問題が閣議に上がり、板垣退助等の武力出兵「征韓論」に反対し、西郷は使節派遣「遣韓論」を唱えた。あくまでも正道を踏み至誠を尽くして朝鮮と交渉を行い、朝鮮の非を改めさせるべきだと述べ、その難しい大任に自らが当る事を主張した。七月十七日、閣議は西郷の遣韓使節派遣を決定する。
だが、欧米との圧倒的な国力の差を実感して帰国した大久保利通は、朝鮮に西郷を派遣した結果戦争となり、紛争に欧米諸国が介入する事を恐れた。大久保は木戸や大隈重信等と岩倉をかついで閣議決定を覆した。十月二十三日、西郷の朝鮮派遣は中止と決定し、西郷は陸軍大将兼参議、近衛都督の辞表を提出(明治天皇の思し召しで陸軍大将のみは留任)、二十八日には横浜から出帆して鹿児島に戻った。
この間の対立を葦津珍彦氏は『大アジア主義と頭山満』の中で
「西郷は、日本の国権を維持し独立を確保して行くのには、絶えず欧米列強の圧力に対する抵抗の決意が大切なのだと信じている。ここでの論争の直接の問題点は、韓国の事に関しているけれども、真実の論争点は、むしろ欧米列強に対する日本外交の姿勢を、いかに定めねばならないかという点についての対決なのである。」と記している。
西郷はあえて争わず、自ら身を引いた。名利にこだわらぬ西郷にとってはごく自然な身の処し方だった。だが、時代は、明治政府の路線とそれに反する立場を取る者達との抜き差しならぬ対立へと向っていた。西郷に心酔する桐野利秋や村田新八等薩摩の猛者達は大挙して西郷の後を追った。板垣退助は土佐に戻って自由民権運動を起こす。江藤新平は佐賀に戻った。
帰郷した西郷は、次代を担う有為なる人材を養成すべく、明治七年六月に私学校(銃隊学校・賞典学校・吉野開墾社)を創設し、自らその綱領を記した。
●一、道を同じうし、義相協うを以て暗に聚合せり。故に此の理を益研究して、道義に於いては一身を顧みず、必ず踏み行うべき事。
一、王を尊び民を憐むは学問の本旨、然れば此の天理を極め、人民の義務に臨みては一向難に当り、一統の義を相立つべき事
西郷が私学校を創設した目的は、天皇に一大事が起きた時と諸外国との間に紛争が起きた時、国難に身を以て当る兵士を養成する事だった。
それ故、明治七年の佐賀、明治九年の熊本、秋月、萩に於ける反政府挙兵が続いて行く中でも西郷は動かなかった。
しかし、西郷隆盛を中心に団結する鹿児島は国家内国家の如き様相を呈し、明治政府にとって大変な脅威と見られる様になって行く。政府は間諜を放って私学校の動向を探り、弾薬庫の引上げを画策する。それを察知した私学校の一部生徒等は弾薬庫を襲い、捕えた警視庁帰郷者から西郷暗殺の口供が為され、生徒等は憤激する。幹部等が協議した結果、政府尋問の為、陸軍大将である西郷隆盛が挙兵上京する事に決した。
かくて、明治十年二月十七日、西郷は私学校一万三千の兵と共に鹿児島を出立した。しかし、熊本城で進軍を阻止され、田原坂の激戦に破れて敗退し、延岡迄転進するも戦い利非ずして鹿児島に戻って城山に籠もり、政府軍総攻撃の九月二十四日、銃弾に傷つき、自刃して亡くなった。享年五十歳だった。
何故、西郷は起ったのか。勝海舟は「ぬれぎぬをほそうともせず子供等がなすがまにまに果てし君かな」と歌を手向けたが、私学校の生徒達に身を預けたという一面も確かに有った。しかし、西郷南洲にとって政府の腐敗堕落に対する厳しい怒り、維新の理想喪失に対する深い悲しみがあった事も事実である。だが、明治天皇を擁する政府に対し軍事攻撃を仕掛ける事は西郷には出来なかった。あくまでも、明治天皇から任じられた「陸軍大将」として天皇の政府に対して「政府え尋問の筋これあり」と、天下に大義を明らかにする為に立ち上がったのである。
西郷は「人」を見つめてはいない、「天」を見つめている。一時の勝ち負けが問題では無い。政府の非を正す為に、自らの誠を尽す事、それが薩摩武士達の堂々たる進軍であった。確かにそれは、政府軍の近代戦法に敗れざるを得なかった。だが、敗れる事で「大義」を歴史に刻んだのである。
明治天皇は、西郷の死を深く悲しまれた。
『明治天皇紀 第四』には
「乱平ぐの後一日、天皇、「西郷隆盛」と云ふ勅題を皇后に賜ひ、隆盛今次の過罪を論じて既往の勲功を棄つることなかれと仰せらる、皇后乃ち、『薩摩潟しつみし波の浅からぬ はしめの違ひ末のあはれさ』と詠じて上りたまふ、皇后又嘗て侍講元田永孚に語りたまはく、近時聖上侍臣を親愛したまひ、毎夜召して御談話あり、大臣・将校を接遇したまふこと亦厚し、隆盛以下の徒をして早く此の状を知らしめば、叛乱或は起こらざりしならんと、」とある。
高島鞆之助は「翁の没後、吾輩が御前に伺候すると、陛下には能く翁の事をお話しなすっては、往時を追懐遊ばしてあの時西郷は斯う言つたとか、あの時にはこうしたとか仰せ給ふたものぢや。」と記している。明治天皇は、国家の柱石の臣を失ったこの様な悲劇は二度と起こしてはならないと、政治全般に亘って強い御自覚を抱かれたと言う。
そして、明治二十二年二月十一日、大日本帝国憲法発布に際し、大赦で罪を赦され正三位を追贈されたのである。
敬天愛人の思想
西郷南洲は、沖永良部に流された三十六歳の時既に、世俗を超脱し、天命を聞き、その声に随って生きて行く自らの人生哲学を体得したのではないだろうか。爾後の十四年の行動は、俗世の物差しでは、維新の大業と明治六年政変敗北による隠棲、西南戦争での敗死と、前半の功業に比べ後半の悲劇が強調されるが、西郷南洲にとっては、一貫して誠を尽くし、天の命じるままに行動した結果に他ならない。西郷の死は天が与えた命を果たし終えた安堵と共にあったのではなかろうか。
●道は天地自然の物にして、人は之を行ふものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛し給ふゆゑ、我を愛する心を以て人を愛する也。
●人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして、己を尽し人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし。
我々は、俗世の毀誉褒貶に愛想を尽かして、「天を相手にせよ」「天を敬する」とか良く口にするが、それは、その時だけの事が多い。真に天のみを相手にして生きる様になるには、不断の修養と自省が伴わなければならず、心に少しの曇りでもあったなら、天の声は聞えて来ないのである。
西郷南洲は「外甥政直に示す」と題し、
●一貫す唯唯の諾、従来鉄石の肝。貧居傑士を生み、勲業多難に顕はる。雪に耐へて梅花麗しく、霜を経て楓葉丹し。
如し能く天意を識らば、豈敢て自から安きを謀らむや。
と詩を書き与えているが、我々もこの詩を心に刻んで、安きを謀らずに、日々の任に当たって行くしかない。
西郷隆盛 敬天愛人の思想3
永遠の維新者
明治元年十月、戊辰戦役の平定を見た西郷南洲は、後事を薩摩藩の盟友大久保利通と小松帯刀に託して、鹿児島の地へと戻った。
西郷には功を為し遂げた後の、恩賞に預かろうとの気持ちは毛頭無かった。四年前の元治元年、薩摩藩は西郷南洲の力を必要として沖永良部島から戻した。そして、西郷は亡君島津斉彬公の遺志を実現すべく至誠を尽くして奔走し、維新を成し遂げたのである。必要とされた自らの責務を果たし終えたと、西郷は考えた。この名利に対する恬淡さこそ、幾度も辛酸を経て生死超脱の境地に立った西郷の西郷らしい点である。西郷のその姿勢は遺訓の冒頭に次の様に語られている。
●廟堂(天下の大政を司る所・朝廷)に立ちて大政を為すは天道を行ふものなれば、些とも私を挟みては済まぬもの也。いかにも心を公平に操り、正道を踏み、広く賢人を選挙(推挙)し、能く其職に任ふる人を挙げて政柄を執らしむるは、即ち天意也。夫れゆゑ真に賢人と認むる以上は直に我が職を譲る程ならでは叶はぬものぞ。
西郷は、新政府の中枢に立って政治を切り盛りすることなど全く考えていなかった。それは自分の任では無いと思っていた。しかし自らの力が必要とされるなら、いつでも国家の為に尽くそうとの志は常に抱いていた。鹿児島では、藩主忠義から藩の参政に任じられ受けている。
だが、時代は西郷の力を求めた。明治三年十二月、勅使岩倉具視が大久保を同行して鹿児島を訪れ、朝権確立・親兵制(明治新政府は独自の軍隊を保有せず、各藩の軍隊に頼っていた)の必要で一致し、明治四年一月、西郷は鹿児島を出立した。西郷の尽力で薩摩・長州・土佐三藩の兵を徴して親兵が組織され、その上で「廃藩置県」を断行した。更に西郷は、明治天皇の輔導の任を全うすべく、七月には宮中改革を断行した。
『明治天皇紀』には「参議西郷隆盛以為らく」として次の様に記されている。
●国威を発揚せんとせば、宜しく根源に遡りて宮禁(宮中)の宿弊(古くからある弊害)を改めざるべからず。即ち華奢・柔弱の風ある旧公卿を宮中より排斥し、之れに代ふるに剛健・清廉の士を以てして聖徳を輔導(たすけみちびくこと)せしむるを肝要(非常に大切)とす
女官を大幅削減して、皇后の下に置き、天皇の回りには西郷の篤く信任する薩摩の村田新八や高島鞆之助、更には山岡鉄舟等剛直の士を侍従に任じた。明治天皇は、西郷の無私無欲の為人を深く尊敬されていた。西郷も明治天皇に純忠を尽くした。
明治五年の西国行幸時、熊本の小島出港の際に、海軍少輔の川村純義が干満時を間違えた結果、陛下の御乗船時刻が甚だしく遅れ、陪従していた西郷は、川村を叱って怒りに任せて西瓜を庭に投げつけた事があった。明治天皇は後々までこの事を話題にされて居た。又、六年四月末の習志野行軍の際、馬に乗って近衛兵の指揮を執って行軍される明治天皇に西郷は徒歩で付き従い、風雨激しき中天幕で野営される天皇を心配した西郷は、自らテントの前の歩哨に立った。明治天皇が西郷を如何に御信任されていたかは、五月五日皇城焼失の際、天皇は西郷がかつて献上した箪笥だけはまず取り出す様命じられた事からも伺われる。
六月六日、天皇は、西郷の肥満を憂えられて、侍医及び大学医学部の内科教師ドイツ人ドクトル・ホフマンを差遣された。西郷は恐縮して板垣退助宛の書簡に記した。
●少弟(私)此節の病気に付、主上(天皇陛下)より御沙汰を以、医師を被命治養仕候間、医師の命ずる通いたし来候所、最早治養所にては無之候得共、難有御沙汰を以加養いたし候付ては、死する前日迄は治養決て不怠と申居候位に御座候。
遣欧使節団との外交政策での対立
西郷の力を得て、内政が整い始めた明治新政府は、幕末に結んだ不平等条約の改正交渉の為に、使節団を欧米諸国に派遣する事を決定した。使節団は特命全権大使に岩倉具視、副使に木戸孝允、大久保利通、伊藤博文等を配す錚々たる陣容であった。明治四年十一月十二日、岩倉らは横浜を出帆した。当時は船しかなく、約二年に及ぶ外遊となる。
西郷にはその間の本国政府の舵取りが任された。先に記した様に西郷は明治天皇の側にあって純忠を尽くし、君徳の涵養を輔佐し奉った。
西郷は、新政府の高官達の華美な生活に極めて不快感を抱いていた。「遺訓」で西郷は荘内藩士達の前で涙を流しながら次の様に語ったという。
●万民の上に位する者、己を慎み、品行を正しくし、驕奢を戒め、節倹を勉め、職事に勤労して人民の標準となり、下民其の勤労を気の毒に思ふ様ならでは、政令は行はれ難し。然るに草創の始に立ちながら、家屋を飾り、衣服を文り、美妾を抱へ、蓄財を謀りなば、維新の功業は遂げられ間敷也。今と成りては、戊辰の義戦も偏へに私を営みたる姿に成り行き、天下に対し戦死者に対して面目無きぞとて、頻りに涙を催されける。
さらに西郷は、「文明」の本質を次の様に透徹していた。
●文明とは道の普く行はるるを賛称せる言にして、宮室の壮厳、衣服の美麗、外観の浮華を言ふには非ず。世人の唱ふる所、何が文明やら、何が野蛮やら些とも分らぬぞ。予嘗て或人と議論せしこと有り、西洋は野蛮ぢやと云ひしかば、否な文明ぞと争ふ。否な野蛮ぢやと畳みかけしに、何とて夫れ程に申すにやと推ししゆゑ、実に文明ならば、未開の国に対しなば、慈愛を本とし、懇々説諭して開明に導く可きに、左は無くして未開蒙昧の国に対する程むごく残忍の事を致し己れを利するは野蛮ぢやと申ししかば、其人口を莟めて言無かりきとて笑はれける。
日本が目差すべき文明とは、西欧の模倣では無く、東洋の王道に立脚した真の文明でなければならなかった。その為に、西郷は自らを厳しく律して行くと共に、天皇の御聖徳を輔佐し、天皇の政府に相応しい綱紀粛正にも意を注いだ。
明治六年六月、維新以来懸案だった朝鮮との外交問題が閣議に上がり、板垣退助等の武力出兵「征韓論」に反対し、西郷は使節派遣「遣韓論」を唱えた。あくまでも正道を踏み至誠を尽くして朝鮮と交渉を行い、朝鮮の非を改めさせるべきだと述べ、その難しい大任に自らが当る事を主張した。七月十七日、閣議は西郷の遣韓使節派遣を決定する。
だが、欧米との圧倒的な国力の差を実感して帰国した大久保利通は、朝鮮に西郷を派遣した結果戦争となり、紛争に欧米諸国が介入する事を恐れた。大久保は木戸や大隈重信等と岩倉をかついで閣議決定を覆した。十月二十三日、西郷の朝鮮派遣は中止と決定し、西郷は陸軍大将兼参議、近衛都督の辞表を提出(明治天皇の思し召しで陸軍大将のみは留任)、二十八日には横浜から出帆して鹿児島に戻った。
この間の対立を葦津珍彦氏は『大アジア主義と頭山満』の中で
「西郷は、日本の国権を維持し独立を確保して行くのには、絶えず欧米列強の圧力に対する抵抗の決意が大切なのだと信じている。ここでの論争の直接の問題点は、韓国の事に関しているけれども、真実の論争点は、むしろ欧米列強に対する日本外交の姿勢を、いかに定めねばならないかという点についての対決なのである。」と記している。
西郷はあえて争わず、自ら身を引いた。名利にこだわらぬ西郷にとってはごく自然な身の処し方だった。だが、時代は、明治政府の路線とそれに反する立場を取る者達との抜き差しならぬ対立へと向っていた。西郷に心酔する桐野利秋や村田新八等薩摩の猛者達は大挙して西郷の後を追った。板垣退助は土佐に戻って自由民権運動を起こす。江藤新平は佐賀に戻った。
帰郷した西郷は、次代を担う有為なる人材を養成すべく、明治七年六月に私学校(銃隊学校・賞典学校・吉野開墾社)を創設し、自らその綱領を記した。
●一、道を同じうし、義相協うを以て暗に聚合せり。故に此の理を益研究して、道義に於いては一身を顧みず、必ず踏み行うべき事。
一、王を尊び民を憐むは学問の本旨、然れば此の天理を極め、人民の義務に臨みては一向難に当り、一統の義を相立つべき事
西郷が私学校を創設した目的は、天皇に一大事が起きた時と諸外国との間に紛争が起きた時、国難に身を以て当る兵士を養成する事だった。
それ故、明治七年の佐賀、明治九年の熊本、秋月、萩に於ける反政府挙兵が続いて行く中でも西郷は動かなかった。
しかし、西郷隆盛を中心に団結する鹿児島は国家内国家の如き様相を呈し、明治政府にとって大変な脅威と見られる様になって行く。政府は間諜を放って私学校の動向を探り、弾薬庫の引上げを画策する。それを察知した私学校の一部生徒等は弾薬庫を襲い、捕えた警視庁帰郷者から西郷暗殺の口供が為され、生徒等は憤激する。幹部等が協議した結果、政府尋問の為、陸軍大将である西郷隆盛が挙兵上京する事に決した。
かくて、明治十年二月十七日、西郷は私学校一万三千の兵と共に鹿児島を出立した。しかし、熊本城で進軍を阻止され、田原坂の激戦に破れて敗退し、延岡迄転進するも戦い利非ずして鹿児島に戻って城山に籠もり、政府軍総攻撃の九月二十四日、銃弾に傷つき、自刃して亡くなった。享年五十歳だった。
何故、西郷は起ったのか。勝海舟は「ぬれぎぬをほそうともせず子供等がなすがまにまに果てし君かな」と歌を手向けたが、私学校の生徒達に身を預けたという一面も確かに有った。しかし、西郷南洲にとって政府の腐敗堕落に対する厳しい怒り、維新の理想喪失に対する深い悲しみがあった事も事実である。だが、明治天皇を擁する政府に対し軍事攻撃を仕掛ける事は西郷には出来なかった。あくまでも、明治天皇から任じられた「陸軍大将」として天皇の政府に対して「政府え尋問の筋これあり」と、天下に大義を明らかにする為に立ち上がったのである。
西郷は「人」を見つめてはいない、「天」を見つめている。一時の勝ち負けが問題では無い。政府の非を正す為に、自らの誠を尽す事、それが薩摩武士達の堂々たる進軍であった。確かにそれは、政府軍の近代戦法に敗れざるを得なかった。だが、敗れる事で「大義」を歴史に刻んだのである。
明治天皇は、西郷の死を深く悲しまれた。
『明治天皇紀 第四』には
「乱平ぐの後一日、天皇、「西郷隆盛」と云ふ勅題を皇后に賜ひ、隆盛今次の過罪を論じて既往の勲功を棄つることなかれと仰せらる、皇后乃ち、『薩摩潟しつみし波の浅からぬ はしめの違ひ末のあはれさ』と詠じて上りたまふ、皇后又嘗て侍講元田永孚に語りたまはく、近時聖上侍臣を親愛したまひ、毎夜召して御談話あり、大臣・将校を接遇したまふこと亦厚し、隆盛以下の徒をして早く此の状を知らしめば、叛乱或は起こらざりしならんと、」とある。
高島鞆之助は「翁の没後、吾輩が御前に伺候すると、陛下には能く翁の事をお話しなすっては、往時を追懐遊ばしてあの時西郷は斯う言つたとか、あの時にはこうしたとか仰せ給ふたものぢや。」と記している。明治天皇は、国家の柱石の臣を失ったこの様な悲劇は二度と起こしてはならないと、政治全般に亘って強い御自覚を抱かれたと言う。
そして、明治二十二年二月十一日、大日本帝国憲法発布に際し、大赦で罪を赦され正三位を追贈されたのである。
敬天愛人の思想
西郷南洲は、沖永良部に流された三十六歳の時既に、世俗を超脱し、天命を聞き、その声に随って生きて行く自らの人生哲学を体得したのではないだろうか。爾後の十四年の行動は、俗世の物差しでは、維新の大業と明治六年政変敗北による隠棲、西南戦争での敗死と、前半の功業に比べ後半の悲劇が強調されるが、西郷南洲にとっては、一貫して誠を尽くし、天の命じるままに行動した結果に他ならない。西郷の死は天が与えた命を果たし終えた安堵と共にあったのではなかろうか。
●道は天地自然の物にして、人は之を行ふものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛し給ふゆゑ、我を愛する心を以て人を愛する也。
●人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして、己を尽し人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし。
我々は、俗世の毀誉褒貶に愛想を尽かして、「天を相手にせよ」「天を敬する」とか良く口にするが、それは、その時だけの事が多い。真に天のみを相手にして生きる様になるには、不断の修養と自省が伴わなければならず、心に少しの曇りでもあったなら、天の声は聞えて来ないのである。
西郷南洲は「外甥政直に示す」と題し、
●一貫す唯唯の諾、従来鉄石の肝。貧居傑士を生み、勲業多難に顕はる。雪に耐へて梅花麗しく、霜を経て楓葉丹し。
如し能く天意を識らば、豈敢て自から安きを謀らむや。
と詩を書き与えているが、我々もこの詩を心に刻んで、安きを謀らずに、日々の任に当たって行くしかない。