年を取ると
自然とドナーツから遠ざかります。
油っぽ食品は避けるようになります。
セブンのドーナツは1回しか食べたことがありません。
油は使った時点で酸化が進みます、
体には有害です。
でも
好きなのに食べないのも精神的によくないので
食べたい時は食べるでいいのでは?
そーすから
昔から傷んだ油は体に悪いと言われてきました。下痢をするだけではなく、脂肪肝や肝臓がんに繋がるという見方もある一方で、最近では酸化した油に害がないなどと言って、揚げ物の油は継ぎ足しだけで交換しないという意見も見られます。
それでも、国内で行われた「普通に調理に使った油」を使用した実験では、やはり古い油は脂肪肝の原因になる可能性が高いことを示していました。
酸化した油に害がないと主張する人たちの論拠は「実験に使う酸化した油というのが極端な物ばかりで、そこまで悪くなった油は不味くて食べられないから、普通に食べられる範囲のものであれば害はないはずだ」という事です。
確かに、さまざまな動物実験などで害の有無を調べる場合、極端な内容や量を使うことが多いのは事実です。しかし、だからと言って害がないと断定してしまうのはどんなものでしょう。調べたところ、面白い実験結果がありました。
ある大学の研究室が、揚げ物を作っている工場から、実際に使っている油をもらってきたそうです。交換時期が来たものや、まだ交換時期ではなく今まさに使っているもの、さらには使う前の新品の油を分けてもらい、それを瓶に詰めて窒素封入し、それ以上傷まないように保管したものを、実験室に持ち帰って実験用ラットに食べさせる実験を行いました。
まずはラットのエサから油分を抜いたものを準備して、それに抜いた油分に相当する量の実験用油を加えて食べさせます。比較グループのラットには、同じ量の新品の油を加えたとあります。これなら、私たちの生活感覚に沿ったものと言えそうで、油分の摂り過ぎによる害も除外して研究できますね。
そのエサで6週間育てたラットの変化を調べたところ、体重の増減については差が出なかったそうです。しかし、新鮮な油を食べさせたものに比べて、悪くなった油で育てたラットの体重に対する肝臓の重さが重くなっていた(脂肪肝の兆候を示した)という結果が得られています。
また、酵素などの検査から新鮮な油を食べさせたものに比べて、悪くなった油で育てたラットの活性酸素の処理能力が、明らかに低くなっていたという実験結果も出ています。
これらのことだけでは、酸化した油はどのように害があるのかまでは具体的に決定できませんが、悪影響があるであろうことは強く示唆されていますね。実験レポートは今後の詳細な研究が必要と締めくくられていますから、やはり悪くなった油の健康に対する害は存在しているようです。
油脂はグリセリンというものと、脂肪酸というものが組み合わさってできています。そして油の酸化とは、油を構成する脂肪酸が酸化するという事なのです。大変たくさんの種類がある脂肪酸ですが、構造的に共通点のある次の4種類の脂肪酸を見て下さい。
•ラードやヘットに多く含まれる飽和脂肪酸のステアリン酸
•オリーブオイルや椿油に多く含まれる不飽和ω9脂肪酸のオレイン酸
•一般に植物性の油に多く含まれる不飽和ω6脂肪酸のリノール酸
•エゴマ油に特に多く含まれる不飽和ω3脂肪酸のα-リノレン酸
この4つの脂肪酸は、すべて骨格に炭素を18個持つという共通要素のあるものですが、酸化されにくい順に並べました。そして飽和不飽和を決める「二重結合」という部分が少ない順でもあります。ステアリン酸は飽和なので0ヶ所。あとは順に1~3ヶ所になっています。
α-リノレン酸は最近人気の健康油の成分なのに、ちょっとショックですよね。でももっとショックなこともあります。魚油の健康成分EPAは、二重結合が5ヶ所、DHAに至っては6ヶ所もあるので、ものすごく酸化されやすいんです。
ですから魚は新鮮なうちに食べましょうって話にもなりますね。でも酸化されにくいからと言って、飽和脂肪酸をたくさん摂っていたのでは、違う病気が心配になります。植物油をやめてラードに変えましょう、なんて思わないですよね。
用途に応じて油を選びましょう
油をもっとも酸化させるのは、揚げ物を作る時です。ですので揚げ物に使う油は酸化しにくい油を選び、家庭では一回使ったら翌日は炒め物などに使用するか、それでも余った分は捨ててしまいましょう。
使用済み揚げ油の回収は、スーパーの店頭にある専用容器や、自治会で設定された回収日などで行われていると思いますから、地元の市区町村役場にお尋ねになって下さい。実際に使う油はについては、二つの考え方があります。
ラード(豚脂)、ヘット(牛脂)、パームオイル(アブラヤシ油)、ココナッツオイル(ココヤシ油)あたりが、酸化に対しては最も強いですが、これらを揚げ物で使うと飽和脂肪酸の摂取量が増えすぎてよくありません。
しかし、飽和脂肪酸はゼロにすればいいというものでもなく、少なすぎるのもまた健康に悪影響を与えます。ですので、揚げ物は月に一回か二回程度しか食べないという人なら、ラードでの揚げ物はいいと思います。そもそも一番おいしく揚がりますしね。
一方、週一以上は食べるという人は、安いオリーブオイルで揚げ物を作るのがお勧めです。もちろん同じようにオレイン酸の多い椿油もOKというか、個人的にはエビのてんぷらには最高だと思いますが、お値段がちょっと美味しくないです。
また、キャノーラ油やハイオレック系の紅花油・ひまわり油も、オレイン酸の含有率という意味では好ましいのですが、逆に飽和脂肪酸の量が少なすぎます。肉類の揚げ物に使うのなら構わないものの、野菜の揚げ物やコロッケ程度が中心なら、よくない可能性が高くなります。
ソースから
店舗数国内2位のドーナツ専門店「クリスピー・クリーム・ドーナツ」(以下、クリスピークリーム)の閉店が止まらない。
今年に入り、京都府、広島県、福岡県などから全面撤退したのをはじめ、都内でも神田小川町や阿佐ヶ谷、玉川島屋の店舗が閉鎖となってしまった。
◆米大手ドーナツチェーン、順調に店舗数を伸ばしてきたが……
クリスピークリームはアメリカで1937年に創業したドーナツチェーン。日本国内では、2006年にロッテが「クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン」を設立し、同年12月に国内1号店となる「新宿サザンテラス店」を出店、日本上陸を果たした。
出店当初は主力商品である「オリジナル・グレーズド」の無料配布サービスを行い、平日でも1時間を超える行列が発生したことで注目を集め、既存のドーナツ専門店の2倍ほどの価格帯ながら順調に顧客の支持を獲得。クリスピークリームと同時期に参入した高価格ドーナツ店「ドーナッツプラント」、「サザンメイドドーナツ」が運営会社の経営悪化により店舗数を大幅に減らした一方で、ロッテが親会社の「クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン」は順調に店舗網を拡大していた。
◆相次ぐ全面撤退。大都市圏でも
ハーバービジネスオンライン: 福岡県からは3月に全店舗撤退した。写真は閉店前の福岡天神地下街店。© HARBOR BUSINESS Online 提供 福岡県からは3月に全店舗撤退した。写真は閉店前の福岡天神地下街店。
順調に見えたクリスピークリームの店舗網拡大だったが、2016年に入ると状況が一変する。1月に岡山市、福岡市から一気に全面撤退したのを皮切りに、2月には広島県、京都府からも全面撤退。相次ぐ撤退は地方のみに留まらず、大阪では2015年12月末になんばCITY店が、都内でも2016年2月に神田小川町店が、3月にディラ阿佐ヶ谷店と玉川島屋SC店が閉鎖となっている。
特に、ゆめタウン廿日市店(広島県廿日市市)は開店から僅か8ヶ月間の営業となり、国内の常設店舗としては最短。従来の拡大路線からの方向転換を大きく印象づける結果となった。
◆好調な催事販売、新たな収益源となるか?
クリスピークリームは店舗網の縮小を続ける一方、埼玉県北部や新潟県、鳥取県など、といった未出店地域の百貨店などでの催事販売は活発化させている。
既に出店済の地域ではブームの沈静化による客離れが見られるが、スターバックスコーヒーの鳥取県初進出時(2015年5月)には、開店前日から行列が発生したように、未出店地域においては「デパートの催事でしか買えない」という「物珍しさ」も相まって、需要が見込めると判断したのであろう。
◆米国でもあった大規模撤退。販売手法転換で活路
クリスピークリームが創業したアメリカでも、かつては日本と同様に大規模な店舗閉鎖が行われている。
米国クリスピークリームは、株式上場前後の1990年代後半から米大手スーパーのウォルマートと業務提携するなどして急速な多店舗化を図ったが、2000年代には経営悪化により店舗の半数以上(約240店)を閉鎖した。
実は、アメリカではクリスピークリームと言うと日本のようなカフェスタイル・単独店舗での販売ではなく、スーパーマーケットで販売されているドーナツをイメージする人も多い。現在、欧米のクリスピークリームでは無店舗販売によるコスト削減を進めており、駅やスーパーマーケット内でのワゴン販売が主流となっているのだ。
日本でも、近年はコンビニ大手各社が店頭でのドーナツ販売を始めるなど、従来型のドーナツ専門店とは異なる販売手法が取られるようになっている。今後は、クリスピークリームも「単独店舗」という形態にとらわれない新たな販売手法を目指していく可能性がある。<取材・文・写真/都市商業研究所>
自然とドナーツから遠ざかります。
油っぽ食品は避けるようになります。
セブンのドーナツは1回しか食べたことがありません。
油は使った時点で酸化が進みます、
体には有害です。
でも
好きなのに食べないのも精神的によくないので
食べたい時は食べるでいいのでは?
そーすから
昔から傷んだ油は体に悪いと言われてきました。下痢をするだけではなく、脂肪肝や肝臓がんに繋がるという見方もある一方で、最近では酸化した油に害がないなどと言って、揚げ物の油は継ぎ足しだけで交換しないという意見も見られます。
それでも、国内で行われた「普通に調理に使った油」を使用した実験では、やはり古い油は脂肪肝の原因になる可能性が高いことを示していました。
酸化した油に害がないと主張する人たちの論拠は「実験に使う酸化した油というのが極端な物ばかりで、そこまで悪くなった油は不味くて食べられないから、普通に食べられる範囲のものであれば害はないはずだ」という事です。
確かに、さまざまな動物実験などで害の有無を調べる場合、極端な内容や量を使うことが多いのは事実です。しかし、だからと言って害がないと断定してしまうのはどんなものでしょう。調べたところ、面白い実験結果がありました。
ある大学の研究室が、揚げ物を作っている工場から、実際に使っている油をもらってきたそうです。交換時期が来たものや、まだ交換時期ではなく今まさに使っているもの、さらには使う前の新品の油を分けてもらい、それを瓶に詰めて窒素封入し、それ以上傷まないように保管したものを、実験室に持ち帰って実験用ラットに食べさせる実験を行いました。
まずはラットのエサから油分を抜いたものを準備して、それに抜いた油分に相当する量の実験用油を加えて食べさせます。比較グループのラットには、同じ量の新品の油を加えたとあります。これなら、私たちの生活感覚に沿ったものと言えそうで、油分の摂り過ぎによる害も除外して研究できますね。
そのエサで6週間育てたラットの変化を調べたところ、体重の増減については差が出なかったそうです。しかし、新鮮な油を食べさせたものに比べて、悪くなった油で育てたラットの体重に対する肝臓の重さが重くなっていた(脂肪肝の兆候を示した)という結果が得られています。
また、酵素などの検査から新鮮な油を食べさせたものに比べて、悪くなった油で育てたラットの活性酸素の処理能力が、明らかに低くなっていたという実験結果も出ています。
これらのことだけでは、酸化した油はどのように害があるのかまでは具体的に決定できませんが、悪影響があるであろうことは強く示唆されていますね。実験レポートは今後の詳細な研究が必要と締めくくられていますから、やはり悪くなった油の健康に対する害は存在しているようです。
油脂はグリセリンというものと、脂肪酸というものが組み合わさってできています。そして油の酸化とは、油を構成する脂肪酸が酸化するという事なのです。大変たくさんの種類がある脂肪酸ですが、構造的に共通点のある次の4種類の脂肪酸を見て下さい。
•ラードやヘットに多く含まれる飽和脂肪酸のステアリン酸
•オリーブオイルや椿油に多く含まれる不飽和ω9脂肪酸のオレイン酸
•一般に植物性の油に多く含まれる不飽和ω6脂肪酸のリノール酸
•エゴマ油に特に多く含まれる不飽和ω3脂肪酸のα-リノレン酸
この4つの脂肪酸は、すべて骨格に炭素を18個持つという共通要素のあるものですが、酸化されにくい順に並べました。そして飽和不飽和を決める「二重結合」という部分が少ない順でもあります。ステアリン酸は飽和なので0ヶ所。あとは順に1~3ヶ所になっています。
α-リノレン酸は最近人気の健康油の成分なのに、ちょっとショックですよね。でももっとショックなこともあります。魚油の健康成分EPAは、二重結合が5ヶ所、DHAに至っては6ヶ所もあるので、ものすごく酸化されやすいんです。
ですから魚は新鮮なうちに食べましょうって話にもなりますね。でも酸化されにくいからと言って、飽和脂肪酸をたくさん摂っていたのでは、違う病気が心配になります。植物油をやめてラードに変えましょう、なんて思わないですよね。
用途に応じて油を選びましょう
油をもっとも酸化させるのは、揚げ物を作る時です。ですので揚げ物に使う油は酸化しにくい油を選び、家庭では一回使ったら翌日は炒め物などに使用するか、それでも余った分は捨ててしまいましょう。
使用済み揚げ油の回収は、スーパーの店頭にある専用容器や、自治会で設定された回収日などで行われていると思いますから、地元の市区町村役場にお尋ねになって下さい。実際に使う油はについては、二つの考え方があります。
ラード(豚脂)、ヘット(牛脂)、パームオイル(アブラヤシ油)、ココナッツオイル(ココヤシ油)あたりが、酸化に対しては最も強いですが、これらを揚げ物で使うと飽和脂肪酸の摂取量が増えすぎてよくありません。
しかし、飽和脂肪酸はゼロにすればいいというものでもなく、少なすぎるのもまた健康に悪影響を与えます。ですので、揚げ物は月に一回か二回程度しか食べないという人なら、ラードでの揚げ物はいいと思います。そもそも一番おいしく揚がりますしね。
一方、週一以上は食べるという人は、安いオリーブオイルで揚げ物を作るのがお勧めです。もちろん同じようにオレイン酸の多い椿油もOKというか、個人的にはエビのてんぷらには最高だと思いますが、お値段がちょっと美味しくないです。
また、キャノーラ油やハイオレック系の紅花油・ひまわり油も、オレイン酸の含有率という意味では好ましいのですが、逆に飽和脂肪酸の量が少なすぎます。肉類の揚げ物に使うのなら構わないものの、野菜の揚げ物やコロッケ程度が中心なら、よくない可能性が高くなります。
ソースから
店舗数国内2位のドーナツ専門店「クリスピー・クリーム・ドーナツ」(以下、クリスピークリーム)の閉店が止まらない。
今年に入り、京都府、広島県、福岡県などから全面撤退したのをはじめ、都内でも神田小川町や阿佐ヶ谷、玉川島屋の店舗が閉鎖となってしまった。
◆米大手ドーナツチェーン、順調に店舗数を伸ばしてきたが……
クリスピークリームはアメリカで1937年に創業したドーナツチェーン。日本国内では、2006年にロッテが「クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン」を設立し、同年12月に国内1号店となる「新宿サザンテラス店」を出店、日本上陸を果たした。
出店当初は主力商品である「オリジナル・グレーズド」の無料配布サービスを行い、平日でも1時間を超える行列が発生したことで注目を集め、既存のドーナツ専門店の2倍ほどの価格帯ながら順調に顧客の支持を獲得。クリスピークリームと同時期に参入した高価格ドーナツ店「ドーナッツプラント」、「サザンメイドドーナツ」が運営会社の経営悪化により店舗数を大幅に減らした一方で、ロッテが親会社の「クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン」は順調に店舗網を拡大していた。
◆相次ぐ全面撤退。大都市圏でも
ハーバービジネスオンライン: 福岡県からは3月に全店舗撤退した。写真は閉店前の福岡天神地下街店。© HARBOR BUSINESS Online 提供 福岡県からは3月に全店舗撤退した。写真は閉店前の福岡天神地下街店。
順調に見えたクリスピークリームの店舗網拡大だったが、2016年に入ると状況が一変する。1月に岡山市、福岡市から一気に全面撤退したのを皮切りに、2月には広島県、京都府からも全面撤退。相次ぐ撤退は地方のみに留まらず、大阪では2015年12月末になんばCITY店が、都内でも2016年2月に神田小川町店が、3月にディラ阿佐ヶ谷店と玉川島屋SC店が閉鎖となっている。
特に、ゆめタウン廿日市店(広島県廿日市市)は開店から僅か8ヶ月間の営業となり、国内の常設店舗としては最短。従来の拡大路線からの方向転換を大きく印象づける結果となった。
◆好調な催事販売、新たな収益源となるか?
クリスピークリームは店舗網の縮小を続ける一方、埼玉県北部や新潟県、鳥取県など、といった未出店地域の百貨店などでの催事販売は活発化させている。
既に出店済の地域ではブームの沈静化による客離れが見られるが、スターバックスコーヒーの鳥取県初進出時(2015年5月)には、開店前日から行列が発生したように、未出店地域においては「デパートの催事でしか買えない」という「物珍しさ」も相まって、需要が見込めると判断したのであろう。
◆米国でもあった大規模撤退。販売手法転換で活路
クリスピークリームが創業したアメリカでも、かつては日本と同様に大規模な店舗閉鎖が行われている。
米国クリスピークリームは、株式上場前後の1990年代後半から米大手スーパーのウォルマートと業務提携するなどして急速な多店舗化を図ったが、2000年代には経営悪化により店舗の半数以上(約240店)を閉鎖した。
実は、アメリカではクリスピークリームと言うと日本のようなカフェスタイル・単独店舗での販売ではなく、スーパーマーケットで販売されているドーナツをイメージする人も多い。現在、欧米のクリスピークリームでは無店舗販売によるコスト削減を進めており、駅やスーパーマーケット内でのワゴン販売が主流となっているのだ。
日本でも、近年はコンビニ大手各社が店頭でのドーナツ販売を始めるなど、従来型のドーナツ専門店とは異なる販売手法が取られるようになっている。今後は、クリスピークリームも「単独店舗」という形態にとらわれない新たな販売手法を目指していく可能性がある。<取材・文・写真/都市商業研究所>










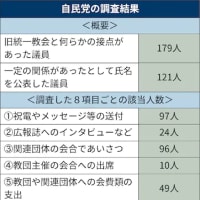


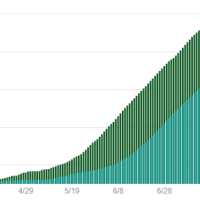





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます