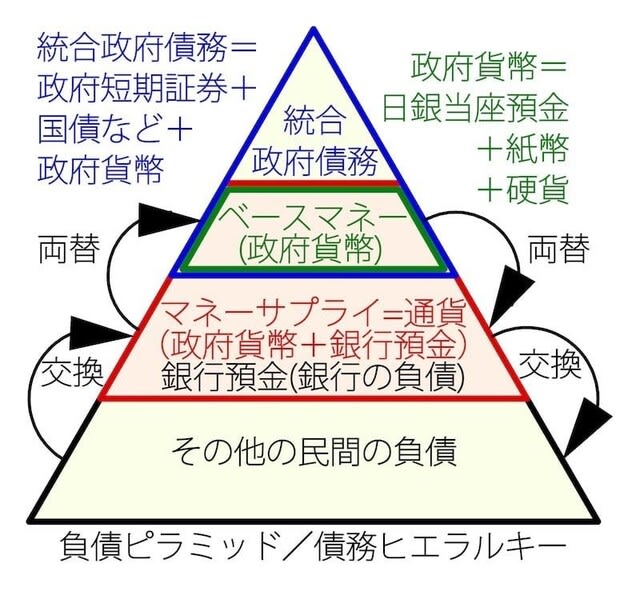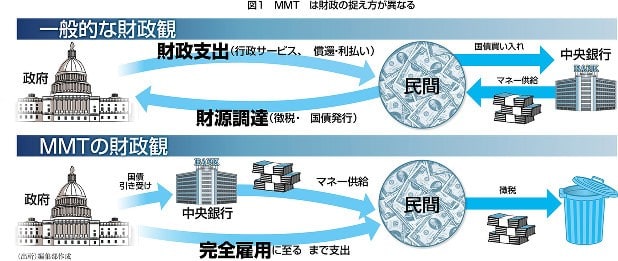MBSNEWS令和6年11月20日
インターネットの発達と普及がもたらしたものは、IT(Information Technology「情報技術」)革命と言われた。情報ツール及びメディアとしては印刷物、初期の電波媒体(電話、ラジオ、TV)に次ぐものであり、実効性は前二者に勝るかも知れない。
という書き出しで、昨年9月13日、SNSについて当ブログに書いたのだが、ここでは「危険性は低いが」書き言葉と話し言葉の中間のような新たな言葉遣いが生まれたような現象に注目し、川口ゆりやフワちゃんのX上での舌禍だか筆禍事件を取り上げた。しかし、すぐ後に、これはぬるかったな、と思えるようなできごとが起きた。
兵庫知事選だ。ここで我々は、実際に起きたはずのできごとに関する物語が、がらりと書き換えられる体験をした。できごと自体はまだ終わっておらず、従ってまだ新たな物語が語り出される可能性もあるが、ここまでで充分衝撃的だ。
できごとは次のように起きた。
令和6年の3月、兵庫県の(当時の。以下すべて同じ)県民局長は、「斎藤元彦知事の違法行為等について」と題した文書を一部の県議や報道機関に配布して、知事による県職員に対するパワハラや業者からの物品の授受などを訴え、さらに4月には、県の公益通報窓口に同じ内容を通報した。
これに対して、県は独自に調査し、告発内容には事実無根の中傷が多く、また県のパソコンの私的利用も明らかになったなどとして、この県民局長を停職3カ月の懲戒処分とした。
県議会は6月14日、この問題に関する百条委員会(自治体の不正や不祥事を調べるため地方議会内で組織される。国会の国政調査権に相応し、虚偽の証言、正当な理由がない証言拒否や記録の不提出には罰則を与えられる強い権限がある。地方自治法100条に基づく)を設置。件の県民局長は7月19日にここで証言予定だったが、7日、自宅で自殺しているのが見つかった。
これをきっかけとして、大手メディアで、斎藤知事に対する報道という名のバッシングが始まった。そこで語られた物語。
曰く、この知事は県庁職員に対してパワハラを揮って独裁体制を敷き、県内の業者からは贈り物を「おねだり」して貢がせている。県民局長が勇気を振り絞って告発したら、公益通報者は保護されるべきであるのに、特定され処罰を受ける圧力をかけられて、ついに自ら死を選んだ。遺書には「一死をもって抗議する」とあった。今時珍しい憤死であり、諌死である、と。
9月19日、百条委員会はなんらの結論も出していないにもかかわらず、兵庫県議会は全会一致で斎藤知事に対する不信任案を決議。これを受けて知事は9月30日に自ら失職(最終的に辞めるという決定はないので、辞職ではない)し、再出馬すると明らかにした上で知事選のやり直しを宣言。選挙は11月17日に決まった。
ところがこの頃からSNSで、第二の物語が語られるようになった。
曰く、すべては斎藤県政によって既得権益を失った兵庫県の旧勢力の陰謀から始まった。斎藤知事はパワハラはほとんどせず、「おねだり」は一度もしなかった。
そして告発文を書いた県民局長は、県庁内で不倫をしており、それに関する文書や画像を役所のパソコン内部に保存していた。
後者の不倫の件は、兵庫県知事の問題とは関係ない、と言う人が今もいる。その通りだが、これが報じられると、県民局長の自死についての物語が大きく揺らぐのは確かだ。
職場内でそんな浮ついたスキャンダルを起すような人と、古めかしいがいまだに日本人の心には強い悲壮美を喚起する憤死・諌死なんぞという文字とは結びつかないからだ。それかあらぬか、この話は百条委員会も大手マスコミも、積極的に隠そうとした疑いがある。
そこから翻って考えると、パワハラにしろおねだりにしろ、確たる証拠はない、と多くの人が気づくようになった。最近のこの手の報道ではお決まりの、怒鳴り声の入った音声録音など、一つも出てこなかった。
それにまた、県民局長の死因も不可解だ。彼は発言を封じられていたわけではなかった。百条委員会に召喚されていたのだから、そこで大いに知事の非を鳴らせばよいものを、12日前に自らその機会を絶ってしまった。これをどう考えればよいのか?
いらぬ誤解はできるだけ避けたいので付け加えるが、他人の心は結局わからない。まして自死する人の気持ちなど、安易に云々すべきではないだろう(だから、最近自死した県会議員について触れることは控える)。そうであるならば、最初から、そのよくわからない、曖昧なことに基づいて、誰かを非難すべきではなかったのだ。
この最後のものまで含めた素朴な疑問や常識が、マスコミから毎日流れてくる情報の大水(内容はほぼ同じで、目先を変えたものを毎日流し続けた)の中に呑まれていると、思いつかなくなるか、思いついても口に出せなくなる。
出したら、「人の命をなんだと思っているんだ」というような見当外れの非難を実際は浴びなくても、どこからか飛んでくるような気がして、身が竦む。そういう空気ができている、気がする。気がする以上、空気は既にある。それを作るのがメディアの力である。
一方、斎藤知事自身は、マスコミからのパワハラに関する攻撃的な「質問」に対して、正面から否定せず、「注意させていただいたことはあります」などと抑制的に答えていた。そして長く強く答えたのは、「着手した県政改革をやり遂げたい」ということだった。
これは最初はパワハラの事実を軽く見せ、あるいは話を逸らそうとする策略かと思われたが、後になると非常に賢明な対応だったことがわかる。
パワハラかどうかは、受ける側の主観・感情に拠るところが大きいから、そこで言い争っても、水掛け論になる公算が高い。
さらにこれまた翻って考えると、兵庫県民からしたら、行政府の長としての知事がどのような政事をしていたか、しようとしていたか、のほうが、職員を怒鳴ったかどうか、業者から贈り物(コーヒーメーカーとかワインとか)を受け取ったかどうかより重大な案件であるのは明らかだ。
しかしこれについては、大手マスコミは何も報道できなかった。それをしたら自分たちが不利になるかどうかより、そもそもニュースとして、他県の人はもとより、兵庫県内向けでさえ、あまり面白い物語になりそうにないから、つまり情報商品としては需要不足だと感じられたからだろう。だから供給側=伝える側の関心も薄く、よく知らないので、追求しようにもしようがなかったわけだ。
報道の多くが何を中心としてなされるか、これでもよくわかる。
SNSは上述の需要―供給関係を一旦壊した。これが最大の効果である。
誰でも発信できる。つまり、情報を供給できる。そこで出てくるものはあまりにも種々雑多で、当事者か、間近で見聞した人の証言もあれば、完全なデタラメもあって、普通の人間ができごとに関する正しい認識を持つことは困難だ。それどころか、情報の海の中に投げ込まれて、上下左右の方向もわからなくなり、結果、何も情報がないよりひどい状態になることさえ考えられる。
そこでマスコミというメディア(媒体)は、情報を取捨選択して、首尾一貫した意味のある物語にまとめあげて人々に提供する。この作業は編集と呼ばれるが、本質的には、作家が小説(フィクション)を作る過程と変わらない。ただノンフィクションを看板とする報道の場合、「それは事実と違う」というツッコミを入れられやすい、という要素があるだけだ。
その意味では、従来は口伝えで広まった噂話の類いが、電子メディアによって圧倒的な量とスピードとで出回るようになった現在こそ、マスコミにとってエディター(編集者)としての腕の見せ所と言えるかも知れない。
しかし、この数の膨大さに対応しきれないからと言って、責めるのは酷というものであろう。また実際、SNS上の言葉の大部分は、先行の言葉への反応であって、わざわざフォローする値打ちなどない。ただ放っておくしかない代物だ。
かくて意識的にか無意識的に捨てられる膨大な言葉が後に残される。それもやがては消えてしまう運命だが、口から耳へと伝わるいわゆる伝聞よりは長く残る。それを改めて拾い集めてまとめるエディターの役割を果たそうとする人も出てくる。これまた、誰でもやれるので、その質も精度も千差万別になる。
質とは、説得力という意味だが、そのためには物語としての面白さをどれほど提供できるかの部分は非常に大きい。この点で兵庫県知事にまつわる鮮やかな悪玉―善玉の変身劇は滅多にあるものではなく、上質の推理小説の趣を備えた素材だった。
あとはこれをどう伝えるかだ。面白い話でも、Xやフェイスブックで発信するだけでは、やはり足りない。エディターと同一人物か、あるいは別でもいいが、敏腕な発信者(プレゼンター)が必要なのだ。
後者の点で、良きにつけ悪しきにつけ、今回大きな役割を果たしたと多くの人が認めるのは、「NHKから国民を守る党」代表の立花孝志氏。
知事選に立候補する。しかし自身の当選は目指さず、斎藤知事の無罪と、彼を逐おうとする勢力への批判に終始する。百条委員会の委員長の自宅兼事務所の前で、選挙演説と称して、公衆の面前で、挑発的な言葉を彼に浴びせる。そしてこれらの活動のすべてをYouTubeの動画で配信する。
もとより、非常に過激なやり口であり、適法と違法の境界線上にある。現に告訴もされている(彼の側からの告訴もある)。だからこそ、「現場」の臨場感もあって、非常にスリリングになり、人目を惹く。
かくして立花氏(エディターが他にいたのかどうかはわからない)のプレゼンは、斎藤知事に対する第二の物語を世に浸透させることに成功し、さらに斎藤氏の再選にまで、大きく貢献した。
これは旧メディア(新聞・TV)に対する新メディア(SNS)の勝利だと言われた。そう言ってもいいのであろう。
もちろんそれを単純に、老害化した情報機関が新たな優良機関に取って代わられたのだ、とすることはできない。SNSは、情報を単純化して、かつ感情に訴えるような形で伝える。それは元々のメディアの得意技だった。それがさらに先鋭になったのだ。
ここでは迂闊な私が、このたびようやく感得したと思えることを簡単に書き付けておく。
以前に、SNSでは「この種の(洗脳による)犯罪の前提にはつきものの閉鎖性は失われる」と書いたのだが、これは我ながら非常に浅い考えだった。
ネット上の情報洪水の中には、特定の信念からみて都合の悪いものも当然あって、そこで思い込みは相対化される機会もあるのではないか、と思ったのだが、熱心なユーザーとはそういう者ではない。洗脳には適当な、狭くて暗い、他の情報が遮断する場所(事務所だのサティアンだの)はなくても、心の中に密室を作ってしまえるのだ。
エコーチェンバー現象というらしいが、自分で選んだ種類の投稿を優先して、多くの場合それだけを、見る。Xでもフェイスブックでもインスタグラムでも、フォローしている人の投稿が、YouTubeなら登録しているチャンネルが、スイッチを入れるとまず表示されるのだから、自動的にそうなる。
そして投稿記事やそのコメントで、賛成できる、さらには「そう思っているのは自分だけではない」という心地よい連帯感をも得ることができる情報にずっと接していると、それに反するものをたまたま目にすると、これまた自然に、不快感がもたれてしまう。
SNSの情報が大手メディアのより必ず怪しいとは言えない。ただ、活字やTV画面より生の肉声がストレートに伝わる感じがあるところが魅力でもあるので、感情先行の傾向が強まる。
もちろん、sympathyが高まるなら、比例してantipathyも高まる。その情報にどれだけ根拠や論理性があるかは、ますます二の次に置かれる。
これからどうなるだろうか。最近、メタのザッカーバーグCEOが、Face Bookやインスタグラムのファクトチェック、それに拠る投稿制限を原則やめる、と発表したばかりだ。生の感情のぶつけ合いは、ますます増えるだろう。
どうすればいいか、については、以前に言ったことを、もう少しラディカル(過激かつ根本的に)繰り返すことしかできない。
よく言われる、根拠があやふやか、まるっきりない言葉はあまり信用しないほうがよい、という(これまた)言葉は、もっともではあるが、限界がある。そもそもその「根拠」からして、誇張されたり(今風の言い方だと、盛られたり)、捏造されることだって稀ではない。今回の兵庫知事選をめぐる騒動で、その一端が露わになったとすれば、それが一番の効能である。
さらにもっと根本的に、フィクションとノンフィクションの間に明確な違いがあるかとなると、普通に考えられているほどではない。どちらにもせよ、発信され受信されるのは、必ず広い意味の(映像を含めた)言葉なのだ。それは事実(と呼べるものが仮にあったとしても)とは次元の違う何ものかなのだ。
我々は事実を言葉にして受け取ることを、「知る」とか「理解する」とか呼んでいる。それ以外の、例えば目の前で人命が失われたときの衝撃は、他者とは共有できない。聞くほうは、せいぜい想像してみることを、「共感する」と呼んだりしているだけだ。
だから、共有され広く知られるようになった事柄については、我々は多かれ少なかれ、誤解している。繰り返すが、「知る」「理解する」とは、そういうことでしかない。もっとも、正解がない以上、誤解というのも誤解を招く言葉になりそうだが。
つまり我々は、人の世で生きる以上、多かれ少なかれ必ず騙されている、あるいは、自分を騙しているのである。
これは厳し過ぎる言い方ではある。しかし、以上を頭の片隅にでも置いておけば、最もひどい間違いに陥ることは防げるのではないだろうかと思い、書き付けた。














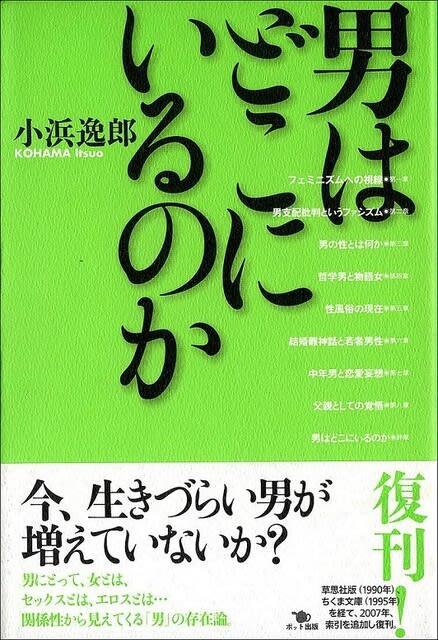


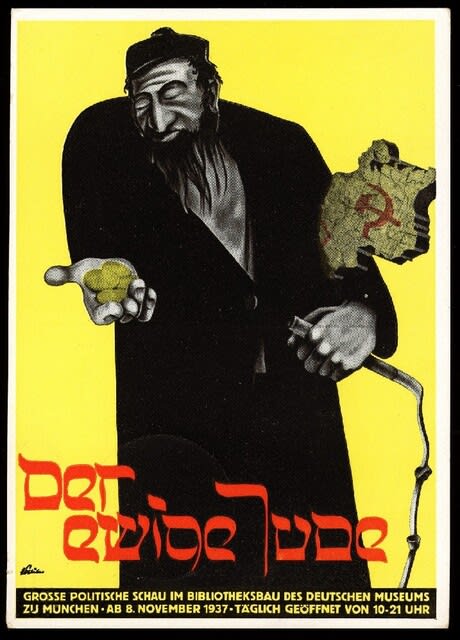



 メソポタミア文明の粘土板
メソポタミア文明の粘土板