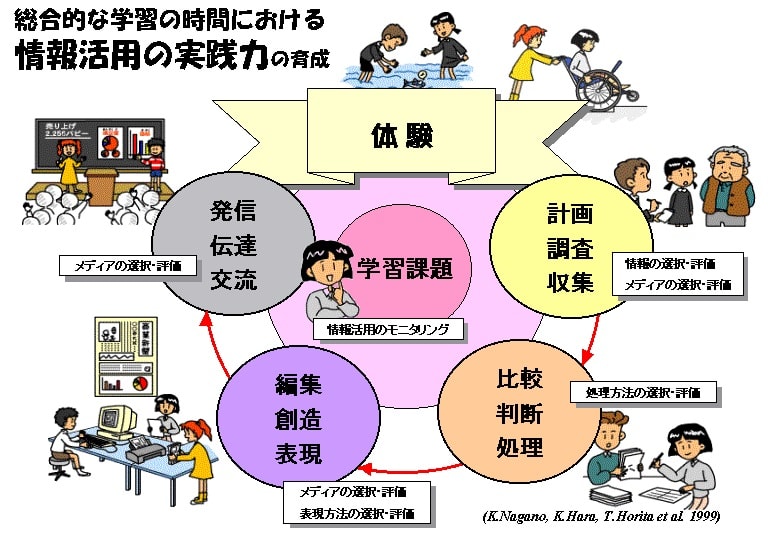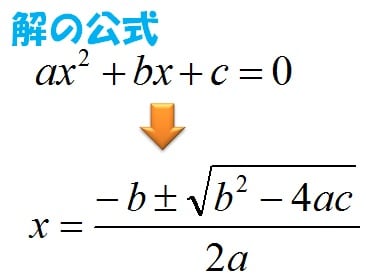メインテキスト:正宗白鳥『作家論(一)・(二)』(創元社。(一)は昭和16年、(二)は昭和17年)

自我の問題とは少し別の角度から日本近代文学を考えたくなった。それで、倫理道徳、だが、これも固より広大無辺にして複雑微妙、とうてい満足のいく解答は示せない、どころか、自分一個の意を尽くす前に止まってしまうに違いないことは以前の通り。せいぜい、考えるためのとば口の一つを示すぐらいのことを期して、今後いくらか漫然と書きつけることにします。
最初にご登場願う正宗白鳥は、現在、誰でも知っているというわけではないが、知る人ぞ知るというほどでもない地位にある。知っているのは、近代日本文学に関心のある人に決まっている。彼らの間では、小説家としてよりはむしろ批評家として優れていた、ということは定説と言ってよいだろう。
主に同時代の日本文学について、小難しい文芸理論を誇示するでもなく、小林秀雄の如き妖しい論法を用いるでもなく、生来の文学好きとして、しかしあくまで理性的に、己の心に映じた文芸観を素直に淡々と綴っている。では、要するに時評家かと言われれば、そうとも言えるが、作家の側では、こういう読者をこそ期待しているのだろう。
そして、文学作品がかく読まれた、という直近の声は、文芸作品が時代の中で占める位置を証言し、作品が書かれて現に世に「在る」意味に光を当てる。「批評とは己の夢を懐疑的に語ること」(小林秀雄)だなんて言う前に、そういうのが文芸批評の第一の役割であり、存在理由であるはずである。その役割を果たし得ている点で、正宗白鳥の文章は、一流の批評であることに疑いない。
中で、芥川龍之介に関する評論をまず取り上げる。残念ながら、高橋英夫編『新編作家論』(岩波文庫)には入っていない。『作家論』は元来、日米戦争が始まった年に、それまでの批評文を、作家別に二巻にまとめて刊行されたものである。戦後、創元文庫に入り、さらに新潮文庫と角川文庫(以上すべて二巻本)で出た。もちろんすべて絶版。「芥川龍之介」が入っている現在の刊行本は全集以外にはない。
と、思っていたら、今回、HNを「やぶちゃん」という人が、なるべく正字正かなのままで、電子書籍化してネット上にアップしてくださっていたのを発見した。貴重なお仕事あり、今後ともお世話になると思うので、それも含めて厚くお礼申し上げます。
さっそくながら、以下の引用は、やぶちゃん氏のアップしたものをコピペにて使用させていただいている。
白鳥が主に取り上げている芥川作品は二つ。「孤獨地獄」(大正5年作)と「往生繪卷」(大正10年作)。いずれも短編作家芥川龍之介の作品中でも特に短く、ともに青空文庫にも入っているので、すぐ読める。
ここでは、「往生繪卷」について言われている箇所を、やぶちゃん氏の注を含めて、少し長く引用する。
(前略)「孤獨地獄」と對照すると、藝術としての巧拙は問題外として、私には作者の心境が面白かつた。孤獨地獄に苦しめられてゐるある人間が、全身の血を湧き立たせて阿彌陀佛を追掛けてゐると思ふと、そこに私の最も親しみを覺える人間が現出するのであつた。しかし、これ等を取扱つてゐる芥川氏の態度や筆致が、まだ微温的で徹底を缺き、机上の空影に類した感じがあつたので、私は龍之介禮讃の熱意を感じるほどには至らなかつた。
私は、この小品の現はれた當時、その讀後感をある雜誌に寄稿した雜文の中に書き込んだ……五位の入道の屍骸の口に白蓮が咲いてゐたといふのは、小説の結末を面白くするための思附きであつて、本當の人生では阿彌陀佛を追掛けた信仰の人五位の入道の屍骸は、惡臭紛々として鴉の餌食になつてゐたのではあるまいか。古傳説の記者はかく信じてかく書きしるしてゐるのかも知らないが、現代の藝術家芥川氏が衷心からかく信じてかく書いたであらうかと私は疑つてゐた。藝術の上だけの面白づくの遊びではあるまいかと私は思つてゐた。
かういふ私の批評を讀んだ芥川氏は、私に宛てて、自己の感想を述べた手紙を寄越した。私が氏の書信に接したのは、これが最初であり最後でもあつたが、私はその手跡の巧みなのと、内容に價値があるらしいのに惹かれて、この一通は、常例に反して保存することにした。今手許にはないので、直接に引用することは出來ないが、氏は白蓮華を期待し得られるらしく云つてゐた。「求めよ、さらば與へられん」と云つた西方の人の聖語を五位の入道が講師の言葉を信じて疑はなかつたと同樣に、氏は信じて疑はなかつたのであらうか。
私はさうは思はない。氏は、あの頃「孤獨地獄」の苦をさほど痛切に感じてゐた人でなかつたと同樣に、專心阿彌陀佛を追掛けてゐる人でもなかつたらしい。芥川氏は生れながらに聽明な學者肌の人であつたに違ひない。禪超や五位の入道の心境に對して理解もあり、同情をも寄せてゐたのに關はらず、彼等ほどに一向きに徹する力は缺いてゐた。
やぶちゃん注:ここに示された芥川龍之介の正宗白鳥宛書簡は、大正一三(一九二四)年二月十二日田端発信の岩波版旧全集書簡番号一一六二である。以下に全文を引用する。
冠省文藝春秋の御批評を拜見しました御厚意難有く存じました十年前夏目先生に褒められた時以來最も嬉しく感じましたそれから泉のほとりの中にある往生繪卷の御批評も拜見しましたあの話は今昔物語に出てゐる所によると五位の入道が枯木の梢から阿彌陀佛よやおういおういと呼ぶと海の中からも是に在りと云ふ聲の聞えるのですわたしはヒステリツクの尼か何かならば兎に角逞ましい五位の入道は到底現身に佛を拜することはなかつたらうと思ひますから(ヒステリイにさへかからなければ何びとも佛を見ないうちに枯木梢上の往生をすると思ひますから)この一段だけは省きましたしかし口裏の白蓮華は今でも後代の人の目には見えはしないかと思つてゐます 最後に國粹などに出た小品まで讀んで頂いたことを難有く存じます往生繪卷抔は雜誌に載つた時以來一度も云々されたことはありません 頓首
二月十二日 芥川龍之介
正宗白鳥樣 侍史
【由紀草一による屋上屋の注。書簡中で芥川の言う「十年前夏目先生に褒められた時以來最も嬉しく感じ」た文藝春秋の批評とは、『文藝春秋』大正13年2月号に載った「故郷にて」という文章で、ここで白鳥は芥川「一塊の土」を絶賛している。
『泉のほとり』は大正13年新潮社から「感想小品叢書 第2編」として出た白鳥の単行本。「往生繪卷」についての言及がある「ある日の感想」が収録されている。「ある日の感想」は「往生繪卷」が掲載された(4月号)のと同じ雑誌『國粹』大正10年6月号初出】
順序として「孤獨地獄」について先に述べる。表題になっているこの言葉は由緒正しい仏語だそうで、何事にも持続した強い興味関心を抱き得ない、西洋語ではニヒルというのが一番近いであろう状態を指す。砕いて言えば、何をやってもすぐに飽きてつまらなくなる、無聊の状態がずっと続く、ということ。作中ではこれは「嫖客(ひょうきゃく)のかゝりやすい倦怠(アンニユイ)」であり、「酒色を恣(ほしいまま)にしてゐる人間がかゝつた倦怠は、酒色で癒る筈がない」と言われている。
幕末の僧侶である禅超が、長年の放蕩の果てに(当時僧侶の酒色は公的には禁じられていたが、けっこう見過ごされていたらしい)、快楽の飽和状態に達し、生きながらこの地獄に堕ちた、と述懐するのが掌編「孤獨地獄」の要である。最後に、作者の生の言葉として、「或意味で自分もまた、孤獨地獄に苦しめられてゐる一人だ」云々と、記されている。
この部分は、芥川作品に時折見られる、なくもながなリフレイン(三島由紀夫の評語)と言えると思うが、白鳥は「年少者が氣まぐれに口にする感傷語とばかりは思はれない。芥川氏の腦裡に嚴存してゐた感じであつたらしいが、その感じが歳を取るにつれてどう働いてゐたのであらうか。作品の上にどういふ風に現はれてゐたのであらうか」と問いを立てる。
その答えが上の長い引用文中にある。「往生繪卷」となぜ繋がるかと言うと、この世のすべてに興味を失った人間が、この世ならぬ彼岸に憧れるとき、その渇望こそ最も激しいであろう、と白鳥は考えるらしい。それが「往生繪卷」の主人公五位の入道の場合である、と。それはそうかも知れない。
で、白鳥は、芥川はどちらの心境も本当にはわかっていない、と断ずる。頭では理解していたろうし、同情もしたろうが、このような問題を芯から「自分のもの」にしていたわけではない。自分が安全な観察者の立場にいる限り、描かれた人間の苦悩もまた「机上の空影」つまり絵空事にしかならない、というわけ。
おなじみの「実感第一」の文学論で、本ブログでも「こんなんでいいんですか、小林秀雄さん」で瞥見した。現在ではけっこうバカにされているようだが、まだ力を失ったわけではない。それはそうと、芥川の最期の頃を知っている私たちからすれば、このような感想は、また違った角度から眺められざるを得ない。
「聽明な學者肌の人」というのは、芥川作品のいかにも知的に整えられた構成やら、驚くべき博学ぶりから、誰もが抱きがちな人物像であろう。しかし、人間はもっと複雑なものである。「赤い帽子の女」が事実彼の作であるかどうかは措いて、芥川のけっこう派手な女性遍歴は各種の伝記に触れられているし、かなり危ない遊びまでやっていたことは、宇野浩二『芥川龍之介』の最初に出ている。何より、自伝、というか自伝の断片集のような「或阿呆の一生」には、女性との次のような対話が記されている。
「死にたがつていらつしやるのですつてね。」
「ええ。――いえ、死にたがつてゐるよりも生きることに飽きてゐるのです。」
松本清張「芥川龍之介の死」(『昭和史発掘』所収)などによって、この女性が誰かはほぼ特定されており、芥川が彼女と帝国ホテルで心中しようとして、女性の側の翻意によって果たせなかった事実も、現在では明らかであるらしい。つまり、「自分もまた、孤獨地獄に苦しめられてゐる」というのは、「氣まぐれに口にする感傷語」どころではなく、芥川の全き実感だったようなのである。どれほど痛切な、かと言うと、実際に死んでしまうほどの。
白鳥の「芥川龍之介」は、『中央公論』昭和2年10月号初出(このときの題は「芥川龍之介氏の文学を論ず」)であり、同年7月の、芥川の自殺を機に書かれている。時間的に、作者の死後に発表された「或阿呆の一生」や「齒車」などの遺稿は読まずに書かれた可能性はある。後には読んだろうが、それでも白鳥は、自身の芥川論に何ものをも付け加えはしなかった。
だいたい、「或阿呆の一生」を、清張その他による伝記的な考証抜きで、純粋に一個の作品として鑑賞しようとしても、まず無理である。その意味で、文芸作品として自立していない、と言い得る。「齒車」は、一種の奇妙なモダンホラーとして愛好する人もいるようだが、私などには、「わけがわからない」としか言いようがない。精神病理学の知識があればわかるのかも知れないが、それはつまり文学の外側から作品を「理解する」ことに他ならない。
「かう云ふ氣もちの中に生きてゐるのは何とも言はれない苦痛である。誰か僕の眠つてゐるうちにそつと絞め殺してくれるものはないか?」(「齒車」の末尾)と言われても、それが作者の生の「実感」から出ていたとしても、否、いればいるほど、読者としてはどうしようもない、ということである。主観はどこまでも主観であって、その人だけのものだ。文学は、そこに一個のフォルムを与えて、そこから客観的に、読者に伝わるようにしたものであろう。
しかし、「フォルムを与える」のは、反面から見ると、対象と距離を置き、ある枠の中に対象を閉じ込めることである。実感主義からすれば、あまりよいこととは言えなくなるのではないだろうか。そのうえ、さらにもっと大きな問題を、ここに見出すことができると思う。
そこでようやく「往生繪卷」に移る。その結末の問題について、最も言いたかった。
結末に至る道筋を改めて辿る。主人公の五位とは、五位の位にある武士ということだが、殺生を好む乱暴狼藉者であった。あるときたまたま講師(講堂内で説法する僧)が、「どのやうな破戒の罪人でも、阿彌陀佛に知遇し奉れば、浄土に往かれる」と言うのを聴いて、「體中の血が、一度に燃え立つたかと思ふ程、急に阿彌陀佛が戀しうなつた」。そこで講師を取り伏せ、刀で脅しつつ、阿彌陀佛のありかを問うと、「西方浄土」だからだろう、苦し紛れに「西、西」とのみ言う。それから五位は「阿彌陀佛よや。おおい。おおい」と呼ばわりつつ、ひたすら西を目指して走る。やがて海にぶつかり、それ以上進めなくなると、松の梢に上って「阿彌陀佛よや。おおい。おおい」と叫び続ける。七日目、絶命した彼の口からは、まっ白な蓮華が開いていた。
以上を踏まえて白鳥と芥川の問答を、改めて見ていただきたい。白鳥は、死体の口から花が咲くなどということは現実にはなく、それをこう簡単に書いたのでは、「遊び」(=絵空事)にしかならないだろう、と言う。それに対する芥川の書簡中の答えは、少し話をそらしているようである。
曰く、自分が題材にした「今昔物語」中の説話(巻十九「讃岐国多度郡五位聞法即出家語」第十四)では、五位の呼びかけに応じて、海中から阿彌陀佛(だろう)が「此に有り」と声に出して応えたことになっているが、それはヒステリックな尼(文字通りの尼僧ではなく、天理教の中山みきや大本教の出口なおのようなケースを言っていると思しい)にこそ相応しい。普通の人はヒステリーにならなくても、信仰心があれば木の上での往生はできると思うので、それは省いた。しかし、口から咲いた白蓮華は、今の人の眼にも見えるのではないだろうか。
「声が聞こえる」のも「花が眼に見える」のも、もちろん物語のレベルでの話である。できたら、芥川「往生繪卷」でも、「今昔物語」でも、読んだ後で考えていただきたいのだが、この結末を、白鳥の言うように、「五位の入道の屍骸は、惡臭紛々として鴉の餌食になつてゐた」で終わりにしたらどうなるか。文字通り、「話にならない」、つまり、「なんだこの無意味な話は?」と思われてきて、とうてい物語になり得ない、と見えるのではないだろうか。
いや実際は、そういう話も、「物語」が「小説」になった現代では、さほど珍しくない。芥川にもある。今後本シリーズでもいくつか取り上げるつもりだが、そこでの「語り」は、もっと別の面から人間を描出することを狙っている。対して今問題にしている説話風の物語は、清純な信仰が嘉される奇跡物語という、古今東西に偏在する物語のパターン(話型)、即ちフォルム・枠を使って、「絵巻物」を、言葉によって織り上げる作業、と言ってよい。
白鳥にもそんなことはもちろんわかっていた。わかっていて敢えて、それを安易に用いていいのか、と問うのである。何より、芥川自身が、こんな奇跡が現に起こり得るとは信じていないし、起こってほしい、と痛烈に望む者でもないだろう。それでいて、お話をまとめるためだけに使った、そこが安易だ、と。
安易ではない例としては、「ある日の感想」には、白鳥が若いころ師事した内村鑑三の例が出ている。「内村氏は一度信じたことを惰力で信じ續けるやうな無神經な人ではない。氏は自己の幻想を續けるためにいかばかり努力してゐるか」。芥川にはその努力が足りない、というわけだ。いやはやなんとも、厳しいと言うより、どうもお門違いな要求にも見える。芥川はもとより宗教者ではなく、作家である。文学者である。
と、そう簡単には割り切れない。近代で宗教の代用にもなるのが文学の役割ではないか。少なくとも白鳥などは、自然にそう信じていた。彼方の、永遠なる存在、それのみがもたらすことのできる究極の救済。あるとき、不図(ふと)、そのようなものに憧れてしまうのは人間の、万古不易の心性であろう。それに応えるものとしては、信仰心が一般に薄れた現在、文学以外にあるべくもない。
そして白鳥は、仮借無く現実を見つめる反面で、激しく救済を求める人でもあった。「孤獨地獄に苦しめられてゐる」からこそ、「全身の血を湧き立たせて阿彌陀佛を追掛けてゐる」人間に親しみを覚える所以である。そして、才気にまかせてそこに近いところを掠めて飛んで見せるような感じの芥川の芸当を、あきたらなく感じるのも、この性向がしからしめている。
問題は幾重にも錯綜している。別の角度からこのすれ違いを眺めてみよう。
近代は、宗教を筆頭とする、それまで人々の生活意識を組み立てていたものの土台を、完全に壊したわけではないが、少なくとも見かけ上、弱くした。昔の人は信仰による奇跡を素直に信じていた、というよりむしろ、素直に信じる心を否定しなかった、と言ったほうがおそらく事実に近い。
近代人はそうはいかない。白鳥にしても、内村鑑三が信じる聖書の真実などは、幻想だ、と言い切っている。それでいてなお彼を尊敬するのは、前述の努力、即ち幻想であってもそれを信じきろうと努める意欲の強さがあるからだ。しかしそれも、おそらくだが、聖書という物語群が、揺るぎない規範(≒フォルム)として、いつも内村の前にあって、彼を支え、導いたからこそできたのではなかったろうか。そうでなければ、聖書にどれほど惑溺(白鳥の評語)しようと、他人を感動させる研究はできなかったのではないだろうか。
芥川もまた、「西方の人」の著者であり、「永遠に超えんとする者」、即ち超越的なものに自身も憧れを抱いていた。しかし、流行作家として、娯楽としての奇跡物語を書く義務も感じていたようだ。その場合、海を割って道を作るような大掛かりな奇跡では、もう子どもをだますこともできないだろう。神の声を聴くのも、そこいらのヒステリー女が、聴いた聴いたと口走り、そのことが広く知られるようなご時世では、あんまり有効には使えそうにない。口から可憐な花が咲き出でた、ぐらいなら、切ない信仰心を伝えるものとして、許されるのではないか。白けさせないで、同情をよぶことができるのではないか。これでいこう、と、特に自覚はしなくても、自然に頭が働くのが練達した作家というものだろう。
通俗的であさましい計算だ、と白鳥のような人に感じられるのに無理はない。しかし、それでさえも、土台、奇跡を信じたい、という気持ちが現代人の心の中になければ、成り立たない話ではある。つまりその心は、ある。
これらをひっくるめると、こういうのが理想だということになりそうだ。奇跡そのものも、奇跡を信じる心も否定される現代で、超越者への渇望の果てに死んだ人の屍もまた腐敗していく、その生の現実からは目をそむけず、それでも究極的の救済をどこかで求めざるを得ない人の心に寄り添い、できるだけ掬い上げること。言い換えると、奇跡に依ってしか癒されない類の人間性の一面に、奇跡なしで関わること。それを客観的に語れるフォルムを作ること。新たな話型、それもできれば聖書のような普遍的な、とまで言えば、それこそ奇跡でも起きなければ無理な話ではあるが、その志は持ち続けること。
「そんなの知らないよ」と、今の作家には軽く言われてしまいそうだが、人間に「内面」があり、「内面」には価値があるという信仰が完全に失われない限り、文学の名におけるこの志もなんとか続くだろう。
いやまあ、未来のことは結局わからないので措くとして、昔の文学者たちがどのように、野暮に、こういう問題に取り組んだか、次回からもう少し見ておきたいと思う。

自我の問題とは少し別の角度から日本近代文学を考えたくなった。それで、倫理道徳、だが、これも固より広大無辺にして複雑微妙、とうてい満足のいく解答は示せない、どころか、自分一個の意を尽くす前に止まってしまうに違いないことは以前の通り。せいぜい、考えるためのとば口の一つを示すぐらいのことを期して、今後いくらか漫然と書きつけることにします。
最初にご登場願う正宗白鳥は、現在、誰でも知っているというわけではないが、知る人ぞ知るというほどでもない地位にある。知っているのは、近代日本文学に関心のある人に決まっている。彼らの間では、小説家としてよりはむしろ批評家として優れていた、ということは定説と言ってよいだろう。
主に同時代の日本文学について、小難しい文芸理論を誇示するでもなく、小林秀雄の如き妖しい論法を用いるでもなく、生来の文学好きとして、しかしあくまで理性的に、己の心に映じた文芸観を素直に淡々と綴っている。では、要するに時評家かと言われれば、そうとも言えるが、作家の側では、こういう読者をこそ期待しているのだろう。
そして、文学作品がかく読まれた、という直近の声は、文芸作品が時代の中で占める位置を証言し、作品が書かれて現に世に「在る」意味に光を当てる。「批評とは己の夢を懐疑的に語ること」(小林秀雄)だなんて言う前に、そういうのが文芸批評の第一の役割であり、存在理由であるはずである。その役割を果たし得ている点で、正宗白鳥の文章は、一流の批評であることに疑いない。
中で、芥川龍之介に関する評論をまず取り上げる。残念ながら、高橋英夫編『新編作家論』(岩波文庫)には入っていない。『作家論』は元来、日米戦争が始まった年に、それまでの批評文を、作家別に二巻にまとめて刊行されたものである。戦後、創元文庫に入り、さらに新潮文庫と角川文庫(以上すべて二巻本)で出た。もちろんすべて絶版。「芥川龍之介」が入っている現在の刊行本は全集以外にはない。
と、思っていたら、今回、HNを「やぶちゃん」という人が、なるべく正字正かなのままで、電子書籍化してネット上にアップしてくださっていたのを発見した。貴重なお仕事あり、今後ともお世話になると思うので、それも含めて厚くお礼申し上げます。
さっそくながら、以下の引用は、やぶちゃん氏のアップしたものをコピペにて使用させていただいている。
白鳥が主に取り上げている芥川作品は二つ。「孤獨地獄」(大正5年作)と「往生繪卷」(大正10年作)。いずれも短編作家芥川龍之介の作品中でも特に短く、ともに青空文庫にも入っているので、すぐ読める。
ここでは、「往生繪卷」について言われている箇所を、やぶちゃん氏の注を含めて、少し長く引用する。
(前略)「孤獨地獄」と對照すると、藝術としての巧拙は問題外として、私には作者の心境が面白かつた。孤獨地獄に苦しめられてゐるある人間が、全身の血を湧き立たせて阿彌陀佛を追掛けてゐると思ふと、そこに私の最も親しみを覺える人間が現出するのであつた。しかし、これ等を取扱つてゐる芥川氏の態度や筆致が、まだ微温的で徹底を缺き、机上の空影に類した感じがあつたので、私は龍之介禮讃の熱意を感じるほどには至らなかつた。
私は、この小品の現はれた當時、その讀後感をある雜誌に寄稿した雜文の中に書き込んだ……五位の入道の屍骸の口に白蓮が咲いてゐたといふのは、小説の結末を面白くするための思附きであつて、本當の人生では阿彌陀佛を追掛けた信仰の人五位の入道の屍骸は、惡臭紛々として鴉の餌食になつてゐたのではあるまいか。古傳説の記者はかく信じてかく書きしるしてゐるのかも知らないが、現代の藝術家芥川氏が衷心からかく信じてかく書いたであらうかと私は疑つてゐた。藝術の上だけの面白づくの遊びではあるまいかと私は思つてゐた。
かういふ私の批評を讀んだ芥川氏は、私に宛てて、自己の感想を述べた手紙を寄越した。私が氏の書信に接したのは、これが最初であり最後でもあつたが、私はその手跡の巧みなのと、内容に價値があるらしいのに惹かれて、この一通は、常例に反して保存することにした。今手許にはないので、直接に引用することは出來ないが、氏は白蓮華を期待し得られるらしく云つてゐた。「求めよ、さらば與へられん」と云つた西方の人の聖語を五位の入道が講師の言葉を信じて疑はなかつたと同樣に、氏は信じて疑はなかつたのであらうか。
私はさうは思はない。氏は、あの頃「孤獨地獄」の苦をさほど痛切に感じてゐた人でなかつたと同樣に、專心阿彌陀佛を追掛けてゐる人でもなかつたらしい。芥川氏は生れながらに聽明な學者肌の人であつたに違ひない。禪超や五位の入道の心境に對して理解もあり、同情をも寄せてゐたのに關はらず、彼等ほどに一向きに徹する力は缺いてゐた。
やぶちゃん注:ここに示された芥川龍之介の正宗白鳥宛書簡は、大正一三(一九二四)年二月十二日田端発信の岩波版旧全集書簡番号一一六二である。以下に全文を引用する。
冠省文藝春秋の御批評を拜見しました御厚意難有く存じました十年前夏目先生に褒められた時以來最も嬉しく感じましたそれから泉のほとりの中にある往生繪卷の御批評も拜見しましたあの話は今昔物語に出てゐる所によると五位の入道が枯木の梢から阿彌陀佛よやおういおういと呼ぶと海の中からも是に在りと云ふ聲の聞えるのですわたしはヒステリツクの尼か何かならば兎に角逞ましい五位の入道は到底現身に佛を拜することはなかつたらうと思ひますから(ヒステリイにさへかからなければ何びとも佛を見ないうちに枯木梢上の往生をすると思ひますから)この一段だけは省きましたしかし口裏の白蓮華は今でも後代の人の目には見えはしないかと思つてゐます 最後に國粹などに出た小品まで讀んで頂いたことを難有く存じます往生繪卷抔は雜誌に載つた時以來一度も云々されたことはありません 頓首
二月十二日 芥川龍之介
正宗白鳥樣 侍史
【由紀草一による屋上屋の注。書簡中で芥川の言う「十年前夏目先生に褒められた時以來最も嬉しく感じ」た文藝春秋の批評とは、『文藝春秋』大正13年2月号に載った「故郷にて」という文章で、ここで白鳥は芥川「一塊の土」を絶賛している。
『泉のほとり』は大正13年新潮社から「感想小品叢書 第2編」として出た白鳥の単行本。「往生繪卷」についての言及がある「ある日の感想」が収録されている。「ある日の感想」は「往生繪卷」が掲載された(4月号)のと同じ雑誌『國粹』大正10年6月号初出】
順序として「孤獨地獄」について先に述べる。表題になっているこの言葉は由緒正しい仏語だそうで、何事にも持続した強い興味関心を抱き得ない、西洋語ではニヒルというのが一番近いであろう状態を指す。砕いて言えば、何をやってもすぐに飽きてつまらなくなる、無聊の状態がずっと続く、ということ。作中ではこれは「嫖客(ひょうきゃく)のかゝりやすい倦怠(アンニユイ)」であり、「酒色を恣(ほしいまま)にしてゐる人間がかゝつた倦怠は、酒色で癒る筈がない」と言われている。
幕末の僧侶である禅超が、長年の放蕩の果てに(当時僧侶の酒色は公的には禁じられていたが、けっこう見過ごされていたらしい)、快楽の飽和状態に達し、生きながらこの地獄に堕ちた、と述懐するのが掌編「孤獨地獄」の要である。最後に、作者の生の言葉として、「或意味で自分もまた、孤獨地獄に苦しめられてゐる一人だ」云々と、記されている。
この部分は、芥川作品に時折見られる、なくもながなリフレイン(三島由紀夫の評語)と言えると思うが、白鳥は「年少者が氣まぐれに口にする感傷語とばかりは思はれない。芥川氏の腦裡に嚴存してゐた感じであつたらしいが、その感じが歳を取るにつれてどう働いてゐたのであらうか。作品の上にどういふ風に現はれてゐたのであらうか」と問いを立てる。
その答えが上の長い引用文中にある。「往生繪卷」となぜ繋がるかと言うと、この世のすべてに興味を失った人間が、この世ならぬ彼岸に憧れるとき、その渇望こそ最も激しいであろう、と白鳥は考えるらしい。それが「往生繪卷」の主人公五位の入道の場合である、と。それはそうかも知れない。
で、白鳥は、芥川はどちらの心境も本当にはわかっていない、と断ずる。頭では理解していたろうし、同情もしたろうが、このような問題を芯から「自分のもの」にしていたわけではない。自分が安全な観察者の立場にいる限り、描かれた人間の苦悩もまた「机上の空影」つまり絵空事にしかならない、というわけ。
おなじみの「実感第一」の文学論で、本ブログでも「こんなんでいいんですか、小林秀雄さん」で瞥見した。現在ではけっこうバカにされているようだが、まだ力を失ったわけではない。それはそうと、芥川の最期の頃を知っている私たちからすれば、このような感想は、また違った角度から眺められざるを得ない。
「聽明な學者肌の人」というのは、芥川作品のいかにも知的に整えられた構成やら、驚くべき博学ぶりから、誰もが抱きがちな人物像であろう。しかし、人間はもっと複雑なものである。「赤い帽子の女」が事実彼の作であるかどうかは措いて、芥川のけっこう派手な女性遍歴は各種の伝記に触れられているし、かなり危ない遊びまでやっていたことは、宇野浩二『芥川龍之介』の最初に出ている。何より、自伝、というか自伝の断片集のような「或阿呆の一生」には、女性との次のような対話が記されている。
「死にたがつていらつしやるのですつてね。」
「ええ。――いえ、死にたがつてゐるよりも生きることに飽きてゐるのです。」
松本清張「芥川龍之介の死」(『昭和史発掘』所収)などによって、この女性が誰かはほぼ特定されており、芥川が彼女と帝国ホテルで心中しようとして、女性の側の翻意によって果たせなかった事実も、現在では明らかであるらしい。つまり、「自分もまた、孤獨地獄に苦しめられてゐる」というのは、「氣まぐれに口にする感傷語」どころではなく、芥川の全き実感だったようなのである。どれほど痛切な、かと言うと、実際に死んでしまうほどの。
白鳥の「芥川龍之介」は、『中央公論』昭和2年10月号初出(このときの題は「芥川龍之介氏の文学を論ず」)であり、同年7月の、芥川の自殺を機に書かれている。時間的に、作者の死後に発表された「或阿呆の一生」や「齒車」などの遺稿は読まずに書かれた可能性はある。後には読んだろうが、それでも白鳥は、自身の芥川論に何ものをも付け加えはしなかった。
だいたい、「或阿呆の一生」を、清張その他による伝記的な考証抜きで、純粋に一個の作品として鑑賞しようとしても、まず無理である。その意味で、文芸作品として自立していない、と言い得る。「齒車」は、一種の奇妙なモダンホラーとして愛好する人もいるようだが、私などには、「わけがわからない」としか言いようがない。精神病理学の知識があればわかるのかも知れないが、それはつまり文学の外側から作品を「理解する」ことに他ならない。
「かう云ふ氣もちの中に生きてゐるのは何とも言はれない苦痛である。誰か僕の眠つてゐるうちにそつと絞め殺してくれるものはないか?」(「齒車」の末尾)と言われても、それが作者の生の「実感」から出ていたとしても、否、いればいるほど、読者としてはどうしようもない、ということである。主観はどこまでも主観であって、その人だけのものだ。文学は、そこに一個のフォルムを与えて、そこから客観的に、読者に伝わるようにしたものであろう。
しかし、「フォルムを与える」のは、反面から見ると、対象と距離を置き、ある枠の中に対象を閉じ込めることである。実感主義からすれば、あまりよいこととは言えなくなるのではないだろうか。そのうえ、さらにもっと大きな問題を、ここに見出すことができると思う。
そこでようやく「往生繪卷」に移る。その結末の問題について、最も言いたかった。
結末に至る道筋を改めて辿る。主人公の五位とは、五位の位にある武士ということだが、殺生を好む乱暴狼藉者であった。あるときたまたま講師(講堂内で説法する僧)が、「どのやうな破戒の罪人でも、阿彌陀佛に知遇し奉れば、浄土に往かれる」と言うのを聴いて、「體中の血が、一度に燃え立つたかと思ふ程、急に阿彌陀佛が戀しうなつた」。そこで講師を取り伏せ、刀で脅しつつ、阿彌陀佛のありかを問うと、「西方浄土」だからだろう、苦し紛れに「西、西」とのみ言う。それから五位は「阿彌陀佛よや。おおい。おおい」と呼ばわりつつ、ひたすら西を目指して走る。やがて海にぶつかり、それ以上進めなくなると、松の梢に上って「阿彌陀佛よや。おおい。おおい」と叫び続ける。七日目、絶命した彼の口からは、まっ白な蓮華が開いていた。
以上を踏まえて白鳥と芥川の問答を、改めて見ていただきたい。白鳥は、死体の口から花が咲くなどということは現実にはなく、それをこう簡単に書いたのでは、「遊び」(=絵空事)にしかならないだろう、と言う。それに対する芥川の書簡中の答えは、少し話をそらしているようである。
曰く、自分が題材にした「今昔物語」中の説話(巻十九「讃岐国多度郡五位聞法即出家語」第十四)では、五位の呼びかけに応じて、海中から阿彌陀佛(だろう)が「此に有り」と声に出して応えたことになっているが、それはヒステリックな尼(文字通りの尼僧ではなく、天理教の中山みきや大本教の出口なおのようなケースを言っていると思しい)にこそ相応しい。普通の人はヒステリーにならなくても、信仰心があれば木の上での往生はできると思うので、それは省いた。しかし、口から咲いた白蓮華は、今の人の眼にも見えるのではないだろうか。
「声が聞こえる」のも「花が眼に見える」のも、もちろん物語のレベルでの話である。できたら、芥川「往生繪卷」でも、「今昔物語」でも、読んだ後で考えていただきたいのだが、この結末を、白鳥の言うように、「五位の入道の屍骸は、惡臭紛々として鴉の餌食になつてゐた」で終わりにしたらどうなるか。文字通り、「話にならない」、つまり、「なんだこの無意味な話は?」と思われてきて、とうてい物語になり得ない、と見えるのではないだろうか。
いや実際は、そういう話も、「物語」が「小説」になった現代では、さほど珍しくない。芥川にもある。今後本シリーズでもいくつか取り上げるつもりだが、そこでの「語り」は、もっと別の面から人間を描出することを狙っている。対して今問題にしている説話風の物語は、清純な信仰が嘉される奇跡物語という、古今東西に偏在する物語のパターン(話型)、即ちフォルム・枠を使って、「絵巻物」を、言葉によって織り上げる作業、と言ってよい。
白鳥にもそんなことはもちろんわかっていた。わかっていて敢えて、それを安易に用いていいのか、と問うのである。何より、芥川自身が、こんな奇跡が現に起こり得るとは信じていないし、起こってほしい、と痛烈に望む者でもないだろう。それでいて、お話をまとめるためだけに使った、そこが安易だ、と。
安易ではない例としては、「ある日の感想」には、白鳥が若いころ師事した内村鑑三の例が出ている。「内村氏は一度信じたことを惰力で信じ續けるやうな無神經な人ではない。氏は自己の幻想を續けるためにいかばかり努力してゐるか」。芥川にはその努力が足りない、というわけだ。いやはやなんとも、厳しいと言うより、どうもお門違いな要求にも見える。芥川はもとより宗教者ではなく、作家である。文学者である。
と、そう簡単には割り切れない。近代で宗教の代用にもなるのが文学の役割ではないか。少なくとも白鳥などは、自然にそう信じていた。彼方の、永遠なる存在、それのみがもたらすことのできる究極の救済。あるとき、不図(ふと)、そのようなものに憧れてしまうのは人間の、万古不易の心性であろう。それに応えるものとしては、信仰心が一般に薄れた現在、文学以外にあるべくもない。
そして白鳥は、仮借無く現実を見つめる反面で、激しく救済を求める人でもあった。「孤獨地獄に苦しめられてゐる」からこそ、「全身の血を湧き立たせて阿彌陀佛を追掛けてゐる」人間に親しみを覚える所以である。そして、才気にまかせてそこに近いところを掠めて飛んで見せるような感じの芥川の芸当を、あきたらなく感じるのも、この性向がしからしめている。
問題は幾重にも錯綜している。別の角度からこのすれ違いを眺めてみよう。
近代は、宗教を筆頭とする、それまで人々の生活意識を組み立てていたものの土台を、完全に壊したわけではないが、少なくとも見かけ上、弱くした。昔の人は信仰による奇跡を素直に信じていた、というよりむしろ、素直に信じる心を否定しなかった、と言ったほうがおそらく事実に近い。
近代人はそうはいかない。白鳥にしても、内村鑑三が信じる聖書の真実などは、幻想だ、と言い切っている。それでいてなお彼を尊敬するのは、前述の努力、即ち幻想であってもそれを信じきろうと努める意欲の強さがあるからだ。しかしそれも、おそらくだが、聖書という物語群が、揺るぎない規範(≒フォルム)として、いつも内村の前にあって、彼を支え、導いたからこそできたのではなかったろうか。そうでなければ、聖書にどれほど惑溺(白鳥の評語)しようと、他人を感動させる研究はできなかったのではないだろうか。
芥川もまた、「西方の人」の著者であり、「永遠に超えんとする者」、即ち超越的なものに自身も憧れを抱いていた。しかし、流行作家として、娯楽としての奇跡物語を書く義務も感じていたようだ。その場合、海を割って道を作るような大掛かりな奇跡では、もう子どもをだますこともできないだろう。神の声を聴くのも、そこいらのヒステリー女が、聴いた聴いたと口走り、そのことが広く知られるようなご時世では、あんまり有効には使えそうにない。口から可憐な花が咲き出でた、ぐらいなら、切ない信仰心を伝えるものとして、許されるのではないか。白けさせないで、同情をよぶことができるのではないか。これでいこう、と、特に自覚はしなくても、自然に頭が働くのが練達した作家というものだろう。
通俗的であさましい計算だ、と白鳥のような人に感じられるのに無理はない。しかし、それでさえも、土台、奇跡を信じたい、という気持ちが現代人の心の中になければ、成り立たない話ではある。つまりその心は、ある。
これらをひっくるめると、こういうのが理想だということになりそうだ。奇跡そのものも、奇跡を信じる心も否定される現代で、超越者への渇望の果てに死んだ人の屍もまた腐敗していく、その生の現実からは目をそむけず、それでも究極的の救済をどこかで求めざるを得ない人の心に寄り添い、できるだけ掬い上げること。言い換えると、奇跡に依ってしか癒されない類の人間性の一面に、奇跡なしで関わること。それを客観的に語れるフォルムを作ること。新たな話型、それもできれば聖書のような普遍的な、とまで言えば、それこそ奇跡でも起きなければ無理な話ではあるが、その志は持ち続けること。
「そんなの知らないよ」と、今の作家には軽く言われてしまいそうだが、人間に「内面」があり、「内面」には価値があるという信仰が完全に失われない限り、文学の名におけるこの志もなんとか続くだろう。
いやまあ、未来のことは結局わからないので措くとして、昔の文学者たちがどのように、野暮に、こういう問題に取り組んだか、次回からもう少し見ておきたいと思う。