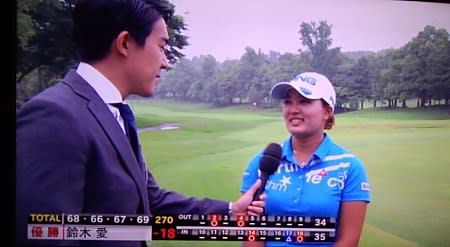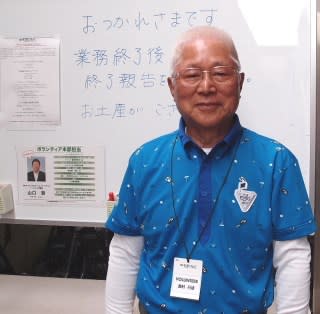実に重い内容の本である。
68歳の主人公は3年半前に最愛の妻を見送り、今はひとり暮らしをしている。
日頃はウォーキングを楽しみ、食事も自分で用意、週に2度の宅配の食事も楽しむ。
日頃は日記を付け、漢字を10字を書いてみる等、認知症の予防にも怠りない。
離れて住む息子夫婦も、体力の衰えた父親の動向を絶えず気に掛けている。
息子のプレゼントの電動自転車で、散歩に出掛けたが、バッテリー切れからパニックを起こす。
その際のトラブルから、息子の嫁は義父の認知症を疑い出す。
時々まだら呆けからの行動が始まるが、ウソの家出をして息子夫婦を驚かそうとする。
行き当たりばったりの旅の終局で、辿り着いたのがある遠方の国民宿舎。
2週間後にその宿舎の館長から、心配する息子夫婦の元に引き取りの要請がある。
さらに帰宅した後の日頃の生活の上で、主人公はトラブルを連発するようになる。
息子夫婦は、何とか認知症の改善を図ろうと、精神科病院や、老人ホームでの生活を強制する。
遂には有料老人ホームの費用捻出の為に、息子夫婦は一人住まいの家屋の処分を決意する。
その決断が、主人公を更に追い詰めて、老人ホームや自宅でも錯乱状態が頻発する様になる。
ある講演会で出会った精神科医から、認知症を忌避するのでなく、受け入れる事を勧められる。
優しかった父親の思い出から、自宅に引き取り、なるべく普段通りの接し方で一緒に生活を始める。
その穏やかな生活の中で、満たされた心根で死を迎える主人公。
小生と同じ年代の主人公が、衰える精神と体力の中で迎える生活を、慄然としながら読んでしまった。