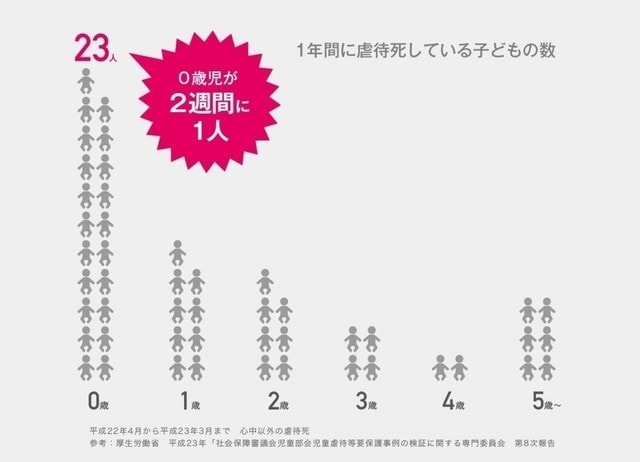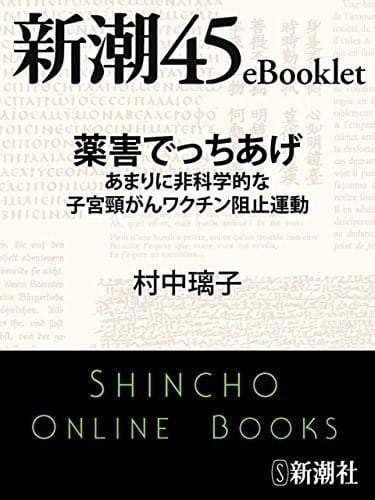震災から23年。神戸にあった『アンサングヒーロー』の物語 ~子ども食堂は、最高の『隠し味』より~
みなさん、カレーに何か隠し味を入れますか?
ハフポス2018年01月16日
村尾政樹のブログ『変化と感謝』http://murao.hatenadiary.jp/entry/201703より
ちょうど1年前は「こども食堂サミット2017」で300人を超える全国の子ども食堂を運営される方々へ、応援メッセージを込めてお話をさせていただきました。
このストーリーは、神戸が舞台です。1月17日で阪神・淡路大震災から23年が経過しますが、私はその神戸で被災した子どもの一人です。当時は4歳でした。生まれ育った街への想いとして、今回は以下にサミットでお話をさせていただいた内容を転載します。
直接的に震災に関する話ではありませんが、最後に触れる『小さな支え』は復興へ向かう、自分たちの街で暮らす子どもを大切に想ってくれた『アンサングヒーロー』です。是非ご一読いただければ幸いです。
子ども食堂は、 最高の『隠し味』
みなさん、こんにちは。子どもの貧困対策を推進する公益財団に勤めている『あすのば』事務局長の村尾と申します。よろしくお願いいたします。
突然ですが、これは、僕がつくったカレーです。
みなさん、カレーに何か隠し味を入れますか?調べてみると、りんご、はちみつ、ソース、チョコレート...。これ以外に何か入れたりすることはありますか?ヨーグルトもありましたね。
色々とあるみたいですけど、僕がつくったこのカレーには、インスタントコーヒーを入れています。最後に少しだけインスタントコーヒーを入れると、お家でつくったカレーではなく、ちょっと、お店でつくったような深みが出るんですね。
ぜひ、『子ども食堂を続ける』というテーマなので、今度カレーをつくるときにインスタントコーヒーを入れてみてもらえると、ちょっと違う味になるかなぁと思います(笑)
なぜ隠し味の話をしたかというと、ずっと思ってることがあって、子ども食堂の取り組みは、子どもたちの人生にとって最高の隠し味だなぁって思っています。
栗林さんは、よく『おせっかいおばさん』と紹介されていて、僕も、栗林さんの世代くらいだとその『おせっかい』を受けてきた子どもの世代かもしれません。そこで、僕は自分のことを『おせっかえしお兄さん』と命名しました(笑)
最初は、栗林さんがWAKUWAKUネットワークで言っている『おせっかえる』みたいに『カエル、おせっかえるのお兄さんです』と言おうとしましたが、まだまだカエルではない、未熟な『おたまじゃくし』の部分もたくさんあるので...。ただ、今、『おせっかい』を返そうとしているお兄さん、という立場です。
僕も『孤立』しそうな子どもだった
少しだけ、僕の話をさせてください。僕は、おせっかいを受けて育ってきた経験があります。僕は、小学校6年生のときに、お母さんを自殺で亡くしました。お母さんが亡くなって、父子家庭で育ちました。
経済的な意味では、子どもの貧困対策を推進する財団法人に勤めていて、厳しいお母さん方の現状を常に聴いているので、相対的な面では少しまだゆとりがあったのかもしれない。
けれど、お母さんが亡くなってから、お父さんも仕事をしていて、しばらく定時で仕事を終えて帰ろうとするんですけど、民間の企業に勤める会社員でしたので、そういう訳にもずっといかないとなりました。
お母さんが亡くなって、数カ月経ったときくらいですかね。お父さんから僕も含めて姉と弟3人に「自分の生活は自分でやってね。それが基本です。」と告げられました。
僕のお父さんは朝の4時半とか5時くらいには起きて、僕が起きる前に仕事へ行って、僕が寝る前、もしくは寝てからかな、仕事から帰ってくる。そういう生活でした。
だったので、実はお母さんが亡くなってからは家で親や大人と一緒に暮らした経験がほとんどありません。弟にいたっては5つ下なので、当時は僕が11歳でしたから、6歳でした。姉は2つ上で、中学生でした。
僕が、その経験をして、そして、あすのばで高校生や大学生世代の同じような経験をした若者たちから話を聴いたり、子どもやお母さん、お父さんにも直接お話をうかがっていく中で、思う事があります。
『誰かに頼ってはいけない』、『強く生きねばならん』、『弱いところも見せちゃいけない』と。周りも言うんですね、「お母さん亡くなってるのに、えらいね。」と。「しっかりしてるね。」と。しっかりしてない時があると、「辛いことがあっても、頑張らないかんやろ。」と言います。
僕は関西、神戸出身なんですけど、そういう風に声をかけてくれることがありました。その方々も悪気があって言ってる訳ではないことは、分かります。
ただ、そう言われて『ああ、頼っちゃいけないんだな。』、『弱みを見せちゃいけないんだな。』、『しっかり生きていかないといけないんだな。』、そう思って育っていくと、よく自立が大事と言われますが、僕は、自立ではなく『孤立』を生み出すと思っています。
今、子どもの貧困対策や色んな活動で『子どもが大きくなって自立して...』と言いますが、その望む自立が『孤立』になってしまっていないか。
私たちあすのばは、子どもたちの声をしっかり代弁させていただいて、自立が『孤立』になることがないよう防がないといけません。
僕も、とがってましたね。『頼っちゃいけない』、『弱みを見せちゃいけない』、『しっかりせなあかん』と。とがって、孤立しそうになってました。
『おせっかえし』の気持ちになれた、三つの出来事
ここで、三つ出来事を紹介します。
まず一つ目。運動会のときです。小学校6年生、最後の運動会。お母さんが亡くなりました。お弁当など、もちろんありません。その運動会の前日の夜、僕の家のインターホンが鳴りました。
友達のお母さんでした。ささっと渡してくれました。運動会のお弁当を。そこで「一つも二つもつくるの一緒だから」と言ってくれました。
「あなたのとこ、お母さんがいないから...」ということは、一切言いませんでした。一つも二つも一緒だから、全然気は使わなくても良いからね、と渡してくれました。
まだあります。二つ目。中学校にあがったときです。
僕は、なかなか料理ができなかったので、大体は冷凍食品を電子レンジで一生懸命『チン』をするか、カップラーメンに一生懸命お湯を入れて、3分間、一生懸命待って食べるか、そういった食生活だったんですね。でも、たまに、お弁当屋さんにお弁当を買いに行ってました。
そこに、僕のお姉ちゃんの友だちのお母さんがパートで働かれていて、僕は、のり弁を頼みます。渡されていたお金が少なかったので、一番安いやつを頼んでいました。
そうすると、そのお姉ちゃんの友だちのお母さんは、こっそりと唐揚げを2個入れてくれるんですね。
お姉ちゃんの友だちのお母さんは、何も言いません。『大丈夫だったのかな』と今は思ったりもするんですけど、こっそりと2個、唐揚げを添えてくれるんです。
『今日も入れといてあげたからね』というようなアイコンタクトをされて、「ありがとう」と言って、帰って唐揚げを食べるんですね。そこには、唐揚げ以上に受け取っているものがあったのかなと思います。
最後に、三つ目。これは、栗林さんから「村尾少年の話をしてください」と言われて色々考えました。小学生、中学生、高校生、何かなかったかなと。他にもあったんですけど、これは、その考えていたときに思い出した話です。
通っていた高校が地元から電車で通うところだったんですけど、その近くに僕のお父さんの同級生がお好み焼き屋さんをやっていたんですね。
『ゆっこ』っていうおばちゃんなんですけど、高校の授業が終わると、僕、そこに行くんです。
「いつものお願い」と言うと、おばちゃんはお好み焼きとご飯を出してくれます。食べ終わると、僕は「じゃあ、ツケで」と言って帰ります(笑)
お父さんが後で払うシステムにしていたそうです。でも、単に後で払ってくれるからというのではなくて、電話をして予約する必要もなかったですし、そのときに行って、じゃあ、今日はお好み焼きじゃなくて、お好み焼き屋さんじゃ出てこないようなハンバーグとかが出てきたりとか、そういうこともあったんですね。きっと、色々と気を使ってくれていたんだなって、思い返して思います。
三つの出来事をお話しましたが、実は、子ども食堂の取り組みも大きな出来事、ビックイベントとしてある訳ではないのかもしれません。
僕も、さっきのお好み焼き屋のおばちゃんのこと、こないだ、ふと思い出しました。でも、目立たなくても、小さなそういった支えが、少なくとも僕の場合は、大きな色んな基礎になっています。
そういった友達のお母さんとか、おばちゃんとか、近所の人とかがいてくれたから、『おせっかえし』をしよう、そういう気持ちになれているのかなって。
「運が良かった」には、絶え間ない『小さな支え』があったから
きっと、みなさん、子ども食堂をされていて、素直になれない子どももいると思います。僕もとがってましたし、ひねくれていた子どもだったので「ありがとう」とか、嬉しいことを「嬉しい」ってなかなか言えなかった。
でも、子どもたちのそういった小さな支えを受ける経験の積み重ねが、5年後、10年後、15年後、どういうときに子どもが思い出すか分かりませんが、大きな力になっていることは、日ごろ子どもの声を聴かせていただいて、そして、僕の経験からもお約束させていただきたい。
あすのばに関わる若者たちも、よく「人に恵まれてたんだよね」と言います。その、「人に恵まれてきたんだよね」、「運が良かったんだよね」という下地には、こういった子ども食堂、みなさんの絶え間ない『小さな支え』があったからなんだなって、きっと、いつか、その子たちは分かるときがきます。
そして、『おせっかえし』、それは次の子どもかもしれない、子ども食堂かもしれない、社会かもしれない、きっと返してくれます。