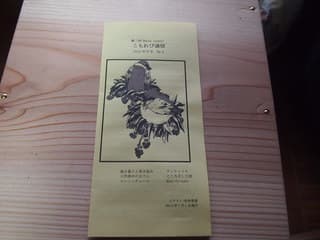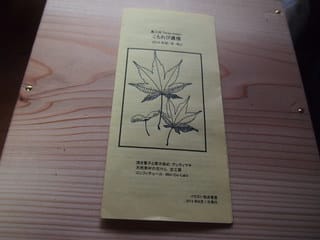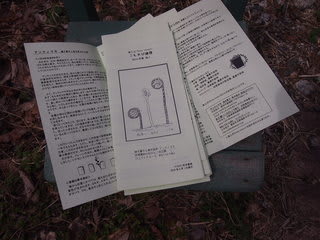今月はじめ、奥三河Three trees+の活動を載せた「こもれび通信」創刊号を発刊しました。
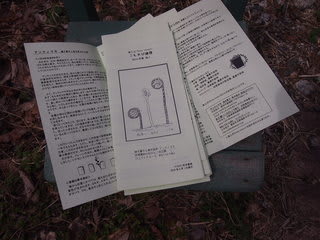
内容は、奥三河Three trees+のメンバー、アンティマキとこころざし工房、Miki-Co-Laboそれぞれが伝えたいこと、いなか暮らしのあれこれを綴ったメモ、イベント出店や講習会のお知らせなど。季刊で発行します。A4判裏表、モノクロ印刷です。まずは、2014年春号です。
イラストを描いてくれているのは、稲武出身の松井香澄さん。この3月芸術系の大学を卒業し、4月からは商業デザイナーの道を歩むことになっている女性です。
こもれび通信は、どんぐり横丁、スーパーやまのぶ梅坪店など奥三河Three trees+の商品を置いているお店や、私達が出店したイベントで配布しています。商品を置いていなくても、この通信だけ置かせて下さっているお店もあります。随時、募集中です。
以下は、創刊号をコピーしたもの。アンティマキは、おかきのつくり方、Miki-Co-Laboはコンフィチュールのつくり方を載せています。松井香澄さんのイラスト、残念ながらスキャンできていません。そのうち、なんでもなくスキャンできるようになったら、載せます。フォント、文字の大きさも同様です。いまのところ、ただのべたうちです。ご了承下さい。
******
奥三河Three trees+
こもれび通信
2014年春 №1
焼き菓子と草木染め アンティマキ
天然素材の石けん 志工房
コンフィチュール Miki-Co-Labo
イラスト/松井香澄
2014
■アンティマキ 焼き菓子と草木染めの工房
<いなぶの玄米おかき>
おかきは、三河・尾張地方で、おへげ、おへぎ、かきもちなどと呼ばれる郷土菓子。子どものころ、母の実家に行くと、祖母が缶に入ったかきもちやあられを出してきて、火鉢の火であぶったり炒ったりしてくれたものです。
アンティマキのおかきは、冬から春にかけて製造します。おかきの基本的な材料は、稲武大野瀬町の筒井重之さんが育てた、低農薬栽培の玄米もち米、フランス産ゲラントの塩、沖縄産粗糖。甘さを抑えて、素材の持ち味を生かしているので、噛むほどにそこはかとない滋味を感じていただけることとおもいます。・
さて、アンティマキのおかきの作り方は単純です。
まず、もち米を3分搗きに精米します。ぬかは捨てません。米を洗って一晩か二晩浸水したあと、餅つき機に米とぬかを入れて蒸します。蒸し終わったら搗きます。ここまでは、普通の玄米もちの作り方と同じ。ただしおかきの場合は、こころもちよく搗いたほうがいいようです。まとまってきたら、分量の粗糖と塩を入れ、さらに搗きます。
金属の箱など深めの容器にラップを敷き、そこに搗きたてのもちを流し込みます。表面をならして、いったんそのまま2日ほどおいておきます。
固くなってきたころ、切ります。私は農協で買ったかきもち切り機を使っていますが、この道具を買うまでは、薄く切るのが大変でした。切ったかきもちは、ざるや木の箱に広げて干します。一日干していると反ってくるので、裏返しては3日ほど、固くなるまでつづけます。
これでいったんできあがり。この状態で密閉容器に入れておけば、一年でももちます。ただし、完全に乾いていないとかびるので、要注意。このおかきを私はオーブンで焼いて、袋につめています。仕事は単純ですが、日にちはかかります。
おかきは、プレーンのほか、黒糖入りとごま塩入りを今年新発売しました。シナモン入りやクルミ入りも検討中です。
<季節の草木染め>
春から初夏にかけては、萌え出たばかりの草から、鮮やかな若草色が生まれます。ヨモギ、スギナ、カラスノエンドウ、セイタカアワダチソウ、フキ。煮出すときに入れるソーダ灰や重曹が、美しい色を染め出す魔法の粉。薄緑や黄緑に染まった布を見ると、山里にも春がやっと訪れたのだな、と実感します。
■志(こころざし)工房 天然素材の手作り石けん
志工房の石けんは、「人と地球にやさしく、安心して使える石けんを使いたい」「毎日使うものだからこそ、余分な物は一切いれたくない」「使ってみて、心地よくなったり嬉しくなったり・・・心が躍るような石けんを作りたい」そんな想いから生まれました。
<手づくり石けんとの出会い>
私が初めて手づくりの石けんと出会ったのは、10年程前、オーストラリアの小さなマーケットでした。精油入りで、とってもいい香りがする石けんを見つけ、無添加で自然な素材だけで作られていることにも惹かれて購入しました。思い切って洗顔に使用してみたところ、そのやさしい使い心地に感激しました。
普段、私の肌は、洗顔後すぐに化粧水をつけないと顔がピキピキと引きつったように乾燥してくるのですが、その時は、すぐに化粧水をつけなくても気にならないくらいでした。その上、洗顔後なのに、肌がしっとり潤っているようにも感じました。
私の肌は乾燥しやすく、しかも肌が弱いので使えない洗顔料がいくつもあります。けれど、この石けんは洗顔後のつっぱり感がほとんどなく、肌への刺激を感じることもありませんでした。
やわらかな泡ですっきりと汚れを落としてくれて、やさしいアロマの香りに包み込まれるような感覚・・・私は心も身体も癒されて、手づくり石けんの魅力にどんどんはまっていきました。
短い間でしたが、オーストラリアでの生活で、自分の手で何かを作り出すことに目覚めた私は、「私もいつかあんな素敵な石けんを作れるようになりたい!」という熱い想いが沸いてきて、帰国後、本や資料を集め、すこしでもその石けんに近づけるようにと試行錯誤を重ねてきました。手づくり石けんは最低一ヶ月以上の熟成期間が必要なため、何年もの月日がかかりましたが、やっと最近、自分でも納得できるような石けんに近づいてきた気がします。
あのマーケットで出会った小さな石けん。それがキッカケで環境についても考えるようになり、私のライフスタイルは大きく変わりました。これからもたくさん学び、あの時私が感じた感動を伝えていけるような石けんを目指して、造り続けていきたいと思っています。
*志工房の手づくり石けんは、個人で作っているものなので、法律上「雑貨石鹸」「キッチン石鹸」の販売となります。薬事法による薬用石鹸・化粧石鹸のいずれにも該当いたしません。そのことをよくご理解の上、ご自身の判断と責任のもとでのご使用をお願いしております。
■Miki-Co-Labo 季節のコンフィチュール
コンフィチュールは果物を甘く煮るシンプルな保存食です。
新鮮な味わいと香りを楽しむために、大切にしていることがあります。
1.できる限り近くで育った新鮮な果物を、生産者から直接入手する。
2.できる限り農薬を使わずに育った、安心安全な果物を使用する。
3.沖縄産の粗糖『本和香糖』を使う。
4.材料を混ぜ、水分が出るまで寝かせる。
5.水は一切加えない。
6.熱伝導率の高い銅鍋で煮る。
7.風味を損なわないよう、強火で短時間で煮上げる。
8.甘さ控えめで保存性を確保するため、糖度計で35~40度になっていることを確認し、瓶詰めする。
9.賞味期限は6ヶ月。少しずつ変化するので、なるべく早く食べて欲しい。
特に、自家栽培しているブルーベリー、ブラックベリー、カシス、クランベリー、ルバーブのコンフィチュールは、濃厚な味わいと香りが格別です。
<春のコンフィチュール>
・甘夏 :蒲郡産、農薬不使用
・金柑 :蒲郡産、農薬不使用
・梅 :稲武産、農薬不使用
・ルバーブ :自家栽培、農薬不使用
・ブラックベリー :自家栽培大粒品種、農薬不使用
奥三河Three trees+は3人の女性のユニットです。
アンティマキ 焼き菓子・草木染め・野遊びクラフト
村田牧子 豊田市夏焼町ワカドチ383-5
auntie-maki@cb.wakwak.com
ブログ:「アンティマキのいいかげん田舎暮らし」
志工房(こころざしこうぼう) 天然素材の石けん
中村志江 北設楽郡設楽町津具西段戸10
yukie_f1221@hotmail.com
Miki-Co-Labo コンフィチュール
三木和子 豊田市大野瀬町中ギリ22-4
k9pcmail8m@yahoo.co.jp
*奥三河Three trees+の詰め合わせも承ります。
■暮らしnote ~山菜の話~
蕗の薹に始まる春の味覚は、美味だからというより、あのほろ苦さが、冬の間に寒さでちぢこまった体を目覚めさせるような気がして、一通りはどうしても食べたくなります。
蕗の薹はたくさんあればてんぷらにもしますが、たいていは、こまかく刻んでいためて蕗の薹味噌にします。蕗の薹が少ないときは、葱や生姜で増量。苦味と辛味が食欲をそそります。以前、知人の家で食べた蕗の薹パスタは、ぜいたくな味でした。
蕗の薹の次は土筆。わたしは子どもの頃から、採るのも食べるのも好きなのですが、このあたりの人は、あまり食べないらしい。農家にとってスギナは畑の大敵。「スギナの地下茎は地獄まで伸びている」といっていやがります。だから、土筆など、にくらしくて食べる気になれないのだ、と聞いたことがありますが、ほんとかしら?
蕨が出る頃は、稲武にもやっと遅い春がやってきます。梅、連翹、水仙、桜と、花が立て続けに咲き乱れ、枯野が鮮やかな春の景色に一変します。
蕨の食べ方で私が好きなのは、蕨ご飯と和風マリネ。ご飯は、アク抜きした蕨をよく洗って刻み、塩味をつけた炊き立てのご飯に混ぜて蒸らすだけ。マリネは、切った蕨を醤油、みりん、酒を煮立てて冷ました液の中に、昆布と一緒に漬け込みます。
最後はコゴミ。数年前、自宅の敷地内の一角で群落を発見し、以来、毎年この山菜だけは自家採取ができています。雑草の中にぼこっと土の上がったようなところができたなと見ていると、数日後にコゴミの株が顔を出します。そしてしばらくすると、黄緑色してまるまったかわいらしいコゴミが登場します。
コゴミが濃い緑色になり、シダのような大きな葉になる頃には、周りの雑草も伸びてきて、初夏の日射しを感じはじめます。 (maki)
●商品のあるところ
■祇粘堂(きねんどう)
浜松市北区引佐町金指 ℡053-542-2737
■どんぐりの里いなぶ
豊田市武節町 ℡0565-82-3666
■やまのぶ梅坪店
豊田市東梅坪町 ℡0565-36-1234
※店によっては置いていない商品もあるので、ご了承ください。
●イベント出店予定 2014年4月~6月
[4月]
1日……グリーンママンまちかど朝市
(アンティマキ)
10日……グリーンママンタキソウ朝市
(アンティマキ/志工房/Miki-Co-Labo)
13日……三好ヶ丘ラヴィマルシェ
(アンティマキ・志工房・Miki-Co-Labo)
[5月]
3日……福蔵寺ご縁市
(アンティマキ・Miki-Co-Labo)
5日……ナゴヤビーガングルメ祭り
(アンティマキ・志工房・Miki-Co-Labo)
8日……グリーンママンタキソウ朝市
(アンティマキ/志工房/Miki-Co-Labo)
[6月]
1日……よさみガーデンマルシエ
(アンティマキ/志工房/Miki-Co-Labo)
8日……三好ヶ丘ラヴィマルシェ
(アンティマキ・志工房・Miki-Co-Labo)
12日……グリーンママンタキソウ朝市
(アンティマキ/志工房/Miki-Co-Labo)
●講習会などの予定
・4/14…こねないパンとスコーンの講習会
(問い合わせ: ヘルシーメイト岡崎本店 ℡0564-52-7000)
・5/11,12…chie流マクロビオティック料理教室
・6/9…こねないパンとスコ-ンとスープの講習会
(いずれも、申し込み問い合わせはアンティマキまで。)
・4/27 , 5/25…どんぐり工房定例草木染め講習会
(問い合わせ: どんぐり工房 ℡0565-83-3838)
※イベント・講習会共に変更することがあります。ブログ「アンティマキのいいかげん田舎暮らし」か、アンティマキのFBページでお確かめください。