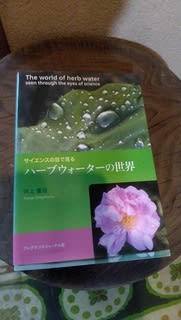ずっと前から、精油や蒸留水を作る手軽な装置を買おうかどうしようか、迷っていました。大きいのはとても高い。でも小さいのならさほどの値段ではないので買ってもいいなとは思うのですが、それでも使わなかったら邪魔なだけ。持っている友人に聞いたら、蒸留水ですらできるのはほんの少しだけ、とのことなので、なおのこと、一歩踏み出せないでいました。
ところが最近ときたまお会いする機会のある方が、幡豆の工房で蒸留水の講座を開いているとお聞きし、さっそく友人たちとお訪ねしました。
彼女は小久保亮子さん。ハーブをこよなく愛し、海の見える小高い丘にあるご自宅兼工房の庭で何種類ものハーブを育てていて、そのハーブで種々の蒸留水を作っています。養蜂も手掛けているので、みつろうを使ってクリームなども手作り。工房の中はかぐわしい香りに満ちていました。
彼女のモットーは、身近にある道具で手軽にハーブを利用すること。私の希望にピッタリです。

蒸留に使ったのは、ステンレスの蒸し器。耐熱ガラスかステンレスが蒸留にはふさわしいそうです。
この日は、同行した友人が山で採取したクロモジとタムシバ、それにコアジサイの花を使って、蒸留水の作り方を教えていただきました。真ん中に匂いのつきにくい陶器や耐熱ガラスの器を置き、刻んだ材料を周りに入れます。
クロモジとタムシバはどちらも大好きな香り。少し量がすくなめなので、お庭のレモングラスも足します。

蒸し器の上にふたをします。この蓋が大事。ひっくり返して蒸し器の中の容器に水滴がしたたり落ちやすいように、なるべく円錐形のものをえらびます。そうすると漏斗状の蓋を伝って水滴が中央の容器に落ちる、というわけです。

蓋が大きくても、蒸し器とぴったり重なるものを選びます。下の鍋に水を入れて点火。蓋の上に用意しておいた氷と湧き水か浄水を入れ、加熱し続けます。どんどん氷を入れると、蒸留が早いのだそうです。
思ったより早めに、植物の匂いがしてきます。植物によって量が採れるものと採れないものがあるそうで、レモングラスは別名「香水ガヤ」といわれるほど、水が採れるけれど、ミントや花は少なめだそう。
加熱の具合は草それぞれ。ある程度の蒸留水が採れたら、植物の様子を見て続行するかどうか決めたらいいのだそうです。

ほぼ20~30分ほどでこれだけ採れました。意外に多い。レモングラスの匂いの中に、クロモジやタムシバの匂いが混ざり、いつまでも嗅いでいたいいい香りになりました。
コアジサイは、鼻を近づけるとほんのり独特の優しい香りがする花です。アジサイは本来毒なのだそうですが、コアジサイは毒のないアジサイ。このコアジサイの花も試しに蒸留水にしてみました。
花の量が少ないこともあって、レモングラス・クロモジ・タムシバのミックス水より少なめの量しかできませんでしたが、香りはしっかり残っていました。

亮子さんの作った、ティートゥリーとラベンダー&ローズマリーの蒸留水も含めて、この4本がお土産。
蒸留水は、本来エッセンシャルオイル(精油)を採るときにできる副産物。精油は古くから自然療法に使われていますが、蒸留水も精油とは異なる効果がたくさんあるのだそうです。
「精油を作るのはたいへん。でも、ハーブウォーターは誰にでも作れます。ということは、植物のいいところを利用した薬も、誰にでも作れる、と私は考えています」と亮子さん。
たとえば、彼女は以前目薬を手放せないほどいつも目が痛かったのだそうですが、目をつぶったまま目の前辺りでハーブウォーターの霧を作り、目を開いて開けたりとじたりを繰り返す、ということをしばしば行っているうちに、目の痛みがすっかりなくなったとか。今は市販の目薬を一切使っていないそうです。
コモンセージやクラリーセージの蒸留水をマウスウォッシュとして使うと、のどの痛みが消えることもしばしば体験済み。蒸し器の下の鍋に残った湯は、足湯や風呂に使うといいそうです。
「植物はいくつかの機能を持っています。一つだけではない。だから、いくつかの植物を合わせて使うことで、足りないものを補ってくれるので、より多機能の効果を手に入れることができます」
蒸し器がない場合は、普通の鍋でも代用できるというので、実演してもらいました。
鍋の中央に容器を置いて、周りに植物を敷き詰めるところは一緒。そのあと、鍋肌から深さ3センチほど水をそっと入れます。蒸し器の場合は最初は強火がいいのですが、こちらは最初から中弱火か弱火で。蒸し器の場合よりしばしば様子を見ないといけないけれど、ほぼ同じように蒸留水ができるそうです。
化粧水やリンスやシャンプーそのほかいろいろ利用できそうな蒸留水。家にある鍋で結構な量ができると知って、わくわくしました。
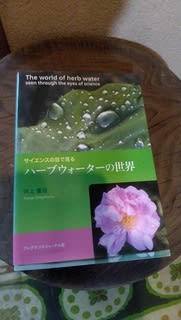
帰宅後さっそく、亮子さんおすすめの本を一冊注文。ハーブウォーターのからだに対する作用~鎮静効果とか消炎効果とかが詳しく書かれていて、42種類のハーブとハーブウォーターについて、とても詳しく書かれています。辞典のような本なので、いざというとき役に立ちそうです。

近々、試みる予定なのは、ローズマリー。若返りのハーブといわれる植物だそうで、日々の生活にふんだんに使えたらいいなとおもっています。いずれ、近くに住む友人の庭で咲いていたエキナセアも試してみたい。手ごろの蒸し器が家にないので、しばらくは深めのステンレスの鍋で代用するつもりです。