豊田市山間地にある足助病院で、ただいま、病院に入院しているお年寄りと、面会にいらしたそのご家族を撮った写真の展示会を開いています。
写真展のタイトルは、「家族 時間の交差点」。撮影したのは、写真家の佐伯朋美さんです。写真はすべて、病院で希望者を募り、面会時間に彼女が同席して撮影したもの。ほぼ寝たきりで病床にある患者さんたちが対象です。

多分親子と思われる二人の、手の表情が印象的な一枚。

ほとんど口を利くのもままならない病人と、意思の疎通ができるのは手だけということなのでしょうか。そのことを佐伯さんは察知して、この写真展では手の印象の強い写真がおおく展示されているように思えます。

撮影は、病人の周りに家族が集い、和気あいあいとした雰囲気のうちに進められたよう。家族の笑顔が、さわやかです。
わたしは、7年前に、この足助病院で実母の看護に当たっていました。当時86歳だった母は、ある日突然意識不明となり、救急車で運ばれました。意識は数日で戻りましたが、口はきけず、全身衰弱状態に。前々からの母の希望もあって、一切の治療は施さず、点滴のみでそのまま過ごすことにしました。
しかし、一月経っても顔色は変わらず、さらに衰弱して死に至る気配が見られません。死を待つことがしだいに胸苦しくなり、親しくしていた友人の医者に診てもらいました。すると、彼は、「胃ろうの措置を施せば、おかあさんはひょっとして元気になるかもしれない。それくらいしっかりしている」と言いました。延命装置をつけることなど、考えてもいなかったのですが、このまま彼女の餓死を待つのがいたたまれなくなり、措置をしてもらうことを決めました。
胃に穴をあけて管を通す、というのは弱っている病人には大変な負担となるので、その前に、のどを切開して管を通し、経管栄養を与えることになりました。与え始めてじきに母の顔色はバラ色になり、その内表情が出始め、ときには笑顔も見せるようになりました。そのときの笑顔が、すばらしかった。母はあまり快活ではなく、どちらかというと暗い表情が多かったのですが、そのときは誰彼となく笑いかけるようになり、キラキラ輝いて見えました。看護師さんたちの中には、「〇〇さん(母の姓)を見ると癒されるわ。ちょっと休みに来た」といって、母の病室に立ち寄ってくださる方もいました。全く社交的でなかった母が、あんなふうに人から遇されたのは初めてだったのではないかと思います。言葉も少しですが発するようになりました。
その後、胃ろうを施したのですが、この措置は結局母にはあわず、ほどなく亡くなりました。本人も望まず、担当医もしぶった延命治療を一時的にも施したことは、母にとってよかったのかわるかったのか、今でも時々思い出しては、どちらとも決めかねる思いでいます。それは、あの経管栄養を施したときの、母の笑顔を見ることができたから。私たちは決して仲のいい親娘ではなかったのですが、あの笑顔は今でもはっきり覚えています。
佐伯さんが撮った写真を見て、あのときのあの笑顔を写真に収めることができていたらなあと何度も思いました。誰よりその写真を見せたかったのは、母自身にですが。
写真展のちらしには、こう書かれています。「面会時間を目標に昔の思い出が溢れ、その時間がまるで本にしおりを挟んだように忘れがたいものになる。意識していないと大切な時間は、指の先からスルスルと落ちて行く。家族の大切な時間を、写真でおさめました。あなたの交差点を見つめるひとときに」

写真展は、2月15日まで。足助病院内の玄関ホールと東側エレベーターホールにて開催しています。
ところで、佐伯朋美さんは、1昨年春、東京から三河山間地に移住した写真家。私の焼き菓子を召し上がってくださったのがきっかけで、交流が始まりました。その彼女が撮ってくれた写真で構成したパンフがこちら。昨年末、できあがりました。
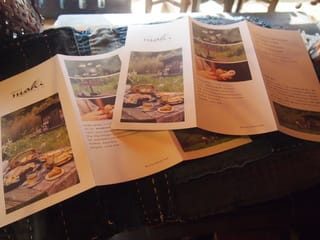
デザインとコーディネートは、稲武出身のデザイナー松井香澄さん。二人が協力して、わたしにはもったいないような素敵なパンフを作ってくれました。イベントや講習会の折にお配りいたします。
なお、佐伯さんは、ヨガのインストラクターでもあります。自らを「呼吸の写真家」と名付けるのは、呼吸をことのほか大事にするヨガを深くご存じだからこそ。息遣いまで撮りたいという思いが込められているようにおもいます。フリーのカメラマンとして、記念日や家族写真、大事な友達との思い出のための写真などの撮影もひきうけてくれます。気軽にご相談ください。連絡は、05035881011 kokyu.photo@gmail.com まで。
写真展のタイトルは、「家族 時間の交差点」。撮影したのは、写真家の佐伯朋美さんです。写真はすべて、病院で希望者を募り、面会時間に彼女が同席して撮影したもの。ほぼ寝たきりで病床にある患者さんたちが対象です。

多分親子と思われる二人の、手の表情が印象的な一枚。

ほとんど口を利くのもままならない病人と、意思の疎通ができるのは手だけということなのでしょうか。そのことを佐伯さんは察知して、この写真展では手の印象の強い写真がおおく展示されているように思えます。

撮影は、病人の周りに家族が集い、和気あいあいとした雰囲気のうちに進められたよう。家族の笑顔が、さわやかです。
わたしは、7年前に、この足助病院で実母の看護に当たっていました。当時86歳だった母は、ある日突然意識不明となり、救急車で運ばれました。意識は数日で戻りましたが、口はきけず、全身衰弱状態に。前々からの母の希望もあって、一切の治療は施さず、点滴のみでそのまま過ごすことにしました。
しかし、一月経っても顔色は変わらず、さらに衰弱して死に至る気配が見られません。死を待つことがしだいに胸苦しくなり、親しくしていた友人の医者に診てもらいました。すると、彼は、「胃ろうの措置を施せば、おかあさんはひょっとして元気になるかもしれない。それくらいしっかりしている」と言いました。延命装置をつけることなど、考えてもいなかったのですが、このまま彼女の餓死を待つのがいたたまれなくなり、措置をしてもらうことを決めました。
胃に穴をあけて管を通す、というのは弱っている病人には大変な負担となるので、その前に、のどを切開して管を通し、経管栄養を与えることになりました。与え始めてじきに母の顔色はバラ色になり、その内表情が出始め、ときには笑顔も見せるようになりました。そのときの笑顔が、すばらしかった。母はあまり快活ではなく、どちらかというと暗い表情が多かったのですが、そのときは誰彼となく笑いかけるようになり、キラキラ輝いて見えました。看護師さんたちの中には、「〇〇さん(母の姓)を見ると癒されるわ。ちょっと休みに来た」といって、母の病室に立ち寄ってくださる方もいました。全く社交的でなかった母が、あんなふうに人から遇されたのは初めてだったのではないかと思います。言葉も少しですが発するようになりました。
その後、胃ろうを施したのですが、この措置は結局母にはあわず、ほどなく亡くなりました。本人も望まず、担当医もしぶった延命治療を一時的にも施したことは、母にとってよかったのかわるかったのか、今でも時々思い出しては、どちらとも決めかねる思いでいます。それは、あの経管栄養を施したときの、母の笑顔を見ることができたから。私たちは決して仲のいい親娘ではなかったのですが、あの笑顔は今でもはっきり覚えています。
佐伯さんが撮った写真を見て、あのときのあの笑顔を写真に収めることができていたらなあと何度も思いました。誰よりその写真を見せたかったのは、母自身にですが。
写真展のちらしには、こう書かれています。「面会時間を目標に昔の思い出が溢れ、その時間がまるで本にしおりを挟んだように忘れがたいものになる。意識していないと大切な時間は、指の先からスルスルと落ちて行く。家族の大切な時間を、写真でおさめました。あなたの交差点を見つめるひとときに」

写真展は、2月15日まで。足助病院内の玄関ホールと東側エレベーターホールにて開催しています。
ところで、佐伯朋美さんは、1昨年春、東京から三河山間地に移住した写真家。私の焼き菓子を召し上がってくださったのがきっかけで、交流が始まりました。その彼女が撮ってくれた写真で構成したパンフがこちら。昨年末、できあがりました。
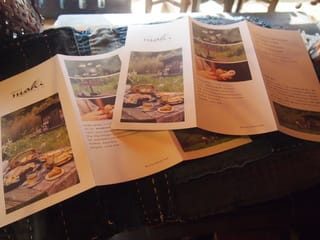
デザインとコーディネートは、稲武出身のデザイナー松井香澄さん。二人が協力して、わたしにはもったいないような素敵なパンフを作ってくれました。イベントや講習会の折にお配りいたします。
なお、佐伯さんは、ヨガのインストラクターでもあります。自らを「呼吸の写真家」と名付けるのは、呼吸をことのほか大事にするヨガを深くご存じだからこそ。息遣いまで撮りたいという思いが込められているようにおもいます。フリーのカメラマンとして、記念日や家族写真、大事な友達との思い出のための写真などの撮影もひきうけてくれます。気軽にご相談ください。連絡は、05035881011 kokyu.photo@gmail.com まで。


































































































































