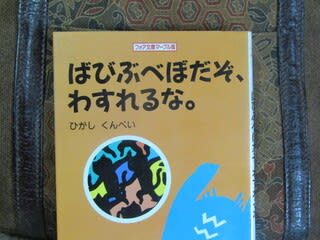7,8年ほど前、私のパンと焼き菓子の会に参加した方から、はじめて化学物質過敏症の実体験の話をお聞きしました。
彼女は、合成洗剤や柔軟剤を多量に使っていて、ある日突然、体調不良となり、まともに生活のできない状態になったといいます。でも、何が原因なのかまったくわからず、あれこれ調べてみてようやく病の原因が合成洗剤や柔軟剤にあることを知ったのだそうです。
発症するまで、彼女は洗剤や柔軟剤そのほか合成香料の入った商品につけられた匂いが物足りず、どんどんきつい匂いのするものを探すようになり、行きついたのはすべてアメリカ製品だったといいます。
原因を突き止めた彼女は、洗剤や柔軟剤のみならず、消臭剤そのほか類似の商品をすべて廃棄し、洗剤はシャボン玉石鹸の製品に替えました。「変えた途端、家族みんなに味覚がもどったのです」つまり、知らないうちに味覚も鈍感になっていたらしいのです。
その会は、自然食品店の店内で開かれたものでしたが、件の参加者は、自分が化学物質過敏症とわかってからずっとその店の顧客となり、食生活にも気を配るようになりました。そして家族全員が健康になったとのこと。
私自身は、ずいぶん前に石鹸洗剤に切り替え、柔軟剤は面倒ということもあって一度も使ったことがなく、消臭剤もたぶんほぼ買ったことがありません。でもはっきりと体に害が生じるからとは思っておらず、環境への負荷を気にしていただけなのですが、この話を聞いて、これはかなりたいへんなことがおきているぞ、と危惧を持ちました。

この本「マイクロカプセル香害」は、200ページほどの変形の新書判なのですが、半分は香害被害者からとったアンケート結果を紹介しています。その内容は上述の、私が出会った人以上のひどさで、唖然とするばかり。
「ある瞬間から、すべての合成洗剤が使えなくなりました。現在も数十メートル先の公園からの柔軟剤臭で、家の中でさえ苦しい。まっすぐ歩行できず、呂律が回らなくなり、計算や文章や言葉の解読できなくなり、感情的になり家族に当たり散らしたこともありました」
「発症後は、全く別の体になったというか、普通の暮らしができない。香料で倒れます。筋肉硬直です。・・・全身に症状が50種類以上出ました。大量の鼻血が出たときは、ものすごく不安でした」
「夫や実家や義理の両親からの理解が得られず、夫婦喧嘩(過敏な私にうんざりした夫から離婚届を突き付けられた)が増えています」
「医者からは原因不明の「腸閉塞」の診断。ただし、胃腸の検査では何ら問題なしと。・・・症状は、喉のかすれ、痛み、めまい、鼻水、頭痛、胃腸の不調が月日を重ねるごとにひどくなっています」
「病気を公表してからママ友だったと思ってた人たちはだんだんと離れていきました。・・・(子供は)一緒に遊んでくれるお友達もほぼいないので、子どもはいつも「死にたい、もっと早く生まれていたらこんな病気にはならなかった」と漏らしています」
小学生の子供から老人まで、発症の年齢はまちまち。それぞれ多種類の症状を抱えて不自由を囲っています。そして皆一様に周囲の理解が得られないことでさらなる苦痛を強いられています。
ここ数年前からとみに増えてきた柔軟剤のテレビCM 。きれいな若い女性が海辺で立っているとそこに花びらがひらひらと散り、若いハンサムな男性が引き寄せられる、という映像もあったのではなかったかな。あの匂い、かなり強烈だと私は思うのですが、「いい匂い」と思うように、もう鼻が慣らされているのだろうと思います。
柔軟剤も合成洗剤も消臭剤もみんな石油製品。香りを長持ちさせるためにマイクロカプセルなるものに香りの成分を閉じ込め、空中に飛散するようしかけてあるのだそう。そのカプセルの壁に使われている化学物質に、イソシアネートという「ごく希薄な吸入でもアレルギー性喘息や中枢神経系・心臓血管系の症状を引き起こす毒性化合物」があります。
このイソシアネート、80年代に農薬の効果を持続させるために開発されたマイクロカプセルの中からこの毒物が生じたことがあったらしく、被害を訴える人がいたそうなのですが、確定的な証拠がないことを理由に、そのままに。ただし今は、もしかしたら危険性を知った消費者の声に製造会社が敏感に反応して、ほかの物質に替えている可能性もあるかもしれないとのことです。でもだからといって、危険性がなくなったわけではありません。
農薬といい、こうした化学合成剤といい、日本は先進国の中ではかなり規制が緩いこともかかれています。
嗅覚というのは、五感の中でもっとも原始的な感覚だと言われています。味覚や聴覚、視覚が現代人はかなり衰えていますが、そこにもってきて、さらに嗅覚までだめになったら、身を守ることができなくなってしまう。土をいじることから遠ざかっているので、触覚も駄目になっていそう。
私の友人たちのなかにも、仕事先で支給された制服の匂いに耐えられなくて仕事を続けられなくなった人や、整髪料などの香料の匂いに耐えられなくて頭痛に悩んだといった経験を持つ人がけっこういます。この本は表紙に、「緊急出版」とあります。さらに「明日、あたらしいマスクが必要になる だれか、助けろ あの子をいますぐ」とも書かれています。
過敏症になった人には、毒ガス用のマスクでも付けないと、つらくて生きていられないほどの事態となっている現実を、多くの人に知ってほしいものです。