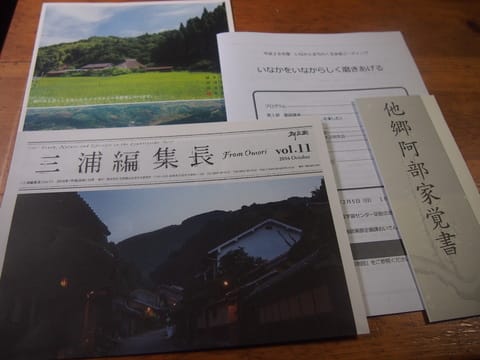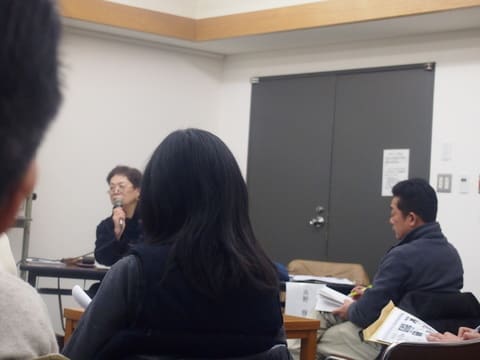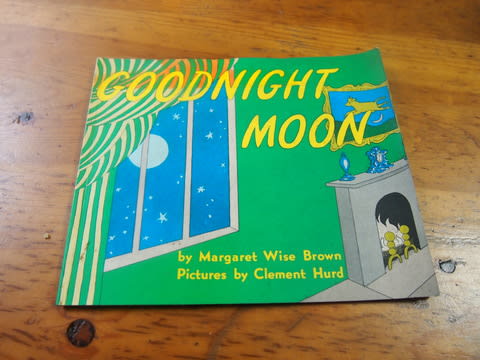またまた告知が遅くなりました。久々のイベント出店のお知らせです。
あした、21日火曜日からはじまる、ヘルシーメイト岡崎本社店の10%セールに、販促のための出店をいたします。セールはあしたから26日日曜日まで。わたしは、セール初日の明日出店します。

お持ちするのは、とっても多種類。こんなにいろいろ作ったのは久しぶりです。
まず、穀物クッキー2種類、ほうろく屋の菜種油を使った、穀物いろいろビスケット。デユラム小麦セモリナ入りの、シンプルなクラッカー、低温焼きしたブルーチーズクッキーもそろえました。おからのガトーショコラ、黒ビールケーキも作りました。
写真は、正式に発売するのは明日がはじめてになる、クリームパン。卵、乳製品不使用で、豆乳とアーモンドパウダー、白玉粉などで作ったカスタードクリームを入れました。これまで、あまり作ってこなかったやわらかめの、ちょっと甘いパンに、この頃製造意欲がわいています。この冬、いくつか試作しましたが、このクリームパンが、その第一号。三日月形のパンの上には、甜菜糖や玄米粉で作った、これまた卵もバターも使っていないクランブルを振りかけました。今回はちょっと水気が多過ぎたので、固まって載っていますが、これもけっこうおいしい。

ほかにもパンは、全くこねずにつくった、玄米ご飯パン、甘いアズキのパン、ライ麦パンをもっていきます。スコーンは、旬のリンゴで作ったジャムをはさんだものと、黒糖&くるみ。いずれも数に限りがあるので、お早めにお越しください。明日は、ほぼ一日店頭に立っています。
あした、21日火曜日からはじまる、ヘルシーメイト岡崎本社店の10%セールに、販促のための出店をいたします。セールはあしたから26日日曜日まで。わたしは、セール初日の明日出店します。

お持ちするのは、とっても多種類。こんなにいろいろ作ったのは久しぶりです。
まず、穀物クッキー2種類、ほうろく屋の菜種油を使った、穀物いろいろビスケット。デユラム小麦セモリナ入りの、シンプルなクラッカー、低温焼きしたブルーチーズクッキーもそろえました。おからのガトーショコラ、黒ビールケーキも作りました。
写真は、正式に発売するのは明日がはじめてになる、クリームパン。卵、乳製品不使用で、豆乳とアーモンドパウダー、白玉粉などで作ったカスタードクリームを入れました。これまで、あまり作ってこなかったやわらかめの、ちょっと甘いパンに、この頃製造意欲がわいています。この冬、いくつか試作しましたが、このクリームパンが、その第一号。三日月形のパンの上には、甜菜糖や玄米粉で作った、これまた卵もバターも使っていないクランブルを振りかけました。今回はちょっと水気が多過ぎたので、固まって載っていますが、これもけっこうおいしい。

ほかにもパンは、全くこねずにつくった、玄米ご飯パン、甘いアズキのパン、ライ麦パンをもっていきます。スコーンは、旬のリンゴで作ったジャムをはさんだものと、黒糖&くるみ。いずれも数に限りがあるので、お早めにお越しください。明日は、ほぼ一日店頭に立っています。