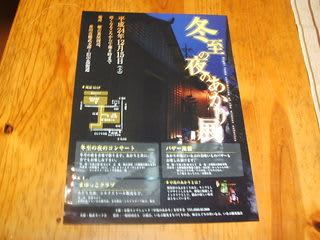旧宝飯郡一宮町・現豊川市に住んでいる知人のところに、古いもみすり機とストーブ用の薪をもらいにいきました。稲武からは、国道257号線を通って新城市に出て約1時間半の道のりです。
設楽町の中心地田口を越して清崎に出る手前に、湧き水が汲める場所があります。交通安全の水、と書いてあります。こういう場所は、この辺りにけっこうあります。

旧鳳来町辺りの風景。稲武に比べると山が迫っています。標高は低いので、まだ紅葉がきれい。

新城市の市街地から豊川を渡り、対岸を走りました。国道は車が多いので苦手。この道なら気楽に走れます。
知人の家は農村地帯のなかにあるのですが、その一角にできたイタリアンレストランに連れて行ってもらいました。

上はフィットチーネ、下は、名前を忘れましたがとても広い巾のパスタ。どちらも自家製のパスタです。こんな田舎でおいしいパスタが食べられるなんて、おもわなかった。お店の名前は、「ジョカーレ」です。

近くにある大公孫樹。小学校の跡地にあります。珍しい形の公孫樹だというので、最近、近在で有名になったそうです。

一般に、公孫樹は上にすっと伸びて箒のような姿をしていますが、この木は、てっぺんが平たくて横に広がっています。

ずっと昔、雷がこの木に落ちたせいで、枝葉が上に伸びずに横に広がった、と言い伝えられているのだとか。

大きな木は、見飽きません。

木の下に、こんな奇妙な造形物がありました。コンクリート製なのですが、背中の辺りが割れています。中を見ると丸太がのぞいています。
いま、60代70代になる人が小学生だった頃から、ここにあったとか。間延びした愛嬌のある顔です。恐竜かな、とおもいましたが、カメレオンかも。

遠くに見える高い山は、本宮山です。あす1日・土曜日は、この大公孫樹の下でお祭りが行われ、近隣の農家の人たちが持ち寄った野菜やたべものがいろいろ並ぶそうです。

ところで、古いもみすり機は、最近農業をはじめた友人のところにもらわれていきます。何年も使っていないので、動くかどうか心配です。役に立つといいのですが。
設楽町の中心地田口を越して清崎に出る手前に、湧き水が汲める場所があります。交通安全の水、と書いてあります。こういう場所は、この辺りにけっこうあります。

旧鳳来町辺りの風景。稲武に比べると山が迫っています。標高は低いので、まだ紅葉がきれい。

新城市の市街地から豊川を渡り、対岸を走りました。国道は車が多いので苦手。この道なら気楽に走れます。
知人の家は農村地帯のなかにあるのですが、その一角にできたイタリアンレストランに連れて行ってもらいました。

上はフィットチーネ、下は、名前を忘れましたがとても広い巾のパスタ。どちらも自家製のパスタです。こんな田舎でおいしいパスタが食べられるなんて、おもわなかった。お店の名前は、「ジョカーレ」です。

近くにある大公孫樹。小学校の跡地にあります。珍しい形の公孫樹だというので、最近、近在で有名になったそうです。

一般に、公孫樹は上にすっと伸びて箒のような姿をしていますが、この木は、てっぺんが平たくて横に広がっています。

ずっと昔、雷がこの木に落ちたせいで、枝葉が上に伸びずに横に広がった、と言い伝えられているのだとか。

大きな木は、見飽きません。

木の下に、こんな奇妙な造形物がありました。コンクリート製なのですが、背中の辺りが割れています。中を見ると丸太がのぞいています。
いま、60代70代になる人が小学生だった頃から、ここにあったとか。間延びした愛嬌のある顔です。恐竜かな、とおもいましたが、カメレオンかも。

遠くに見える高い山は、本宮山です。あす1日・土曜日は、この大公孫樹の下でお祭りが行われ、近隣の農家の人たちが持ち寄った野菜やたべものがいろいろ並ぶそうです。

ところで、古いもみすり機は、最近農業をはじめた友人のところにもらわれていきます。何年も使っていないので、動くかどうか心配です。役に立つといいのですが。