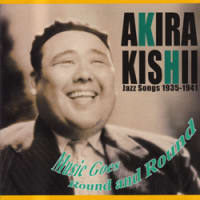十月革命10周年記念作品『聖ペテルブルクの最後』(1927)が美しい作品だとするなら、その理由は、革命についての物語が、いままさに「革命をしながら」撮られたためであろう。本作はプドフキンらの製作陣にとって、革命をしている現在進行形のセルフ・ポートレイトなのである。
しかし同時にこの無声映画は、わずか20年後のアメリカで吹き荒れることになる「赤狩り」をも、革命の前段階として普遍化しているのだ。それは「たれ込み」「情報提供」「当局に仲間の名前を売る」という行為を語る際の恐るべきタッチとなって現れる。
田舎で食いつめた一青年が、帝政末期の都サンクトペテルブルクに出稼ぎにきたものの、居場所がなく途方に暮れた末、ほんの腹立ちまぎれに、同じ村出身のある労働者が工場ストライキの扇動者を務めている事実を、当局にたれ込んでしまう。
アパートメントの中庭で1つの家族をたくまずして破滅に追いやったばかりの青年は、自分のしでかしたことの重大さを受け止めきれぬまま、そして当局の男からもらった駄賃を半ば放心状態で掴んだまま、天に救いを求めるかのように頭上を見上げることしかできない。すると、聳え立つアパートメントの窓という窓から、物音ひとつしない、だが明らかに激しい軽蔑に満ちた視線が、青年めがけ一斉に突き刺さる。
アパートメントの無数の窓は、引きの仰角で撮られるばかりで、投げ下ろされる視線の主たちの姿は、豆粒の大きさに過ぎず、そのディテールは確かめようもない。しかしこれほど苛酷にして美しい、革命の前段階を直裁的に示した映像は、そうあるものではないように思える。
プドフキン映画祭は、2月7日(土)までアテネ・フランセ文化センターで開催中
http://www.athenee.net/culturalcenter/
しかし同時にこの無声映画は、わずか20年後のアメリカで吹き荒れることになる「赤狩り」をも、革命の前段階として普遍化しているのだ。それは「たれ込み」「情報提供」「当局に仲間の名前を売る」という行為を語る際の恐るべきタッチとなって現れる。
田舎で食いつめた一青年が、帝政末期の都サンクトペテルブルクに出稼ぎにきたものの、居場所がなく途方に暮れた末、ほんの腹立ちまぎれに、同じ村出身のある労働者が工場ストライキの扇動者を務めている事実を、当局にたれ込んでしまう。
アパートメントの中庭で1つの家族をたくまずして破滅に追いやったばかりの青年は、自分のしでかしたことの重大さを受け止めきれぬまま、そして当局の男からもらった駄賃を半ば放心状態で掴んだまま、天に救いを求めるかのように頭上を見上げることしかできない。すると、聳え立つアパートメントの窓という窓から、物音ひとつしない、だが明らかに激しい軽蔑に満ちた視線が、青年めがけ一斉に突き刺さる。
アパートメントの無数の窓は、引きの仰角で撮られるばかりで、投げ下ろされる視線の主たちの姿は、豆粒の大きさに過ぎず、そのディテールは確かめようもない。しかしこれほど苛酷にして美しい、革命の前段階を直裁的に示した映像は、そうあるものではないように思える。
プドフキン映画祭は、2月7日(土)までアテネ・フランセ文化センターで開催中
http://www.athenee.net/culturalcenter/