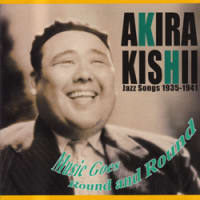初期レンフィルム(ソフキノ・レニングラード撮影所)の中核を担ったグリゴリー・コージンツェフとレオニード・トラウベルグのサイレント映画『新バビロン』(1929)を、小林弘人のピアノ伴奏付きで見る。
普仏戦争におけるナポレオン3世軍の敗北直後の1871年春に一時的に成立を見たパリ・コミューンに対し、ソビエト・ロシアの立場から明瞭にプロレタリア独裁の嚆矢として位置づけた作品である。威勢のいい開戦のかけ声と共にブルジョワジーのあいだで狂乱的な消費ブームが起き、パリ市内の百貨店「新バビロン」はバブル期の日本のように、着飾った女たちの物欲の揉み合いが日々繰り広げられる。
敗戦後は一転して、「新バビロン」の売り子であるヒロインのルイーズ(エレーナ・クジミナ)が毅然たる振る舞いで画面を引きしめはじめ、政府軍の敗残兵ジャン(ピョートル・ソボレフスキー)がやがて彼女の恋人となる。私たち観客は、この敗残兵がルイーズの後押しを受けてパリ・コミューンの運営に全面的に参画し、英雄的に命を散らせて、美しく愛と政治への讃歌を高らかに謳い上げたらどんなにか感動的な映画となるだろう、と夢想しながらスクリーンと向かい合う。
しかし、現実はまったくそうはならないだろう。
ルイーズと熱い抱擁を演じたまではいいが、ジャンはいっこうに目覚めず、結局は保身のためか、単に体制に飼い慣らされた田舎者なのか、ルイーズの引き留めもむなしく政府軍の隊列に復帰してしまう。そしてパリ・コミューンが瓦解し、逮捕されたルイーズが死刑を宣告されたとき、皮肉にも死刑囚の墓掘り要員として動員されるのがジャンなのである! なんたる愚弄、なんたる滑稽だろうか。私たち日本の観客は、溝口健二のあの悲痛なラストをもつ傑作『滝の白糸』(1933)の、女と男がたどる皮肉な運命の源流を、──あるいは、動乱に生き急ぎ、動乱のバリケードを駆け抜ける大島渚の傑作『太陽の墓場』(1960)の女と男の破れかぶれな夢想の源流を、ここに確かに見るのである。この運命の皮肉をまのあたりにして一時的に悲嘆に暮れるものの、やがて男を指さしてワハハ!と高笑いしてみせるエレーナ・クジミナの演技の強烈さに、ぐっと目を凝らそうではないか。
たとえばプドフキンの『母』(1926)なら、息子の犬死にを見たら最後、意を決して騎兵隊に立ちはだかる母(ヴェラ・バラノフスカヤ)の神々しい身体を写してみせるが、これより3年後のコージンツェフとトラウベルグは、愚劣さそのものに最後まで付き合ってみせたわけである。
トラウベルグといえば、オランダの映画評論家テオドール・ファン・ハウテンの『レオニード・トラウベルグと彼のフィルム:いつも予期せぬものが』(1989)の英書を20代半ばのころ、どこかで買い求めてきて「こういうもので勉強しなければ」とがんばって読み耽った思い出がある。現在のわが身はあるいはジャンのように、どこまでも覚醒せざる墓掘り兵となんら変わらずどうにもやりきれないが、少なくとも、矢面に立ったルイーズ(エレーナ・クジミナ)の毅然たる肉体の美しさだけは伝えなければと思う。
国立フィルムセンター(東京・京橋)にて、〈シネマの冒険 闇と音楽2012 ロシア・ソビエト無声映画選集〉開催
http://www.momat.go.jp/
普仏戦争におけるナポレオン3世軍の敗北直後の1871年春に一時的に成立を見たパリ・コミューンに対し、ソビエト・ロシアの立場から明瞭にプロレタリア独裁の嚆矢として位置づけた作品である。威勢のいい開戦のかけ声と共にブルジョワジーのあいだで狂乱的な消費ブームが起き、パリ市内の百貨店「新バビロン」はバブル期の日本のように、着飾った女たちの物欲の揉み合いが日々繰り広げられる。
敗戦後は一転して、「新バビロン」の売り子であるヒロインのルイーズ(エレーナ・クジミナ)が毅然たる振る舞いで画面を引きしめはじめ、政府軍の敗残兵ジャン(ピョートル・ソボレフスキー)がやがて彼女の恋人となる。私たち観客は、この敗残兵がルイーズの後押しを受けてパリ・コミューンの運営に全面的に参画し、英雄的に命を散らせて、美しく愛と政治への讃歌を高らかに謳い上げたらどんなにか感動的な映画となるだろう、と夢想しながらスクリーンと向かい合う。
しかし、現実はまったくそうはならないだろう。
ルイーズと熱い抱擁を演じたまではいいが、ジャンはいっこうに目覚めず、結局は保身のためか、単に体制に飼い慣らされた田舎者なのか、ルイーズの引き留めもむなしく政府軍の隊列に復帰してしまう。そしてパリ・コミューンが瓦解し、逮捕されたルイーズが死刑を宣告されたとき、皮肉にも死刑囚の墓掘り要員として動員されるのがジャンなのである! なんたる愚弄、なんたる滑稽だろうか。私たち日本の観客は、溝口健二のあの悲痛なラストをもつ傑作『滝の白糸』(1933)の、女と男がたどる皮肉な運命の源流を、──あるいは、動乱に生き急ぎ、動乱のバリケードを駆け抜ける大島渚の傑作『太陽の墓場』(1960)の女と男の破れかぶれな夢想の源流を、ここに確かに見るのである。この運命の皮肉をまのあたりにして一時的に悲嘆に暮れるものの、やがて男を指さしてワハハ!と高笑いしてみせるエレーナ・クジミナの演技の強烈さに、ぐっと目を凝らそうではないか。
たとえばプドフキンの『母』(1926)なら、息子の犬死にを見たら最後、意を決して騎兵隊に立ちはだかる母(ヴェラ・バラノフスカヤ)の神々しい身体を写してみせるが、これより3年後のコージンツェフとトラウベルグは、愚劣さそのものに最後まで付き合ってみせたわけである。
トラウベルグといえば、オランダの映画評論家テオドール・ファン・ハウテンの『レオニード・トラウベルグと彼のフィルム:いつも予期せぬものが』(1989)の英書を20代半ばのころ、どこかで買い求めてきて「こういうもので勉強しなければ」とがんばって読み耽った思い出がある。現在のわが身はあるいはジャンのように、どこまでも覚醒せざる墓掘り兵となんら変わらずどうにもやりきれないが、少なくとも、矢面に立ったルイーズ(エレーナ・クジミナ)の毅然たる肉体の美しさだけは伝えなければと思う。
国立フィルムセンター(東京・京橋)にて、〈シネマの冒険 闇と音楽2012 ロシア・ソビエト無声映画選集〉開催
http://www.momat.go.jp/