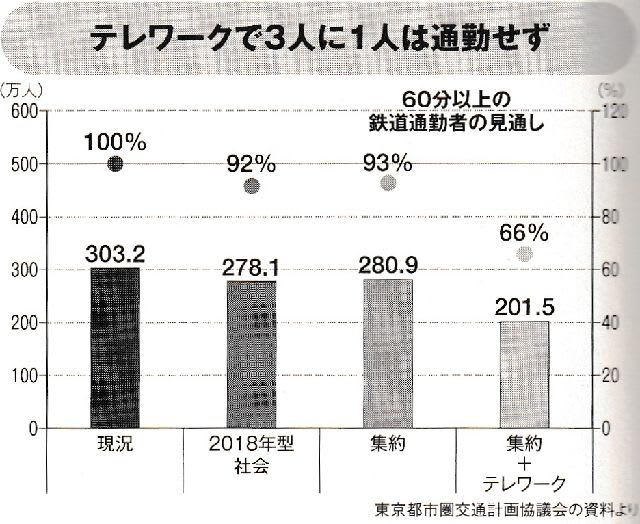🌸コロナ蔓延2020年(3)
⛳安倍晋三コロナ治療薬「アビガン」不承認問題答える
☆抗ウイルス薬の「アビガン」
*新型コロナの治療薬として承認を目指しましたが、実現しなかった
*安倍承認すると答えていたが承認出来なかった
*「アビガン」防衛省の自衛隊中央病院でも顕著な成果が出ていた
*妊娠中の女性が飲むと、障害がある赤ちゃんが生まれる恐れがあった
*ここで、広く使用することにたじろいでしまった
*ここで、広く使用することにたじろいでしまった
*そうした人に処方しなければいいだけの話なのだが
☆厚労省の局長は「アビガンを承認します」と話していた
☆厚労省の局長は「アビガンを承認します」と話していた
*その後、薬務課長が反対し覆った
*厚労省、私の考え方が甘い、という感じでした
☆薬事承認の実質的な権限を持っているのは薬務課長
*内閣人事局は幹部官僚700人の人事を握っている
*課長クラスは対象ではない
*官邸が何を言おうが、人事権がなければ、言うことは聞かない
☆薬務課長は、何故頑なだった理由
*薬害エイズ事件では、厚生省の官僚が罪に問われた
*当時の厚生省薬務局長は、事務系のキャリアで不起訴
*薬害エイズ事件では、厚生省の官僚が罪に問われた
*当時の厚生省薬務局長は、事務系のキャリアで不起訴
*有罪が確定したのは、薬務系の技官です
*局長がハンコを押して承認したのに薬務課長だけが有罪となった
*薬務系の官僚には不満でしょう
☆多くの薬務系の技官、その様な歴史の過程で
☆多くの薬務系の技官、その様な歴史の過程で
*「責任を取るのは私たち、私たちで決めさせてもらう」意識が強い
☆厚労省内もバラバラ
☆厚労省内もバラバラ
*医系技官、薬務系技官、キャリア(事務官)に分かれている
*医系やキャリアは次官までポストがあり、局長も多い
*医系やキャリアは次官までポストがあり、局長も多い
*薬務系技官は、課長か審議官止まり
*しかし、薬とワクチンを承認する権限を握っている
*組織が全体として円滑に回っていない
⛳安倍晋三病床削減での病床逼迫&医師会問題を答える
☆政府や自治体が国公立病院の削減
*削減を進めた背景には、競争相手を減らしたい医師会の意向があった
*医師会は「圧力に屈しない医師会」を掲げ病床を増やそうとせず
*国民に圧力をかけているのは、医師会側とも言える
☆医師の中にも医師会とは距離を置いている人もいた
☆医師の中にも医師会とは距離を置いている人もいた
*医師会は、機能しているとは言えない
⛳安倍晋三リスクを取った一斉休校決断答える
☆学校の休校も、文部科学省は自治体の判断に委ねていた
⛳安倍晋三リスクを取った一斉休校決断答える
☆学校の休校も、文部科学省は自治体の判断に委ねていた
*安倍さんが一斉休校を要請する考えを表明した
☆安倍首相が一斉休校を要請した背景
*当時は、子どもが重症化した症例は無かった
*しかし、喘息など基礎疾患を持っている児童生徒もいる
*小さな子どもが重症化による、国民的なショックは計り知れない
*パニックにつながっていく可能性もある
*人流&通学なくせば減少するので、休校にはそういう利点があった
☆子どもの教育権を奪うという指摘に関して
*人流&通学なくせば減少するので、休校にはそういう利点があった
☆子どもの教育権を奪うという指摘に関して
*教育を受ける権利と命、どっちが重要との考えた上での決断だった
*調整不足だったのは事実でしょうが、走りながら考えた
*やり過ぎだ、という批判は喜んで受けます
☆マスコミから、 メチャクチャなことをやっていると批判されたが
*国民に危機感を持ってもらう点でも、判断は正しかったと思っている
*その後の世論調査で、一斉休校は評価が高かった
⛳安倍晋三、コロナ問題を国民説明機会少ないとの批判に答える
☆緊急事態宣言の発表や解除、1時間はかけて丁寧にやった
☆秘書官や事務方は、基本的に私が記者会見をする以上
☆秘書官や事務方は、基本的に私が記者会見をする以上
*新しい「玉」(具体的施策)を探さなければならないと必死になる
*新たな発信や対策、 ニュースがなければ、やるべきではない進言する
☆首相の記者会見は鬼門で、大失敗になる危険性が常にある
☆首相の記者会見は鬼門で、大失敗になる危険性が常にある
*秘書官たちは、非常に正確性を重んじる
*私の答えの中には、必ずしも正しくないものもあるわけです
*それをできるだけ少なくしたいから
*それをできるだけ少なくしたいから
*記者会見は少ない方がいいと彼らは考えていた
☆安倍さんプロンプターを使って原稿を読んでいると批判されたが
*海外の首脳だって皆がそうです
*海外の首脳は質問を受け付けず、 発信するだけのケースも多い
*新聞が記者会見のやり方まで非難するから
*インターネットで発信と考えましたが周辺から諫められた
(敬称略)
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『安倍晋三回顧録』
⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載
⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介
☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で
⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください
⛳出典、『安倍晋三回顧録』


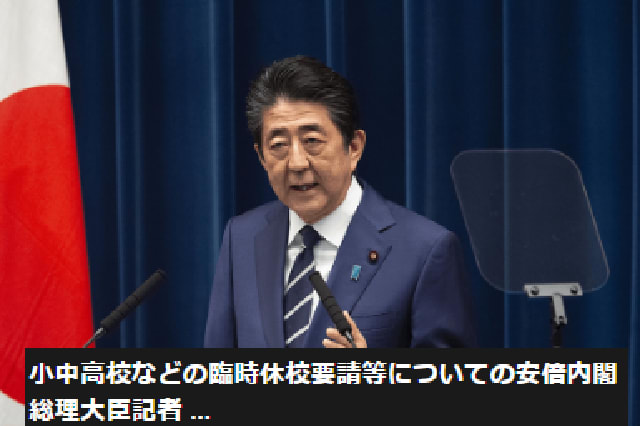
薬務課長・病床逼迫・一斉休校他
(ネットより画像引用)