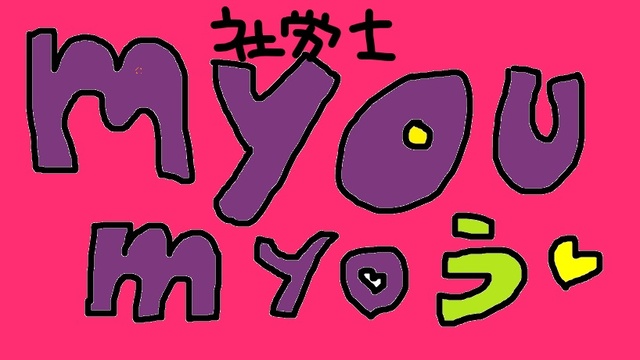危険ドラッグ法案が成立する見通しとのことです。危険ドラッグとはかつては脱法ドラッグと呼んでいたものですが、そもそも危険ドラッグとはいかなるものなのでしょうか?
自殺やメンタルヘルス、ネット・コミュニケーションの分野で執筆活動を行うフリーライターの渋井哲也さんが、規制するだけでは足りないとして、取り組みについて書かれています。
危険ドラッグとは、法律の規制を逃れるために生み出された新型の薬物である。世の中には様々な薬物が存在し、規制の方法は薬物規制の条件が化学式によって定められているため、薬物の知識を持った人間が、ほんの少し化学式を変化させた薬物を生み出してしまえば、どれほど危険な効果をもたらすものであっても、法律で取り締まることはできない。行政は次々と危険ドラッグを取り締まる規定を重ねているが、薬物を作り出す側はそれを上回るペースで新たな危険ドラッグを生み出してしまい、いたちごっこのような状態に陥っている、ということです。
新種の危険ドラッグが市場に出回って約1か月ほどで規制されてしまえば、皮肉なことだが果たしてその薬物がどのような効果があったのか検証できず、今後の方針に生かせない。市場に出回る危険ドラッグが、無害なものなのか、自傷・他害を引き起こし最悪の場合死へと至る危険な薬物であるかは使ってみない限りわからない。覚せい剤や大麻よりも危険な面があるともいえる、として
名称を変えただけでは本当に伝えるべき相手には伝わらない。今の若者たちの多くは、不良的なものにあこがれて危険ドラッグに手を出すわけではない。かっこいいからとか、ちょっと危ないことをしてみようという気持ちで薬に手を染めているのではないと言います。
危険ドラッグには、人間の生きづらさといった問題がかかわっているため短期間に解決策を見つけ出すことはできない。危険ドラッグは奇行や暴力、自傷行為を引き起こすだけでなく、依存性が強い場合もあるので、規制に引っ掛かって手に入らなかった人が人生に絶望して自殺してしまうということも起きているということです。
渋井さんは、危険ドラッグ問題の専門家を増やし、専門家同士をつなぐネットワークを構築し、政府主導で危険ドラッグ総合研究所のようなものを設立してほしいと言っています。
青少年の心のケアという点では、児童相談所の大規模拡充も欠かせない。解決の倫理を作り出すことができても活動の担い手がいなければどうしようもない。現在児相の職員一人あたりが受け持つケースは100にも及び、職員を増員するだけでも問題を相当改善することが可能であるとのことです。
危険ドラッグの話に児童相談所が登場することを不思議に思う人もいれば、よい着眼点と思う人もいるでしょう。児童という名称から、小学生かせいぜい中学生ぐらいの子どもを思い浮かべる人がいるかもしれませんが、児童福祉法では、18歳未満が児童なのです。児童に関するありとあらゆる問題が持ち込まれるのが児相なのです。
かつて児童養護施設に勤務していたときには、感情的な反感があったりもしましたが、里親として児相とかかわるうちにその仕事の大変さが見えてきました。
危険ドラッグ問題は、規制したり成分分析に取り組むといった対処療法はもちろん必要ですが、「社会の生きづらさ」という根本問題に取り組まなければ真の撲滅は目指せないと思います。一児の母として、このような観点から社会問題に取り組む人の存在は頼もしいかぎりです。
渋井さん、今後のご活躍を応援していますよ!