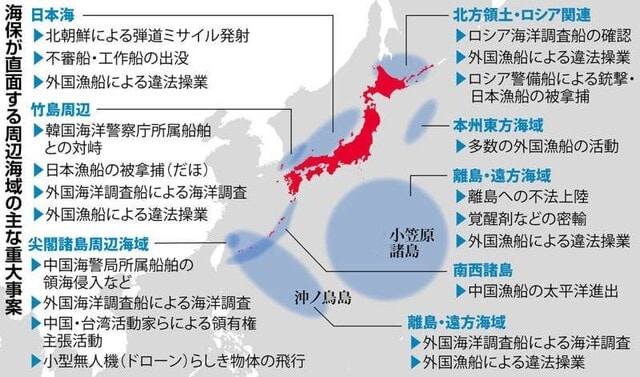JLPGAツアー2022シーズン第17戦『アース・モンダミンカップ』(賞金総額3億円、優勝賞金5400万円)大会最終日が6月26日、千葉県袖ヶ浦市・カメリアヒルズカントリークラブ(6639ヤード/パー72)で行われ、プロ8年目の木村彩子が通算4アンダーでツアー初優勝を飾った。この日は6打差を追いかけ、9位タイからスタート。大混戦の展開ながら、4バーディー、1ボギーの69をマークした。1打差の通算3アンダー、2位タイは西村優菜、ささきしょうこ。
(天候:晴れ 気温:30.9℃ 風速:4.1m/s)
《グリーン=スティンプ:12 1/2フィート コンパクション:24.5mm》
きょうは、絶対に逃さない。木村彩子の表情は、そう大きく書いてあるようだった。首位の4アンダーでホールアウト。ただし、プレー中の選手が9人いた。後続の3組を待ちながら、プレーオフへ備え万全の準備を整える。
初のプレーオフ経験は昨年のスタンレーレディス。「あの時は、ホールアウトして2時間ぐらい待ったかなぁ」という。結局、PO進出は果たしたものの、あっさりと敗れた経験を忘れない。それだけに、「ここで負けたら、一生勝てない。そのぐらいの覚悟で、気合を入れていた」そうだ。
しかし、1打差が効いた。ついにドリームステージが訪れる。「夢みたい。まさか、まさか-です」と、優勝が決定すると少し拍子抜けした表情を浮かべる。ただし、「これからも勝てるうちにたくさん勝ちたい。息の長い選手でいられるように、もっと精進します」。
プロ8年目の初V。「いつでも勝てるよ、と周囲の方はいってくださったけど、ここまでかかった」と、しみじみと語った。この日は首位から6打差を追い、9位タイから駆け上がる。「きのう、後半で40を叩いた。特に最終18番がボギー。本当に悔しかった。まだ、優勝のチャンスはある。トータルで5アンダーを目標にした」。
この日も風が強い。コースセッティングが難しい。それほどハイスコアの勝負にはならない、という予想を立てた。自身の特性を存分に生かせる条件が揃う。
指導を受ける南秀樹コーチからは、「第1打を死ぬ気でフェアウエイキープ。パー5のレイアップも、死ぬ気で-」とゲキが飛んだ。飛距離よりも精度。第1日=14/14の再現はならなかったものの、12/14のフェアウエイキープ率はさすがだった。また、3番ではドライビングディスタンスで262ヤードを記録するなど、気迫がボールへ乗り移る。
上位は大混戦。ターニングポイントは11番だった。グリーン手前のエッジから、25ヤードの第3打をPWでチップインバーディー。こんな前日譚がある。「第2日の中継をみていた南コーチから、グリーン手前からのランニングアプローチをやっておいたほうがいい。そんなアドバイスがあった。10番でボギーの後、11番もあまり雰囲気がよくない。でも、あの一打-。しかも、最後のひと転がりがカップへ入った」と振り返る。
これまた準備を怠らず、精進を続けてきた成果。優勝会見では、時おり遠くを見るような目をすることがあった。「18歳で最初の最終プロテスト受験で失敗。もう、ショックでクラブを握る気にもなれなかった。ずっと家にいたわけですけど、母からお金は無限ではない。せめて自分の買いたいものぐらいは稼いだら、といわれて都内の中古クラブショップでアルバイトをはじめた。時給は当時1000円ぐらいです」とひと息つく。
そして、「私、実家は千葉ですけど、東京は時給が高いから選びました。ちょっとレジでバーコードをピッとやる、あれがしたかったから。だけど、楽しかったです。そういえば、はやくプロになってツアーへ出場すればたくさん稼げるよ-といわれました」。
今大会の優勝賞金は5400万円だ。余談だが、わずか4日間で従来の獲得金額の約半分を稼いでしまった。生涯獲得賞金が節目の1億円を突破。パー5の14番、第3打も大いに印象に残った。残り103ヤードをピンへピタリ。オッケーバーディーで単独首位に立って、結果からいえば、優勝を決めたワンショットになった。

「(身長が)小さくても、西村優菜さんのように勝てることを証明できた。飛距離ではないと思うけど、最近の大会は全体の距離が長くなっている。やっぱり、飛距離が出る選手がうらやましい。(155センチの)私、165センチになりたかった」と笑いながら話した。
百花繚乱、プレーの個性も人それぞれ違う。準備を徹底し、特性を最大限に発揮。サクセスストーリーが耳に心地よかった。
以上、日本女子プロゴルフ協会
ささきしょうこが、トップを牽引していたが、伏兵の木村彩子選手にやられた感じです。
このトーナメント初日だけ、快晴無風でコンディションはばっちりでしたが、2日目から強風が吹き、厳しいものになりました。
最終日の今日は、スコアを落とす中、69の好スコアでラウンドできた木村選手が大金5400万円稼ぎました。
私は山下みゆうを応援していたのですが、初日8アンダーでスタートは良かったのですが、2日目以降強風に負けてしまいました。
観たことある?
参政党のユーチューブ、本当に面白い!!感動ものです。