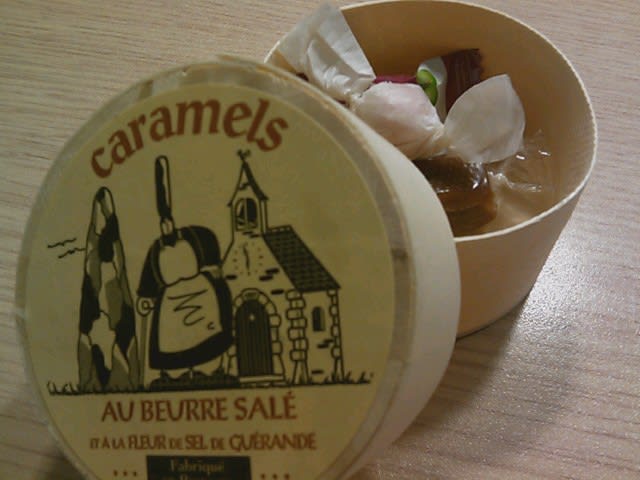本名Alessandro Filipepi(アレッサンドロ・フィリペピ)、
俗名Botticelli(ボッティチェッリ)。
2010年は1510年5月17日にフィレンツェで永眠した
彼の没後500年に当たります。
しかし、悲しいことにフィレンツェでは未だ何も企画されていません。
2009年11月23日にオープニングとなる
没後500年を記念する展示会は
ボッティチェッリが活躍し、骨をうずめたフィレンツェではなく
フランクフルトのStaedel Museumで開催されます。
このため11月初めからフィレンツェにあるいくつかの作品は
2010年2月末までフランクフルトに貸し出されることになります。
ウフィツィ美術館に所蔵される
かの有名な「ヴィーナス誕生」や「春」は
門外不出に近いお宝なので
懇願されても
そう簡単にウフィツィから離れることはありませんが、
2年にわたって続けられてきた交渉の結果、
ボッティチェッリの絵画作品5点と
周辺画家の作品がアルプスを越えます。
今回貸し出されるのはウフィツィ美術館所蔵の
上記2点の間に飾られている
「ケンタウルスを調教するミネルヴァ(パラス)」、
同じくウフィツィ所蔵のフレスコ画「受胎告知」、
アカデミア美術館から「海の聖母」、
パラティーナ美術館から
「紳士の肖像画」と「聖母子と洗礼者ヨハネ」。
絵画作品以外にもウフィツィ版画デッサンコレクションからは
ボッティチェッリの「洗礼者ヨハネ」、
ほかに弟子のフィリッピーノ・リッピのデッサン画、
ボッティチェッリ派の作品1点、
そしてフランチェスコ・グラナッチのデッサン1点。
バルジェッロ美術館からは
パッツィ家の陰謀のメダルなどが出展されます。
フィレンツェでは2004年にストロッツィ宮殿で
ボッティチェッリ展が開催されていることから
短いスパンで同じテーマでの展覧会の企画はしないようです。
それに代わってボッティチェッリも中心的役回りを担っていた
ルネッサンス期の人文主義にスポットを当てた
展覧会が予定されているようです。
これに合わせて
これまでフィレンツェで展示されたことのない
ボッティチェッリの作品が海外からやってくるといわれていますが、
極秘情報とされて未だ公開されていません。
フィレンツェとボッティチェッリを代表する大作は残るといっても、
11月以降2月までにフィレンツェを訪れる予定の方は
鑑賞できない作品もありますので、お気をつけください。