
―表象の森― マルクスの疎外論 -承前-
<A thinking reed> 吉本隆明「カール・マルクス」光文社文庫より
・マルクスの全体系を辿ろうとする者は、たれも、彼の思想から三つの旅程を見つけることができるはずである。
ひとつは、宗教から法、国家へと流れくだる道であり、
もうひとつは、当時の市民社会の構造を解明するカギとしての経済学であり、
さらに、第三には、彼みずからの形成した<自然>哲学の道である。
マルクスが、青年期につくりあげた三つの道は、やがてそのなかの一つの道を太くさせ、そのほかを間道に転化させる。これを彼自身の体験が強いたものとみるかぎり、たれも、それに文句をつけることはできない。-略- 現在、みることができる資料によるかぎりは、「ヘーゲル法哲学批判」以後に、宗教、法、国家、いいかえれば、相対的には幻想性にたいする考察はマルクスからあとを絶っている。また、彼の<自然>哲学は、ただ経済学的なカテゴリーのなかでだけ、「資本論」にいたるまでの道をたもっているにすぎない。
・政治的国家というものは、<家族>という人間の自然的な基礎と、<市民社会>という人工的な基礎が、自己自身を<国家>にまで疎外するものであるにもかかわらず、ヘーゲルは、逆に、現実的理念によって国家が作られたように考えているというのが、マルクスの根本的ヘーゲル批判であった。
たとえば、古代の国家では、政治的な国家がすべてであり、人間の現実的な社会は、すみずみまで政治的な国家の手足のように存在している。しかし、近代的な国家では、政治的な国家と非政治多岐な国家とが<法>によって調節されて二重に存在している。政治的国家は、非政治的な国家の具体性である市民社会を内容としながら、それから疎外された形式上の共同性として存在する。
だから国家と、家族や市民社会とはヘーゲルのいうような矛盾のない存在ではありえない。国家は、家族や市民社会自体の生活過程が表象されたものではなく、家族や市民社会が、自己から区別し分離する-<疎外>する-理念の生活過程である。
・人間と自然との相互規定としての<疎外>が、マルクスの自然哲学の根源としてあり、それが現実の市民社会に<表象>されるとき、<疎外された労働>から派生する現実的<疎外>の種々相があらわれる。
市民社会の<自己意識>-いいかえれば共同意識-は、あたかも、共同性の意識の<表象>として現実的国家を<疎外>する。ところで、市民社会の<自己意識>は、あたかも宗教として神という至上物を<疎外>するように、市民社会の至上の<自己意識>として政治的国家制度、政治的国家、法を<疎外>するのである。これを宗教、法、国家という歴史的な現存性への接近としてかんがえるとき、政治-哲-学の問題があらわれる。
・プロレタリアートという概念は、市民社会の経済的なカテゴリーとしての人間の基底として登場する。マルクスのプロレタリアートという概念が、現実のプロレタリアートそのものでないのは、経済的カテゴリーとしての人間が、全人間的存在でないのと同じであり、同じ度合においてである。
・<疎外>という概念は、マルクスによって、ある場合には、非幻想的なものから幻想性が抽出され、そのことによって非幻想的なものが反作用をうけるという意味で、またある場合には、人間の自然規定としてぬきさしならぬ不変の概念であり、したがって人間の自己自身にたいするまた他の人間にたいする不変の概念として、またある場合には、<労働>により対象物と<労働者>とのあいだに、したがってその対象物を私有する者とのあいだに、具体的におこる私的な階級の概念として使われているが、もちろん彼の思想にとって重要なのは、それがどのように使われていても、累層と連環によって他の概念におおわれているという点にあった。そこにマルクス思想の総体性が存在している。
彼の思想が、宗教・法・国家・市民社会・自然をつなぐ総体性として完結したとき、まだ、ほんとうの意味で社会の歴史的現存性のおそろしさを知らぬ青年であった。
なぜ、愚劣な社会が国家として現存し、たれにでもわかる愚劣な人物たちが牛耳っているこの社会は滅びないのか? なぜ、一見すると脆弱そうにみえるこの不合理な社会はこれほど強固なのか? マルクスが、こういう自問自答をほんとうの意味で強いられたのは、西欧のデモクラートの蜂起が挫折し、そのあおりをくらって解体した<共産主義者同盟>が内紛のうちに彼を締め出し、彼が貧困のさなかに公然と孤立したときである。ここで、マルクスの現実的な体験が、転向としてその思想に関与する。その意味は、マルクス自身がかんがえたよりも、おそらく重要であった。
<連句の世界-安東次男「風狂始末-芭蕉連句評釈」より>
「梅が香の巻」-21
たゞ居るまゝに肱わづらふ
江戸の左右むかひの亭主登られて 芭蕉
次男曰く、登ると云えば東国から上方へ、とくに江戸から京へ上ることだ。左右は消息、とかくの様子である。
其の人が江戸の土産話に興味を持つのか、「肱わづらふ」は向の亭主の旅疲れか、それとも、前句は「江戸の左右」を伝える口付か、一読しただけではわからない。
上五の作りにいささか無理があるようだが、普通に読めばこれは第一の場合だろう。「登られて」は「たゞ居るまゝに‥わづらふ」にいどんだ突っ掛けの興である。それなら「左右」も平穏息災と読める、と。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。















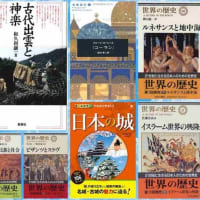




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます