
Information-Shihohkan Dace-Café-
-表象の森- フロイト=ラカン:「一の線」と「対象a」
――Memo:新宮一成・立木康介編「フロイト=ラカン」講談社より
「一の線」⇔「唯一特徴」
・「私を見ている目がどこかに在る」という、「私を見ている目」の在り場所は、
神の不在となった現代において、それはもはや「目」ではありえなく、「線」となった。
人は自分を「一人の人」として自覚する。
自覚と、「数えるという行為」とは切っても切れない関係にある。
・「一の線」-エディプスコンプレクスにおける「同一化」の問題。
人がエディプスコンプレクスを乗り越えて得る超自我の導きも、そもそも無媒介的に想定される人間の絆も、実は一つの「症状」である。
「症状」の地位は、突然、高められる。人は症状から逃げて生きるのではなく、症状を純化して生きるべきなのである。
「対象a」⇔「失われた対象」
・対象aに向けられる欲望が、欲望の原基である。
この対象に向けられている欲望は、己の欲望のようでありながら、実は他者から、自己の不在に対して向けられている欲望である。
・「人間の欲望は大文字の他者の欲望」なのである。
「一の線」と「対象a」とは、このように普遍の他者と個別の自己の間を繋ぐ。
その繋がりが実現しているとき、人は生きる喜びを感じる。
・対象aには「失われたもの」という性格が備わっている。
<歌詠みの世界-「清唱千首」塚本邦雄選より>
<秋-61>
朝まだき折れ伏しにけり夜もすがら露おきあかす撫子の花 藤原顕輔
左京大夫顕輔卿集、長承元(1132)年十二月、崇徳院内裏和歌題十五首、瞿麦(なでしこ)
邦雄曰く、終夜露の重みに耐え続けていた撫子が、朝になるのを待ちあえず折れてしまった。誇張ではあるが、あの昆虫の脚を思わせる撫子の茎は、あるいはと頷かせるものがある。この歌は河原撫子をよんだものであろう。表記は万葉以来、石竹・瞿麦その他混用され、秋の七草の一つに数えられている。常夏もその一種だが、これは夏季の代表花、と。
寝られめやわが身ふる枝の真萩原月と花との秋の夜すがら 下冷泉政為
碧玉集、秋、月前萩、侍従大納言家当座。
邦雄曰く、冷泉家の末裔、定家から既に三世紀近くを経て、歌も連歌風の彩りを加え、濃厚な美意識は眼を瞠らせる。初句切れの反語表現、懸詞の第二句、第三句に遙かに靡く萩原を描き、第四句は扇をかざして立ち上がったかの謳い文句、各句の入り乱れ、寄せては返すかの呼吸は間然するところがない。しかも何かが過剰で快い飽和感・倦怠感を覚えさせる、と。
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。















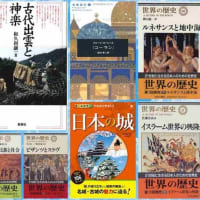




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます