
-表象の森- 書の近代の可能性・明治前後-12-
石川九楊編「書の宇宙-24」より
・河東碧梧桐「自詠句」二首
河東碧梧桐の自詠句二首を書いた二曲半双屏風。あるいは多くの人は、この作を変な寺、変わった作品の一言で済ませるかもしれない。だが、碧梧桐の書の姿と書体は、有季定型-無季自由律-短詩と表現を激しく変革しつづけた自らの俳句の句体と連動していた。俳句が変わらねばならぬように、書も変わらねばならなかったのだ。
規範として我々の目の前に登場してくる文字、その規範のひとつひとつを解体、再構成して、新たな文字への転生を試みている。和歌や俳句は深部で散らし書きと共鳴してるものとみえて、行頭・行末の高さを逐一変えた散らし書きの姿で出現している。

/雪散る青空の又た/此頃の空

/君を待したよ/櫻散る/中をあるく
―山頭火の一句― 行乞記再び -65-
3月3日、晴、春だ、行程わづかに1里、佐賀市、多久屋
もう野でも山でも、どこでも草をしいて一服するによいシーズンとなつた、そしてさういふ私の姿もまた風景の一点描としてふさはしいものになつた。
今日はあまり行乞しなかつた、留置の来信を受取つたら、もう何もしたくなくなつた、それほど私の心は友情によつてあたためられ、よわめられたのである。
或る友に、-どうやら本物の春が来たやうですね、お互にたつしやでうれしい事です、私は先日来ひきつづいての雪中行乞で一皮脱ぐことが出来ましたので、歩いても行乞しても気分がだいぶラクになれました、云々。
緑平老の手紙は私を泣かせた、涙なしには読みきれない温情があふれてゐる、私は友として緑平老其他の人々を持つてゐることを不思議とも有難すぎるとも思ふ。-略-
佐賀へは初めて来たが、市としては賑ふ方ぢやない、しかし第一印象は悪くなかつた。-略-
※句作なし、表題句は2月28日付記載の句
鍋島藩の居城であつた佐賀城は、明治7-1874-年、江藤新平らの佐賀の乱で大半を焼失した。

Photo/平成16年に復元成った本丸御殿

Photo/近頃では、毎年秋に市内を流れる嘉瀬川沿岸で開催される佐賀インターナショナルバルーンフェスタが、100万人規模の観客を動員するイベントになっている

Photo/バルーンフェスタの夜の係留風景











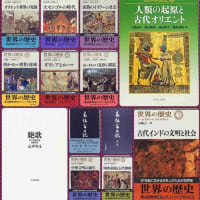
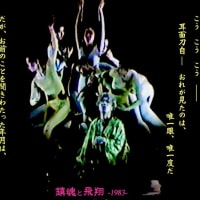
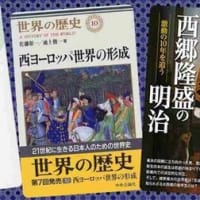
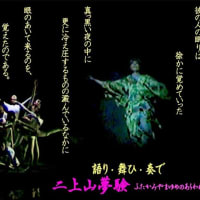
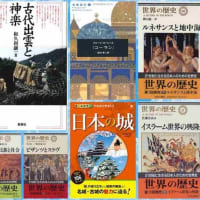
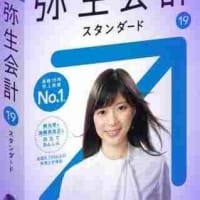
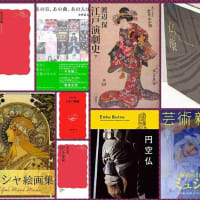
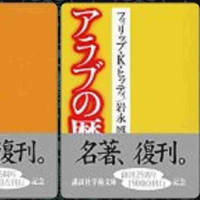
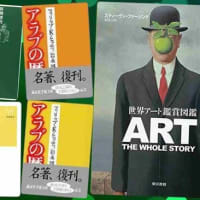
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます