<古今東西-書畫往還>

<人の欲望は他者の欲望である>
人間の欲望は、内部から自然と湧き上がってくるようなものではなく、常に他者からやってきて、いわば外側から人間を捉える。
だがこのことはけっして人間の主体的決定の余地を奪うものではない。人間の主体的決定は、まさに、この他者からやってくる欲望をいかに自分のものにするかということのうちに存するのだ。フロイトの発見した「無意識」とは、そのような主体的決定の過程において、いいかえれば、他者から受け取った欲望を自分のものに作り替えていく過程において、形成されるものにほかならない。
人が成長してゆくなかで、他者の欲望との出会いは繰り返される。人が幼少時から重ねてきたさまざまな決断や選択は、どれほどそれを自分自身で行ったと思っていても、実はもともと親や教師や友人といった他者から与えられたもの、あるいは伝達されたものにすぎない。だが、人はいつしかそれらの出会いを忘れてゆく。出会われた欲望がやがて忘れられてゆくのは、それが他のものに取り換えられるからである。一つのシニファン――というのも、他者の欲望は常に一つのシニファンのもとに出会われるだろうから――を他のもう一つのシニファンに取り換えること。ラカンは、フロイトの「抑圧」をこのようなシニファンの「置き換え」のメカニズムとして捉え直すのである。他者からやってきた欲望を抑圧することで、人はその上に自分の欲望を築いてゆくのであり、抑圧された他者の欲望は「無意識」を構成し、無意識において存続する。
このように、精神分析における「無意識」とは厳密には他者の欲望の場である。それは他者の止むことなき「語らいの場」である。先述のように、欲望はシニファンの連鎖によって運ばれるが、その連鎖が形作るものを名指すのに「語らい」ほど適した言葉はない。それゆえラカンは、「無意識は他者の語らいである」と繰り返す。主体が生まれる前から常にそこにおいて語らっていた「大文字の他者」は、この語らいが運んでいる欲望が主体のうちで抑圧され、無意識を構成するようになった後も、けっして語らうことをやめない。私たちに毎夜夢を紡がせるのは、まさにこの「他者の語らい」にほかならないのである。
――新宮一成・立木康介編「フロイト=ラカン」講談社 P43-45
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。

<人の欲望は他者の欲望である>
人間の欲望は、内部から自然と湧き上がってくるようなものではなく、常に他者からやってきて、いわば外側から人間を捉える。
だがこのことはけっして人間の主体的決定の余地を奪うものではない。人間の主体的決定は、まさに、この他者からやってくる欲望をいかに自分のものにするかということのうちに存するのだ。フロイトの発見した「無意識」とは、そのような主体的決定の過程において、いいかえれば、他者から受け取った欲望を自分のものに作り替えていく過程において、形成されるものにほかならない。
人が成長してゆくなかで、他者の欲望との出会いは繰り返される。人が幼少時から重ねてきたさまざまな決断や選択は、どれほどそれを自分自身で行ったと思っていても、実はもともと親や教師や友人といった他者から与えられたもの、あるいは伝達されたものにすぎない。だが、人はいつしかそれらの出会いを忘れてゆく。出会われた欲望がやがて忘れられてゆくのは、それが他のものに取り換えられるからである。一つのシニファン――というのも、他者の欲望は常に一つのシニファンのもとに出会われるだろうから――を他のもう一つのシニファンに取り換えること。ラカンは、フロイトの「抑圧」をこのようなシニファンの「置き換え」のメカニズムとして捉え直すのである。他者からやってきた欲望を抑圧することで、人はその上に自分の欲望を築いてゆくのであり、抑圧された他者の欲望は「無意識」を構成し、無意識において存続する。
このように、精神分析における「無意識」とは厳密には他者の欲望の場である。それは他者の止むことなき「語らいの場」である。先述のように、欲望はシニファンの連鎖によって運ばれるが、その連鎖が形作るものを名指すのに「語らい」ほど適した言葉はない。それゆえラカンは、「無意識は他者の語らいである」と繰り返す。主体が生まれる前から常にそこにおいて語らっていた「大文字の他者」は、この語らいが運んでいる欲望が主体のうちで抑圧され、無意識を構成するようになった後も、けっして語らうことをやめない。私たちに毎夜夢を紡がせるのは、まさにこの「他者の語らい」にほかならないのである。
――新宮一成・立木康介編「フロイト=ラカン」講談社 P43-45
⇒⇒⇒ この記事を読まれた方は此処をクリック。











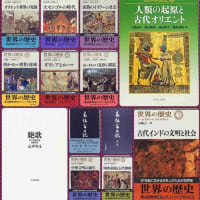
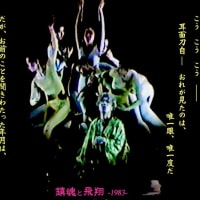
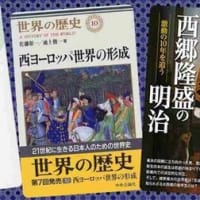
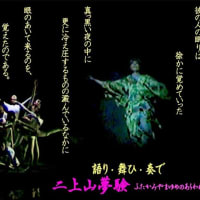
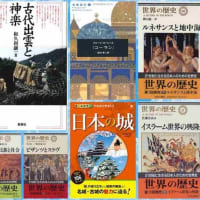
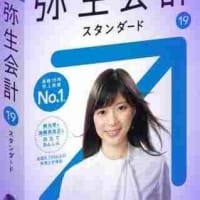
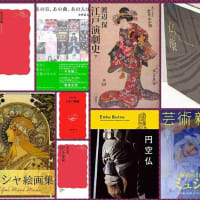
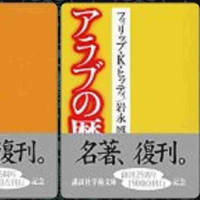
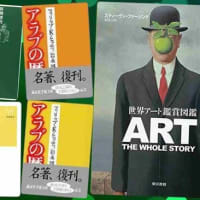
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます