北海道 留寿都村から
加地 学さんの うつわが届きました。





大きく分けて 2種類の うつわ。
薪で焚く 蛇窯で焼いた「焼締め」

同じ土でも、窯の中の置き位置で
様々な色で 焼き上がります。
鮮やかで、透明感のある黄色い うつわは
とても難しいそうです。

赤い色が多いですが、グッと締まった黒も 趣があり
ぼくは 好きです。

もう1種は、石炭を燃料にした窯で焼く「粉引き」

北海道 江別市で、自ら手掘りしてくる粘土をベースに
作陶している加地さんは、焼締めも 粉引きも
同じ粘土を使っています。
最近は 北海道の別の地の粘土も試しているそうです。
今回も 新しい粘土の うつわを1点だけ持ってきてくれています。
今年に入り、石炭での焼成に熱心に取り組んでいるようで
今回届いた うつわも 粉引きが目を引きます。

鉄分の多い土のようで 表面に滲み出ています。
鉄分の滲み量は、皆さんの好みもあると思いますが
ぼくは、この位出ているのも 好きです。
湯呑は シンプルな筒状もありますが
このラインに 惹かれます。

白化粧土と透明釉をかける粉引きといえば
白いうつわを思い浮かべる方も居ると思いますが、
加地さんの探究心でとても粉引とは思えない
色味が出ている うつわも あります。


表面の色は、ぱっと見ただけだと
焼締めかと思ってしまいます。
内側は、粉引きの化粧土はかけないで
釉薬がかかっていますが、この艶は
石炭で 焼成することによって出てくるそうです。
本日、売れてしまいましたが
この急須も 粉引きです。

ちょっと びっくりですね。
重ねて焼く時の目跡、加地さんのは やさしい感じです。
焼締めは、もみ殻の目跡

粉引きは、うつわ同士が付かない様に
小さく丸めた 土の跡

酒呑みには たまらない とくり

一点一点、趣があります。

ぜひ手に取って じっくりと見てもらいたいです。
学生時代には、ボクシングで
インターハイに出場した事のある加地さん
37度を超えた 本日の さいたま市で
朝、ランニングも こなしたそうです。
スポーツマンらしい 爽やかな 加地さんの笑顔と
北海道の大地で 生まれた うつわたちに
会いに来て下さい。
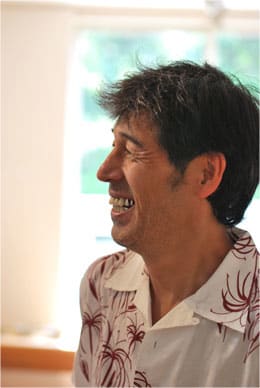

加地 学 陶展
2011年8月18日(木)~8月29日(月)
11:00-18:00 8/23火曜休み
作家在廊日 8/18(木)・19(金)・20(土)・21(日)・29(月)















