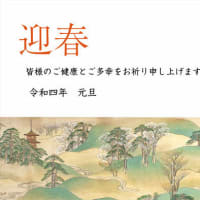哲学、特にヘーゲル哲学を何処まで完全に消化吸収し、自家薬籠中のものにできるかに、すべてがかかっている。特に、概念、判断、推理の三つの思考規定を必然的な発展過程として、認識の道具、武器として自由自在に活用できるか、また、科学研究における研究論文の展開として自覚的に駆使できるか。
とくに概念と言語の関係を明らかにする必要がある。人間は言語を通じて概念を獲得する。言語なくして概念はあり得ず、また、概念なくして言語は無意味である。言語は思考の肉体であり、概念は思考の精神である。言語の特質は、それが概念として個別と特殊と普遍を統一して内在させていることである。
すべての事物は個別と特殊と普遍の内在的統一である。言語も例外ではない。日本語も個別性と特殊性と普遍性の統一物として捉えなければならない。哲学が認識論の対象として言語を捉えるとき、もちろんそれは言語の普遍性を問題にするのであっ、個別性を対象とする言語論とは領域を異にしている。










 review @myenzyklo
review @myenzyklo