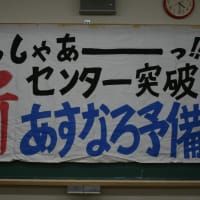数学の勉強法について
(うわ、重いタイトル!! )はじめてのblog、少し緊張気味です。
)はじめてのblog、少し緊張気味です。
最近、校内生は夏休み中の大手予備校主催マーク試験が戻ってきましたね。
結果はどうだったかな?
結果に大満足・・なんて人はそういません。
そんな人に何とか勉強法を話す機会がほしいと思っていたとき、
このblogの話がやってきました。
そこで・・
2つの勉強法を紹介します。好きな方をお選び下さい。
1つ目はこんな勉強法です。
① 教科書で苦手な単元のページを読む。
② 問題集の基礎→標準→発展と順にやっていく。わからないところは、なんどもなんども教科書を読む。
分かるまで読めば、必ず分かる。(数学の極限みたいだなぁ。)
「読書百遍(ひやつぺん)義(ぎ)自(おのずか)ら見(あらわ)る」(百遍も繰り返して書物を熟読すれば、よくわからなかった意味も自然にわかる。
という意味です。)という言葉を思い出せ!!(>_<)
もっともな意見ですね。
ただ、こんな風に、100%正しい(正しそうな?)方法なんて、大概役にたちません。
それができたら苦労はないですし、それができる生徒さんは、もう数学が得意なのです
それでは2つ目の勉強法。この方法は頑張っているとだんだん楽しくなります(^-^)。
苦手分野はやはり教科書を読みます。
ただし、「上から目線」で読むことです。
そういう意見もあるね。お前もなかなかやるやんけ~・・くらいの調子で。
ポイントは2回しか読まないところ。問題は解きません。
1回目は、言葉を覚えながら、分かる部分はあるかな~っていう気持ちで読んで下さい。2回目は、分からなかったところを集中的に。分かってくることもあれば、分からないままのところもあるでしょう。先生や友人に聞くか、まあこんなモンだとわりきって、次に進むかして下さい。必要なことなら戻ってくることになりますから。運命とはそんなものです。
ただ注意は、
「字は全部読むこと。図中の文字も全部読むこと。」
これを守って下さい。
それが終わったら、センター対策の問題集をやりましょう。
ここで多くの人が1、2、3、…と進んでいきます。
ベクトルなら、ベクトルの和と差を5問、ベクトルの内積が5問、平面ベクトルが5問、空間ベクトルが5問。計20問。
それから数列を・・・。ただ、数列が終わるころには、「え?ベクトル?何それ?」となっている場合が多いでしょう。さらに、ベクトルの内積をじっくりやっているうちに、マーク模試で空間ベクトルが出題されたりしたら、やる気を喪失。
これでは、せっかく面白くなってきた勉強が続きにくいですね。
ですから、3問とばしくらいいくのがベストなんです(1、4、7、10、13、…という感じです。)そんな進み方でも答えを見れば理解できるように教科書を読んだのですからね。
ところで
とばすというと、不真面目だと思われがちですが、そうではありません。
この方が全体をつかめるんです。
一歩一歩山を登るより、鳥になって空から眺めるみたいなものです。
お前のなかなかやるなあ・・なんて言いながら。
そうそう、僕のすすめる勉強法には、たった一つ厳しいところがあります。
「問題文を覚えなさい。」というところ。
何を聞かれているのか(結論)、何を使ってもいいのか(仮定)をしっかりおさえるためです。
考える時間は1問につき20~25分くらいです。解けそうなら、もっと時間をとってもかまいません。その後、答えをよくみましょう。
それからその解法のすばらしい点を探してあげて下さい。
「これ、すっげ~」って思う部分が多いほうが楽しいです。
それとよくある間違い。センター試験は時間との勝負っていいます。
でも、最初から時間を厳しく制限する方法は実はNGなんです。
「ゆっくりでも解けない」から「速く解ける」への道は、
「ゆっくりでも解けない」→「速く解けない」→「速く解ける」ではなく、
「ゆっくりでも解けない」→「ゆっくりなら解ける」→「速く解ける」でしょう。
そんなの決まってます。
(だって、ゆっくりでも解けないのに、急に早く解けるようになるわけないですからね。)
そのあと、誰かにそれを教えるんだったら、どうするかなって考えながら、解答をつくりましょう。(問題を見てはいけません。)
この方法なら、どんどん進むし、全体の把握もできます。また、どんどん進んでいくので、気持ちがいい。
ただ、どんな方法でもつまずくことがあると思います。そんなときは、あすなろの職員室に入ってきて下さい。待ってます。
(うわ、重いタイトル!!
 )はじめてのblog、少し緊張気味です。
)はじめてのblog、少し緊張気味です。最近、校内生は夏休み中の大手予備校主催マーク試験が戻ってきましたね。
結果はどうだったかな?
結果に大満足・・なんて人はそういません。
そんな人に何とか勉強法を話す機会がほしいと思っていたとき、
このblogの話がやってきました。
そこで・・
2つの勉強法を紹介します。好きな方をお選び下さい。
1つ目はこんな勉強法です。
① 教科書で苦手な単元のページを読む。
② 問題集の基礎→標準→発展と順にやっていく。わからないところは、なんどもなんども教科書を読む。
分かるまで読めば、必ず分かる。(数学の極限みたいだなぁ。)
「読書百遍(ひやつぺん)義(ぎ)自(おのずか)ら見(あらわ)る」(百遍も繰り返して書物を熟読すれば、よくわからなかった意味も自然にわかる。
という意味です。)という言葉を思い出せ!!(>_<)

もっともな意見ですね。
ただ、こんな風に、100%正しい(正しそうな?)方法なんて、大概役にたちません。
それができたら苦労はないですし、それができる生徒さんは、もう数学が得意なのです
それでは2つ目の勉強法。この方法は頑張っているとだんだん楽しくなります(^-^)。
苦手分野はやはり教科書を読みます。
ただし、「上から目線」で読むことです。
そういう意見もあるね。お前もなかなかやるやんけ~・・くらいの調子で。
ポイントは2回しか読まないところ。問題は解きません。
1回目は、言葉を覚えながら、分かる部分はあるかな~っていう気持ちで読んで下さい。2回目は、分からなかったところを集中的に。分かってくることもあれば、分からないままのところもあるでしょう。先生や友人に聞くか、まあこんなモンだとわりきって、次に進むかして下さい。必要なことなら戻ってくることになりますから。運命とはそんなものです。
ただ注意は、
「字は全部読むこと。図中の文字も全部読むこと。」
これを守って下さい。
それが終わったら、センター対策の問題集をやりましょう。
ここで多くの人が1、2、3、…と進んでいきます。
ベクトルなら、ベクトルの和と差を5問、ベクトルの内積が5問、平面ベクトルが5問、空間ベクトルが5問。計20問。
それから数列を・・・。ただ、数列が終わるころには、「え?ベクトル?何それ?」となっている場合が多いでしょう。さらに、ベクトルの内積をじっくりやっているうちに、マーク模試で空間ベクトルが出題されたりしたら、やる気を喪失。
これでは、せっかく面白くなってきた勉強が続きにくいですね。
ですから、3問とばしくらいいくのがベストなんです(1、4、7、10、13、…という感じです。)そんな進み方でも答えを見れば理解できるように教科書を読んだのですからね。
ところで
とばすというと、不真面目だと思われがちですが、そうではありません。
この方が全体をつかめるんです。
一歩一歩山を登るより、鳥になって空から眺めるみたいなものです。
お前のなかなかやるなあ・・なんて言いながら。
そうそう、僕のすすめる勉強法には、たった一つ厳しいところがあります。
「問題文を覚えなさい。」というところ。
何を聞かれているのか(結論)、何を使ってもいいのか(仮定)をしっかりおさえるためです。
考える時間は1問につき20~25分くらいです。解けそうなら、もっと時間をとってもかまいません。その後、答えをよくみましょう。
それからその解法のすばらしい点を探してあげて下さい。
「これ、すっげ~」って思う部分が多いほうが楽しいです。
それとよくある間違い。センター試験は時間との勝負っていいます。
でも、最初から時間を厳しく制限する方法は実はNGなんです。
「ゆっくりでも解けない」から「速く解ける」への道は、
「ゆっくりでも解けない」→「速く解けない」→「速く解ける」ではなく、
「ゆっくりでも解けない」→「ゆっくりなら解ける」→「速く解ける」でしょう。
そんなの決まってます。
(だって、ゆっくりでも解けないのに、急に早く解けるようになるわけないですからね。)
そのあと、誰かにそれを教えるんだったら、どうするかなって考えながら、解答をつくりましょう。(問題を見てはいけません。)
この方法なら、どんどん進むし、全体の把握もできます。また、どんどん進んでいくので、気持ちがいい。

ただ、どんな方法でもつまずくことがあると思います。そんなときは、あすなろの職員室に入ってきて下さい。待ってます。