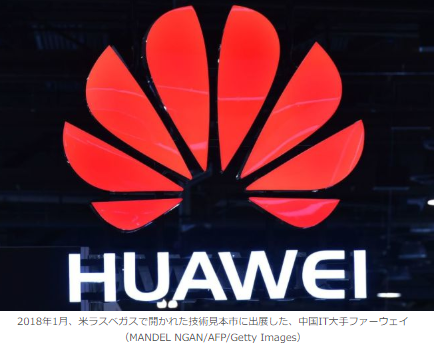映画「ミッション:インポッシブル」から学ぶ真剣勝負【ヒット映画の仕事術に学ぶ。】
2018.12.18https://the-liberty.com/article.php?item_id=15236 The Liberty Webより
ロンドンやニューヨークの美術館で開かれる、早朝の美術教室(ギャラリートーク)の参加者は、今まで観光客が多かった。しかし近年、背広を着たビジネスパーソンが、出勤前に顔を出すようになっているという。
世界有数の美術系の大学は、グローバル企業の幹部に向けた美術プログラムを提供し始めている。そこには、フォードやビザといった名だたる大企業の幹部が送り込まれている。
アップル社の創業者スティーブ・ジョブズもデザイン哲学を学んでいた。商品開発に芸術性を盛り込むことで、今世紀最大のヒット商品「iPod」「iPhone」を世に送り出した。
今、世界においても日本においても、経済における競争の局面が、「商品の機能の差別化」から「情緒の差別化」へと変化している――。社会の潮流を予測し、世界的なベストセラーになったダニエル・ピンク著『ハイ・コンセプト』は2005年、そう指摘した。
人々は、自分の美意識に合った商品や芸術性が高いものを所持し、精神的な高揚や満足感を得ることを求め始めている。
こうした付加価値を生み出す商品やサービスは、今までMBAで教えていたような、論理や分析のみで創造することが難しい。ビジネスパーソンたちは、より高度な芸術性や創造性が求められる時代となっている。
この傾向は、AI(人工知能)の発達で、さらに加速する。ロジカルな分析に基づく仕事は、コンピューターにシフトしていく可能性が高い。
本欄では、映画、小説、アニメーションなどにおける「ヒットが生まれた現場」に目を向ける。そしてそこから、ビジネスマンが仕事に「芸術性」「創造性」を加え、感動を創造するヒントを探っていく。
◆ ◆ ◆
(1) 映画「ミッション:インポッシブル」の主役トム・クルーズの真剣勝負に学ぶ
第6回は、映画「ミッション:インポッシブル」のトム・クルーズ(製作兼主演)から「真剣勝負」の大切さについて考えてみたい。
映画「ミッション:インポッシブル」は、1作目を1996年に公開して以来、すでに6作のシリーズを世に送り出している。新作ごとに興行収入の記録を大幅に塗りかえ、回を追うごとに観客・評論家の評価も高まる。シリーズ映画のお手本とも言うべき作品だ。
このシリーズの製作を一貫して担い、主役も務めるのがトム・クルーズである。彼は主人公イーサン・ハントになり、世界の危機を救う凄腕スパイを演じている。アメリカの情報機関IMFに所属するハントが、仲間と協力しながら、秘密道具を駆使し、体を張って難題を解決する。
本作の最大の見どころは、命がけのアクション・シーンにこそある。しかも、トム自らがすべてのアクションに挑む。スタントはなしだ。
- ロッククライミングで巨岩に登頂する。
- 自らの眼球の数ミリ手前に鋭いナイフを突き立てさせる。
- 世界一高いビルのハリファ・タワー(160階)の壁面を下に向かって駆け降りる。
- 航空機の機体に背広でへばりついたまま高度5000フィート(約1500メートル)まで飛行する。
- 操縦するヘリコプターを切りもみさせながら落下させる。
すべて、一歩間違えば大ケガか即死するようなものばかりだ。スタントなしで血も凍るような危険なアクションに、まさに真剣勝負で挑むトムの姿は、狂気すら感じさせる凄みがある。
もちろん、撮影にあたっては、周到な訓練と可能な限りの準備をして臨んでいる。しかし万が一ということはある。実際、アクション映画の撮影現場でケガ人や死者が出ることもよく起こる。
ではなぜ、スタントマンに任せず、自らアクションを演じるのだろうか?
トムは言う。「俳優はアフガニスタンにいる兵士のようなもの」。自らの職業を兵士に例え、文字通りの真剣勝負を前提としたプロ意識を持っているのだ。
確かにトムは、映画「トップガン」で空軍兵士を演じたことで人気俳優に駆け上がり、映画「7月4日に生まれて」では、ベトナム帰還兵を演じ、アカデミー主演男優賞に初ノミネートされている。この作品では、実際の従軍兵レベルのトレーニングを不満も言わずにこなし切った。
しかし一方で彼は、「しなくてはいけないことを楽しんでやっている。他の人たちにとっては危険に見えるかもしれないけど、ぼくにとっては楽しいことなんだよ」とも語る。なんと「楽しんでやっている」というのだ。
このように言える理由について、トムはしばしばインタビューの最後に「映画が好きなんだ」「好きだからできるんだ」と、充実しきった顔で語る。(南波克行著『トム・クルーズ キャリア、人生、学ぶ力』3、193~194頁)
ただトムのアクションは、無謀なチャレンジで人の目を引くことだけを狙っているわけではない。そのアクションに、人間のあるべき姿や責任感・使命感の尊さ、自己犠牲の精神を宿らせている。
言葉で語るのではなく、トム自らがそうした精神を体現し、全身全霊のアクションによって"語りかける"。それによって、無言の説得力で胸に迫ってくる。真剣勝負の演技だからこそ、崇高なテーマが深く刺さるのである。
映画「ミッション:インポッシブル」には、「トム・クルーズが真剣勝負の演技とアクションで魅了してくれる」という観客の大きな期待が常にある。トムはいつも、その期待のハードルを超える挑戦で応えてくれる。
だからこそ彼の映画は、いつも世界中の観客を興奮させ目を離させないのだ。
映画『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』日本版本予告
映画『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』ティザー予告映像
(2) 映画監督・黒澤明の真剣勝負
日本を代表する映画監督・黒澤明も、トム・クルーズのような真剣勝負で映画製作に取り組んでいた。
映画「七人の侍」(1954年公開)には、降りしきる雨のなか、野盗たちに対して武士と農民が戦いを挑む有名なラストシーンがある。
このシーンのために膨大な水をセットに撒いたため、現場は泥で足をとられてまともに歩けない状況となった。そのような中で、数頭の馬と数十人の人間が入り乱れる戦闘シーンを撮影するのである。そのうえ、撮影は二月の厳寒の中で行われる。
現場には「このまま撮影すれば、馬に踏まれて死人が出るかもしれない」という懸念があった。しかし黒澤監督は、死者が出る覚悟までしたうえで撮影を決行した。その結果、幸い死者は出なかったが、落馬して骨折した者が5名、軽傷者は数えきれないほどであったという。
だが、決死の撮影によって、映画史に刻まれる名場面が誕生したのである。(『日本の100人 NO.098 黒澤明』18頁)
同じく黒澤監督による映画「蜘蛛巣城」(1957年公開)には、悪王の城主が、城攻めを仕掛けてきた敵から無数の矢で打たれるシーンがある。その場面のリアリティを増すために、黒澤監督は本物の矢を使って撮影した。
矢が外れて俳優に当たらないように、弓矢の名人に依頼したようだが、城主を演じた三船敏郎の顔のすぐ近くに、矢が何本もブスブスと刺さっていく。本物の矢と知って見ると、とても正視にたえない恐怖シーンに仕上がっている。これには、さすがの三船敏郎も「後でぶっ殺すぞ」と思っていて怒り心頭だったという。(松田美智子著『サムライ 評伝 三船敏郎』125~126頁)
もちろん、可能な限りの安全確保は実施しているのだが、それにしても鬼気迫るものがある。
ビジネスマンに活かせるヒント
"真剣勝負"は、ビジネスパーソンでも以下のように活用できる。
1.「経営マインド」に活かす―責任の自覚が真剣勝負を生む
HONDA(本田技研工業株式会社)の創業者・本田宗一郎の片腕として経営を担当した藤沢武夫は真剣勝負で生きた人だった。
今では大企業となったHONDAにも、経営危機が幾度もあった。なかでも1954年は深刻で、銀行からの緊急融資によって何とか危機を脱した。
その時期に、社員とその家族による社内運動会が開催された。競技に参加した家族のなかに、ズボンに継ぎを当てている子供がいた。
運動会を終えて家に戻ってきた藤沢武夫は、妻の前でボロボロ、ボロボロと涙を流しはじめた。理由をたずねた妻に、藤沢は答えた。
「たとえ借金をしてでも子供にいいシャツを着せて、いい運動パンツを穿かせて運動会に連れていきたいのが親の心情なのに、そんなズボンしか穿かせられない俺は、なんて経営者なんだ……」「こんなことが絶対にないような会社にしなければ、俺は死んでも死にきれん」(『月刊 致知 2010年2月号』53頁)
藤沢武夫は「たいまつは自分で持て」と述べている。「どんなに苦しくても、たいまつは自分の手で持って進まなければいけない」と語り、それが「私の根本の思想」だと言い切る。(『経営に終わりはない』161頁)
真剣勝負は、他人任せにせず、向かうべき課題に立ち向かっていく責任感から生じるということを教えてくれる言葉だ。
2.「商品開発」に活かす――真剣になれば、商品の声が聞こえてくる!?
現パナソニックの創業者・松下幸之助は、「真剣であれば物が語りかけてくる」という。
松下幸之助は次のように説明している。
「たとえば、試作品ができるとぼくは、できる限り自分でも実際に手に取り使ってみることにしていました。電気コタツでもラジオでもテレビでも、しばらくのあいだ、じっと眺めたり、手でなでまわしたりしながら、それぞれの機能を試してみる。
そうすると、もの言わぬはずのコタツやテレビがぼくに語りかけてくる。『この角をもう少し削って丸みをつけてくれないか』とか、『スイッチをもう少し太くしてほしい』とかいう声が、実際に聞こえてくるような気になるのです。
もの言わぬはずの商品が何ごとかを語りかけてくるというのは、いったいどういうことなのか。ぼく自身もよくわからないのですが、結局、そのような声が聞こえるかどうかは、自分の側にどれだけの真剣さがあるかによるのではないかと思います」(『松下幸之助の見方・考え方』45頁)
松下幸之助は、「経営は真剣勝負だ」「商売は真剣勝負だ」と語っていた。(『「経営成功学の原点」としての松下幸之助の発想』57頁)
真剣勝負をすればこそ、人もついてくるし、アイデアが湧いてくる。そして危機に直面しても克服できる。「真剣勝負」は、日々の心がけとしても大切だが、特に、危機のときには心に刻んで仕事にあたっていきたい。

筆者 内田 雄大
(うちだ・ゆうだい)京都造形芸術大学芸術学部卒、放送大学大学院修士課程修了。ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ アソシエイト・プロフェッサーとして、「総合芸術論」「世界宗教史」等を教える。第6回「幸福の科学ユートピア学術賞」優秀賞(「プラトン芸術論の真相と現代的意義」)。筆名・小河白道で美術評論を執筆し、「幸福の科学ユートピア文学賞」において、2013年度から2015年度まで連続入賞を果たす。著作は『ルネサンス・コード』『クリエイティブ幸福論』