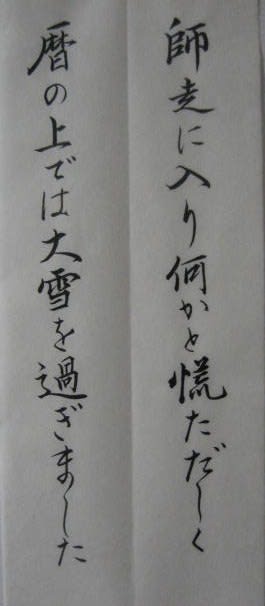海老名の映画館、今日は「ファーストデー」サービスで、1000円
そんな訳で、1人で行ってきました。

三国志に出会ったのは、小学校6年生の時。当時は、今ほど本があふれていないので・・・・・。
たまには学校の図書館からも借りましたが。
小学校5年生ぐらいからは、叔父が、本を数多く所蔵していたので、黙って借りては読んでいましたね。
たぶん面白い本がたくさん図書館よりあったのだと思います。
叔父の本を読むきっかけとなったのは、「ビルマの竪琴」・・・・。
そこから、山本有三の路傍の石・・・・「三国志」。
今でも、当時のこと鮮明に覚えたいます。
まだ、テレビが普及されていないので、自分勝手に、水島上等兵を作り、吾一も
諸葛孔明も・・・・・。
今回この映画で・・・・・。諸葛孔明を演じていたのは、金城武・・・・。
もちろん彼は、ハンサムで文句ないのですが、私の中の孔明は、もっとおじさんをイメージしていたのに・・・・・。
逆に劉備は、もう少し若い方の様に想像していました。
だって、孔明を「三顧の礼」で迎えた人なので・・・・。
関羽・張飛はイメージ通りでしたね。
中村獅童が演じた「甘興」については、知識がなかったのですが、今回も彼は、
きらりと光る演技でしたね。私は個人的には好きなんですが・・。
トゥーランドットの時も彼の演技素晴らしいと思っていたので・・・・。
パート2は
赤壁の戦い・・・・来年4月だそうです。
また、見に行かないと。今から楽しみです。
後に蘇軾(蘇東坡)の『赤壁の賦』。長江に舟を浮かべ、名月を仰ぎながら、
酒を酌み交わしつつ、夜の白むまで、英雄たちをしのでいるので・・・・。
映画となったらどのようになるのか・・・・。
これから、見に行かれる方は「旗」を見て来て下さい。この時代の字がどの様な字が使われていたのか・・・・。
それから、今回は出てきませんが、曹操に仕えた鍾繇と言う書家がいたこと。
そして鍾繇は隷書と行書に巧みであった。楷書が特に有名であるが、三国時代には
楷書という言葉がなく、後世の書家によって楷書に当てはめられたものであり隷書
と楷書の中間のような書体である。これを「鍾繇体(しょうようたい)」という。
鍾繇の楷書は、書聖王羲之をはじめ非常に多くの書家が学んでおり、現代でもよく学ばれていること。
こんなこと頭の隅に置いてみていただけたら、書の方面からの見方があるかもしれません。
そんな訳で、1人で行ってきました。

三国志に出会ったのは、小学校6年生の時。当時は、今ほど本があふれていないので・・・・・。
たまには学校の図書館からも借りましたが。
小学校5年生ぐらいからは、叔父が、本を数多く所蔵していたので、黙って借りては読んでいましたね。
たぶん面白い本がたくさん図書館よりあったのだと思います。
叔父の本を読むきっかけとなったのは、「ビルマの竪琴」・・・・。
そこから、山本有三の路傍の石・・・・「三国志」。
今でも、当時のこと鮮明に覚えたいます。
まだ、テレビが普及されていないので、自分勝手に、水島上等兵を作り、吾一も
諸葛孔明も・・・・・。
今回この映画で・・・・・。諸葛孔明を演じていたのは、金城武・・・・。
もちろん彼は、ハンサムで文句ないのですが、私の中の孔明は、もっとおじさんをイメージしていたのに・・・・・。
逆に劉備は、もう少し若い方の様に想像していました。
だって、孔明を「三顧の礼」で迎えた人なので・・・・。
関羽・張飛はイメージ通りでしたね。
中村獅童が演じた「甘興」については、知識がなかったのですが、今回も彼は、
きらりと光る演技でしたね。私は個人的には好きなんですが・・。
トゥーランドットの時も彼の演技素晴らしいと思っていたので・・・・。
パート2は
赤壁の戦い・・・・来年4月だそうです。
また、見に行かないと。今から楽しみです。
後に蘇軾(蘇東坡)の『赤壁の賦』。長江に舟を浮かべ、名月を仰ぎながら、
酒を酌み交わしつつ、夜の白むまで、英雄たちをしのでいるので・・・・。
映画となったらどのようになるのか・・・・。
これから、見に行かれる方は「旗」を見て来て下さい。この時代の字がどの様な字が使われていたのか・・・・。
それから、今回は出てきませんが、曹操に仕えた鍾繇と言う書家がいたこと。
そして鍾繇は隷書と行書に巧みであった。楷書が特に有名であるが、三国時代には
楷書という言葉がなく、後世の書家によって楷書に当てはめられたものであり隷書
と楷書の中間のような書体である。これを「鍾繇体(しょうようたい)」という。
鍾繇の楷書は、書聖王羲之をはじめ非常に多くの書家が学んでおり、現代でもよく学ばれていること。
こんなこと頭の隅に置いてみていただけたら、書の方面からの見方があるかもしれません。