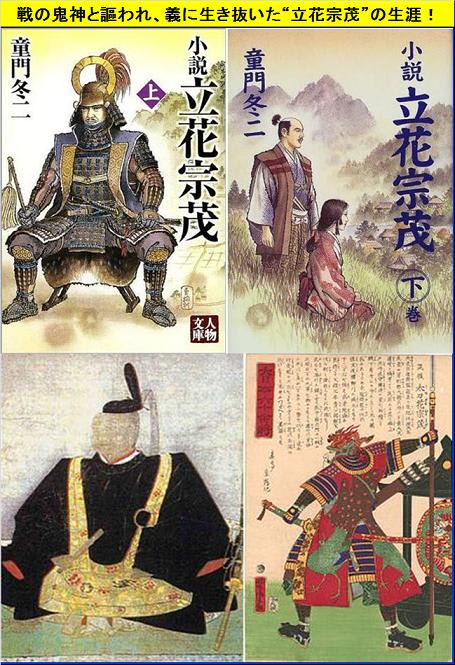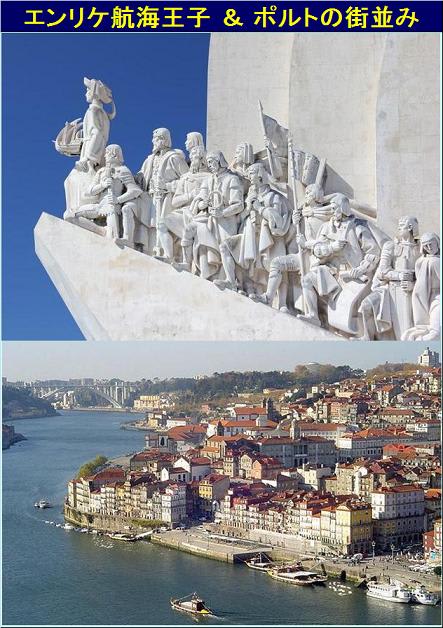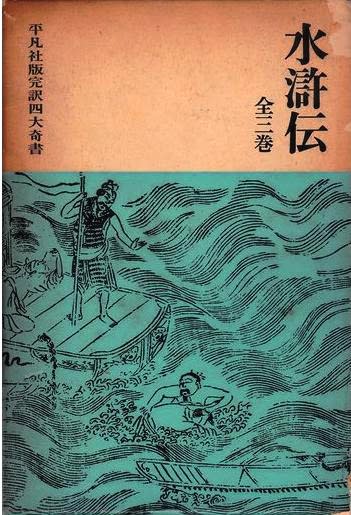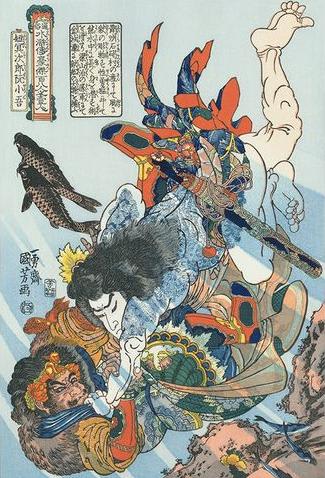「侠客」 池波正太郎:著作
日本の侠客元祖とも言われる【幡随院長兵衛】が唐津と関わりがあるとは、全く知らんかった。
佐賀県東松浦郡相知町久保地区の生まれで、JR肥前久保駅傍には「長兵衛公園」&「記念碑」も有るとか。
唐津藩主の子孫の小笠原長生公の題字による高さ6.3m、台座2.1m、石垣含め地上15mの記念碑は、昭和14年除幕式が有り、横綱・双葉山による幕の綱引き式典と記念興行も開催されたんだって。
幡随院長兵衛(1614~1650)、大河野(現佐賀県伊万里市大川野)城主・鶴田因幡守勝の家臣・塚本伊識の子として慶長19年、相知町久保で生まれ、幼名:伊太郎。
父に伴って江戸へ向かい(下関にて父は病没)神田山幡随院に身を寄せ、後に幡随院長兵衛と名乗る。
やがて江戸侠客の総元締めで庶民の英雄ともてはやされ、その生き様は江戸の華と呼ばれ、「人は一代、名は末代」の有名なセリフで歌舞伎公演もなされている。
水野十郎左衛門(旗本奴)と幡隋院長兵衛(町奴)の関わりと友情と対立とを、伊太郎の父の仇である唐津藩城主寺沢兵庫頭への仇討を背景に描かれている。 徳川幕府が武断政治から官僚的システム化へと移行する時代に、長兵衛は人足や運送業者を率いる「町奴」として人望を集めるようになり、「人いれ宿」(現在の職業安定所や人材派遣会社に準じる様な、もっと泥臭い人間関係と思いやりが感じられるシステムと言えようか?)で新しい江戸作りと庶民との関わりで、謂わば“地域創り・街づくり”に勤めている。
「火事と喧嘩は江戸の華」との言葉があるが、歴史的背景を絡み併せて、仇討から「江戸の大火(振袖火事)」等の社会不安の中、謂わば“地域の安全と安心の街づくり”に奔走しゆく「町奴頭」長兵衛。
後の時代になるが「町火消し」と旗本・大名を中心とする武家社会の自営消防団「大名火消し」「定火消し」との関わりとかもTV・映画「南町奉行・大岡越前守忠相」とかで描かれている通りである。
一方で、時代社会の変革と流れに付いていけない一部の旗本奴たちは、過去の栄光だけに生きる無用の武力集団の象徴として描かれ、遂に二つの勢力の対立となって、宿命的・運命的な長兵衛の「死」へと進んでいく。
旗本奴とは、大名に対してさえも堂々と物言い、時に喧嘩さえ惜しまぬ気迫と度胸を備え、時に権力中枢(幕閣)とも対立していた時代状況であったとか。 若いころ見ていた映画「旗本退屈男」(市川歌右衛門:主演)での『天下御免の向こう傷!』のセリフで旗本の立場ながら各藩と対立する物語を思い出させてくれる。
大きな流れで見れば、権力中枢から置き去りにされ不平不満が渦巻く「旗本奴」の捌け口が町民や町奴へと向かう。
「火事と喧嘩」の仲裁と「職業紹介&運送業」等を束ねる「町奴」。
其の対立が頂点に達し、水野十郎左衛門邸における幡随院長兵衛の暗殺へと悲劇的な結末で終了する。
当時の庶民の暮らしと旗本達の置かれた時代社会の状況が目に浮かぶ様に描かれ、スピード感もあって面白く、ハマって一気に読了してしまった。
イヤァ~オモロカッタなぁ~。
今度、相知町「見返りの滝」や「温泉」とかに行った時、訪ねてみよう~っと!